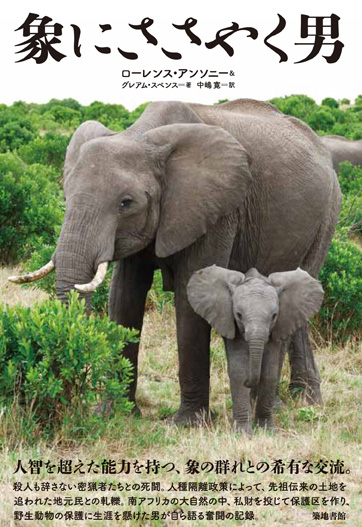鳥の不思議な生活ハチドリのジェットエンジン、ニワトリの三角関係、全米記憶力チャンピオンVSホシガラス

| ノア・ストリッカー[著]片岡夏実[訳] 2,400円+税 四六判上製 304頁 2016年1月刊行 ISBN978-4-8067-1508-5 フィールドでの鳥類観察のため南極から熱帯雨林へと旅する著者が、ペンギン、アホウドリ、純白のフクロウなど、 鳥の不思議な生活と能力についての研究成果を、自らの観察を交えて描く。 北米を代表するバードウォッチャーによる、鳥への愛にあふれた鳥類研究の一冊。 著者ホームページ: http://noahstrycker.com/ |
ノア・ストリッカー(Noah Strycker)
 ©Bob Keefer
©Bob Keefer
アメリカ野鳥協会発行の『バーディング』誌編集委員。元『ワイルドバード』誌コラムニスト。その他の鳥に関する出版物にひんぱんに寄稿している。
オーストラリアの原野、南極など世界有数の過酷な環境の地域を含め、世界各地で鳥の研究を行なっており、
最初の著書である "Among Penguins"(2011年)では、基地から遠く離れたキャンプでペンギンを研究したひと夏を描いている。
ライフリスト(確認した鳥のリスト)は6大陸で2500種に迫り、世界の鳥の5分の1に当たる。テニス選手でもあり、フルマラソンを5回完走している。
2011年には自然歩道パシフィック・クレスト・トレイルをメキシコからカナダまで4290キロ踏破し、
最近では太平洋岸北西部の自然保護区域を1日に102キロ歩いている。フィールドワークに出ていないときにはオレゴン州で執筆と講演を行なっている。
片岡夏実(かたおか・なつみ)
1964年神奈川県生まれ。主な訳書に、
マーク・ライスナー『砂漠のキャデラック アメリカの水資源開発』、
エリザベス・エコノミー『中国環境リポート』、
デイビッド・モントゴメリー『土の文明史』、
トーマス・D・シーリー『ミツバチの会議』、
デイビッド・ウォルトナー=テーブズ『排泄物と文明』、
スティーブン・R・パルンビ+アンソニー・R・パルンビ『海の極限生物』(以上、築地書館)、
ジュリアン・クリブ『90億人の食糧問題』、
セス・フレッチャー『瓶詰めのエネルギー 世界はリチウムイオン電池を中心に回る』(以上、シーエムシー出版)など。
序
知られざるハトの帰巣能力
ロックリーの実験
帰巣能力と鳩レース
ハトの情報処理能力
ハトが迷子になる理由
ムクドリの群れの不思議
「集団行動」と「創発」
ボイドプログラムと鳥の群れ
ホークアイとムクドリ
ムクドリの過ち
物理学者の挑戦
ヒメコンドルの並はずれた才能
嗅覚か視覚か
ガス漏れ探知能力
味にうるさいヒメコンドル
シロフクロウの放浪癖
シロフクロウとの遭遇
北極圏からハワイまで
居場所を求めて
なんでも食べるシロフクロウ
放浪癖とDNA
闘うハチドリ
小さなジェット戦闘機
燃料は常に満タン
スピードの代償
闘争か逃走か――ペンギンの憂鬱
ペンギンの無関心
天敵ヒョウアザラシ
生存確率を高めるための感情
闇への恐怖
オウムとヒトの音楽への異常な愛情
拍子をとるオウム
踊る動物たち
音声模倣とリズム感覚
音楽は進化に必要か
ニワトリのつつき順位が崩れるとき
ワールド・ツアー・ファイナルとニワトリ
ニワトリの三角関係
ニワトリ王の法則
赤いコンタクトレンズ
ホシガラスの驚異の記憶力
隠し場所の数は5000
エベレスト登山と記憶力
ホシガラスの空間記憶
全米記憶力チャンピオンの記憶法
鳥の脳も縮む
鏡を見るカササギ
世界でもっともかしこい鳥
怨恨・嘲笑・鎮魂
自我と他者理解9
ニワシドリの誘惑の美学
モテるためのアート
ニワシドリとピカソ
芸術が進化を促す
孤独な芸術家
オーストラリアムシクイの利他的行動
血縁にはしばられない
友好的にふるまう
最大の利益を得るもの
協調行動と進化
喜びを感じて
アホウドリの愛は本物か
愛の定義
一雌一雄制の幻想
放浪者の婚姻
永遠の絆
謝辞
註釈および参考文献
索引
訳者あとがき
鳥が私たちを研究したらどうなるか、想像してみよう。
ヒトの特徴のどれが、鳥たちの関心を引くだろう? どのようにして結論を導き出すだろう?
たぶん鳥たちは、たいていの優れた科学者がするように、基本的なことから始める。時間をかけて、ヒトの身体を計測するだろう。
体重、身長、筋力、脈拍、脳の大きさ、肺活量、色、成長速度、平均寿命などだ。
学究肌の鳥たちは、人間の臨床的、身体的観察記録を満載した本を何冊も書くだろう。
もちろん、彼らはデータ収集のために野外調査団を派遣しなければなるまい。
ある朝、玄関を一歩出たあなたは目に見えない網にからめ取られ、物差しや秤を手にした若く優秀なヒバリたちに取り囲まれるかもしれない。
言うまでもなくすぐに解放され、捕まったきまり悪さと髪の毛を2、3本慎重に抜かれたほかは、何一つダメージはない。
その後ヒバリたちは帰って、得られた数字を分析するだろう。
こうした計測値から、鳥は私たちについて実際どれほどのことがわかるのだろう?
私たち人類が日ごろ誇っている、脳の大きさを例に取ろう。ヒトの脳の大きさ自体は、特別なものではないと、鳥は当然のように指摘するだろう。
たとえばクジラやゾウの脳は、もっと大きい。さらに鳥は、ヒトの脳の大きさを体重と比較するだろうが、それでもヒトは突出してはいない。
ヒトの脳の重さと体重の比は、ハツカネズミとほぼ同じくらい(約1/40)であり、ある種の鳥(1/14)より小さい。
相対的な大きさでは、アリが最大の脳の持ち主(1/7)かもしれない。この凡庸な数字を説明するために、脳の大きさは体重の増加につれて、
指数法則に従って大きくなると人間は主張している―つまり、脳は体と正比例で増大するわけではないということだ。
しかしこの公式は、哺乳類が哺乳類のために考え出したものだ。鳥は、もし私たちの脳を研究したとすれば、この理論を採用しないかもしれない。
鳥はヒトの脳が―さらに言えばヒトという動物が―取り立てて面白いとは思わないかもしれないのだ。
だからヒトについて本当に知ろうとするなら、好奇心の強い鳥たちは、私たちの身体を研究するだけでは不十分だ。
私たちがどのように行動するかをつぶさに観察し、そのような行動を取るのはなぜかを解明するように努めなければならないだろう。
これは大仕事だ。一見単純な問題を考えてみよう。なぜあなたは、この本を読んでいるのか?
「鳥について知りたいから」「楽しみのため」、そんな答えが返ってきそうだが、おそらくそれ以上の理由がある。
読書は広く行きわたったヒトの衝動であるらしいのだ。
人類史の大部分に書物は存在しなかったにもかかわらず、多くの文化圏に属する人々が読書を楽しんでいると、進化生物学者は指摘する。
紙に書かれた言葉を解読するには、私たちの中に刻み込まれた能力を駆使しなければならないが、なぜ人間が読書を好むのか、誰もはっきりとは知らない。
そして、なぜそうするのか自分自身が知らないとすれば、この本を読んでいるあなたを鳥はどう理解できるというのだろう?
鳥は、自分たちにはまったく異質な行動について、どのように結論づけるだろう?
鳥がヒトの行動の研究を始めるとしたら、ほぼ間違いなく自分たちが知っているものから手をつけるだろう。
たとえば、睡眠の習慣から。ヒバリの野外調査団は、あなたの寝室の隅にキャンプして、シーツの色やいびきの音量などを事細かに記録する。
間違いなく鳥は、毎晩の休息の必要性を理解するだろう。
しかし、こうした寝室での徹夜の観察から、鳥はヒトの特徴一般についてどのように結論づけるだろうか?
特に、鳥の眠りが私たちとは違うことを考えた場合。
ほとんどの鳥は非常に眠りが浅く、人間にとって当たり前の、ぐっすり眠り込むという状態に落ちることはまれだ。
また一部の鳥にはきわめて奇妙な睡眠の習慣がある―飛びながら、一度に脳を半分ずつ休ませているらしいと考えられるものもいるのだ。
ある種のオウムは、コウモリのように逆さまにぶら下がって眠る。ハチドリは暗くなるとエネルギーを節約するために仮死状態に入る。
睡眠のようなもっとも基礎的な行動さえも、研究すればするほど複雑になり、そして理解するのが難しくなるのだ。
鳥は、ヒトの習慣の調査から、人類が鳥になりたがっているとさえ結論するかもしれない。
過去1世紀、私たちが飛行機に、スペースシャトルに、その他の空を飛ぶ機械に莫大な金を費やしてきたことを考えてみるといい。
鳥はどう思うだろう?
鳥とヒトの行動の違いについて―そしてその違いが絶対的なものか、程度の差に過ぎないのかについて―かつてダーウィンが言ったように鳥は議論するだろうか?
鳥はある種の飛行機を哀れみの目で調べ、被験者に対して優越感を感じるかもしれない。それも無理のないことだろう。
鳥が人間を研究するという発想は、まったくの擬人化であり、強調のために人間の性質を鳥に当てはめたにすぎない。
鳥にはヒトの研究のほかにやることがあるし、科学的探求のような概念を認識する知的能力を持っているかどうかさえ疑問だ。
バードウォッチャーは、よく冗談で鳥が自分たちを観察していると言うが、鳥はおそらく捕食者への必要最低限の恐れ以外、
人間に対してさほどの関心を抱いていない(詳しくは「闘争か逃走か―ペンギンの憂鬱」の章を参照)。
私たちが鳥の世界で果たす役割は、ごくわずかなのだ。
それでも私たち人類が鳥について研究し、その行動についての発見が増えるほど、私たち自身と羽を持つ友達とのあいだに多くの類似点が見つかる。
鳥の行動のほぼあらゆる分野―繁殖、分布、移動、日周リズム、コミュニケーション、方向感覚、知能など―に私たちのものと大変に似ている点があり、
それには大きな意味があるのだ。最近、動物行動についての科学的な考え方が変わってきたことで、人間の独自性よりも、
ヒトという動物と他の動物との共通部分が注目されるようになった。
もともとヒトの特徴とされていたもの、たとえば音楽に合わせて踊る(「オウムとヒトの音楽への異常な愛情」の章参照)、
自分の鏡像を理解して自分だと認識する(「鏡を見るカササギ」の章参照)、芸術を創造する(「ニワシドリの誘惑の美学」の章参照)、
愛とロマンスまでもが(「アホウドリの愛は本物か」の章参照)、鳥にも認められている。これは擬人化などではない。
擬人化だという者はすべて、鳥であることが意味するものの大半を無視している。
さらに、次々と行なわれる人間に対する神経学的研究が示すのは、同じ行動がヒトに現れた場合、
それは多くの人間が自覚している以上に本能的なもので、長い年月にわたる自然選択の結果であるかもしれないということだ。
言いかえればそれは、生存に有利であるために進化した行動なのだ。
つまりヒトと他の動物の間にあるとされるギャップは最近、両方の端から縮まっているわけだ。
幸運なことに私は、ここ10年間の大部分を野外で過ごし、鳥の行動を研究する科学者と共に、実地研究プロジェクトに携わっている。
このようなプロジェクトのおかげで私は、世界の辺境地で一度に数カ月鳥を観察して過ごすことができた。
エクアドル・アマゾン、南極のペンギン・コロニー、オーストラリアの奥地、カリフォルニアのファラロン諸島、
コスタリカとパナマのジャングル、ガラパゴス諸島、フォークランド諸島、メイン州の離島、ハワイ島などなど。
私は2500種近い鳥を観察し、それが実験材料などではなく、むしろ生き生きとした、予想のつかない、個性と生命力あふれる存在であるとの認識を深めていった。
鳥を知るためには、人を知るのと同じように時間がかかる。
鳥の行動の中にはヒトに当てはまらないものがあり、そうしたものは特に魅力的で興味深い。
「第6」の磁気感覚(「知られざるハトの帰巣能力」参照)、磁石として機能する群れ(「ムクドリの群れの不思議」参照)、
ヒメコンドルの嗅覚(「ヒメコンドルの並はずれた才能」参照)などがそれだ。
こうした超能力を持つのがどのようなものか想像するのは難しいが、鳥は時に、想像してみるように私たちに促す。
しかしよく見てみると、一見信じがたい鳥の芸当には、われわれ人間と共通するものが多くあり、そこには興味深い教訓がある。
オーストラリアムシクイによる共同営巣(「オーストラリアムシクイの利他的行動」参照)は、ヒトが多くの場合他人に親切である理由を説明する。
目が回るようなハチドリのスピード(「闘うハチドリ」参照)は、慌ただしさを増す私たち自身の生活への警告となる。
シロフクロウ(「シロフクロウの放浪癖」参照)は、放浪する者すべてが道に迷っているわけではないことを裏付ける。
ニワトリでさえも(「ニワトリのつつき順位が崩れるとき」参照)自然のつつき順位について何かを教えてくれる。
この本は鳥の世界について書いたものかもしれないが、人間の世界についての本でもある。
鳥の行動は奇妙で派手で驚くべきものだろうが、私たちと同じ基本的なもの、つまり食料、すみか、なわばり、安全、交流、遺産を求めている。
それぞれの章は鳥のきわめて興味深い行動を探り、それを実現する鳥に焦点を当てている。これから驚くべき鳥の物語が続々と登場する。
圧倒されることを覚悟してほしい。
たとえば、ハイイロホシガラスの記憶力(「ホシガラスの驚異の記憶力」参照)に。それは脳に何ができるかを私たちに教え、
自分自身の脳の力を高めようという気にさせるかもしれない。
鳥を研究することで、私たちは最終的に自分自身を知ることになる。鳥の行動はヒトの行動を映す鏡になる。
本書の中では、鏡はいたる所にあり、私たちと地球を共有する1万種の鳥の数知れぬ翼端に輝いている。幸運にも、鳥はどこにでもいる。
ただそれを観察するだけでいいのだ。
本書は20代の若き鳥類研究者、ノア・ストリッカーの2冊目の著書である。「鳥オタク」を自任する著者は、
高校生のころにシカの死骸を拾ってきて自宅にコンドルをおびき寄せ、写真を撮影したという筋金入りのバードウォッチャーだ。
現在ではフォークランド諸島、オーストラリアの原野、南極(その様子は1冊目の“Among Penguins”と本書のペンギンの章に描かれている)
など辺境地を含めた世界各地を飛び回り、ときには真冬だというのに汗まみれになって泥沼を渡り、
また灼熱の荒野でウォークイン冷蔵庫にたびたびこもりつつ観察を続けている。こうした豊富な野外観察の成果と鳥類学や動物行動学の知見に、
さまざまな分野の話題─記憶競技、ゲーム理論、奇妙なベンチャー・ビジネス、テニスまで─を織りまぜ、時にユーモラス、時に詩的な文体で語ったのが本書だ。
ここに描かれた鳥の興味深い生態や行動は、必ずしもすべてが新発見というわけではなく、中には昔からよく知られたものもある。
ハトの帰巣本能、ニワトリのつつき順位などは、多くの読者がこれまでにどこかで見聞きしているだろう。ムクドリの群れは実際に目にする機会も少なくない。
それでもなお、この本は新鮮だ。その理由の一つは「人間と他の動物のへだたりは、両方の端から縮まってきている」
という本書を貫くテーマが新しく、魅力的だからだと思う。
最近の研究により、人間の特質とされていたもの、たとえば音楽に合わせて踊る、鏡に映った自分の姿を自分だと認識する、
芸術の創造、利他的行為、愛などが鳥にも認められ、一方で人間のそうした行動も、かなりの程度本能に根ざしているらしいことがわかってきたという。
これが両端から縮まっているということだ。したがって、鳥と人間の何が共通し何が違うのかを考えることは、人間の本質について考える哲学的な考察に通じる。
そもそも芸術とは何か。自己の利益を顧みない純粋な利他主義はありえるのか。愛のありかたにはどのようなものがあるのか。
そして鳥の中に映しだされた人間性をどう見るかは、とりもなおさず人間そのものをどう見るかを表す。
「鳥を研究することは、究極的には人間について知ること」という著者の持論は、鳥と人間への深い洞察として、この本のはしばしに現れている。