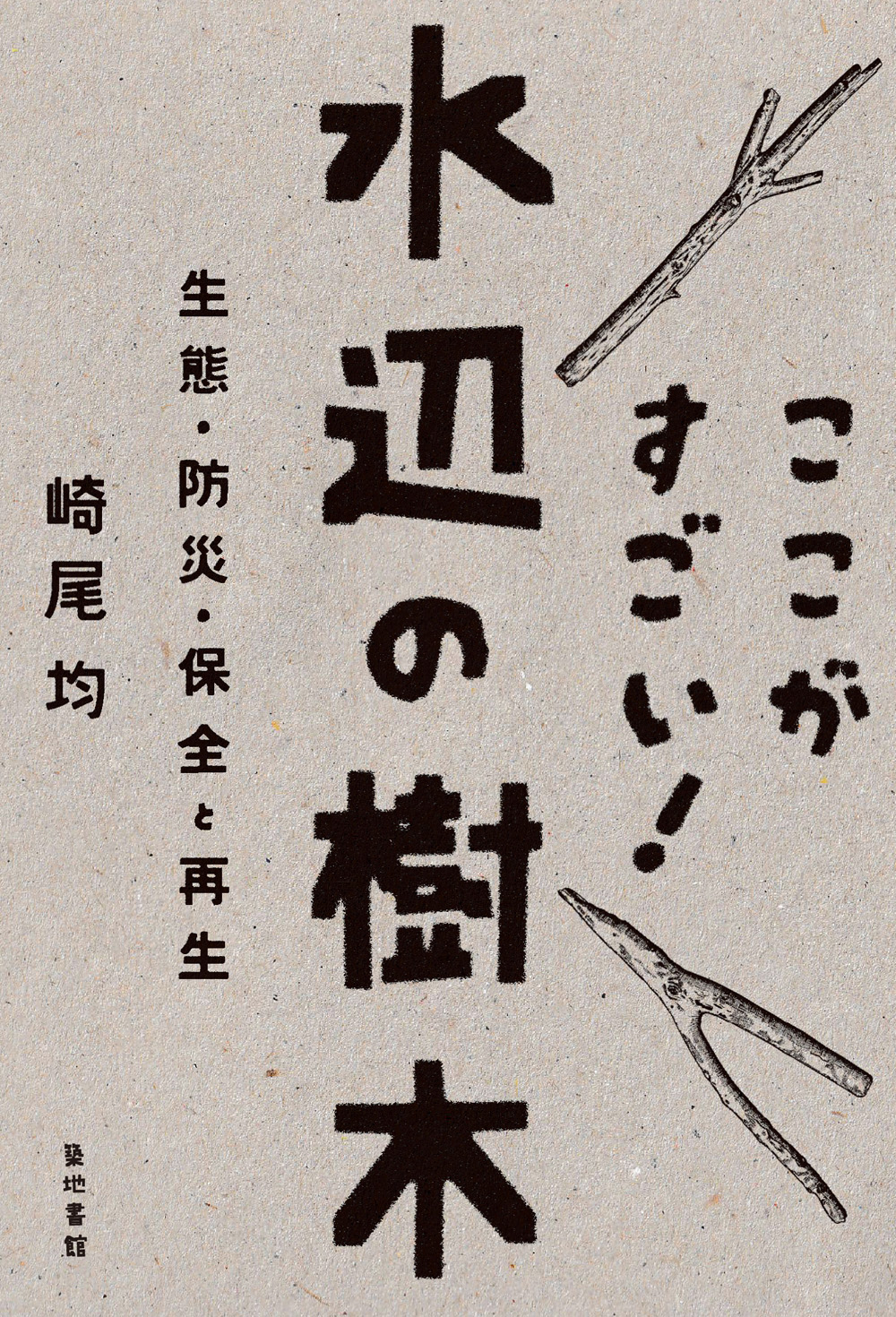マスが語る、川の記憶 水辺の生き物と森と人類のつながり

| ビル・フランソワ[著] 門脇仁[訳] 2,400円+税 四六判並製 292頁 2025年11月刊行 ISBN978-4-8067-1698-3 パリのセーヌ川からアマゾン源流の森まで。 水辺の生き物が教えてくれる生命の不思議と、自然環境と人類のつながり。 マスの一生を物語風に表現しながら、水辺に棲まう生き物たち(トンボ、イモリ、ナマズ、ウナギ、カエルなど)の興味深い生態を独特な感性とユーモアで語る自然科学ノンフィクション。 また、オウムの羽の色を変える「タピラージュ伝説」に迫るため、アマゾン流域の先住民の暮らしに潜入取材。 その謎に迫るとともに、自然と共存する先住民の暮らしから感じた自然への畏敬の念と、環境や生態系に対する危機感を伝える。 日本語版では、原著にはない日本の生き物についても加筆。 |
ビル・フランソワ(Bill Francois)
作家、生物物理学者。
EPSCI Paris(パリ市立工業物理化学高等専門大学)で魚類流体力学の博士号を取得。
海の生き物の生態や歴史を描いたエッセイ『Eloquence de la sardine : Incroyables histoires du monde sousmarin』(Fayard)は、
17カ国語に翻訳され、2冊目の著書『Le plus grand menu du monde: Histoires naturelles dans nos assiettes 』(Fayard) は、
フランス政府高等教育・研究・イノベーション省が年に1回優れた一般向け科学書に与える
「科学の醍醐味」賞の最終候補3冊に選ばれるなど、高く評価された。
自然科学的な知識と歴史上のエピソードを組み合わせ、
私たち人間を取り囲む自然の魅力へ目を向けさせる著述活動をおこなっている。
門脇 仁(かどわき・ひとし)
フランスの森と林業、生態学史、環境文化論を専門とする著述家、翻訳家、大学教員。
1996年、パリ大学人間生態学上級研究課程修了。
日本で初めてフランスの森林と林業を紹介した著作で知られる一方、大学や専門学校で環境学や外国語を担当。
また海外調査や講演活動もおこなっている。
著書に『広葉樹の国フランス──「適地適木」から自然林業へ』(築地書館)、
『エコカルチャーから見た世界──思考・伝統・アートで読み解く』(ミネルヴァ書房)、
訳書に『香りの起源を求めて──香水を支える植物18 の物語』(築地書館)、『樹盗──森は誰のものか』(築地書館)、
『エコロジーの歴史』(緑風出版)などがある。
Mail:hitoshi.kadowaki3@gmail.com
プロローグ 源流へ
命を託すマスたちの最期のバレエ
川からはじまる命の連なり
偏光メガネがくれた魔法
水を読む力との出会い
第1章 魚として
小さな卵に訪れる世界との出会い
マスたちのからだに残る水の記憶
ヒトは皆、かつて魚だった
しゃっくりに残る魚の記憶
第2章 変態
稚魚ファリオとトゥリュッタの旅立ち
恋するカゲロウと、川底で目覚める小さな命たち
カゲロウの奇跡の一夜
見えざる狩人、トンボの物語
水にとどまる生き物たちの進化論
オウムの羽に色を灯すカエルの毒
第3章 陰謀と共謀
学びの川で出会った第3の生き物
絵画に変わる貝
他者のからだを借りて命をつなぐ生き物たち
寄生生物が動かす生き物たちの相関図
第4章 水を分かちあう
夏を耐えるマスたち
川がつくる見えない国境
マスが語る、川の記憶と地質
コイとウサギの世界征服
第5章 流れに逆らって
マスたちの旅立ち
川を生きるか、海を越えるか
サケのしたたかな繁殖戦略
川をのぼるウナギの謎
消えゆくウナギと失われる自然の記憶
第6章 水を読む
トゥリュッタ、未知の川をゆく
セーヌ川の水中オリンピック
水を「読む」ことのレッスン
川の声を聴く
タピラージュ伝説を探す旅へ
第7章 楽園の儚さ
迷い鳥の旅路
川と森の逆転劇──アマゾン、生と死の境界へ
水の奥にひそむもの
ひげを振るう者たちと、夢の楽団
夜の水辺で、魚と模様を読む
足なきカゲロウと極楽鳥
第8章 世界でもっとも長い儀式
隠れる魚と、溶け込む魚の戦略
カエルの力を知る民
精霊と魚に導かれる、川辺の暮らし
アマゾンの恵みと精霊信仰にもとづく儀式
第9章 彩羽鳥(いろばどり)のことば
海から呼び戻される記憶
羽根色に秘められた宇宙の秩序
森を守り、文明に挑んだ男
命と引き換えに守られた森
第10章 ナマズ大臣
影に潜む知恵と、知られざる救いの手
エナウェネ・ナウェの祈りと闘い
自然破壊の影と失われゆく伝統
秘密は羽ばたきとともに森に溶ける
第11章 からっぽの貝殻の追想
記憶の川を求めて
都会に眠る川の記憶と古代からつづく水辺の暮らし
川が嘆いたとき
生態系と文化の喪失
変わりゆく川と生き物たち
第12章 キャビアあるいはチョウザメ
水の記憶と貝の時間
チョウザメの栄光と絶滅の軌跡
消えゆく魚と人間の忘却
真珠の鱗は夢に光る
第13章 終奏のマス
羽根と影とともに川は踊る
都市の片隅に息づく小川と命
マスとカゲロウの儚い共演
最後のマスを守る、カラスを連れた男
訳者あとがき
訳注
索引
命を託すマスたちの最期のバレエ
冬の最初の雨粒が、川に新しい水音を立てた。砂利のうえで水の流れがかさみ、水音もにぎわいだす。マスたちにとって、それはひとつの合図だ。ふた晩もまえからおたがい顔も合わせず、浅瀬をめいめいに陣取っていた。岸辺の近くに集まり、おなじ本能にしたがって、きっちりとおなじ場所で、いっせいに川底の砂利を掘って巣ごしらえをしていた。
水面(みなも)と水底(みなぞこ)のあいだで、マスたちはダンスをしている。月の光をかき乱さず、おなじ水あとを曳いて昇っていく。ずんぐりしたオスたちはかわるがわる身をひるがえし、メスたちはバレエのように次々とまえへでてくる。やおら尾びれをひと打ちし、みんなが向きを変えた。ワンペアずつで川底に戻り、激しく身をふるわせる。暗い水底で入り混じるのは、オレンジ色の卵、砂利、そして精子──。
魚たちは最期の息を吐くように、命を吐きだしていた。いちばん大きいマスは、北極海からまっすぐに南下してきて、夏至の日から何も食べていない。背にはアザラシの捕食から逃れたときの爪あとや、川の急流でついた傷あとが残っている。ぼろぼろになったひれを動かし、最後の性衝動で力をふりしぼり、身をそらせ、からみ合い、またそらせては生の鼓動に身をまかす。ときどき疲れ果てて岸辺に身を寄せるが、そのたびに不思議と気力を取り戻し、からだを揺さぶって戻っていく。
すぐ下流ではサケが何匹か、木陰にあたる土手の岩のうしろで息を切らしていた。この魚種はひと月まえに産卵を終えている。水位が上がって、海まで流されるのを待っている。険しい目と、ふしくれだったからだで、流れのなかを枯れた葉っぱのように漂っていた。海までたどり着く者はほとんどいないだろう。
岸からはそんな姿はひとつも見えなかった。水面は静かに流れ、月の光に染まり、雨粒がはね返っている。マスの勢いに水面がうねることもほとんどない。聞こえてくるのは、きらめきわたるせせらぎにほのかなトリルをつけ足す、ひかえめなトレモロだ。
ハンノキの根元で、目立たないようにしているサギがいた。首をたたんで、両肩のあいだにしまったままだ。その姿は灰色のマントをまとい、帽子に羽根飾りをつけ、黒い口ひげを生やした兵隊のように見える。すると今度は首を伸ばし、でっぷりしたマスの輪舞を見やり、そいつが自分の嘴(くちばし)の届くところまでやってくるなりゆきを待ちわびていた。
一撃は至近距離から繰りだされた。すぐさま羽を広げ、サギはマスを飲み込んで飛び去る。ふたつの生き物は、ぎこちない羽ばたきでいっしょになって上昇し、砂のうえに琥珀色の真珠を撒き散らした。しばらく旋回したかと思うと、木々のあいだに姿を消す。ガサガサという音を立て、森が彼らを包み込んだ。魚たちはまた忘我の、エクスタシーの境地へ。
川の音が戻ってくる。月は枝の巣のなかの卵のように、ふたたび丸くまどろんでいく。
川からはじまる命の連なり
読者は手に一冊の本をもっている。
それは紙でできている。紙は木でつくられる。木は森で生まれる。
さてその森は、何からできているだろうか。
この本のもとになる森の起源を、あなたはいま目撃したところだ。森はある冬の晩、川から命をさずけられ、川は魚に命をさずかった。
それは約2万年前、最後の氷河期の終わり頃だった。氷河があとずさりすると、真下にあった岩だけが残った。すっかり不毛の地。それでも石づたいを走る川には、サケ、シャッド、シートラウトなどがやってきた。海で育ったあと、こうした回遊魚は生まれた川に戻ってきて繁殖する。その旅は命を削るもので、多くは生き残れずに死んでいく。クマからサギにいたるまでの天敵にとって、弱った魚たちは絶好の獲物だった。
巣穴のなかにいる卵をはらんだ魚をたらふく食べるのである。魚たちが海で暮らしていたあいだ、たっぷり取り込んだ窒素とリン酸が、こうして土のなかへ撒き散らされ、陸地の内部を肥沃にしていく。すべての森はそこから生まれた。
こうして魚たちは、ほとんどの温帯地域の生態系ができるきっかけをつくった。その後、すこしずつほかの段取りも加わったが、そもそも大地のすべてを養う必須栄養素は海からきている。僕たちがここにいるのも、魚たちのおかげだ。
こういったすじがきは、自然界のいたるところに刻まれている。カナダの科学者たちが明らかにしたところでは、鳥の鳴き声がいろいろなのも、回遊魚の群れの多さと関係がある。そこで毎年春になると、クロウタドリやコマドリのさえずりで川全体がにぎわうことになる。
また、サケが大量に戻ってくる年には、木の幹の年輪が平均して1.5ミリ厚くなるため、材木の木目のあいだにもこのストーリーが刻まれる。
足もとの床や、まわりの家具の板面をよく観察するといい。その木目のすべてに、川とその住民である生き物たちの物語がしるされている。昆虫や水生植物、甲殻類、細菌など、魚のライフサイクルにひと役買ったおびただしい種族たちが、そこに足あとを残している。
あなたが読書しながら聴いているかも知れないバイオリンのメロディーは、それより古い生き物たちから返ってきたエコーだ。おそらく一九世紀に育ったカエデの木から生まれたもので、その木の音の波動は、特大チョウザメや銀色のワカサギ、そしていまは絶滅しているほかの動物たちが海を渡ったことではぐくまれた。だからその音楽は、彼らの運命にあやかっている。シューベルトの『鱒(ます)』を奏でるまでもなく!
本はふつう、紙に書かれたストーリーを伝える。今日あなたが手にしている紙をとおして、本はそこに刻まれたものをあなたに伝える。川に住む生き物たちは姿を変え、旅をし、奇妙な生をいとなんできたが、その内容はまさにこのページのなかにある。
数千億の窒素原子とリン原子が、遠くからやってくることもある。それは食物連鎖を経て、ザリガニや何世紀もまえの貝類とともに航海し、昆虫や鳥に乗って飛んできた。
だから驚かなくていい。章ごとのページとページのあいだにひそんでいた魚が水面に浮かんできて、何らかの秘密を打ち明けたとしても。それは本の過去がまた不意に姿をあらわしただけなのだから。
紙よ、水しぶきにご用心! あなたの忘れられた川に、いまからダイブするからね。
偏光メガネがくれた魔法
超能力を信じるだろうか。僕は子どもの頃、長いことそんなものはないと思っていた。
だがそれは、かなり変わったバースデープレゼントをもらうまでの話だった。
僕はその頃、すでにおもちゃ屋の「はかせコーナー」の棚にはほとんど手を出していた。双眼鏡、ミニ顕微鏡キット、さらには太陽黒点を観察するためのプレートつき段ボール箱まで。
でもこのときは、スポーツ用品店から届いた荷物だというのが梱包でわかった。薄くて軽いケースには、「偏光メガネ」と書いてあった。マニュアルには心がはずんだ。反射を取り除くことで、このメガネは水をとおして物を見ることができるというわけだ。
大満足だった。
水中の世界に魅了された。ほかの何もかもとおなじように、この世界は海とつながっていた。クジラ、タコ、金曜の夜の番組で紹介される遠くの群島、夏休みに探検する地中海の入り江──。
「水の世界」について考えるとき、川が頭に浮かんだことは一度もなかった。濁っていてアクセスしにくい川面のなかは、あまりワクワクしそうもなかった。ただ水辺としてはそこがいちばん近かったので、僕は川岸へと走り、この魔法のメガネを試してみた。何か特別なものが見つかるとは思ってもみなかったが──。
偏光メガネを鼻のうえにのせたとたん、ぶっ飛んで息が止まった。まるで水面がいきなり消え失せたようだ。そのあやふやなガラスの境界線が、このときから格好の道具になった。川底の砂の谷間では、小さな甲殻類が貝がらのあいだでキラキラ輝いている。もっと遠くには、そよぐ水草をいただいた岩場があった。泳ぐ魚はまるで、宙吊りにされながら突っ走っていくようだ。あっというまの2時間だった。
こんな見たこともない風景に、僕の目はくぎづけだった。夜になり、空が星のまたたきとコウモリの舞いとで縞(しま)模様をなすまで、いっこうに飽きることなく。
それからというもの、僕はずっと探しつづけてきた。水の流れをたえまなく、一つひとつ──。
どんな小さな溝にも、生き物たちが住んでいる。パリのセーヌ川の岸辺には、ノートルダム大聖堂のお膝もとで波打つ体長2メートル超えのナマズ。ポン・ヌフのしたには、エビや海綿動物が群がっている。
それをまんじりともせず見守ることなしには、もう夜をすごすことなどできやしない。車で橋を渡るときも、水のなかの出来事を想って夢見心地になり、二度に一度は橋の沿道に車体を突っかけてしまったものだ。
水のなかを覗けば、そこにはヨコエビ、イバラモ、レプトケファルス、トビケラなどがおびただしく息づく宇宙があった。どれも名前を聞いただけではかたちのわからない生き物だが、その存在はSF小説にもふさわしく、僕たちの知らないうちに目のまえで進化していく。
月並みに見える種でさえ、人にはいえない秘密をもっていた。目に見えないところで、マスはスキャンダラスな二重生活を送っている。カエルは用心深いコソ泥だし、遺伝学によればトンボは空飛ぶ恐ろしい海賊だ。
僕たちは動物を「友だち」だと思い、よく知っていると思っている。子ネコも子ブタも、動画のなかではアイドルだ。アフリカやアジアのカリスマ的な哺乳類のゾウは、絵本の『ぞうのババール』シリーズ以来僕たちの記憶に刻まれている。カクレクマノミの「ニモ」やシャチの「ウィリー」にいたっては、海の動物相まで身近にしてくれた。
では、川に住む生き物はどうだろうか。僕がこの本を書きはじめたのは、もっぱら彼らにまっとうなステータスを与えるためなのだ。
この見知らぬ世界を探検していたら、僕はじきにそれがまんざら知らない世界でもないと気づいた。ヒトのほうも原人初期から何百万年にわたって、この世界で進歩してきた。
水生動物は僕たちに食べ物を与え、服をほどこし、イマジネーションを刺激してきた。人類の偉大な都市はサケと出会える川のほとりに築かれ、ルーブル美術館のいちばん有名な絵画は、淡水産のムール貝から生まれた。また僕たちみんなの先祖は、かつてヒルによって命を救われたことがあるのだ。
水がもっぱら資源として使われ、水路がつくられ、「遊泳禁止」の立て札で囲われるようになるまで、水辺は妖精や怪物、ファンタジックな生き物に出会える暮らしの場だった。
彼らは見えなくなったのではない。僕たちが彼らの見方を忘れているだけだ。
水を読む力との出会い
ある晴れた朝、僕はサケをよく見ようと身を乗りだした。すると大きな水しぶきが聞こえた。偏光メガネは鼻先からすべり落ち、深い水の底へと消えて拾いだせなくなった。
もちろん、すぐに新しいのを手に入れた。
その夏、僕はさらに多くの動物に感動することとなる。川のマスや湖のザリガニを観察し、セーヌ川のおだやかな支流で初めてカワカマスを見た。ところが休暇から戻って初めて、視界に異常な反射があることに気づいた。そこでメガネをひっくり返してみたところ、逆さまに組み立てていたことに気づいた。それはまったく機能していなかったのだ。
なのにこうした生き物たちが、僕にはよく見えていた。それまで何カ月も、僕は生き物たちをよく観察していた。そのあいだに「水を読む」ことを学んだので、もうそのためのメガネは必要なくなっていたのである。
「水を読む」は、もともとフライフィッシングのことばだ。水面があらわすサインを読み取って、水のなかに隠れている生き物を見ぬく技術を指している。いくつかの渦、わずかな揺らぎ、そして微妙な感性の遊びをとおして、僕たちの脳は動物を思い浮かべる。淡水生物を観察することで、僕の目は彼らに慣れ、彼らの世界を読みときはじめていたのだった。
もっともっと見たい。そんなふうに思って、科学者、漁師、芸術家と会ってきた。彼らは目に見えないものをとらえる方法、とくにそれを理解する方法を僕に教えてくれた。
水に命を宿らせ、そこに住む生き物たちを僕たちにも見えるようにしてくれる、こうした眼差しに立ち返る必要がある。そのため僕は、世界中の川を旅し、水辺環境と調和しながら生きつづける最後の文明を追った。
そしてそんな僕の探求は、アマゾン中央部の、水路とともに日々の暮らしを送る孤立した部族へとつながっていく。
彼らは僕に、夢の水面下に隠れている生き物の見つけ方を教えてくれた。それもいくつかの不思議な経験を織り交ぜながら。また彼らは、環境問題のことになると驚くほど現代的で、自然とのつながりについていろいろなことを教えてくれる。
その能力はあまりに強烈だ。僕の生き方を、また何よりも、水の物語に対する僕のとらえ方をすっかり変えてしまった。そして今度は、僕がそれを伝えたいと思うようになった。
そんなわけで、水を読むことを学んだあとには、ごくあたりまえにそれを書きたいと思った。川がわれわれに伝えようとしていることを、皆さんと分かち合うためだ。
足を水にひたしたり、偏光メガネをかけたりはせずに、水中の宇宙へのダイビングにご招待しよう。この本全体で、僕たちは不死のウナギや魔法のカエルといっしょに泳いだり、カゲロウのダンスを目にしたり、ナマズの鳴き声を聞いたりする。またこうしたすべての生き物が教えてくれることを、いまから見ていくことになる。
彼らの生態について、僕たち自身について、そして僕たちの避けられないかかわりあいについて。水生生物の多様性がかつてないほど貴重になっているいま、彼らのメッセージを知ることは何より大切だ。
というわけで、僕らはみんな川を抱えて生きている。それは気持ちの切り替えの場だったり、子どもの頃の思い出の場だったり、または景色の一部だったりする。
この本を通じて、生き物が住みつく場所、かけがえのない命がやどる場所について、皆さんが「目からウロコ」とならんことを!
「科学というのは何よりもまず物語なのです。私たちを驚かせ、夢見させ、感情を揺さぶる物語。人は自分が知っているもの、夢を与えてくれるものを好きになるのだと思います。そして好きになったものを守るのです」
フランスのテレビ局「France」で、著者ビル・フランソワはそう語っている。
本書のフランス語オリジナル版La truite et le perroquet(Albin Michel 刊)の発表直後におこなわれたインタビューでのことである。
生物物理学者、作家、科学コミュニケーターと多彩な顔をもつ著者だが、その仕事の核心がこの言葉には窺える。物語るという行為には、彼の基本的な立ち位置やヴィジョンが表れているからだ。
そしてフランソワの著作のなかで、この言葉をもっともわかりやすく、効果的に実践しているのが本書である。
セーヌの岸辺から、大西洋の海を隔てたアマゾン流域の生態系へ──。ある春の宵に生まれたファリオとトゥリュッタは、どこまで泳いでも生まれ故郷と似たり寄ったりの障壁によって遡上を阻まれる水環境の現実に出くわし、もはや生存の道が閉ざされていることを知る。
一見かかわりをもたないような、遠く離れた物象どうしの関係性を読み解くことを、ネイチャーライティングでは「コネクティビティの探究」と呼ぶ。古くはファーブルやヴェルヌやカーソン、現在ならアラン・コルバンやスザンヌ・シマードまで、類例は山ほどある。単なる比喩的なつながりではなく、システマチックな対比や統合によって共通の本質を見抜き、読者を導いていくところがその特徴だ。
また、こうした自然の読み解きが説得力をもつためには、環境知性へのやむにやまれぬ欲求や、ある種シャーマン的な特権も必要になる。
著者フランソワの場合、「水を読む」という特殊技能、暗黙知がそれだった。
「水を読む」ことができなければ、物語の水先案内人はつとまらない。フランソワがみずからの来歴をつまびらかにしたことはないが、子ども時代に手にした「偏光メガネ」というパワフルなきっかけ以来、「水を読む」ことへの情熱と、それがもたらした成果によって人生を切り拓いてきたことは間違いない。
ちなみにその暗黙知(つまり感覚としての知)が心と身体になじんでくるにつれ、やがて道具を必要としなくなったというくだりもまた興味深く、右に挙げた多くの語り部たちにも共通する彼の「見者(ヴォワイヤン)」ぶりを覗かせている。
さらにそんなストーリーテラーとしての資質をよく映しているのが、本書のいたるところに見られる感覚表現である。その大半は人間以外の生き物の感覚でありながら、人間の感覚にそっくり置き換えられている。
たとえば、レモンシャーベットをわれわれが好むのは、魚だった頃のなごりだという。その理由は、水のなかの酸性が呼吸による二酸化炭素に由来していることから、水中で獲物を探すのに酸っぱさの感覚が役立ったというわけだが、濃度やら受容体の違いやらのさまざまな議論をスキップし、「これでいいのだ」とばかり飛躍する文体には、多少のとまどいを感じる読者も多いだろう。
ところが実際、レモンの小片を川にまいて魚をおびき寄せる釣り人たちもいる。著者がことあるごとに鼻先を水面に突っ込んだり、濁り水のなかで目を凝らしたりしながら、ヒトの体感で水辺の生き物の感覚に近づこうとするのは、じつは経験にも理論にも裏打ちされたサイエンスリテラシーなのである。
もちろん、夢と現実の境界に踏み込む物語であるからには、ときに誇張もあれば演出もある。『鳥獣戯画』を思わせるパロディー、翻案もある。だが、それをもってこの本を非科学的と決めつける読者はおそらくいないだろう。自然誌と修辞法を並行して論じたアリストテレスのように、ビル・フランソワも言葉によって人間の想像力をリードする務めをみずからに課しながら、真理を、世界を探求している。
緑の茂みの奥に偶然見つけた池のほとりで、いま訳者はこのあとがきの草稿を書き終えたところだ。
目のまえの水面をヌートリアが滑るように横切っていく。ビーバーに似たこの齧歯目の動物は、かつて毛皮を採るために南米から移入されたが、いまでは害獣としての扱いを受けることも多い。本書に出てきたチョウザメや極楽鳥とおなじく、われわれ人間の都合に生殺与奪を握られてきた生き物である。
こぼれた水を嘆いても始まらないという人がいる。だが努力と叡智しだいでは、こぼれた水も盆に返すことができる。いまわれわれに問われているのは、「自分が知り、好きになったものを懸命に守る」という、人間本来の欲求に根差した修復と創造の営みではないだろうか。本書がすこしでもその後押しとなるなら、訳者としてこれほど嬉しいことはない。
(後略)