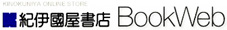立体と鏡像で読み解く生命の仕組み ホモキラリティーから薬物代謝、生物の対称性まで
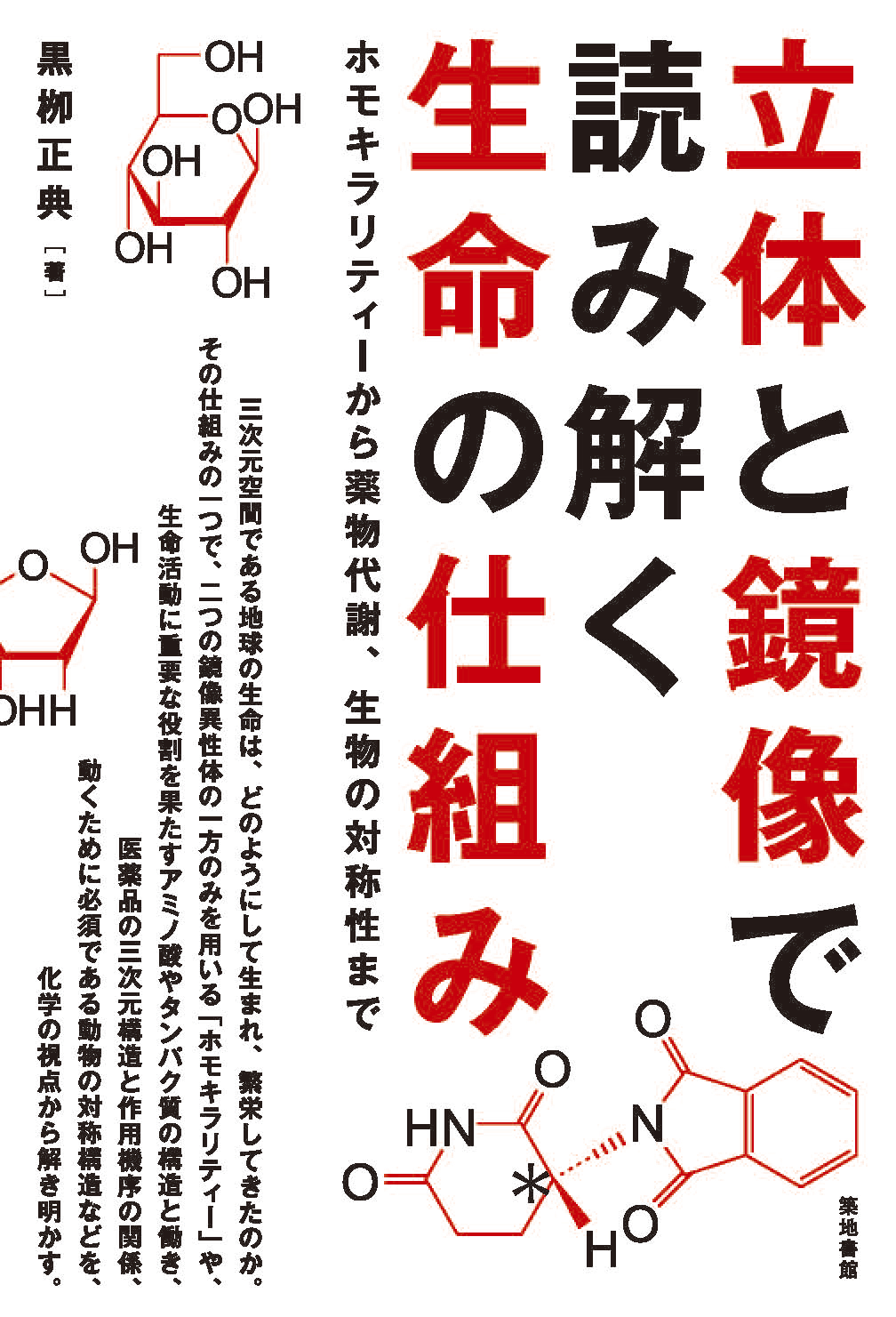
| 黒栁正典[著] 2,400円+税 四六判並製 224頁 2024年12月刊行 ISBN:978-4-8067-1675-4 地球の生命は、L-アミノ酸のみによって構成されている 「ホモキラリティー」という現象に助けられて誕生し進化してきた。 地球上で繁栄する生命は、どのようにして生まれ、繁栄してきたのか。 その仕組みの一つであるホモキラリティーや、 生命活動に重要な役割を果たすアミノ酸やタンパク質の構造と働き、 医薬品の三次元構造と作用機序の関係、 動くために必須である動物の対称構造などを、化学の視点から解き明かす。 |
黒栁正典(くろやなぎ・まさのり)
専門は生薬学、天然物有機化学、有機立体化学。
1968年、静岡県立静岡薬科大学(現:静岡県立大学薬学部)修士課程修了。
1968年、国立衛生試験所(現:国立医薬品食品衛生研究所)研究員。
1978年、薬学博士学位取得(東京大学)。
同年、静岡県立大学薬学部教員。
1982年、米国コロンビア大学留学。
1998年、広島県立大学生命資源学部(現:県立広島大学生命環境学部)教授。
2009年、同大学名誉教授。
2012~2024年静岡県立大学客員教授。
著書に『植物 奇跡の化学工場──光合成、菌との共生から有毒物質まで』
『人の暮らしを変えた植物の化学戦略──香り・味・色・薬効』(築地書館)、
『健康・機能性食品の基原植物事典』(中央法規、分担執筆)。
はじめに
第1章 生命誕生と進化
生物の定義
生命誕生は謎だらけ
生命誕生には化学進化が必要だった
ユーリー=ミラーの実験
生命誕生の場、熱水噴出孔
パンスペルミア説──地球外生命の痕跡を求めて
生命誕生後の生物の進化
コラム1 共生
コラム2 人類の大いなる旅路
第2章 ホモキラリティー
生命活動に必須のホモキラリティー
ホモキラリティーの起源は今でも謎
2つの起源説 / 宇宙におけるホモキラリティーの必然性
ホモキラリティー完結に必須の不斉増殖
ホモキラリティーの成立過程
ホモキラリティーが起こらなければ地球生命は誕生しなかった
第3章 有機立体化学の歴史
次元と時間の考え方
時間の概念
鏡の世界と右左
有機化学は無機化学の後を追って発展した
幸運を逃さなかったパスツール
有機化合物における中心性不斉の概念
不斉炭素とは
コラム3 「鏡の国」のミルクの味
コラム4 セレンディピティー
第4章 有機立体化学の理論
不斉炭素と光学活性
鏡像異性体は旋光度で区別する
鏡像異性の表記法
D/L表記 / R/S表記
ジアステレオマーと鏡像異性体の関係
不斉炭素を持たない鏡像異性体
軸性不斉誘導体 / 面性不斉誘導体
第5章 生物におけるホモキラリティーの働き
アミノ酸がつながってタンパク質が作られる
アミノ酸の構造と働き
天然の糖はD-系列
糖の環状構造
デンプンとセルロースは似て非なるもの
生命活動における糖類の役割
核酸は高度に不斉
その他生体成分の立体化学
ステロイド誘導体 / テルペノイド誘導体 / 脂質関連化合物
コラム5 D-アミノ酸
第6章 鏡像異性がヒトの体に与える影響
サリドマイド薬害が薬の未来を変えた
体内に取り込まれた薬の運命は?
医薬品の鏡像異性体は生理活性が異なる
香りや味は鏡像異性体で異なる
コラム6 ドラッグリポシショニング──既存薬の転用
第7章 目的の立体配置を持つ医薬品の供給
鏡像異性体の一方のみを得る方法
光学分割
入手容易な鏡像異性体からの化学的誘導──キラルプール法
不斉を持たない出発物質からの不斉合成
植物や微生物の力を借りる
植物や微生物の生産物を利用 / 生物の力を借りる不斉合成 / 植物組織培養による方法 / 微生物培養による生産
第8章 生物の対称性
動物は基本的に対称構造
ヒラメとカレイ / 昆虫は左右対称 / シオマネキ / 巻貝 / 右利き左利き
動かない植物は対称構造がいらない
植物の部分は基本的に対称構造 / 蔓性植物の蔓の巻き方
ネジバナは右巻き? 左巻き?
コラム7 トラック競技は反時計回り
コラム8 ネジやツマミ、道具の回転方向
コラム9 貝毒の話
おわりに
用語解説
参考文献
索引
我々が生活している世界は、縦・横・奥行の3つの方向から成り立つ三次元の空間である。そのため私たちは朝、目が覚めれば起き上がり、洗顔し朝食を食べて勤めや学校へ出かける。人間はもちろん、イヌやネコも自由に動き回り、鳥や虫たちも自由に飛び回っている。植物たちも前後左右上下に枝葉を伸ばして、花を咲かせ果実を実らせている。
このように我々地球上の生物が空間的に広がって活動できるのは、世界が三次元空間だからである。二次元空間ではこのような動きを行うことは不可能である。景色を写真やテレビなどの画面で見ても何か物足りない感じがするが、それは三次元世界が画像という二次元の形で表現されているからである。我々が住む世界が二次元空間で平面の中でしか行動できないとしたら、景色は点やさまざまの長さの直線としてしか見ることができない。日々の生活はまったく面白みのないつまらないものになってしまうだろう。
スポーツでは、走る、跳ぶ、投げる、打つ、泳ぐことで三次元の空間を存分に利用することにより迫力あるプレーが成り立っており、大谷翔平の豪快なホームランも楽しむことができる。これが平面だけの動きしかできないとしたらやはり迫力のないつまらないものになってしまう。理論物理学の世界では三次元以上の多次元の空間があるといわれているが、それがどんなものかは我々門外漢には知ることができない謎である。ただ、三次元空間に四次元目として時間を加えた四次元時空という概念がアインシュタインの特殊相対性理論で用いられ、我々の住むこの世界に適用されており、一般に受け入れられている。もしも時間がなかったら物事の動きというものが止まってしまうことになる。一体どんな世界になってしまうのだろうか。時間のない世界も到底考えることができない。
我々の住む世界が三次元空間であるために、思わぬところでいろいろな現象に遭遇することがある。地球上の生物の生理現象をコントロールしている、生命維持に最も重要な生体成分であるタンパク質はアミノ酸で構成されている。そのアミノ酸は三次元構造を持っており、タンパク質は例外なくL-アミノ酸のみで構成されている。L-アミノ酸の鏡像異性体(鏡に映した構造)であるD-アミノ酸が同様に用いられる可能性もあるのに、地球上の生物ではどうして一方の鏡像異性体であるL-アミノ酸だけを用いているのか疑問が湧く。当然、一方のアミノ酸のみを用いることが生物の生存にとってメリットがあるためであることは間違いない。しかし、L-アミノ酸とD-アミノ酸のうちL-アミノ酸が選択されることになった理由はわかっていない。いつどんな理由でL-アミノ酸が選ばれたのかは生命誕生と並んで今なお解決されない謎である。
アミノ酸だけでなく糖や核酸はじめ地球の生物の生命活動に関わる物質のほとんどは三次元の構造を持っており、2つの鏡像異性体の一方のみが用いられている。このような現象は生命のホモキラリティー(homochirality)と呼ばれている。ホモキラリティーという現象が維持されることで地球上に生命が誕生し進化し、繁栄することができたのである。
我々の知る限りでは、奇跡的に誕生した地球の生物以外この宇宙に生物は存在しない。そんな地球の生命がいかにして誕生したのかは最大の謎である。生命の起源は地球にあるのか、地球外からやってきたのかなどいろいろな議論があるが、いまだ結論は得られていない。しかし、原始的な生物から植物や動物などの生物への進化については多くのことが明らかになっている。生命誕生とその進化にはホモキラリティーが必然であったと考えられる。地球生命は植物の光合成に支えられていることなどを含め生命誕生とその後の進化の歴史を第1章で眺めてみる。
生物が生きていくために、体内ではタンパク質や核酸などの高分子が関与して代謝に関連する有機化学反応が行われている。この中心となる有機化合物がアミノ酸や糖、核酸などである。しかも、タンパク質の素材となるアミノ酸はL-アミノ酸だけが用いられ、自然界に存在する糖は基本的にD-グルコース、D-ガラクトース、D-リボース、D-デオキシリボースなどD-系列のものが生命活動に用いられている。このような生物が持つ独特のホモキラリティーという現象について第2章で述べる。
アミノ酸や糖だけでなく多くの有機化合物は三次元構造を持っており、お互いに実像と虚像の関係にある鏡像異性体が存在する。有機化合物の鏡像異性の理論に関する発見の歴史は比較的新しく、ルイ・パスツールなどの若き科学者による貢献が大きい。鏡像異性という現象発見の歴史について第3章で述べる。
三次元構造を持つ生理活性物質の鏡像異性の関係を論じていくためには、物質の三次元構造を二次元の紙面で議論する必要があり、規則や約束事が必要となる。そのために有機化学の一分野として有機立体化学が確立してきた。アミノ酸や糖の鏡像異性を表示するためにはD/L表記が用いられ、その他の多くの光学活性物質の鏡像異性表示にはR/S表記が用いられる。光学活性の理屈や立体表示の規則について第4章で述べる。専門外の読者には理解が難しいかもしれないので読み流していただいても問題ない。
タンパク質は酵素や化学物質受容体、筋肉、皮膚などとして働いており、地球の生物にとって最も重要な生体成分である。そのタンパク質を構成するアミノ酸はすべてがL-型である。遺伝子であるデオキシリボ核酸(DNA)を構成する糖であるデオキシリボースや、タンパク質に結合してその機能を修飾する各種の糖はすべてがD-型である。これらアミノ酸や糖は厳しくホモキラリティーを維持している。その他にもホルモンや脂質などの生体成分もホモキラリティーを維持している。アミノ酸や糖など生命活動に重要な役割を持つ生体物質について第5章で解説する。
医薬品開発が進み、特に新規の合成医薬品が広く用いられるようになり我々の平均寿命は大幅に改善されてきたが、その半面多くの薬害も問題になっている。医薬品は有効性と共に有害な副作用を持つことがあり、医薬品の鏡像異性が関係している場合がしばしば見られる。特にサリドマイドの鏡像異性体による薬害の問題は有名で、この事件をきっかけに一方の有効な鏡像異性体のみを医薬品として供給することが望まれるようになった。また、自然界には香り物質や味覚物質が存在するが、香りや味覚では化学物質の鏡像異性の違いが大きく影響することが知られている。鏡像異性体と生理活性の関係について第6章で述べる。
有機合成技術が大きく発展し多くの合成医薬品が供給される現在では、医薬品の鏡像異性体では生理活性に違いがあることが常識となり、医薬品として求められる鏡像異性体を供給することが当たり前となっている。そのための研究が行われ技術が進歩してきた。特定の鏡像異性体を供給するための方法について第7章で述べる。
動物の外形はほとんど左右対称の形をとっているのに、植物の全体的な姿はあまり左右対称にはこだわっていないような印象を受ける。しかし植物の部分である花や葉などの形になると対称形を持っているのが普通である。一方で巻貝や植物の蔓の巻き方など対称性を持たない形がしばしば見られる。生物の対称性に関して第8章で述べる。
本文中で述べなかった興味深い関連事項についてはコラムで記載しているので読んでいただきたい。また難解と思われる専門用語は巻末に解説しているので参考にしていただきたい。
アミノ酸や糖などの生体成分が三次元構造を持つために起こるホモキラリティーという現象は、専門性が高く難解な点もあると考えられるが、我々生物誕生と進化にとって大事な現象であることを理解していただければ幸いである。