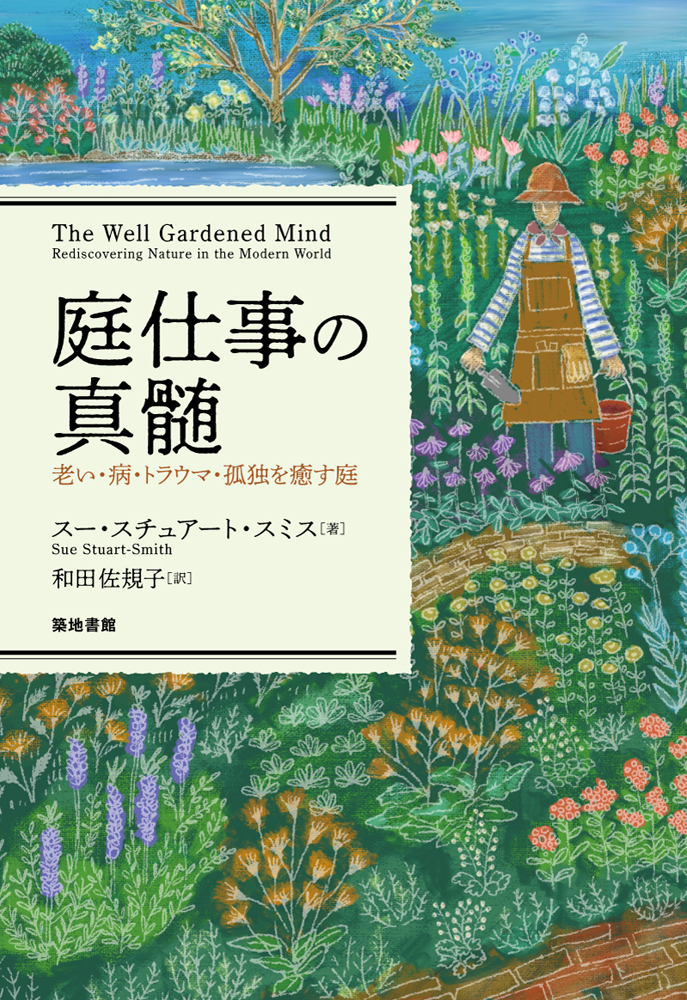脳科学で解く心の病 うつ病・認知症・依存症から芸術と創造性まで
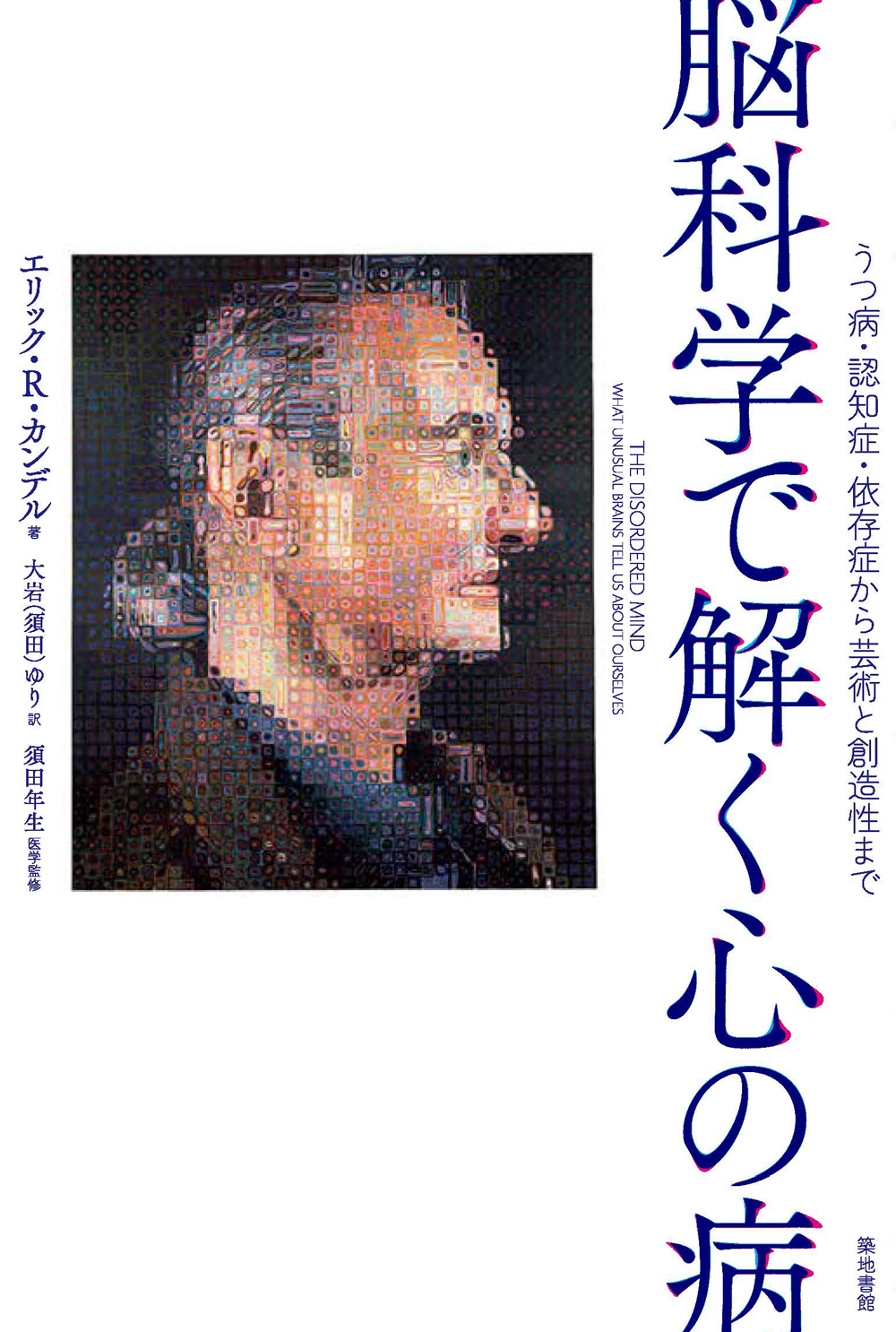
| エリック・R・カンデル[著] 大岩(須田)ゆり[訳] 須田年生[医学監修] 3,200円+税 四六判上製 360頁 2024年3月刊行 ISBN978-4-8067-1664-8 私たちの脳内には860億個のニューロンがあり、 ニューロン同士が正確に繋がることで、コミュニケーションを取っている。 ニューロンとニューロンの繋がりは、ケガや病気によって変化してしまう。 また、成長の過程で繋がりが正常に発達しなかったり、全く形成されなかったりすることもある。 そうした事態に陥ると、脳機能に混乱が生じて、 自閉スペクトラム症、うつ病、統合失調症、パーキンソン病、 依存症、心的外傷後ストレス障害(PTSD)など 精神疾患の原因となる。 こうした脳の混乱がどのように生じるかを研究し、その治療法の可能性を探ることは、 私たちの思考、感情、行動、記憶、創造性がどのようにして脳で生み出されているのか、 その解明にも繋がっていく。 神経科学者たちの研究成果、精神疾患の当事者や家族の声、治療法の歴史を踏まえながら、 ノーベル賞受賞の脳科学の第一人者が心の病と脳を読み解く。 2024/5/18(土)日経新聞書評欄で紹介されました。 筆者は池谷裕二氏(脳研究者)です。 |
エリック・R・カンデル(Eric R. Kandel)
1929年、ウィーン生まれ。前コロンビア大学フレッド・カブリ冠教授、ハワード・ヒューズ医学研究所上級研究員。
学習と記憶の研究で2000年ノーベル生理学医学賞を受賞。
著書『In Search of Memory: The Emergence of a New Science of Mind』でロサンゼルス・タイムズ・ブックプライズを受賞。
『The Age of Insight : The Quest to Understand the Unconscious in Art, Mind, and Brain, from Vienna 1900 to the Present』
(須田年生/須田ゆり訳『芸術・無意識・脳──精神の深淵へ:世紀末ウィーンから現代まで』九夏社、2017年)
でオーストリア最高の文学賞であるブルーノ・クライスキー賞受賞。
その他の著書は『Reductionism in Art and Brain Science: Bridging the Two Cultures』
(高橋洋訳『なぜ脳はアートがわかるのか──現代美術史から学ぶ脳科学入門』青土社、2019年)など。
また、脳神経科学の標準的な教科書である『Principles of Neural Science』
(『カンデル神経科学 第2 版』メディカル・サイエンス・インターナショナル、2022年)の主要な著者でもある。
大岩(須田)ゆり子[おおいわ・(すだ)・ゆり]
科学医療ジャーナリスト。翻訳家。
朝日新聞社科学医療部専門記者(医療担当)などとして医療と生命科学を中心に取材・執筆し、
2020 年4 月からフリーランスに。
同社在籍中に執筆した連載「清原和博、薬物依存と向き合う」は2022 年、
「依存症問題の正しい報道を求めるネットワーク」のグッド・プレス賞受賞。
須田年生(すだ・としお)
シンガポール国立大学医学部教授、熊本大学国際先端医学研究拠点卓越教授。
臨床医として勤務した後、幹細胞・発生学の基礎研究に専念するようになる。
現在はシンガポールと日本を行き来しながら研究を続ける。慶應義塾大学名誉教授。
まえがき
第1章 脳障害からわかる人類の本質
脳神経科学と精神医学のパイオニア
ニューロン──脳の構成要素
ニューロンの秘密の言語
精神医学と脳神経科学の隔たり
脳障害に対する現代の研究手法
遺伝学
脳イメージング
モデル動物
精神障害と神経障害の隔たりを埋める
第2章 人類のもつ強力な社会性──自閉スペクトラム症
自閉スペクトラム症と社会脳
社会脳の神経回路網
自閉スペクトラム症の発見
自閉スペクトラム症とともに生きる
自閉スペクトラム症における遺伝子の役割
コピー数の変異
デノボ変異
突然変異の標的となる神経回路
モデル動物からわかる遺伝子と社会的行動の関係
今後の展望
第3章 感情と自己の統一感──うつ病と双極性障害
感情、気分、自己
気分障害と現代精神医学の起源
うつ病
うつ病とストレス
うつ病に関与する神経回路
思考と感情の断絶
うつ病の治療
薬物療法
精神療法──話す治療
薬物療法と精神療法の組み合わせ
脳刺激療法
双極性障害
双極性障害の治療
気分障害と創造性
気分障害の遺伝学
今後の展望
第4章 思考、決断、実行する能力──統合失調症
統合失調症の主な症状
統合失調症の歴史
統合失調症の治療
生物学的治療法
早期介入
素因となりうる解剖学的異常
統合失調症の遺伝学
欠失した遺伝子
過剰なシナプス刈り込みを引き起こす遺伝子
統合失調症における認知症状のモデル
今後の展望
第5章 自己の貯蔵庫である記憶──認知症
記憶の探求
記憶とシナプス接続の強度
加齢と記憶
アルツハイマー病
アルツハイマー病におけるたんぱく質の役割
アルツハイマー病の遺伝学的研究
アルツハイマー病のリスク因子
前頭側頭型認知症
前頭側頭型認知症の遺伝学的研究
今後の展望
第6章 生来の創造性──脳障害と芸術
創造性の展望──〈芸術家〉
〈鑑賞者〉
創造的なプロセス
創造性の生物学的基盤
統合失調症の人の芸術
プリンツホルン・コレクションの統合失調症の名匠たち
サイコティック・アートの特徴
サイコティック・アートが現代美術にもたらした影響
他の脳障害と創造性
自閉スペクトラム症と創造性
アルツハイマー病の人の創造性
前頭側頭型認知症の人の創造性
生まれながらに備わっている創造性
今後の展望
第7章 運動──パーキンソン病とハンチントン病
運動系の驚異的な技能
パーキンソン病
ハンチントン病
たんぱく質折りたたみ異常に起因する疾患の共通点
たんぱく質の異常な折りたたみに関与する遺伝子研究
今後の展望
第8章 意識と無意識の感情の相互作用──不安、PTSD、不適切な意思決定
感情の生物学的基盤
感情の解剖学
恐怖
恐怖の古典的条件づけ
不安障害
不安障害の治療
意思決定における感情の役割
倫理的な意思決定
サイコパスの生物学的基盤
今後の展望
第9章 快楽の原理と選択の自由──依存症
快楽の生物学的基盤
依存症の生物学的基盤
依存症の研究
他の依存症
依存症の治療
今後の展望
第10章 脳の性分化と性自認
解剖学的な性
ジェンダーに特異的な行動
ヒトの脳における性的二型
性自認
トランスジェンダーの子どもや思春期の若者
今後の展望
第11章 今も残る脳の大いなる謎──意識
心についてのフロイトの考察
意識についての認知心理学的考察
意識の生物学的基盤
グローバル・ワークスペース
相互関連か因果関係か?
意識の生物学的基盤に関する総合的な展望
意思決定
精神分析と新しい心の生物学
今後の展望
むすびの言葉──一巡してまた初心にかえる
謝辞
訳者あとがき
注
索引
私は生涯、脳の働きと、人類が行動する際の動機について理解しようと努めてきた。ヒトラーがウィーンを占領した直後に国外へ逃避したという少年時代の体験から、人類の実存に関連する大きな謎の一つに心を奪われるようになった。地球上でもっとも発展し、洗練された文化をもつ社会が、どのようにして突然、悪に向かって突き進むことができたのだろうか? 倫理的なジレンマに直面した人は、どのように選択をするのだろうか? 分裂した自己は、専門知識を備えた人々との相互作用によって癒やされるのだろうか? 私はこういった難問に取り組み、解答を得たいと願って、精神科医の道を選んだ。
しかし、心の問題がいかに難解であるかを認識するにつれ、科学的な研究でもっと明確な答えが得られる問題に目を向けるようになった。非常に単純な動物の、ごく少数の神経細胞(ニューロン)に焦点をあてて研究し、やがて学習や記憶の基本的なプロセスのいくつかを発見した。私自身、研究を大いに楽しんできたし、他の人からも十分に評価してもらった。ただし、宇宙でもっとも複雑な存在である人類の心の探求において、私の発見はほんの小さな進展をもたらしたにすぎないことは認識している。
心についての探求は、人類の誕生以来、哲学者や詩人、医師たちを魅了してきた。デルフォイのアポロン神殿の入り口には、「己を知れ」という言葉が刻まれている。ソクラテスやプラトンが最初に心の本質を考察して以来、あらゆる時代の思想家たちは、人類を人類たらしめている思考や気持ち、行動、記憶、創造力を理解しようと真剣に取り組んできた。近代までは、心の探求は哲学の領域に限定されていた。それを如実に表したのは、17世紀のフランスの哲学者ルネ・デカルトの、「我思う、故に我あり」という言葉だ。近世哲学の道しるべとなったデカルトの宣言の意味するところは、人類の心は身体とは別にあり、身体とは無関係に機能する、という点にある。
17世紀以降の重要な進展の一つは、現実はデカルトの宣言の逆であった、と認識されるようになったことだ。「我あり、故に我思う」のが実際なのだ。この認識の転換は20世紀後半に起こった。哲学者ジョン・サールやパトリシア・チャーチランドらが主導した哲学の学派が、心の科学である認知心理学と融合し、さらには両者が脳の科学である脳神経科学と融合したことでもたらされた。その結果、心に関する新たな生物学的な研究方法が誕生した。それまでとは異なる、心についての新たな科学的研究が前提とするのは、ヒトの心の動きは脳の一連のプロセスから生じるという原則である。脳は驚くほど複雑なコンピューターだ。我々が外部世界をどのように知覚するのかを左右し、内的な経験を生成し、行動を制御する。
ヒトの身体的形態の進化に関する知的探求は、チャールズ・ダーウィンの1859年の洞察から始まった。新しい心の生物学は、ヒトの進化についての探求の最終段階に位置づけられる。ダーウィンは『種の起源』で、ヒトは全能の神によって創造された他の動物とは異なるユニークな存在ではなく、より単純な動物の祖先から進化した生物である、という見解を披露した。そして、ヒトの行動が本能に基づく行動と学習に基づく行動の組み合わせであるという点も、より単純な動物の祖先と共通していると指摘した。ダーウィンは、1872年の『人及び動物の表情について』でこの考えをさらに精巧に練り上げ、より革新的で深淵な考えを提示した。人類の精神的な活動のプロセスも、身体の形態的な特徴と同じように、動物の祖先から進化したという。つまり、ヒトの心は霊的な存在ではなく、物理的な用語で説明することができるというのである。
私を含め、脳科学者はすぐに気がついた。身体的な危害や、群れの中での社会的な地位の低下といった状態に対して生じる恐怖や不安など、ある意味でヒトと似た感情(情動)をより単純な動物がみせるなら、動物でヒトの感情の性質を研究できるはずであると。その後、ダーウィンが予測したように、原始的な形態の意識も含め、ヒトの認知機能ですら動物の祖先から進化したことがモデル動物による研究で明らかになった。
精神的な活動のプロセスにおいて、ヒトがより単純な動物と共通する特徴をもっているために、ヒトの心の働きの根本について動物を使って研究できるのは幸運なことだ。なぜなら、ヒトの脳は驚くほど複雑だからだ。中でも自己についての認識はもっとも複雑で、またもっとも神秘的である。
自己認識は、自分は何者なのか、なぜ存在するのか、という疑問を抱かせる。人類の起源について語っているさまざまな創造神話は、宇宙のあり方や、その中で人類がどのように存在するのかをきちんと説明したい、という人類の欲求から生まれたものだ。自らの存在にまつわる疑問への答えを探し求める行為そのものが、我々を人類たらしめている重要な要素である。ニューロンの複雑な相互作用がどのように意識や自己認識を生じさせているのだろうか。これは、脳科学における最大の未解決の謎だ。
どのようにして脳内の物質から人類の本質的な性質が生じるのだろうか。脳内には860億のニューロンがある。自己を意識し、驚くほど迅速かつ正確にコンピューターのような偉業を成し遂げられるのは、ニューロン同士が正確につながっており、コミュニケーションをとっているからだ。私の研究チームは、単純な海洋生物の一種、無脊椎動物のアメフラシを使った研究で、「シナプス」と呼ばれるニューロンとニューロンのつながりが、体験によって変化することを明らかにした。シナプスが変わることによってヒトは学習したり、周囲の環境の変化に適応したりすることができる。しかし、ニューロン間のつながりはけがや病気によっても変化する。さらに、成長の過程で、つながりが正常に発達しない、あるいは、つながりがまったく形成されないこともある。そういった事態に陥ると、脳の働きは混乱をきたす。
脳機能の混乱、つまり脳の障害についての研究は、精神が通常はどのように機能しているのかを解明するための新たな洞察を次々ともたらしている。とくに最近は、かつてないほどその傾向が著しい。複数のニューロンがシナプスを介して複雑につながり合った神経回路の研究が脳の障害を理解するのに役立つのと同じように、自閉スペクトラム症や統合失調症、うつ病、アルツハイマー病などに関する研究は、社会的な交流や思考、気持ち、行動、記憶、創造性といった活動に関与する神経回路を解明するのに有用な知見を与えてくれる。コンピューターの部品が壊れたときにその部品のになう本来の機能が明らかになるように、脳の神経回路も、衰弱したり正しく回路が形成されなかったりするときに、その機能が劇的に明白になる。
脳内の精神的活動を生みだすプロセスの混乱は、自閉スペクトラム症やうつ病、双極性障害(躁うつ病)、統合失調症、アルツハイマー病、パーキンソン病、そして心的外傷後ストレス障害(PTSD)といった、人類を苦しめる精神疾患の原因となる。本書は、そういった脳の混乱がどのように生じるのかを探求する。脳の障害が生じるプロセスを理解することは、脳の健全な機能についての理解を深めるために欠かせない。新しい治療法を見つけるためにも不可欠である。その点も、取り上げる。
また、正常な範囲内での脳の機能の違い、たとえば発達の途上で生物学的な性別(セックス)や社会的な性別(ジェンダー)が決まっていく際に脳内ではどのような差異が生じているのかを調べることが、脳の機能をより深く解明するためにいかに重要であるかについても示す。
そして最後に、心や精神的活動についての生物学的研究は、創造性や意識に関する謎も解き明かし始めていることを描く。とくに、驚くべき創造性を発揮する統合失調症や双極性障害の人について触れ、彼らの創造性は、誰もがもつ脳と心、行動の関係に由来することを明らかにする。意識や、意識の障害についての最近の研究は、意識が脳の単一で不変の機能ではないと示唆している。異なる環境では異なる意識状態が生じる。それだけでなく、過去の科学者が発見し、ジークムント・フロイトが強調したように、意識下の知覚や思考、行動は、無意識の精神的プロセスによって形成されている。
大局的にみれば、心についての生物学的研究は、脳に関する理解を深め、脳の障害に対する新しい治療法の開発への期待をもたらすだけにとどまらない。心に関する生物学の進展は、新たなヒューマニズム創生の可能性をひらく。自然界に焦点をあてる科学と、人類の経験にどのような意味があるのかという点に焦点をあてる人文科学の融合である。脳機能の差異についての生物学的洞察に基づく、新しい科学的なヒューマニズムは、自己や第三者に対する見方を根源的に変化させるだろう。我々は自己意識により、すでに自分が独特の存在であると感じているが、今後は、生物学的にも個性を確認できるようになる。そして人間性について新たな洞察が生まれ、他の人とも共通している人間性と、一人ひとりが独自にもつ人間性の両方をより深く理解し、それぞれの真価を認めることができるようになるだろう。
本書の著者エリック・カンデルは、脳神経科学の代表的な教科書『カンデル神経科学』の主要な著者である。2000年には、記憶や学習に関する神経メカニズムの研究でノーベル生理学医学賞を受賞した。生涯の研究テーマとしてヒトの心、つまり精神の本質を解明しようと取り組んできた。
心と身体の関係について、17世紀の哲学者デカルトは、「我思う、故に我あり」と述べ、心は身体とは別にあり、身体とは無関係に動く、とする心身二元論を唱えた。しかし20世紀後半、現実はデカルトの考えとは逆で、「我あり、故に我思う」、つまり我々の身体、とくに脳があってこその心の動きであり、意識も含めた心の動きは脳内の神経回路の一連のプロセスによって生じる、と認識されるようになった。
カンデルは、この認識の転換がもたらされたのは、哲学と認知科学、そして脳神経科学が融合して誕生した、「新しい心の科学」の成果であると説明する。そして本書で、新しい心の科学によって心の本質がどこまで解明されたのかを、「心の病(精神疾患)」という視点から記した。
なぜ心の病なのか。カンデルはその理由を、次のように書いている。「コンピューターの部品が壊れたときにその部品のになう本来の機能が明らかになるように、脳の神経回路も、衰弱したり正しく回路が形成されなかったりするときに、その機能が劇的に明白になる」。
本書が取り上げる精神疾患は自閉スペクトラム症からうつ病、双極性障害、統合失調症、認知症、パーキンソン病、ハンチントン病、PTSD、依存症など幅広い。こういった精神疾患を通して、人間の社会性や感情、気分、意思決定、記憶、動作、意識、無意識といったさまざまな精神的活動が、脳のどの神経回路から生じているのか、あるいはどんな遺伝子が関与しているのかといった生物学的な基盤について、どこまで解明されているのかを紹介している。さらには、精神疾患の患者の芸術作品を介して、創造性にも生物学的な基盤があり、創造性も脳の活動から生じている点についても解説している。
例外的に心の病以外で本書に含まれるテーマは、性分化と性自認である。生物学的な性と性自認が一致しない状態は病気ではないものの、不一致が生じる過程をひもとくことで脳の性分化についての理解が深まるために、本書で扱われている。
本書は、最先端の研究だけを紹介しているわけではない。精神疾患についても脳の働きについても治療法についても、過去にどのように理解されていたのか、それがどう推移してきたのかという歴史も紹介している。そのおかげで読者は、現在の認識や治療法について、より深く理解することができる。しかも、自閉スペクトラム症やうつ病などさまざまな精神疾患や、トランスジェンダーの当事者や家族の詳細な体験談がいきいきとした自伝やインタビューを引用しながら紹介されているため、それぞれの疾患やトランスジェンダーの当事者について、より身近に知ることができる。
歴史的にみて、精神疾患には多くの偏見がつきまとってきた。たとえば親の愛情が足りないから、心が弱いから、といったように。しかし、それぞれの精神疾患の特徴や原因が生物学的に解明されるにつれ、いかに偏見が誤った根拠に基づくもので、いわれのないものであるかが科学的に立証されてきた。
ただ、薬物依存症については、意思の弱い、違法薬物を使うような悪い人の病気といった偏見がいまだに根強く残っているのではないだろうか。そのような見方がいかに科学的に誤っているのかは、本書を読むとよくわかる。
薬物によって快楽が得られるのは使い始めの初期だけである。その後は、薬物によって「報酬系」と呼ばれる神経回路に変化が生じ、快楽が得られにくくなる。それでも薬物の使用をやめられない、あるいはいったんやめても再発するのは、脳内に長期記憶が刻まれたがゆえだ。つまり、快楽を得られていた時期に薬物を使った環境、たとえば場所や人、状況などと薬物が関連づけられて記憶されているがゆえに、そういった環境に接すると、薬物が連想され、実際には快楽は得られないのに薬物を使いたいという渇望が生じる。この渇望は、無意識のレベルで生じる。つまり、意思の強さとは無関係である。
薬物依存症に限らず、ゲーム依存症やアルコール依存症など、ほかの依存症で起きている脳内の変化も、ほぼ共通していると考えられている。
自閉スペクトラム症から依存症まで、多くの精神疾患の発症に遺伝的要因、つまり遺伝子の変異(変化)などゲノムの変異の果たす役割が大きいことが明らかになっている。ただし、本書に記されているように、遺伝子の変異は必ずしも親子が共通してもっているものだけでなく、父親の精子の遺伝子に生じた、新しい変異であることも少なくない。また、自閉スペクトラム症をはじめとして遺伝的要因が大きな役割を果たしている心の病でも、多くは関連する遺伝子の数は百種類以上にのぼるなど多数である。遺伝に対しては、精神疾患と並んで偏見が多いが、心の病の発症には遺伝的要因が大きいと言っても、それは家族に原因があるという意味ではない。
精神疾患を生物学的に解明することは、より効果的な治療法の探索や開発につながると同時に、すでに行われている治療の効果を検証することにもつながる。たとえばうつ病に対する認知行動療法を含めた精神療法の効果である。かつては、薬物療法は脳に働きかけ、精神療法は心に働きかけると考えられていたが、脳から心の動きが生じると明らかになった現在、どちらも脳に働きかけていることがわかった。そして、対照グループを置いた客観的な臨床研究や、脳イメージングなどを使い、精神療法の効果が明らかにされつつある。さらに、うつ病の治療では、治療を始める前の脳の特定の部位の活動量によって、薬物療法と認知行動療法のどちらが効果的かを判定することも可能になってきている。
ところで、精神療法の一分野である精神分析についてカンデルは、20世紀後半の精神分析学は科学的な検証をおこたり、脳神経科学の知見もとり入れようとしてこなかったと批判する。精神分析医として臨床に携わった経験があるだけに、その批判には説得力がある。ただし、カンデルは苦言を呈する一方で、最近は科学的になりつつある精神分析を含めた精神療法が、さまざまな精神疾患の治療においていかに重要であるかについて、繰り返し強調している。精神療法を生物学的にみれば、学習や経験によってニューロン間の接続に解剖学的な変化をもたらす、学習と記憶という一連のプロセスであるという。批判すべき点は批判し、評価すべき点は評価する、という是々非々の姿勢は科学的である。
精神疾患の生物学的基盤の解明により、予防についても新しい可能性が考えられるようになっている。たとえば、薬物依存症については、著者が本書を捧げるデニス・カンデルらの疫学研究と動物実験から、喫煙によってニコチンに曝露されると、脳内が変化し、より薬物依存症が起きやすくなるということがわかったという。思春期の子どもたちに禁煙教育をより徹底的に行うことが、薬物依存症の予防にもつながることになる。
脳神経科学は、人類の倫理的な判断の背景にある生物学的なプロセスについても明らかにしつつある。アメリカの刑事裁判で、そういった脳神経科学の知見がとり入れられつつあるというのには驚く。思春期の子どもは、行動を制御する際に、成人とは異なる脳の領域を使っているという脳科学の知見を踏まえ、米連邦最高裁判所は、未成年犯罪者に対する、仮釈放の無い終身刑の判決は違憲であると判断したという。将来的には、倫理的判断をになう脳の神経回路に損傷があり、適切な倫理的判断ができない人が犯した犯罪について、罪を問えるのかどうか、という新たな議論が必要になるのかもしれない。
カンデルは、新しい心の科学を牽引してきた主要な要因として、遺伝子を含めたヒトゲノムに関する知見と、機能的MRIなどの脳のイメージング技術、そしてモデル動物による実験をあげる。
そして、新しい心の科学のさらなる進展によって、脳機能と精神との関係がさらに解明されれば、やがて神経科と精神科は融合し、一つの診療科になるだろうと予想する。日本ではまだ精神科を受診することに抵抗を感じる人がいることを考慮すれば、神経科と一つの診療科になることは、心の病に悩むより多くの人が、早期に専門的な治療を受けられるきっかけになり、好ましいことではないだろうか。
新しい心の科学は、創造性を生みだす生物学的な基盤についても解明しつつある。そういった知見を踏まえ、カンデルは将来的には自然科学と人文科学が融合し、新たなヒューマニズムが誕生する可能性があると展望する。そして、新たなヒューマニズムは、脳機能の差異を生みだす生物学的な背景を踏まえており、自己や第三者についての理解が、これまでと根源的に変わるだろうと予見する。そのような理解が深まれば、生物学に根づいた一人ひとりの人間性を、心の病も含めてよりよく理解できるようになる。それが実現すれば、心の病に対する偏見や差別も解消されると期待できる。
訳者にとって本書は、カンデルの著書の二冊目の翻訳である。カンデルの経歴については、前の翻訳書『芸術・無意識・脳──精神の深淵へ 世紀末ウィーンから現代まで』(九夏社、共訳)の訳者あとがきに詳しく書いたので、本書では、カンデルが生涯の研究テーマであるヒトの心になぜ興味を持つようになったのか、そしてどのように研究してきたのかについて簡単に紹介する。
カンデルがヒトの心に興味をもつようになったきっかけは、ユダヤ人一家の子どもとしてウィーンに住んでいた1930年代の体験だ。ナチスが台頭し、とくにオーストリア侵攻後は、それまで仲良くしていた学校の友だちが急に口をきいてくれなくなったり、いじめられたりするようになった。実家のおもちゃ屋は略奪にあった。そんな体験から、ヨーロッパの知識人がナチス時代に突然、非道で野蛮な行動をとるようになり、洗練された文化をもつ社会が急に悪に向かって突き進んだのはなぜか、そしてその背景にある、矛盾だらけの動きをする、ヒトの心の本質は何かを知りたいと思った。
大学の学部生時代には、19世紀から20世紀にかけてのヨーロッパの歴史を専攻した。その後、精神分析医を目指すようになった。精神分析医になるには医師免許が必要であるため、ニューヨーク大学医学校に進学。そこで基礎生物学にひかれるようになる。しばらくは、精神分析の臨床医として働きながら脳神経学の基礎研究も行う生活を続けた。しかし、臨床医を続けながら基礎研究を究めるのは困難だと痛感し、基礎研究に専念するようになった。
本書の原題は「The Disordered Mind」である。現在、英語の専門用語では、「Dipressive Disorder」「Integration Disorder」など、精神疾患の多くにdisorder がつく。研究社の新英和大辞典によると、disorder は、(心身機能の)不調、障害、(軽微な)病気、疾患といった意味をもつ。
国内ではこれまで、disorder は原則的に「障害」と訳されてきた。しかし、世界保健機関(WHO)の「疾病及び関連保健問題の国際統計分類 第11版」(ICD ─11)が2019年のWHO総会で採択されたのを機に、厚生労働省が関連学会の意見を参照しながら和訳の見直し作業を進めている。日本精神神経学会など精神疾患関連学会の見解によると、ICD ─11では、うつ病のようにすでに社会的に広く根づいている病名を除き、disorder は「障害」ではなく「症」と和訳されることになる見通しだ。
日本語の障害は、disability の意味でも使われるため、治療によって治ることもある精神疾患に使うと、不可逆的に治らないという偏見を助長する恐れがあることや、患者にとっても「〇〇障害」と診断されることは負担感が大きいという懸念などがあるのが変更の理由だ。Autism Spectrum Disorder についてはすでに「自閉スペクトラム症」という訳が使われている。
本書の翻訳にあたっては、原則として2023年時点で日本精神神経学会が一般向けの解説で使用している精神疾患名を使った。今後、疾患名の変更がある点はお含みおきいただきたい。
カンデルが書いているように、精神疾患は、落ち込んだり、気分が高揚したり、何かを忘れたりといった誰でもが日常的に経験する精神状態が極端に高じたり、過剰に長く続いたりして、日常生活に支障が出るときに診断される。つまり病気と病気ではない状態は連続的で、どこで境界線を引くのかは難しい。歴史的にみると、時代によって境界線の位置は変わってきた。
したがって、正常、標準的、典型的な状態と、そうではない異常な状態を線引きするのも難しい。また、日本語で「異常」という言葉は、何か好ましくないこと、というニュアンスで使われることが多い。そのため、翻訳にあたっては、なるべく「正常・健常」「異常」という言葉を使わないように心がけた。ただし、使わないと意味が伝わりにくい場合には使用した。本書で使用した「異常」には、好ましくない状態というニュアンスは一切含まれない点もご理解いただきたい。同様に、遺伝子の欠陥などに使った「欠陥」にも、好ましくないというニュアンスは含まれない。あくまで生物学的な状態を中立的に表現している。
本書に記されているように、カンデルは、「感情(emotion)」と「気持ち(feeling)」という言葉について、感情は「観察可能な無意識の行動に関与する要素に限定」、気持ちは「感情の主観的な体験」と使いわけている。これは神経学者アントニオ・ダマシオの見解に沿っている。emotion は、医学や心理学では「情動」と訳されることが多いが、あまり一般的な言葉ではないので、「感情」と訳した。
「genetics」は「遺伝学」が定訳である。遺伝学は、親から子孫に伝わる遺伝に関する学問という意味で使われることが多いが、本書のgenetics は、本来の遺伝学という意味だけでなく、遺伝子やヒトゲノムの分子生物学的な研究も含めた、幅広いゲノムに関連した研究という意味で使われていることが多い。できるだけその意味が伝わるような訳を心がけたが、読みにくくなる部分などは「遺伝学」という訳を、広義の遺伝学として使っている。
最後に、本書の引用文は、邦訳された書籍がある場合も含め、すべて訳者が原書に記載されている英文から翻訳した。
著者自身も含め、多くの脳科学者の研究により、
さまざまな精神疾患が、ほんのちょっとした脳の異変によって生じること、
精神疾患を発症していない状態が奇跡のように思えるほど、複雑極まりない脳の機能に衝撃を受けたのと、
研究が進んでこれからどういった機能が解明されていくのか、脳への興味が増していく。
また、注意深く症状と折り合いをつけながら日々を送る、自閉スペクトラム症の子を持つ親と患者本人の話、
この症状を抱えて生きるのがどれほど困難か、想像を絶する統合失調症の当事者の話、
依存症は精神的な弱さからくるのではなく、脳の報酬系をになう回路がうまく機能しないためなど、
目にする機会や耳にする機会が増えていたが、詳しいことはよく知らないでいた精神疾患への理解が進むのだ。
神経科学者たちの研究成果、精神疾患の当事者や家族の声、治療法の歴史を踏まえながら、
ノーベル賞受賞の脳科学の第一人者が心の病と脳を読み解きます。