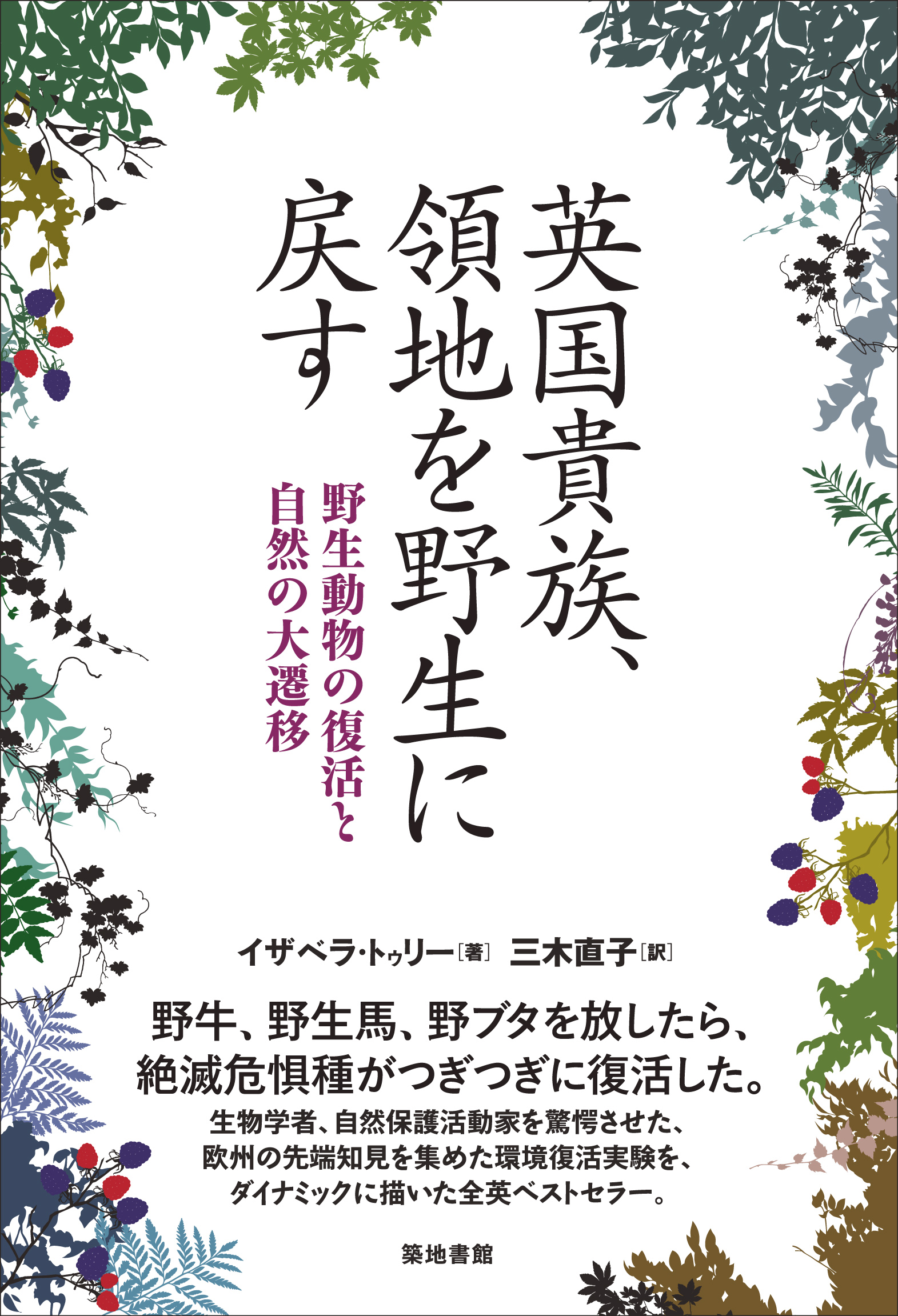都市に侵入する獣たち クマ、シカ、コウモリとつくる都市生態系

| ピーター・アラゴナ[著]川道美枝子、森田哲夫、細井栄嗣、正木美佳[訳] 2,700円+税 四六判上製 312頁 2024年3月刊行 ISBN978-4-8067-1662-4 【日本でも街中に出没するクマが話題になっている今、非常にタイムリーな1冊】 『スミソニアン・マガジン』の2022年お気に入り本に選出! 都市はいかにして野生動物たちにとって魅力的な住みかとなったのか? 道を横切る二足歩行のクマ、 巣のライブ配信中に子猫を獲ってきてヒナに与えるワシ、 動物園のコアラを連れ去ったピューマ――。 リスやコウモリなどの小型動物から大型猛獣まで、 人工的なものの象徴である都市が 思いがけず野生動物を引き寄せることになった理由を歴史的に振り返り、 駆除か保護かの二元論ではない共生への道を探る。 2024/5/4(土)朝日新聞書評欄で紹介されました。 筆者は小宮山亮磨氏(朝日新聞デジタル企画報道部記者)です。 2024/5/11(土)日経新聞書評欄で紹介されました。 筆者は小林照幸氏(作家)です。 2024/5/12(日)北海道新聞書評欄で紹介されました。 筆者は小野有五氏(北大名誉教授)です。 |
書籍案内――都市はなぜ野生動物たちのすみかとなったのか?
ピーター・アラゴナ(Peter S. Alagona)
アメリカの環境史家、保全科学者、自然文化地理学者で、
カリフォルニア大学サンタバーバラ校の環境学教授。
2011年に、21世紀の学術的リーダーになる可能性を秘めた研究者を支援する
米国国立科学財団(NSF)主催のCAREER助成金を獲得した。
絶滅危惧種についての研究に加え、
現在は野生生物との共存や失われた種の再導入といった課題に取り組んでいる。
カリフォルニアにグリズリー(ハイイログマ)を再導入することを目指して立ち上げられた
California Grizzly Research Networkの創立者兼ファシリテーター。
本書はカリフォルニアの絶滅危惧種について綴った最初の著書『After the Grizzly』(2013)
から約10年を経て書き上げられた著者の第2作である。
川道美枝子(かわみち・みえこ)
1947年北海道生まれ。関西野生生物研究所代表。
立命館大学歴史都市防災研究所客員研究員。
リス類の生態研究をするとともに外来生物、特にアライグマ・ハクビシンの有効な対策を研究。
北海道大学理学部卒、同大学院博士課程単位取得退学。理学博士。
森田哲夫(もりた・てつお)
1950年三重県生まれ。小型哺乳類で見られる日内休眠の生態学的役割について研究。
京都大学大学院農学研究科博士課程単位取得退学。
宮崎大学名誉教授。環境カウンセラー。
宮崎大学フロンティア科学総合研究センタープロジェクト研究員。
細井栄嗣(ほそい・えいじ)
1962年静岡県生まれ。農林業加害獣と希少動物を対象にシカ、イノシシ、クマ、ヤマネなどの生態を研究。
京都大学農学部を経て博士課程はコロラド州立大学で野生動物学を学ぶ。
博士(Range Science:牧野科学)。山口大学大学院准教授。
正木美佳(まさき・みか)
1975年長野県生まれ。生息地域差による小型哺乳類の休眠の多様性に関して研究。
宮崎大学農学研究科修士課程修了。九州保健福祉大学薬学部講師。
まえがき──あるボブキャットとの出合い
序論 猛獣たちのいるところは、今
都市生態系をめぐる2つの立場
「都市」「野生生物」の定義と本書の主役
第1章 都市は生命あふれる場所にこそつくられた
地理的な特徴
都市の発展と生態系へのダメージ
第2章 家畜が都市を支配していた時代
うろつく家畜
汚物と病気
家畜の追放と都市の浄化
第3章 都市の緑が野生生物を繁栄させた
野生生物抜きの都市計画
公園・街路樹・保護区の出現
第4章 郊外の成長と狩猟の衰退がもたらしたもの
都市と野生の境界
都市化に伴うハンターの急減
増えすぎた個体数
第5章 生息地を保全する
小さな鳥のための広大な土地
オープンスペース・ネットワークの形成
政策の変化と保護法の制定
見捨てられた土地の再生
保護の恩恵
第6章 都市で成功する動物
新しい生態系
都市とその周辺で見られる動物の分類
出没動物への過剰な反応
都市で子育てするコヨーテ
第7章 大型獣と生息地を共有するということ
害獣から愛すべきキャラクターへ
都会のクマ
国立公園での餌付けと食物管理
殺さずに対処する
新たな倫理観の構築
第8章 都市の生態学的な価値
都市生態学の萌芽と成長
群がるワシ
第9章 動物のための道
P-22の足跡
移動の障壁
分断を解消する
都市の食物網
ゴミをあさる者たち
捕食者のパラドックス
袋小路の都市と遺伝的多様性の欠如
第10章 不快生物を理解する
コウモリの生態
コウモリに対する誤解
動物由来感染症を正しく理解する
コウモリよりも危険なもの
コウモリであるということ
第11章 動物たちがいるべき場所
棲み着いた外来種
外来動物ブームと脱走
動物園にやってくるもの
クリニックの存在意義
最も効果的な行動にコストをかける
飼育下と野生の線引
第12章 駆除 時間とコストが永続的にかかり、暴力的で効果がなく、根本的原因を解決するより新たな問題をつくり出す野生生物管理の形態の正当性が疑われている
駆除の歴史
殺すと状況が悪化することもある
殺鼠剤による巻き添え被害と非致死的アプローチの難しさ
賢明な解決策を目指して
第13章 都市と共進化する生き物たち
イエスズメの急速な進化
進化と適応
生態系の寡占化と生物多様性の低下
変わりつづける都市で
第14章 都会の野生をいつくしむ
「魚泥棒」
アシカ追い払い作戦
共生のための課題
明るいニュース
求められるリーダーシップと連携
野生生物と共存するには
おわりに──コマツグミの巣が教えてくれたこと
より良い社会にするために
謝辞
訳者あとがき
参考文献
原註
索引
数年前のよく晴れたある冬の日、私は荷物をまとめ、服を着替え、自転車に飛び乗って、職場から家に向かった。その日は金曜日で、週末を早く迎えるにふさわしいと思ったからだ。10年近くを費やした私の最初の本の最後の仕上げをちょうどしたところで、手が空いていたのだ。しかし、今のところ、私は午後の休暇を取ることで満足していた。
自宅へと向かう自転車道は、職場である大学のキャンパスから海辺を抜け、高速道路に沿って湿地を横切り、いくつかの小さな農場を回り、静かな郊外を抜け、にぎやかな繁華街へと続いている。この道は私の研究室から約1・6キロメートルのところでアタスカデロ川に合流する。アタスカデロとは、可愛らしくない場所を表す可愛い言葉である。スペイン語で「沼地」のような意味だが、この悲しい小川はその名にふさわしいものだ。砂利道と平行に流れるこの川は、小川というより運河のような形をしていて、不自然なほどまっすぐだ。鉄砲水対策のために、長い区間がコンクリートで固められている。しかし、ほとんどの日は、ぬるぬるした緑の岩の上を濁った水がちょろちょろ流れ、アスファルトのように真っ黒で生ぬるい淀みのあるドブ川と化している。
走りはじめて15分ほどで、小川にかかる橋を渡り、分譲地とゴルフ場の間を東に曲がった。その時、私の90メートルほど前を、何か変わったものが大股で横切った。小型犬くらいの大きさだったが、小さな丸い頭、とがった大きな耳、漫画のように大きな腰と、遠くから見ると、大皿のように平らで幅広の足をしていた。惰力走行で進みながら、私は容疑者リストをチェックした。シカ? いいえ。アライグマ? いいえ。スカンク? いいえ。コヨーテ? たぶん違う。イヌ? もしかしたら、イエネコ? 大きすぎるが、ネコのような動きをしていた。
その生物を見たと思しき場所に着くと、自転車を止め、茂みの中を覗き込んだ。私からわずか4・5メートル先に座っていたのはボブキャットだった。丸々と太った成熟個体で、豪華なまだら模様の毛に明るい緑色の目、そしてトレードマークの房がついた耳をもっていた。そのボブキャットは最盛期にあった。ボブキャットの体重は9キログラムにも満たないことが多いが、私をじっと見つめるその姿は、まるでライオンのように大きく見えた。私たちは数秒間、目を合わせた。2匹の哺乳類が互いに相手を見極めようとする古来の行為であった。
私は過去に二度、野生のボブキャットを見たことがある。一度目は、秋のさわやかな朝、夜明け直後のハイシエラの高山湖畔で。その斑点のある灰色のネコは、花崗岩の背景に完璧に溶け込んでいた。二度目は、暖かい夏の夕方、モントレーの丘陵地帯にある牧場で。この2匹目のネコは。周囲の小麦色によく似た黄褐色の毛をもち、草地の丘の上に立ち止まり、肩越しに私をちらりと見てから藪(やぶ)の中に消えていった。
ボブキャットにはこれまでにも出合ってはいるにもかかわらず、この3匹目のボブキャットとの出合いは驚きと新事実の連続だった。
これまで見たことのあるような野生の場所にいるボブキャットばかりをいつも思い描いていたので、驚いた。さらに驚いたのは、私が目撃したのは特別なことではなかったということだ。北アメリカの温帯から亜熱帯にかけて生息するボブキャットは、フロリダのエバーグレーズ、ケベックのノースウッズ、メキシコのソノラ砂漠など、大きく変化する生息地で生活している。ボブキャットは人間を避ける傾向があるのだが、彼らが好む餌にネズミなどの小型哺乳類が含まれるため、まれに郊外やその周辺に出没する。私の友人や同僚の多くは、以前に私の地元で彼らを目撃していた。どうやら、私はその存在を知った最後の一人のようである。
次に明らかになったのは、このことだ。私はそれまで10年間、絶滅危惧種――すなわち大まかな定義によればほとんどの人が見ることができない生物、その研究をしてきた。しかし、ここにこの野生の捕食者がいたのである。ある視点から見れば、アラスカヒグマやベンガルトラと同じくらい大胆で美しく恐るべき存在が、南カリフォルニアの郊外をうろついていた。それからの数日間、私は都市に棲む野生動物についていろいろと考えるようになった?あのボブキャットのおかげでこの本ができたのである。
また私は、自分が既存の思考パターンに陥っていたことに気づいた。何十年もの間、科学者や自然保護活動家の多くは、都市部とそこに生息する生き物を敬遠し、代わりにもっと遠隔地に生息する希少種に注目してきた。野生生物に関心をもつ人々は、都市を人工的で破壊的、そして退屈なものと考えていたのだ。そのような場所から学ぶことはほとんどなく、都市の中に救ったり養ったりすべき動物などいないと思われていた。野生生物保護団体が都市部に関心をもつようになったのは、ごく最近のことである。私と同じように、彼らも都市部に目を向けるようになるまでに長い時間がかかった。しかし、ついには、私もそうだったが、自分たちが発見したものにびっくり仰天したのである。
自転車道でボブキャットと出合ってから数年後、私が都会の野生動物を研究していると言うと、必ずと言って良いほど、その手の話が返ってきた。この本を書いたり、そのような話すべてを聞いたりしているうちに、あの出合いを注目すべきものにしたのは、それがめずらしいことではなく、ごく普通のことだったからだということがわかってきた。この後のページで私が目指すのは、このような状況にいたった経緯と、アメリカのあらゆる都市のほぼすべての住民が自分自身の野生動物の物語をもっているということの意味の両方を説明することである。
飛行機の窓から大阪の中心部を見ると、灰色の四角い建物たちが立ち並び、ほんの少しの緑と中心部を流れる、コンクリートで護岸された川が見える。人が住みはじめる前は、森や湿地、草原が広がり、シカや、イノシシやツキノワグマも自由に闊歩していたことだろう。今は大型の獣は姿を消し、樹上棲のリスやムササビを見ることもない。
北アメリカへ人々が移住を始めた時、そして徐々に人口が増加していった時、何が起こったのかをこの本で作者は劇的に明らかにしてくれる。
著者によれば「マンハッタン島だけでも、同規模の典型的なサンゴ礁や熱帯雨林よりも多い55の異なる生態学的群集が存在したと推定されている。その草原、湿地、池、小川、森林、海岸線には、600〜1000種の植物と350〜650種の脊椎動物が生息していた」という。それらの生態学的群集は人々の手ですっかり破壊され、今ではコンクリートとアスファルトに覆われた無機質な空間に変貌している。
環境は少しずつ改変されていった。初めはネイティブアメリカンはおもに狩猟採集をし少人数の集落を形づくっていた。一部の人々は農耕に従事していたが、大きく環境を変えることはなかった。集落の周りには多くの野生動物が行き来していただろう。やがて移民してきた人々は最も生物多様性が豊かな土地に集中するようになり、野生動物のすみかは人々の住居と家畜に占拠されはじめた。その頃にはすでに大型の哺乳類や食肉類は人間の暮らしに入り込む余地はなかったのだろう。やがて、文明の進化とともに、街にいる動物はイヌ、ネコ、ネズミと行動の自由度の高い鳥類だけになり、街はウマやウシ、ブタの糞尿にまみれることなく、スマートで清潔な都市へと変貌を遂げた。
著者は、その都市部で新たに見かけるようになった野生動物に注目した。これは、これまであまり語られることも研究対象になることもなかった分野だ。本書のタイトルは「都市に侵入する獣たち」としたが、人間の立場からするとこれらの獣たちは侵入者であるが、実際には彼らは失われた土地を再び取り戻そうとしているように見える。
今、日本でも多くの獣たちが都市部へと侵入しはじめていることが報告されている。タヌキ、キツネ、アナグマ、テンなどの小型から中型の動物たち。これらは人にとってあまり問題になるような侵入者ではないが、シカ、イノシシ、ツキノワグマ、ヒグマのような大型動物はさまざまな人との軋轢を生じさせている。人はクマを見ると恐れ、人的被害が生じることから駆除されるものも多い。しかし、クマは本来狂暴な生き物なのだろうか? 訳者の一人はかつて知床半島の奥にある漁師の番屋を訪ねたことがある。年老いた漁師が漁網をつくろっているすぐそばをヒグマの親子がのんびりと通り過ぎ、海岸で食べ物を探していた、そこには人と獣の間になんの緊張感も無く、平和な光景が広がっていた。人と獣がこのように平和に共存できないものか? 著者は語りかける。
アメリカ各地で緑地があればリスがいるのは今では当たり前の光景だが、1840年代まではその姿を都市部では見かけなかった。リスは都市への最初の侵入者であり、現在では考えられないが、人々はリスをめぐって「リスと一緒に暮らすことの賢明さについて確信がもてず、人々はトウブハイイロリスが社会にどのような貢献をしたか、そして人間がそれらをどのように扱うべきかについて議論した。中傷する人は害獣と見なした。この魅力的で働き者の小さな生き物を隣人にもつことで、人々は神の創造物すべてに対して、より優しく、より慈しむようになると支持者たちは主張した」と議論した。しかし、リスは受け入れられ、都市で自由に暮らすようになった。「良い都会の動物であるということは、頭が良く、友好的で、比較的おとなしいことだった」と著者は書いている。
さらに環境づくりとして?アメリカ中の都市が公園を建設し、何百万本もの木を植え、森林保護区をつくり、重要な水源の周りに保護区域を設置した。その結果さまざまな動物たちが生息可能となった。それに続く生物多様性の保全や絶滅危惧種を保護する法律制定など、アメリカ政府と環境保護団体は動物たちが生息できるさまざまな環境の保全対策を行ってきている。そして、大型動物を含む野生動物の生息可能な場所は準備され、野生動物の「侵入」が可能となった。ただ漫然と都市部に動物たちが戻ってきたのではなく、戻る条件を整えるための長年にわたる努力が実を結びつつあるということだ。
戻ってきた動物たちに都市の人々はどう対応したのだろう? クマやピューマ、コヨーテをひたすら恐れたのだろうか?
「人間の食べ物を食べたクマは人間に対する恐怖心を失い、子グマに同じことを教えるようになる。(中略)しかし、誰が彼らを責めることができようか。一度ピーナッツバターを食べてしまったら、もう木の実や葉っぱには戻れないのだ」。この本では、クマに対する有効な対策は示されていない。しかし、餌を与えないことやゴミを適切に管理することが、人間との軋轢を避ける方策であると示している。
コヨーテは幼い子どもを殺した。人々は恐れたが、やがて「ニューヨークでは。人々がコヨーテとの生活に慣れるにつれて、恐怖心は寛容さへと変化し、ある種の微妙な受容さえ生まれた」。これは、危険をもたらすかもしれない野生動物への対処の仕方というよりは慣れが一つの解決法であると述べている。
ピューマが動物園に侵入し、コアラを食べたという事件があったが、これも人々はピューマを追い詰めず、共存することを選んでいる。
著者は最後にこう書いている。「本書では、数十年の間に、どのようにして都市が予期せず野生動物でいっぱいになったかを、そしてこれが現在これら都市の生息地を共有している人々や他の動物にとってどのような意味をもつかを説明しようとした」
原題は「Accidental Ecosystem」であり、著者の主張は都市の生態系は偶然に形成されたというものである。「自然保護の歴史において最も偉大な勝利の一つは、ほとんど偶然に起こったものだ。おもに人が数十年前に他の理由で下した決断により、18世紀から19世紀にかけて激減した野生種が、20世紀から21世紀にかけて、多くの新参者とともに都市部に戻ってきたのである」。そしてこう主張する。「野生生物への配慮を都市生活のあらゆる側面に取り入れることを始めるべき時なのだ。それは簡単なことではない。しかし、科学に基づいた対策を採用して、地域社会の意見と支持を得ながら実施し、信頼できる公共投資で対策を維持する。しかも、最も貧しくて最も弱い立場にある人々にも配慮した対策として設計する。そうすれば、いつか私たちはみんな、より清潔で、より緑豊かで、より健康的で、より公正で、より持続可能な、多様性と共生に満ちた地域社会に住めるようになるだろう」。果たして、日本人は都市に侵入してきた野生動物に寛容であることができるだろうか? 本書は共生のための即効薬という内容ではない。しかし、現在、都市部に出現するクマやシカ、イノシシたちとの共生を考える手がかりになるのではないだろうか。
都市部に侵入してきた動物たちは小さな個体群を形成している。これらのやや孤立した個体群に変異が多く起こっていることも本書で指摘されている。やがてこれらの変異の積み重ねから新たな種が生まれるかもしれない。都市は進化の実験場になって、私たちは生物の進化を目の当たりにすることができるのではないだろうか? 動物たちの生態や行動、社会、そして進化に興味を持つ若い研究者たちにぜひ本書を読んでいただきたい。多くの研究のヒントがここにはある。(後略)
2023年は、OSO18をはじめ街中に出没するクマによる被害が大きな話題になりました。本来「自然」の領域にいるはずの猛獣が人間の暮らす領域で行動するようになったのはなぜなのか、その理由に多くの人々が関心を寄せています。
本書は、アメリカ・カリフォルニア大学で環境学を教える著者が、アメリカの都市が「奇妙な野生生物保護区」になった理由を歴史的・科学的に振り返る『Accidental Ecosystem』(2022)の翻訳です。訳者陣は、長年京都などで野生動物の研究、保護と駆除に取り組んできた動物学者です。
まず、大都市となった場所がかつてサンゴ礁やイエローストーン国立公園よりも豊かな生態系を有していたことが明かされます。開発が進み野生動物が激減してからはウマ・ウシ・ブタなどの家畜が都市を支配し、糞尿の悪臭で人々を困らせつつも人間の生活を支えていました。しかし衛生観念の高まりとともに家畜が追放され、緑地が増えるにつれて、クリーンになった都市に野生動物が再び姿を現すようになりました。人のために創られ発展した都市環境は、いまや人だけではなく野生動物にとっても有用なすみかとなったのです。
野生動物が戻ってきた都市では過剰な個体数や人に危害を加える個体が問題となり、しばしば反対派と擁護派が激しく対立しました。著者は、そのどちらか一方に肩入れするのではなく、歴史に学び、科学的事実に基づいた対策を実施する重要性を説きます。危険性の低い動物を過剰に恐れて殺したり、生態系にダメージを与えている動物--たとえばネコ--をかわいいからと言ってむやみに保護したりすることは、人にとっても動物にとっても良くありません。野生動物による被害に遭わないために人間側がすべき対策もたくさんあります。
21世紀の都市の野生動物を理解し、都市とその周辺を人間と野生動物がともに繁栄していけるような場所にするためには何が必要なのか。コロナ禍やクマ出没で都市を利用する野生動物たちへの関心が高まっている今、駆除か保護かの二元論ではない共生への道を提案します。