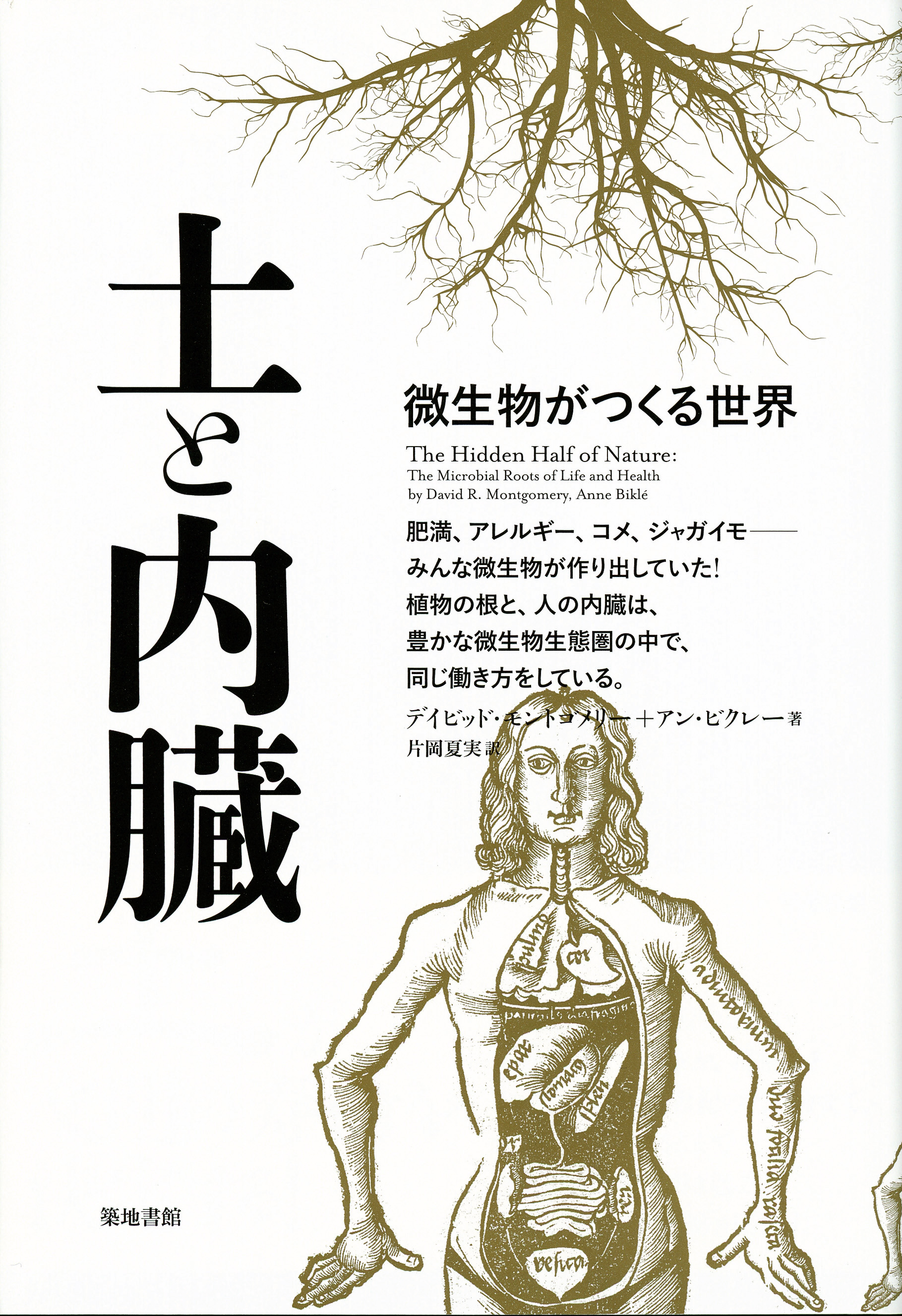僕が肉を食べなくなったわけ 動物との付き合い方から見えてくる僕たちの未来

| ヘンリー・マンス[著]三木直子[訳] 2,900円+税 四六判並製 464頁 2023年9月刊行 ISBN978-4-8067-1656-3 タイムズ紙「今年(2021年)のベストブック」選出! 人間とすべての生き物の関係を、 畜産・食肉業、レストラン、漁業者、ハンター斡旋業者、 動物園経営者など動物と関わる多様な分野の人々への取材を通じて考える。 アニマルライツ、疫学、生態系保全の視点も踏まえた21世紀の非・肉食論。 英国で大きな反響を呼んだリポート。 |
ヘンリー・マンス(Henry Mance)
『フィナンシャル・タイムズ』紙の特集記事責任者として、主に長編記事を担当している。
2017 年のブリティッシュ・プレス・アワードで最優秀インタビュアーに選ばれ、
BBC のラジオ番組やテレビのニュース番組にも頻繁に登場するほか、
CNN とPBS にも出演している。
妻と2人の娘とともにロンドン在住。本書はマンスの初の著作である。
三木直子(みき・なおこ)
東京生まれ。国際基督教大学教養学部語学科卒業。
外資系広告代理店のテレビコマーシャル・プロデューサーを経て、1997 年に独立。
訳書に『CBD のすべて 健康とウェルビーイングのための医療大麻ガイド』(晶文社)、
『アクティブ・ホープ』(春秋社)、『コケの自然誌』『錆と人間 ビール缶から戦艦まで』
『植物と叡智の守り人 ネイティブアメリカンの植物学者が語る科学・癒し・伝承』
『英国貴族、領地を野生に戻す 野生動物の復活と自然の大遷移』(以上、築地書館)、他多数。
イントロダクション
僕の動物愛テスト
人間以外の、意識を持った生き物
子どもの世界は動物だらけ
発見と希望の物語――動物愛護の倫理と環境保護主義の融合
1 人間と動物の歴史
紀元前から20世紀までの動物観
変わりつつある世界と意識
PART1 動物を殺す
2 屠殺場のルール
調査の始まり
ヒツジとブタの屠殺場
現代的工場畜産
家畜化が変えた生物学的特徴
ミート・パラドックス
酪農家フィンレイの実験
採卵鶏の雄をどうするか
ポジティブ・ウェルフェア
3 肉のない世界
ヴィーガン・レストラン
流行を超えるヴィーガニズム
幹細胞肉の可能性
植物由来肉の時代がやって来る
工場畜産の経済的破綻――ファッション業界と動物
実践可能な食生活
4 損をするのはいつも海
ニジマス釣り体験
混獲と乱獲
魚たちの感覚と思考
漁業という文化
魚とタコの養殖
安心して食べられるシーフード、二枚貝
動物実験を考える
漁業が存在しない世界への道
5 サイコパスの休暇旅行
『バンビ』と現実のシカ問題
シカ狩り
狩猟に関する倫理の変遷
人はなぜ狩りをするのか
生態系のバランスを保つ
トロフィーハンターと地域経済
各国の狩猟事情
動物を支配していることを受け入れる
PART2 動物を愛す
6 歴史の方舟
動物園をなくしたい理由
啓蒙主義と動物園
スペースが足りない
種の保全に果たす役割
動物の人権
人間による支配の限界
7 あるのは足跡だけ
広がる農地、減る生息地
ハーフ・アース――地球の半分を自然保護のために
捕食動物の隣で暮らす人々の悩み
イギリスで広がる再野生化
変化に適応できない生き物を救う
動物を愛する一人ひとりができること
抗議行動を起こす人々
8 問題は犬じゃない
ペットという存在
現代の犬事情
人間の献身と欲望
輸入される野生動物
ネイティブアメリカンのコンドル再導入
身近な動物に目を向ける
9 人間は神か
技術の発展がもたらすもの
動物の言葉を解読する
遺伝子編集で苦しみを取り除く
動物のコントロール――現実的なやり方を探る
人新世の動物愛
必要なのは自制心
結論 美女と野獣
庭の池の野生
採卵鶏と過ごした二か月間
動物に対する新たな価値観
人獣共通感染症が示したもの
動物の愛し方
訳者あとがき
参照文献
索引
タイムズ紙「今年(2021)のベストブック」選出
我々が動物にひどいことをするのは、
自分の行動の結果をきちんと考える能力が欠如している結果だ、
とヘンリー・マンスは確信する。
『僕が肉を食べなくなったわけ』はその空隙を、
読みやすく、明快かつ愉快な言葉で埋めてくれる。
――ピーター・シンガー(『動物の解放』著者)
挑戦的ではあるが同時に面白おかしく、珍しいほど偉ぶったところがない本書は、
単に議論をふっかけようとしているのではない。
これを読んだ多くの人は間違いなく、
我々の誰もがそれを構成する一員であるシステムについて、
これまでとは違った理解を持ち、異なった選択をするようになるだろう。
そうでない人は、動物を愛しながらも
その苦しみから利益を得ている者がビクビクしながら避けて通っている、
倫理的な理由という難しい問題を突きつけられることだろう。
マンスは、優しく、好奇心に満ちて広い心で我々を導いてくれる。
――フィナンシャル・タイムズ紙
生き生きとしたマンスの初の著作は、
人間と人間以外の生き物の関係を徹底的に考え直すよう我々に訴える。
その巧みな筆致は、悲痛な物語を語ることも決して避けようとはせず、
どんなに暗い事実にもユーモアを吹き込む。
彼はまた、難しい倫理的議論を温かく、またわかりやすく表現できる稀な才能の持ち主だ。
――エコノミスト誌
緻密なリサーチに基づき、丁寧に紡がれた本書の内容は、
多岐にわたり、非常に興味深く、ときに笑いを誘う。
マンスの書きっぷりは陽気で、
重い主題を扱うときもその文章は軽々と、流れるようである。
夢中で読み、触発された。
――スペクテイター誌
非常に説得力があり、皮肉っぽく、ときに大笑いさせる。
優れた記者がみなそうであるように、マンスには偏見がなく、しっかりした倫理基準があり、
綿密で、何でも試す度胸があり、人の話を引き出すのがうまい。
この、思慮深くかつ刺激的な本を読んで気づいたのは、
動物に思いやりと尊敬を持って生きようと努力し、ときに失敗する方が、
それを初めから諦めてしまうよりずっとましだということだ。
――ニュー・ステーツマン紙
ユーモアと人間性にあふれる著者の主張は、説得力があり、同時に一刻の猶予も許さない
――生態系の破壊を防ぎたければ、我々は生き方の大々的な変革が必要だ。
――ガーディアン紙
愛とは、自分以外の存在がそこにある、という、とてつもなく難しい気づきのことである。
愛とは、真実を発見するということなのだ。
――アイリス・マードック
この世でうわべだけでも意味のある振る舞いを続けたければ、
物事には正しいことと正しくないことがあると信じないわけにはいきません。
――ジョーン・ディディオン
僕と同世代のなかでも一番の優秀な頭脳が、猫の動画に破壊されるのを僕はこの目で見ている。ペットの猫がピカピカの床の上を滑る。箱に飛び込む。隣の家の屋根に飛び移るためのジャンプの軌道を計算し損なう。それはインターネットの黄金時代のことだ──ワクチン陰謀論者や、反・反右翼派が台頭して物事をめちゃくちゃにする前の話である。
そういう動画は、僕たちのある側面を物語っている。僕たちは自分たちのことを、動物愛好家(アニマル・ラバー)だと思っているということ。野生動物のドキュメンタリーや、動物のお手柄についての心温まる物語を片っ端から観る。動物を可愛がる政治家に共感する──彼らのペットが選挙に出たら、再選される可能性は彼らよりも彼らのペットの方が高いかもしれない。
だが、僕たちが動物に感じる愛情には自己不信がついてくる。人間社会が動物とかけ離れた方向に進んでいることを僕たちは知っている。敢えて問われれば、僕たちは、ほとんどの家畜は幸せに暮らしてはいないこと、野生動物の多くは棲みかをなくしていることを認めるだろう。そうじゃなかったらいいのに、とは思うが、これは僕たちが豊かであることの代償なのだ。
だから僕たちは動物のことはあまり考えない。僕たちの食べ物や衣服の多くは動物由来だし、人間社会の盛衰には動物が大きく関わってきたし、人間が地球上からいなくなってもおそらく彼らは残るのだろうが、でも僕たちは彼らの存在について深く考えたりはしない。
ここは人間の住む惑星なのだ。現在の世界人口のほとんどがそうであるように都会暮らしの僕は、一日のうちにお目にかかる動物と言えば数えるほどだ。ハトの群れの横を通り、ミバエを追い払い、広げた雑誌の、ちょうど読んでいるページの上に陣取っている飼い猫クランブルをそおっとどかしてからまた読み続ける。動物は、陳腐な喩えに使われたり奇抜なロゴに使われていたりもするが、意識を持つ生物の大多数を占める存在として描かれることはない。人間は、500種ほどの霊長類、6400種の哺乳類、推定で700万から800万種類いる生物の、たったの一種にすぎない。だが、その事実を僕たちが認識することはめったにない。
僕たちは、動物を生物種やグループに分けて考える──ウシ、犬、キツネ、ゾウ、といった具合に。そしてそれぞれに、人間社会における居場所を与える──ウシは皿の上、犬はソファの上、キツネはゴミ箱の中、ゾウは動物園。それ以外の無数の野生動物たちは、どこか他所(よそ)にいて、願わくば、デイビッド・アッテンボローのドキュメンタリーシリーズの次回に登場してほしい。この、分類する、という能力は素晴らしく人間の役に立った。そうすることによって僕たちは、食べ物を手に入れ、友人や娯楽を見つけ、危険な動物から身を護ることができたのだ。サンドイッチを買うたびに哲学的な議論をする必要もない。自分の存在そのものに罪悪感を感じずに済むのもそのおかげだ。
だがその分類は脆く、壊れやすい。事実、今やこうした分類はバラバラに崩れようとしているのだ。身近な動物たちについての新しい知見が毎日のように報告される。人間が食べ物として扱ってきた動物──なかでもブタとウシ──は、複雑な知性と社会性の持ち主だということが今ではわかっている。昔から、必要のないものとして扱ってきた動物──たとえばオオカミやビーバー──は、実はこの世界になくてはならないものだった。非常に貴重だとされる動物──ジャガーやオランウータンなど──は、人間の進出によって棲むところを失っている。
こうした分類は、動物たちについてよりも、僕たち自身についてより多くのことを語っている。動物たちの、その存在そのものを愛するようになればなるほど、分類はあやふやなものになる。西欧では、日本人がクジラを、韓国人が犬を、カンボジア人がネズミを食べるのは間違っていると考える人が圧倒的に多い。でも、ブタやウシを食べるのは良くてクジラや犬を食べてはいけないのがなぜなのかを説明しようと試みれば、哲学の迷路に迷い込んで出られなくなる。クエンティン・タランティーノの映画『パルプ・フィクション』の中で、犬には「性格がある」から汚い動物じゃない、と主張する殺し屋みたいなものだ。ブタにも性格はある。だったらどうして、年間に15億頭のブタを殺すのは良くて、犬を1匹殺したと言って激怒するのだろう? ブタを味気ない囲いの中に閉じ込めるのは良くて、犬にそれをしてはなぜいけない? 十数頭のクジラを捕獲するのが倫理的に間違っているのに、何百頭ものイルカが絡まってしまう魚網を使うのは間違っていないとされるのはなぜなのか?
平たく言えば、動物愛護は西欧社会の核をなす概念の一つだし、合理的思考もそうだ。ところが、僕たちの動物の扱い方はそのどちらにも沿っていない──昔からの慣習と惰性に従っているだけだ。迫りくる野生動物の集団絶滅を良しとする人はいないだろうし、動物自身だってもちろんだろう。いったいぜんたい僕たちはどうやって、次の世代に集団絶滅を釈明するのか。でもそれは、僕たちの目の前で起こっているのだ。チャールズ・ダーウィンは、顔を赤らめるというのが最も人間らしい表情である、という結論に至った。よかったと思う──だって僕たちには、顔を赤らめる理由が山ほどあるのだから。
新型コロナウイルスが蔓延する以前、楽観論者たちはよくこう言ったものだ──今ほど人間でよかった時代はない、歴史上、好きな時代を選んで生きることができるなら、今がそのときだ、と。でも、他の動物はどの時代を選ぶだろう? 仮にあなたが今、人間以外の哺乳動物に生まれるとすると、畜産場の、狭苦しくて不自然な環境に生まれる可能性が、かつてないほど高い。大規模な酪農場では、1頭の雌牛から搾れる牛乳はおそらく100年前の4倍になっているが、雌牛の寿命は実は短くなっている。野生動物に生まれるとしたら自分の生息地が破壊される、あるいは気候変動に適応できない危険性が先祖たちに比べて高いだろう。「生きている地球指数(Living Planet Index)」によれば、1970年代以降、野生動物の数は平均して3分の1になっている。野生動物の売買が、特にアジアで盛んになっているので、捕獲されて過酷な環境に置かれる可能性も高い。現代のアメリカで飼われている犬の生活──ソファの上でのんびり寝そべり、オーガニックのビスケットを齧り、気の利いたインスタグラムのアカウントだってある──を思い浮かべる人もいるかもしれない。でも、もしも僕たちが無作為に何かの動物に生まれ変わるとしたら、アメリカの畜産場でニワトリとして生まれることになる可能性の方が、少なくとも20倍は高い。いつの時代に生まれるかを選べるとしたら、動物たちは今を選ぶだろうか? 選ばないと僕は思う。
人間が動物のことを──すべての動物のことを考えたらどうなるだろう? 僕たちは、食べ物を手に入れる方法を、自然界の扱い方を、動物園の動物に対する態度を変えるだろうか?
(中略)
ダーウィンの進化論は人々の心の中で、生存を懸けた残忍で非道徳的な競争と結びついた。進化論の起案者であるダーウィンは、人間と動物の関係についてこの科学的発見が何を意味するのか、その答えを出すことを後世に委ねたのである。
嬉しいことに人間は、動物についてじっくり考える時間さえあれば、動物に対する態度を変えることが多い。イギリスで最も有名な自然保護主義者の一人に、南極探検家スコット大佐の息子であるピーター・スコットがいる。1909年生まれのスコットは、WWFの共同創設者の一人である(あの有名なパンダのロゴをデザインしたのも彼だ。パンダが選ばれた理由の一つは、白黒の方がコピーするのに向いていたからだった)。彼は大の愛鳥家で、多くの自然保護活動家に影響を与えた。だが彼は人生の大半を、鳥を撃つのを趣味として過ごした。「狩りをするのは人間の本能の一部であり、狩られるのは鳥の本能の一部である」と彼は書いている。前装式の鉄砲に撃たれるのが鳥の本能であるという理屈はどうしても真実とは思えず、40代になって、狩猟があまりにも容易で残酷であるという現実を突きつけられたスコットは、考えを見事180度転換させた。
同様に、ホールフーズ[アメリカの食料品店チェーン。健康や環境に対する意識の高い店として知られる]の創業者、ジョン・マッキーは、長年ベジタリアンとして店を経営していたが、あるとき、養鶏場や酪農場の環境が劣悪であるのに、自分は卵や牛乳を食べることに抵抗はないのか、と内省した。のちに彼は、ヴィーガンになる前は「見て見ぬふりをしていた」のだと回想し、「そのことをはっきりと認識したくなかったのだ」と言っている。
僕の経験から言うと、動物に対する見方を変えるのは(言葉遊びをするつもりはないが)一つの進化過程である。その過程はまず、漠然とした不快感から始まる。思い出すのは、ある日、飼い犬を去勢したばかりの同僚にたまたま出くわしたときのことだ。「何が問題なのかなんとなくわかったよ」と彼は言った。「まるで『侍女の物語』[カナダの作家マーガレット・アトウッドによるディストピア小説。出生率が低下した架空の国で、数少ない健康な女性はただ子どもを産むための道具として支配者層に仕える「侍女」とされる]みたいでヤバイよな」。それは、他の動物の行く末を人間がコントロールしている、という不愉快な認識だ。
この本のための取材を始める前の僕は、漠然と自然を愛するベジタリアンだった。今はヴィーガンとなり、特定の状況での狩猟や漁獲を支持し、地球上に、他の動物たちのための場所をたっぷり確保する必要があると考えている。あなたが達する結論はそれとは違うかもしれない。この本では、「僕たちは」こう思う、という言い方をすることがある。すべての人間が同じ考え方をするからではない。実際、動物に対する態度が全員一致する家族にさえ、僕はほとんど会ったことがない。だが、僕たちはみな、今よりももっと動物のことを考えるべきだし、動物のことを考えれば、意見が一致する点はたくさんあるということに気づくはずだ。
第一章では、動物に対する人間の態度が、近年のヴィーガン・ブームに至るまでの過去数百年間にいかに変化したかを要約する。その後、人間が現在、畜産・漁猟・医学研究・狩猟などによって動物を殺すことをいかに正当化しているかを検証する。80億人いる雑食性の人間の食料を得るためには何が必要なのか? 後半では、人間がいかにして動物を愛そうとしてきたかについて考える。そのために僕は、サンフランシスコ、モンゴル、コロンビア、インドネシア、そしてイギリスの田舎を訪れ、動物園の所有者、保全生物学者、ペットを飼っている人たちに取材した。本書の最後に、人間だけでなく生きとし生けるものすべてにとってより良い世界をつくるために、僕たちが個人として、また社会としてできる、いくつかの実践的な提案を示す。僕たちはすでに、一部の動物を大事にしている。次はそれを徹底させる番だ。
僕にとってそれは、発見と希望の物語だ──今はまだ脇役だが、これから社会の主流になり得る物語である。「精神(マインド)とは混沌とした喜びであり、そこから未来の世界とより静かな喜びが生まれる」と、ビーグル号での航海中にダーウィンは書いた。人間と他の動物の一番の違いは、人間の精神にある。そして、動物たちとの均衡点を見出すために最も役に立つのも人間の精神だ。
以前の僕は、今現在人間が動物に対して行っているひどい仕打ちは、意図した選択の結果であり、人間は単に、人間以外の動物が大切だと考えていないのだと思っていた。だが今では、それは僕たちが、自分の行動が引き起こす結果についてきちんと考えていなかったせいだと確信している。僕たちには、動物に対して持っている根本的な愛情と矛盾しない生き方をすることが可能だ。動物が僕たちに何を与え、僕たちは彼らに対してどんな責任があるのか、きちんと答えを見つけることができる。動物について、もっと頻繁に、もっと深く考えることで、僕たちは心の平安を見出すことができるのだ。
白状すると、この本を訳しながら、私は翻訳をお引き受けしたことを後悔していた。本書がつまらないからでも、本書の主張に賛同できないからでもない。逆だ。筆者が次々と繰り出す「事実」の、有無を言わさぬ説得力に圧倒され、筆者の主張に賛同しながらも、この本に自分がどこまで影響されたいか、賛同したからと言って本書の主張を自分がどこまで実践できるのか、自信がなかったからだ。言い換えれば私は、あとがきにいったいなんと書けばいいか、皆目わからなかったのだ。
筆者はヴィーガンになれと言う。でも、今の日本では、生半可な覚悟ではヴィーガンになどなれない。美味しいものを食べるという共通の関心で結ばれている友人たちに何と言えばいい? 集まって美味しいものをいただく席で、自分だけ肉や魚や乳製品を食べないなんて申し訳ないではないか。第一、肉を食べないというのはまだしも、大好きな寿司もチーズも食べられないなんて、老い先短い身にあまりにも酷ではないか。まさに理性と感情のせめぎあいである。こんな極端なこと言ったって、実践なんかできっこないじゃない、という反論の声が聞こえてくる。
こんな頼りない人がこの本を訳してよかったんだろうか? 筆者と志を一つにする動物愛護・自然保護活動家で、すでに動物を食べないと決意している人が訳した方がよかったんじゃなかろうか──。そう思いながら、でもその一方で、おそらくこの本を読む人の大多数は私と同じように感じるはずだし、そういう人にこそ読んでもらいたい。だから、この本を読もうか読むまいか迷っている人に向けて、そういう人の代表として、このあとがきを書いている。
本書の原題は『How To Love Animals』である。直訳すれば「動物の愛し方」、あるいは「いかに動物を愛すべきか」とでもなるだろう。筆者ヘンリー・マンスは無類の動物好きで、読者もまた動物が好きであることを前提にしているところがある。私自身も動物は好きだ。かなり好きな方だと思う。インスタグラムの動物動画にはつい時間を忘れて没頭してしまうし、自然が豊富なアメリカの自宅に滞在中には、庭に遊びに来るシカやウサギやアライグマや無数の小鳥たちを眺めて過ごすのが何よりも好きだ。これを書いている今この瞬間も、窓の外にはシカの親子がいて、まだ斑点のある仔鹿が庭を跳ね回っている。私はそれを飽きずに眺める。お金と暇があったら、巨大な望遠レンズを抱えて野生動物を日がな一日撮影していたいと思うくらいだ。
もちろん、世の中そういう人ばかりではない。動物になんかとんと興味がないという人だってたくさんいる。だがこの本は、動物なんか好きじゃない人に動物を好きになれと言っているのではないし、そもそも、動物を愛するというのは動画を眺めてほんわかとした気分になることでも、ペットの犬や猫を溺愛することでもないのだということをわからせてくれる。ひどい扱いをされている動物を見て義憤に駆られる、それだって動物を愛するということなのだ。
そして何よりも、自分が暮らす地球という惑星の未来が、それを意識していようがいまいが、人間と動物の関係のあり方にどれほど影響されているか。本書を読めばもはや「知らなかった」では済まされない。その意味で、本書の日本語タイトル『僕が肉を食べなくなったわけ──動物との付き合い方から見えてくる僕たちの未来』というのは、原書よりも的を射ていると思う。
筆者であるマンスは30代後半のイギリス人ジャーナリストで、『フィナンシャル・タイムズ』紙の特集記事責任者として、主に長編記事を担当している。本書はマンスの初の著作である。インタビュアーとしても評価が高く、ラジオやテレビのニュース番組にも頻繁に登場するという。若いだけあって、その行動力は素晴らしい。本書で展開される彼の主張は単なる机上の空論ではない。豊富なデータによる裏付けももちろんだが、イギリス、アメリカはもとより、ポルトガル、モンゴル、ポーランドに足を運び、「食べ物を入手する」という行為にさまざまな立場で関わる人々や、動物と人間の関係についての研究に従事する人々に得意のインタビューを行い、あるいは自身が屠殺場で働き、ニジマス釣りをし、シカを撃つ、という体験をした中から直接得られた洞察が彼の主張を支えている。
彼が若くしてこの本を書いてくれたことが私は嬉しい。環境問題について書かれた本を読んだり訳したりするたびに、頭のどこかに、自分があと30年若くなくてよかった、地球がめちゃくちゃになる頃まで私は生きていない、逃げ切れてラッキーだった!と思っている自分がいる。どちらかと言えば環境問題に関心が高いつもりではあるし、環境をこれ以上破壊したくない、今かろうじて残っている自然を(動物も植物も含めて)このまま残したい、と思う気持ちはもちろんあるけれど、結局我がこととしてあまり切実には考えていないのかもしれない。だがマンスの世代以降の人たちにとっては、それは自分が直面せざるを得ない火急の課題である。私たち「大人」が地球にしてきた仕打ちに、グレタ・トゥーンベリの世代が怒るのは当然だ。
私が本書で特にハッとさせられた一文に次のようなものがある。
僕たちは、なぜベジタリアンなのか、と人に尋ねるのではなくて、どんな大義のために肉を食べることが必要なのか、と訊くべきではないだろうか?(68ページ)
そうなのだ。私たちはみな、自分はなぜ肉を食べるのだろう、と考えてみる必要がある。本文中にもそれに対する答えはいろいろ出てくるし、たとえば『動物の解放』の著者であるオーストラリアの哲学者ピーター・シンガーの、「昔から肉が、蛋白質とビタミンの供給源として広く普及していること。文化的生活の大きな一部であること」という言葉が引用されていたりもする。蛋白質とビタミンの供給源が他にもあることは明らかだ。では仮に大きな文化的変容が起こって生き物を食べないことこそが「文化的生活」になったとしたら、私に肉や魚を食べなければいられない必然性はないのである。そうして、何が「文化的」な所作であるかなんて、何かのきっかけであっという間に変化する、ということは、ここ10年あまりの間にLGBTQをめぐる人々の考え方に起こった変化を見れば明らかだと思う。だったら私たちは、動物を食べないことこそが文化的であるという「気分の創造」に積極的に加担することで、未来の世代だけでなく、自分たち自身も救うことになるのではないか? 要するに、仲間をどんどん増やすことが文化を変えるのだ。
面白いことに、今日こそはあとがきを書かなければ、と思っていたまさにその日に、たまたま仕事で出席した会議のケータリングをした人が、プラントベース・フード専門のセレブリティ・シェフだった。もちろんその人はこの本のことは知らない。ヴィーガニズムについてレクチャーするためにそこにいたわけでもない。でも、自分の料理を紹介しながら、今この時代にプラントベースのシェフであることほどエキサイティングなことはない、とその人は言った(本書に登場するミシュランの三つ星シェフも同じことを言っている)。全国を飛び回って有名人のためにケータリングを行っている彼女は、自分自身の経験から、(少なくともアメリカの東西の沿岸沿いの都市部では)ベジタリアニズムやヴィーガニズムへの関心が急速に高まっていることをひしひしと感じているという。本書に登場する肉の代替品、インポッシブル・バーガーも話題に出た。
帰りに早速、バーガーキングに立ち寄って、インポッシブル・フーズ(本書122ページ参照のこと)がつくる、植物性蛋白質をベースにした「インポッシブル・ワッパー」を注文した。家に持ち帰り、おそるおそる食べてみたそれは、普通に美味しいハンバーガーだった。
彼女の言葉、そしてインポッシブル・ワッパーの美味しさに、私は勇気づけられている。私は今すぐにベジタリアンやヴィーガンにはなれないかもしれない。でも、肉を食べない(食べなくても他に美味しいものが食べられる)という選択肢があったら、肉を食べないことを選ぼうと思う。そして、本書を読もうかどうか迷っている友人・知人には、読みたくないかもしれないけど、そして肉を食べるか食べないかはあなたの自由だけど、事実を知っておくだけ知った上で決めたほうがよくない? だからよかったら読んでみない?と言ってみようと思っている。反対意見があってもいい。この本が物議を醸すことを私は願う。そしてもう一つ、読後頭から離れないこの言葉を紹介しておきたいと思う。
オックスフォード大学の哲学者、トビー・オードは、人類が絶滅する確率は、20世紀中は100分の1だったが、現在は6分の1であると言う。これは、種の生き残りを賭けたロシアンルーレットなのだ。(329ページ)
(後略)
本書の特徴は、肉食の是非を問うにあたり、屠畜や畜産現場だけではなく、
狩猟、動物園、遺伝子編集研究所などさまざまな動物産業への取材を行い、
人間と動物の関わりを多角的に見つめている点です。
動物を愛し、環境問題に関心を持つ人でも目をそらしがちな刺激的なテーマを、苛烈な感情論ではなく、
家族とのやりとりや英国人らしい肩のこらないジョークをちりばめて軽やかに描きます。
著者はフィナンシャル・タイムズ紙で、主に長編記事を担当している、受賞歴のある特集記事責任者。
イギリス、アメリカはもちろん、ポルトガル、モンゴル、ポーランドなどに足を運び、
食肉工場で働いたり、レストランや動物園経営者を訪ねたりと体験と取材で情報を集めて本書を執筆しました。
地球という惑星の未来が、人間と動物の関係のあり方にどれほど影響されているのか、
「知らなかった」では済まされない現実を描き、
自身と子どもたち、そして地球上すべての動物を公正に扱うためには何を食べ、どう生きるべきかを考える本です。