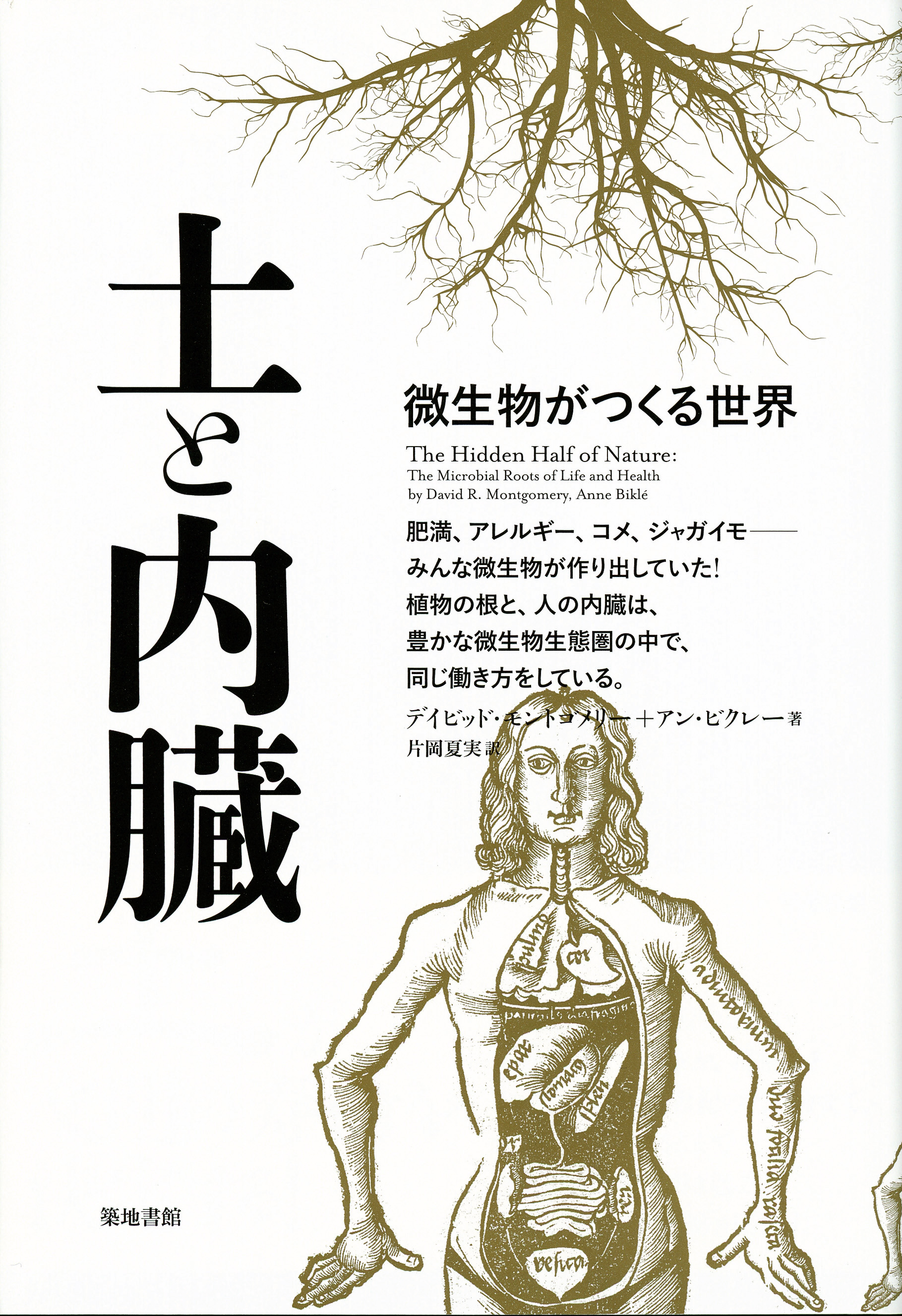ƒIپ[ƒKƒjƒbƒN —L‹@”_–@پAژ©‘RگHƒrƒWƒlƒXپA”Fڈطگ§“x‚©‚çژY’¼ژsڈê‚ـ‚إ
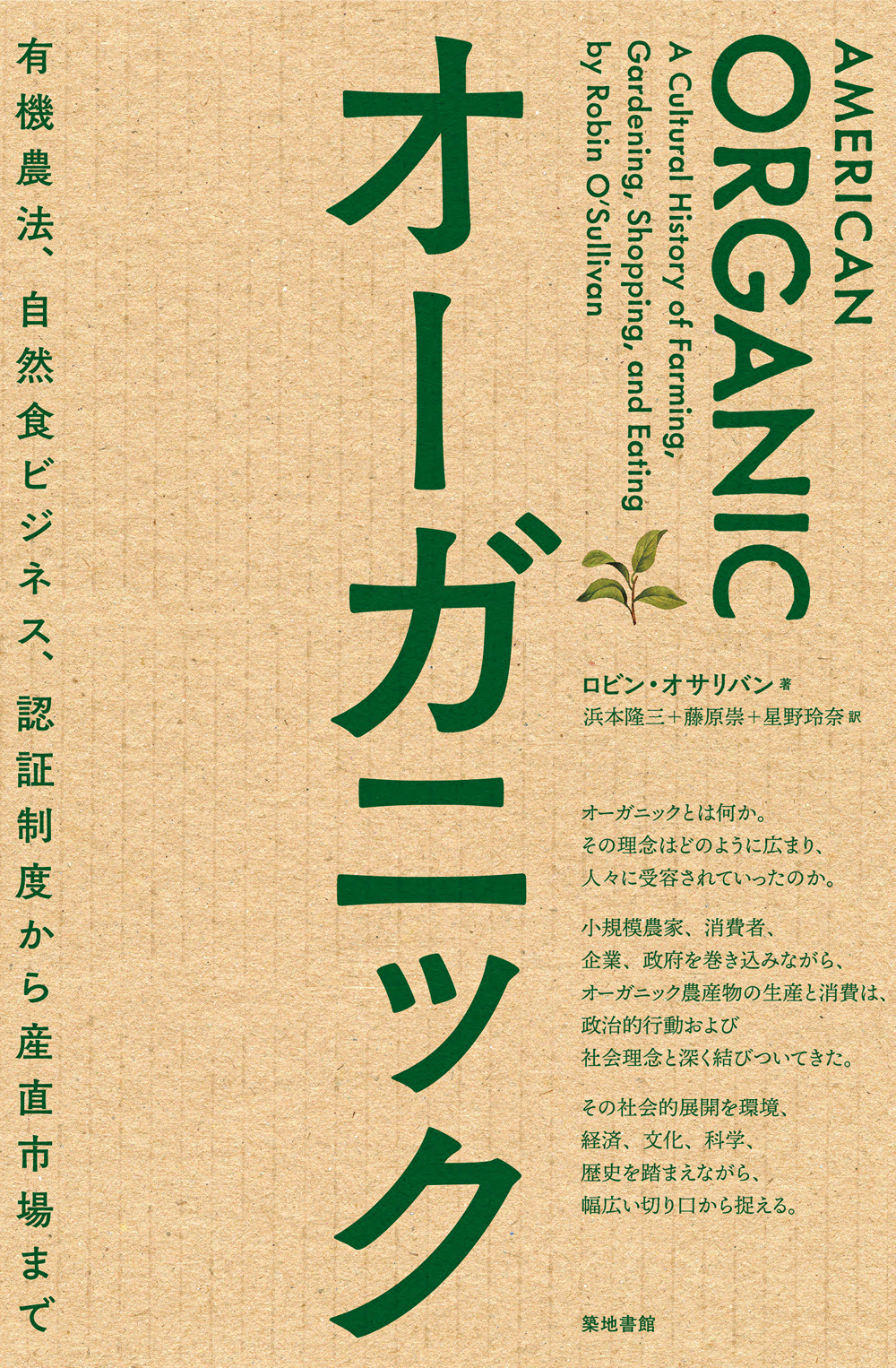
| ƒچƒrƒ“پEƒIƒTƒٹƒoƒ“پm’کپn •l–{—²ژOپA“،Œ´گ’پAگ¯–ى—و“قپm–َپn 3,600‰~+گإپ@ژlکZ”»پ@468•إ 2022”N5Œژٹ§چsپ@ISBN978-4-8067-1636-5 چ‚“«‚·‚鉻ٹw”ى—؟‚âپA’n‹…‚ة•‰‰×‚ً‚©‚¯‚ب‚¢”_‹ئ‚جچف‚è•û‚ھ’چ–ع‚³‚ê‚é’†‚إپA ‰ك‹ژ70”N‚ج•ؤچ‘‚جƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚ج—ًژj‚ً‚ـ‚ئ‚ك‚½پB ژ©‘RگH•i‚â—L‹@”_‚ج‹•‘œ‚ئژہ‘œپA—L‹@”Fڈطگ§“x‚ج”“W‚âپA ”½‘جگ§‰^“®‚ئ‚µ‚ؤ‚جƒIپ[ƒKƒjƒbƒNپAƒAƒ}ƒ]ƒ“‚ھ”ƒژû‚µ‚½—L‹@ƒXپ[ƒpپ[ƒ`ƒFپ[ƒ“‚ب‚اپA ”_‹ئژز‚àپAڈء”ïژز‚àƒnƒbƒsپ[‚بƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚جچف‚è•û‚ً•`‚«پA ‚±‚ê‚©‚ç‚ج“ْ–{‚جژ©‘RگH‚جچف‚è•û‚ً•‚‚«’¤‚è‚ة‚·‚éƒ^ƒCƒ€ƒٹپ[‚ب‚PچûپB پyژه‚ب“à—eپz ‰»ٹw”ى—؟‚ئ”_–ٍ‚ب‚µ‚إ‚ج”_‹ئ ژ©‘R‚ةٹٌ‚è“Y‚¤•é‚炵‚ئƒIپ[ƒKƒjƒbƒN ژ©‹‹ژ©‘«‚ئ‘S—±•² ”_–ٍ‚ئ”_–±ڈب ƒIپ[ƒKƒjƒbƒNپEƒfƒgƒbƒNƒX ƒtƒ@پ[ƒ}پ[ƒYƒ}پ[ƒPƒbƒg ƒxƒWƒ^ƒٹƒAƒ“ ƒGƒRƒ‰ƒxƒ‹ ‘¼ ٹھ––‚ج’چ‚ة‚آ‚«‚ـ‚µ‚ؤپAˆب‰؛‚ج’ت‚èŒfچعکR‚ê‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½‚ج‚إپA‚¨کl‚ر‚µ‚ؤŒfچع‚¢‚½‚µ‚ـ‚·پB https://www.tsukiji-shokan.co.jp/mokuroku/hon-imgs/1636a.pdf |
ƒچƒrƒ“پEƒIƒTƒٹƒoƒ“پiRobin O'Sullivanپj
ƒ_پ[ƒgƒ}ƒX‘هٹwڈ@‹³ٹw‰غ’ِ‘²‹ئپBƒTƒUƒ“پEƒپƒCƒ“‘هٹw‘هٹw‰@ڈCژm‰غ’ِپA‚¨‚و‚رƒeƒLƒTƒX‘هٹw‘هٹw‰@”ژژm‰غ’ِڈC—¹پAPh.DپiƒAƒپƒٹƒJŒ¤‹†پjپB
Œ»چفپAƒAƒ‰ƒoƒ}ڈB—§ƒgƒچƒC‘هٹw—ًژj“Nٹw•”گê”CچuژtپB
ƒAƒپƒٹƒJژjپAƒAƒپƒٹƒJŒ»‘مژjپAƒAƒپƒٹƒJ•¶‰»ژjپAƒAƒپƒٹƒJٹآ‹«ژj‚ب‚ا‚جچu‹`‚ً’S“–پB
ƒAƒپƒٹƒJ•¶‰»ژjپAٹآ‹«ژjپA”_‹ئژjپA•¶‰»’n—ٹwپAƒ|ƒsƒ…ƒ‰پ[ƒJƒ‹ƒ`ƒƒپ[پAگH•iŒ¤‹†پAژذ‰ï‰^“®ک_‚ب‚ا‚ج•ھ–ى‚ةٹضگS‚ًٹٌ‚¹‚ب‚ھ‚çپA
ƒAƒپƒٹƒJŒ¤‹†ٹw‰ïپAٹآ‹«ژjٹw‰ï‚ب‚ا‚إŒ¤‹†ٹˆ“®‚ًچs‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éپB
2015”N‚ةڈ‰‚ج’P’ک‚ئ‚ب‚é–{ڈ‘‚ًƒJƒ“ƒUƒX‘هٹwڈo”إ‹ا‚و‚èٹ§چsپBٹw‰ïژڈ‚ب‚ا‚ةڈ‘•]‚ھŒfچع‚³‚ê‚ؤکb‘è‚ًŒؤ‚ٌ‚¾پB
•l–{—²ژOپi‚ح‚ـ‚à‚ئپE‚è‚م‚¤‚¼‚¤پj
1979”NپA‹“s•{گ¶‚ـ‚êپB“¯ژuژذ‘هٹw–@ٹw•”گژ،ٹw‰ب‘²‹ئپB
“¯‘هٹw‘هٹw‰@ƒAƒپƒٹƒJŒ¤‹†‰بپiŒ»ƒOƒچپ[ƒoƒ‹پEƒXƒ^ƒfƒBپ[ƒYŒ¤‹†‰بپj”ژژmŒمٹْ‰غ’ِ’Pˆتژو“¾–ٹْ‘قٹwپB
Œ»چفپAچb“ى‘هٹw•¶ٹw•”‰pŒê‰p•ؤ•¶ٹw‰بگê”CچuژtپBگê–ه‚ح19گ¢‹IƒAƒپƒٹƒJ‚ج•¶ٹw‚ئ•¶‰»پB
ASLE-Japan/ •¶ٹwپEٹآ‹«ٹw‰ï‚¨‚و‚رƒGƒRƒNƒٹƒeƒBƒVƒYƒ€Œ¤‹†ٹw‰ï‰ïˆُپB
’کڈ‘‚ةپwƒNپ[پEƒNƒ‰ƒbƒNƒXپEƒNƒ‰ƒ“پxپi•½–}ژذگVڈ‘پA2016”NپjپAپwƒAƒپƒٹƒJ‚ج”rٹOژه‹`پxپi•½–}ژذگVڈ‘پA2019 ”NپjپA
’P–َڈ‘‚ةƒoپ[ƒiƒrپ[پEƒRƒ“ƒ‰ƒbƒh‡Vگ¢پwƒAƒuƒTƒ“‚ج•¶‰»ژjپF‹ض’f‚جژً‚ج“ٌ•S”Nپxپi”’گ…ژذپA2016 ”NپjپA
‹¤–َڈ‘‚ةƒ”ƒBƒNƒgƒٹƒAپEƒ”ƒ@ƒ“ƒgƒbƒNپwƒWƒFƒbƒgپEƒZƒbƒNƒXپFƒXƒ`ƒ…ƒڈپ[ƒfƒX‚ج—ًژj‚ئƒAƒپƒٹƒJ“Iپuڈ—گ«‚炵‚³پv‚جŒ`گ¬پxپi–¾گخڈ‘“XپA2018”Nپj‚ب‚ا‚ھ‚ ‚éپB
“،Œ´گ’پi‚س‚¶‚ي‚çپE‚½‚©‚µپj
1979”NپA•؛ŒةŒ§گ¶‚ـ‚êپB“¯ژuژذ‘هٹw•¶ٹw•”‰p•¶ٹw‰ب‘²‹ئپB
“¯‘هٹw‰@•¶ٹwŒ¤‹†‰ب”ژژmŒمٹْ‰غ’ِ’Pˆتژو“¾–ٹْ‘قٹwپB
“¯ژuژذ‘هٹwپA‹ك‹E‘هٹw“™‚إ”ٌڈي‹خچuژt‚ً‹خ‚كپA2018”N“x‚و‚èگغ“ى‘هٹwچ‘چغٹw•”گê”CچuژtپBگê–ه‚ح‰pŒêٹwپB
‹¤–َڈ‘‚ةƒtƒŒƒbƒhپEƒ~ƒjƒbƒNپwƒEƒCƒXƒLپ[پEƒEپ[ƒ}ƒ“پFƒoپ[ƒ{ƒ“پAƒXƒRƒbƒ`پAƒAƒCƒٹƒbƒVƒ…پEƒEƒCƒXƒLپ[‚ئڈ—گ«‚½‚؟‚ج’m‚ç‚ê‚´‚é—ًژjپxپi–¾گخڈ‘“XپA2021 ”NپjپA
ƒٹƒ`ƒƒپ[ƒhپEƒtƒHƒXپw‹َ‚ئ‰F’ˆ‚جگHژ–‚ج—ًژj•¨ŒêپF‹C‹…پA—·‹q‹@‚©‚çƒXƒyپ[ƒXƒVƒƒƒgƒ‹‚ـ‚إپxپiŒ´ڈ‘–[پA2022”Nپj‚ب‚ا‚ھ‚ ‚éپB
گ¯–ى—و“قپi‚ظ‚µ‚جپE‚ê‚¢‚بپj
ٹضگ¼ٹw‰@‘هٹw•¶ٹw•”‰p•¶ٹw‰ب‘²‹ئپBƒ~ƒVƒKƒ“ڈB—§‘هٹw‘هٹw‰@ƒAƒپƒٹƒJŒ¤‹†ƒvƒچƒOƒ‰ƒ€ڈCژm‰غ’ِڈC—¹پB
“¯ژuژذ‘هٹw‘هٹw‰@ƒAƒپƒٹƒJŒ¤‹†‰بپiŒ»ƒOƒچپ[ƒoƒ‹پEƒXƒ^ƒfƒBپ[ƒYŒ¤‹†‰بپj”ژژmŒمٹْ‰غ’ِ’Pˆتژو“¾–ٹْ‘قٹwپB
ٹé‹ئ“àTOEIC Œ¤ڈC‚âژہ–±–|–َ‚ةŒg‚ي‚éپBŒ»چفپAƒoƒ“ƒRƒNچفڈZپB
‚ح‚¶‚ك‚ة
ƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚ً‘¨‚¦‚ب‚¨‚·
ژذ‰ï‰^“®‚ئ‚µ‚ؤ‚جƒIپ[ƒKƒjƒbƒN
پuƒIپ[ƒKƒjƒbƒNپv‚ئ‚ح‰½‚©پH
‘و‚Pڈحپ@ƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚حپu“yپv‚ة’…–ع‚·‚邱‚ئ‚إژn‚ـ‚ء‚½پi1940پ`50”N‘مپj
‚iپE‚hپEƒچƒfƒCƒ‹‚جٹmگM‚ئگي—ھ
ƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚ج‰èگپ‚«
ƒIپ[ƒKƒjƒbƒNژGژڈ‚ج‘nٹ§
ƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚ج‹³‰بڈ‘پwƒyƒCپEƒ_پ[ƒgپx
ƒwƒ“ƒٹپ[پEƒ\ƒچپ[‚ئژ©‹‹ژ©‘«
پu•é‚炵‚جٹwچZپv‘nگف‚ئپw—خ‚جٹv–½پx
—ٍ‰»‚ھگi‚ق“yڈë”ى—€“x
ڈ¬گà‰ئƒuƒچƒ€ƒtƒBپ[ƒ‹ƒh‚ئ”_ڈê
‰بٹw“Iچھ‹’‚جŒ‡”@
ç°گi‚·‚éƒچƒfƒCƒ‹
ژE’ژچـپA“yڈë‰ü—اچـ‚ج•پ‹y
ƒIپ[ƒKƒjƒbƒNگMژز‚ئ‰ù‹^”h
‘و‚Qڈحپ@پw’¾–ظ‚جڈtپxپEƒJƒEƒ“ƒ^پ[ƒJƒ‹ƒ`ƒƒپ[‚©‚çƒGƒRƒچƒWپ[‰^“®‚ضپi1960پ`70”N‘مپj
ƒŒƒCƒ`ƒFƒ‹پEƒJپ[ƒ\ƒ“پw’¾–ظ‚جڈtپx‚ج”g–ن
ƒJƒEƒ“ƒ^پ[ƒJƒ‹ƒ`ƒƒپ[‚ئƒIپ[ƒKƒjƒbƒN
ƒچƒfƒCƒ‹‚جگM•ٍژز‚½‚؟
ƒjƒAƒٹƒ“ƒO•vچب‚جژ©‹‹ژ©‘«گ¶ٹˆ
چL‚ھ‚è‚ًŒ©‚¹‚éƒIپ[ƒKƒjƒbƒN”_‹ئ
‚c‚c‚s‚©‚çƒGƒRƒچƒWپ[‚ض
ƒAƒپƒٹƒJڈ‰‚جƒIپ[ƒKƒjƒbƒN”FڈطƒvƒچƒOƒ‰ƒ€
ƒIپ[ƒKƒjƒbƒNگH•i‚ض‚جٹضگS‚جچ‚‚ـ‚è
ƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‰^“®‚ج“]ٹ·ٹْ
‘و‚Rڈحپ@ƒrƒWƒlƒX‚ئژذ‰ï‰^“®پi1970پ`80”N‘مپj
ƒIپ[ƒKƒjƒbƒNگH•i‚ض‚ج”ل”»
ƒIپ[ƒKƒjƒbƒNگHچق‚جƒuƒ‰ƒ“ƒh‰»
ژ©‰c”_‰ئ‚ئ”_–{ژه‹`
ƒIپ[ƒKƒjƒbƒNƒtƒ‹پ[ƒc‚ًگH‚ׂéƒZƒŒƒu‚½‚؟
ƒIپ[ƒKƒjƒbƒNگH•i‚جچLچگگي—ھ
ƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚ةڈء‹ة“I‚ب•ؤچ‘”_–±ڈب
ƒIپ[ƒKƒjƒbƒNٹé‹ئ‚جڈoŒ»
ƒٹƒ“ƒS‚ئ‚ھ‚ٌ
‘و‚Sڈحپ@–{•¨پ^Œy”–„ں”Fڈط‚ئٹµڈK‰»پi1990”N‘مˆبŒمپj
—L‹@گH•iگ¶ژY–@‚ھ‚à‚½‚炵‚½چ¬—گ
گV‚µ‚¢ƒ^ƒCƒv‚جƒIپ[ƒKƒjƒbƒN”_‰ئ‚½‚؟
ٹآ‹«•غŒىژه‹`‚ئƒIپ[ƒKƒjƒbƒN
ƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚ح–{“–‚ة’n‹…‚ة—D‚µ‚¢‚©پH
ƒچƒJƒ”ƒHƒA‰^“®‚جچL‚ـ‚è
‹گ‘هٹé‹ئ‚ج”_‹ئƒrƒWƒlƒXژQ“ü
ƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚جچ°‚جڈءژ¸
پu–{•¨پv‚جƒIپ[ƒKƒjƒbƒN
‘و‚Tڈحپ@ƒrƒbƒOپEƒoƒbƒhپEƒIپ[ƒKƒjƒbƒN„ںŒ’چNژuŒü‚ئڈ¤‹ئ‰»
ƒIپ[ƒKƒjƒbƒNگH•i‚ج‰h—{‰؟
ƒIپ[ƒKƒjƒbƒNگH•i‚ئ•sŒ’چN‚بƒAƒپƒٹƒJگl
ˆâ“`ژq‘g‚فٹ·‚¦گH•i‚ج“oڈê
گ”‘½‚جƒIپ[ƒKƒjƒbƒNƒuƒ‰ƒ“ƒh‚ًڈٹ—L‚·‚é‹گ‘هٹé‹ئ
“û—cژ™‚ئƒIپ[ƒKƒjƒbƒNگ»•i
ƒIپ[ƒKƒjƒbƒNپEƒ‰ƒxƒ‹‚ض‚ج‰كگM
ƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚ج‹چ“û‚ً‚ك‚®‚é‘›“®
ƒIپ[ƒKƒjƒbƒNگH•i‚ج‰h—{‰؟‚ض‚ج‹^–â
ƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚ة‚ـ‚آ‚ي‚é–µڈ‚
ƒچƒfƒCƒ‹‰ئ‚ج‰e‹؟—ح
‘و‚Uڈحپ@”ü–،‚µ‚¢ٹv–½„ںچ‚‹‰‰»‚ئ‘هڈO‰»
’N‚إ‚à”ƒ‚¦‚éƒIپ[ƒKƒjƒbƒNگH•i
ƒIپ[ƒKƒjƒbƒNگH•i‚ً”ƒ‚¤——R
گ^‚جژ©‘Rژه‹`ژزپAƒچƒnƒVƒAƒ“پAƒjƒ…پ[پEƒ‰ƒOƒWƒ…ƒAƒٹ
ƒzپ[ƒ‹ƒtپ[ƒYƒ}پ[ƒPƒbƒg‚ج‘ن“ھ
چL‚ھ‚éچw”ƒژز‘w
گ»•i‚جچw“ü‚ح“ٹ•[‚إ‚ ‚é
ƒIپ[ƒKƒjƒbƒNژsڈê‚جگوچs‚«
ƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚ح‘±‚¢‚ؤ‚¢‚
–َژز‚ ‚ئ‚ھ‚«
’چ
ژQچl•¶Œ£
چُˆّ
–{ڈ‘‚حAmerican Organic: A Cultural History of Farming, Gardening, Shopping, and Eating‚ج–M–َڈ‘‚إ‚ ‚éپBŒ´ڈ‘‚حƒJƒ“ƒUƒX‘هٹwڈo”إ‹اپiUniversity Press of Kansasپj‚و‚è2015”N‚ةٹ§چs‚³‚ꂽپB
Œ´’کژز‚جƒچƒrƒ“پEƒIƒTƒٹƒoƒ“پiRobin O'Sullivanپjژپ‚حƒAƒپƒٹƒJ“ى•”پAƒAƒ‰ƒoƒ}ڈB‚ة‚ ‚éƒgƒچƒC‘هٹw—ًژjٹw‰ب‚جگê”Cچuژt‚إپA‘هٹw‚إ‚حƒAƒپƒٹƒJŒ»‘مژjپAƒAƒپƒٹƒJ•¶‰»ژjپAƒAƒپƒٹƒJٹآ‹«ژj‚ب‚ا‚جچu‹`‚ً’S“–‚µ‚ؤ‚¢‚éپB
–{ڈ‘‚حŒ»‘مƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚جژj“I“WٹJ‚ًڈعگà‚µ‚½–{–Mڈ‰‚جˆê”تڈ‘‚إ‚ ‚éپB—L‹@”_–@‚ةٹض‚·‚镶Œ£‚حپA‚»‚ج—”O‚âژv‘z‚ًک_‚¶‚½‚à‚ج‚©‚çپAژہ‘H•û–@‚⌻ڈَ•ٌچگ‚ة‚¢‚½‚é‚ـ‚إپA‚·‚إ‚ةگ”‘½‚‚جڈ‘گذ‚ھگ¢‚ةڈo‚ؤ‚¢‚éپB‚»‚جˆê•û‚إپA—L‹@”_–@‚جگ–ى‚جچL‚ھ‚è‚ً–ش—…‚µ‚ب‚ھ‚çپA‚»‚ج—ًژj“IپA•¶‰»“IپAŒoچد“I‚ب”“W‚ج‰ك’ِ‚ًگ®—‚µپA‘جŒn‰»‚µ‚ؤک_‚¶‚½•¶Œ£‚ح‚±‚ê‚ھڈ‰‚ك‚ؤ‚ئ‚¢‚¦‚و‚¤پB
–{ڈ‘‚حŒ´‘è‚ھژ¦‚·’ت‚èپAƒAƒپƒٹƒJ‚ًژه‚ب‘خڈغ‚ئ‚µ‚ؤ‚¨‚èپAƒˆپ[ƒچƒbƒp‚â“ْ–{‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حژث’ِٹO‚ئ‚ب‚éپB‚µ‚©‚µپA–{ک_‚إ‚ح‰pچ‘“yڈ닦‰ïپAƒCƒ“ƒh‚جƒCƒ“ƒhپ[ƒ‹ژ®ڈˆ—–@‚©‚ç“ْ–{گl”_‰ئ‚ج•ں‰ھگ³گM‚ـ‚إپA•چL‚¢Œn•ˆ‚ً‚½‚ا‚è‚ب‚ھ‚猻‘مƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚ج”“W‰ك’ِ‚ً•`‚«ڈo‚µ‚ؤ‚¢‚éپB
Œ»چفپAƒIپ[ƒKƒjƒbƒNڈ¤•i‚جژsڈê‹K–ح‚حپAگ¢ٹE‚إ10’›‰~‚ً’´‚¦‚é‚ـ‚إ‚ة–c‚ç‚ٌ‚إ‚¢‚éپB2015”NپAچ‘کAƒTƒ~ƒbƒg‚إپuSDGsپپژ‘±‰آ”\‚بٹJ”–ع•Wپv‚ھچج‘ً‚³‚ê‚ؤپAگH‚ً‚ك‚®‚éژ‘±‰آ”\گ«پiƒTƒXƒeƒCƒiƒrƒٹƒeƒBپj‚ح’n‹…‘S‘ج‚ج‰غ‘è‚ئ‚ب‚é‚ب‚©پAƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚ة‘خ‚·‚éٹضگS‚à‚³‚ç‚ةچ‚‚ـ‚è‚آ‚آ‚ ‚éپB‚¾‚ھƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚حپA‚»‚جêt–¾ٹْ‚©‚ç‚¢‚آ‚àچDˆس“I‚ةژَ‚¯“ü‚ê‚ç‚ê‚ؤ‚«‚½‚ي‚¯‚إ‚ح‚ب‚©‚ء‚½پBƒIپ[ƒKƒjƒbƒN”_–@‚ة‚حپA‚آ‚ث‚ة‰h—{چ¼‹\‚â‚ع‚ء‚½‚‚è‚ئ‚¢‚ء‚½‹^کfپA‚ ‚é‚¢‚حگ¶ژYگ«‚ھ—ژ‚؟‚邽‚ك‚ةگH—ئ•s‘«‚â‹Q‰ى‚ًڈµ‚‚ئ‚¢‚ء‚½”ل”»‚ھ‚آ‚«‚ـ‚ئ‚ء‚½پB
‚»‚à‚»‚àپAƒIپ[ƒKƒjƒbƒNگHچق‚ھ‚»‚êˆبٹO‚جگH•i‚و‚è‚à—D‚ꂽ‰h—{‰؟‚ً‚à‚آ‚ئ‚¢‚¤’èگà‚ح‚ب‚¢پB‚ـ‚½ژc—¯”_–ٍ‚جŒœ”O‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚àپAŒ¤‹†ژز‚ة‚و‚ء‚ؤچl‚¦‚ح‚³‚ـ‚´‚ـ‚إپAŒ©‰ً‚حˆê’v‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚¢پB‚±‚ج‚و‚¤‚ب”ل”»“I‚بژ‹چہ‚ة—§‚آ‚ئپAƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚ح‰بٹw“IپAچ‡—“I‚بچھ‹’‚ةٹî‚أ‚گH‚ج—D‰zگ«‚ًژ¦‚·‚à‚ج‚إ‚ح‚ب‚پAژَ‚¯ژè‚جٹ´ٹo“IپAگS—“I‚بˆَڈغ‚ةٹî‚أ‚گH‚جژuŒü‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ة‚ب‚éپB
‚±‚ج–£کf“I‚¾‚ھ‘¨‚¦‚ة‚‚‚à‚ ‚éƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚ھپA‚ا‚ج‚و‚¤‚ة”“W‚µپA‚¢‚©‚ة‚µ‚ؤ10’›‰~‹K–ح‚جژsڈê‚ًگط‚èٹJ‚¢‚ؤ‚«‚½‚ج‚©پB‚³‚ـ‚´‚ـ‚بژذ‰ïٹضŒW‚â—کٹQٹضŒW‚ة†‚ـ‚ê‚ب‚ھ‚çپAƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚ھŒ»چف‚جڈَ‹µ‚ة“‚é‚ـ‚إ‚جپA‚»‚ج—ًژj“IپA•¶‰»ژj“I‚ب•د‘J‚ً–{ڈ‘‚ح‰ً‚«–¾‚©‚µ‚ؤ‚¢‚éپB
‚»‚ê‚إ‚حپAٹeڈح‚ج“à—e‚ة‚آ‚¢‚ؤٹب’P‚ةڈذ‰î‚µ‚ؤ‚¨‚±‚¤پB1ڈح‚إ‚حپA1940”N‘م‚©‚ç50”N‘مپAƒAƒپƒٹƒJ‚إƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‰^“®‚ًژn‚ك‚½‚iپE‚hپEƒچƒfƒCƒ‹‚جچvŒ£‚ة’…–ع‚·‚éپB‚ئ‚‚ةƒچƒfƒCƒ‹‚ھ‰e‹؟‚ًژَ‚¯‚½—L‹@”_–@‚ًٹTٹد‚µ‚ب‚ھ‚çپA”ق‚ھ‚¢‚©‚ةگو’B‚ج’mŒb‚ً‘چچ‡‚µپAƒIپ[ƒKƒjƒbƒN”_–@‚ً‚ا‚ج‚و‚¤‚ة’è‹`‚µ‚ؤپA‘ه‚«‚ب‰^“®‚ض‚ئ”“W‚³‚¹‚ؤ‚¢‚ء‚½‚ج‚©ڈعڈq‚·‚éپB
ƒچƒfƒCƒ‹‚حƒIپ[ƒKƒjƒbƒNژہ‘Hژز‚ئ‚¢‚¤‚و‚è‚àپAڈo”إ‹ئ‚ً—§‚؟ڈم‚°‚ؤپAگ”پX‚جژGژڈ‚ئڈ‘گذ‚جٹ§چs‚ً’ت‚µ‚ؤƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚ج•پ‹y‚ةگs—ح‚µ‚½ٹé‹ئ‰ئ‚إ‚ ‚ء‚½پBٹµچs‚ج”_‰ئ‚إ‚ح‚ب‚‚و‚è—ا‚¢گH‚ةٹضگS‚ج‚ ‚éˆê”تژs–¯‚ةŒü‚¯‚ؤپA“ï‰ً‚إژèٹش‚ج‚©‚©‚é—L‹@”_–@‚ً•ھ‚©‚è‚â‚·‚‰ًگà‚µپA‚ـ‚½ژڈڈم‚ةڈî•ٌŒًٹ·‚جڈê‚ًگف‚¯‚ؤپAƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚ج‰è‚ً‘هژ÷‚ض‚ئˆç‚ؤڈم‚°‚½پB
‚»‚جˆê•û‚إپAƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚ة‚ح–G‰èٹْ‚©‚ç‹^”O‚â”ل”»‚ھ‚آ‚«‚ـ‚ئ‚ء‚½پBƒچƒfƒCƒ‹‚حژ©‘R‚ج‚â‚è•û‚إژ©‘R‚ً–ح•ي‚µ‚½”_‹ئ‚ً‹’²‚·‚éˆê•ûپAƒIپ[ƒKƒjƒbƒNگH•i‚ئ‚»‚ج”_–@‚ج—Lˆسگ«‚ًژ¦‚·‰بٹw“Iچھ‹’‚ً–حچُ‚µ‚ؤپA”ل”»‚ئ‘خ›³‚·‚邽‚ك‚ة•…گS‚µ‚½پB‘هگيŒمپA‰»ٹw”ى—؟‚âڈœ‘گچـپAژE’ژچـ‚ج•پ‹y‚ة‚و‚èپAگ¢ٹE‚ج”_ژY•¨‚جژû—ت‚ح’ک‚µ‚‘‰ء‚µ‚ؤ‚¢‚½پBٹµچs”_‰ئ‚ة‚حپAƒIپ[ƒKƒjƒbƒN”_–@‚ح‚ ‚ـ‚è‚ة‚à“IٹO‚ê‚إپAژو‚é‚ة‘«‚ç‚ب‚¢‘¶چف‚ةژv‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚½پB
‘و2ڈح‚إ‚حپAƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚ھچL‚ژذ‰ï‚ةگZ“§‚·‚é1960پ`70”N‘م‚جڈَ‹µ‚ًٹTٹد‚·‚éپBƒxƒgƒiƒ€”½گي‰^“®‚ب‚ا‚ھƒAƒپƒٹƒJ‚ً—h‚é‚ھ‚µ‚ؤ‚¢‚½‚±‚جژ‘مپAƒŒƒCƒ`ƒFƒ‹پEƒJپ[ƒ\ƒ“‚ج‰»ٹw‰کگُ‚ًچگ”‚µ‚½پw’¾–ظ‚جڈtپx‚ھژذ‰ï‚ة‘ه‚«‚بڈصŒ‚‚ً‚à‚½‚炵‚ؤپAٹآ‹«–â‘è‚ھگl—ق‚ج•ّ‚¦‚é‰غ‘è‚ئ‚µ‚ؤچL‚”Fژ¯‚³‚ê‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½پBƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚حژ©‹‹ژ©‘«‚جگ¶ٹˆ‚ً‚·‚é‘خچR•¶‰»‚جٹˆ“®‰ئ‚âƒqƒbƒsپ[‚ç‚ئ‹¤‘¶‚µ‚ب‚ھ‚çپA‚µ‚¾‚¢‚ةگ–ى‚ًچL‚°‚ؤ‚¢‚ء‚½پBŒ’چNگH•i“X‚âژ©‘RگH•i“XپAگ¶ٹˆ‹¦“¯‘gچ‡‚ھٹe’n‚ةڈoŒ»‚µپAٹآ‹«‚ة—D‚µ‚¢گH‚ו¨‚ض‚جٹضگS‚ھچ‚‚ـ‚ء‚½پB
ƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚ھژذ‰ï‚إ‘¶چفٹ´‚ًژ¦‚µ‚ح‚¶‚كپA—L‹@چح”|‚جگH—؟‚ة‘خ‚·‚éژù—v‚ھ‹ں‹‹—ت‚ًڈم‰ٌ‚é‚ئپAƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚ج‹U‘••\ژ¦‚ھ‰،چs‚µپAڈء”ïژز‚ج‚ ‚¢‚¾‚ة‚ح•sگMٹ´‚ھ•ه‚ء‚½پB‚±‚¤‚µ‚½ژ–‘ش‚ًژَ‚¯‚ؤپA1970”N‚ح‚¶‚كپAƒIپ[ƒKƒjƒbƒN”_ژY•¨‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ًژ¦‚·پA”FڈطƒvƒچƒOƒ‰ƒ€‚ھٹe’n‚إژn‚ـ‚éپBƒچƒfƒCƒ‹‚àپuگH•iچ¼‹\ژtپv‚ة’چˆس‚·‚é‚و‚¤ڈء”ïژز‚ة‘i‚¦‚½‚ھپA‘¼•û‚إ‚حپuƒIپ[ƒKƒjƒbƒNگH•iƒJƒ‹ƒg‚ج‹³‘cپv‚ئˆ‰‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½پB
‘و3ڈح‚إ‚حپA1970پ`80”N‘م‚ة‚©‚¯‚ؤپA‘خچR“I‚بگH‚ج‰^“®‚إ‚ ‚ء‚½ƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚ة‘هٹé‹ئ‚ھٹضگS‚ًژ¦‚µژn‚ك‚ؤپAƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚ھژsڈêƒrƒWƒlƒX‚ةژو‚èچ‚ـ‚ê‚ؤ‚¢‚‰ك’ِ‚ً’ا‚¤پB‚±‚جژ‘مپAƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚ة‚ح‘ٹ•د‚ي‚炸”ل”»‚ھ•t‚«‚ـ‚ئ‚ء‚ؤ‚¢‚½پB•ؤچ‘‰h—{ٹw‰ï‚حƒIپ[ƒKƒjƒbƒNگH•i‚ة‚ح“ء•ت‚ب‰h—{‰؟‚âژ،–ü—ح‚ح‚ب‚¢‚ئ’f‚¶پA”_–±’·ٹ¯‚جƒAپ[ƒ‹پEƒoƒbƒc‚حڈ¬‹K–ح”_‰ئ‚ً’÷‚كڈo‚·•ûگj‚ًŒpڈ³‚µ‚ؤ‚¢‚½پB
ˆê•û‚إپAƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚ئ‚¢‚¤ƒuƒ‰ƒ“ƒfƒBƒ“ƒO‚ج’n•à‚ھŒإ‚ـ‚ء‚½‚ج‚à‚±‚جژ‘م‚إ‚ ‚ء‚½پBژذ‰ï–â‘è‚ھ‘ƒ‚‚¤“sژs‚ئپAگ´•n‚ب”_‘؛‚ئ‚¢‚¤‘خ—§‚جچ\گ}‚حپAŒ’‘S‚ب“cژة•—ڈî‚ئ‚¢‚¤Œ¶‘z‚ًگ¶‚فڈo‚µپAƒAƒپƒٹƒJ‚جگ¼•”ٹJ‘ٌ‚ج—ًژj‚ةچھچ·‚µ‚½“ئ—§ژ©‰c”_–¯‚ھچ‚Œ‰‚³‚جŒ©–{‚ئ‚µ‚ؤ‚à‚ؤ‚ح‚₳‚ꂽپB“ْ–{‚إ‚àگl‹C‚جچ‚‚©‚ء‚½ƒeƒŒƒrƒhƒ‰ƒ}پEƒVƒٹپ[ƒYپu‘ه‘گŒ´‚جڈ¬‚³‚ب‰ئپv‚جگ¢ٹE‚إ‚ ‚éپBƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚ح‚±‚ج‚و‚¤‚ب”_–{ژه‹`‚جگ_کb‚ئŒ‹‚ر‚آ‚«پA“cژة‚ج‘f–p‚ب‰ئ‘°Œo‰c‚ج”_ڈê‚ئ‚¢‚¤ƒCƒپپ[ƒW‚ھƒIپ[ƒKƒjƒbƒNگ»•i‚ً”„‚èچ‚à‚¤‚ئ‚·‚éٹé‹ئ‚جچLچگگي—ھ‚ةچI‚ف‚ةژو‚èچ‚ـ‚ê‚ؤ‚¢‚ء‚½پB‚؟‚ه‚¤‚اŒoچد•s‹µ‚⌴–ûچ‚‚ھٹµچs”_‰ئ‚ً‹ê‚µ‚ك‚ؤ‚¢‚½ژ‘مپA—ک‰v‚ًŒ©چ‚ٌ‚إ—L‹@”_–@‚ةˆئ‘ض‚¦‚·‚é”_‰ئ‚àڈoژn‚ك‚½پB
‘و4ڈح‚إ‚ح1990”N‘م‚©‚çچ،“ْ‚ة‚©‚¯‚ؤپAƒIپ[ƒKƒjƒbƒN”Fڈطگ§“x‚ج•پ‹y‚ئپA‚»‚ê‚ھ‚à‚½‚炵‚½—]”g‚ة‚آ‚¢‚ؤ’ا‚ء‚ؤ‚¢‚éپB1990”NˆبŒمپA”Fڈطگ§“x‚ج‰وˆê‰»‚ھگi“W‚µ‚ؤ‚¢‚‚ئپAƒIپ[ƒKƒjƒbƒNژsڈê‚ة‚حڈ«—ˆگ«‚ًŒ©چ‚ٌ‚¾گV‚½‚بژ‘‹à‚ھ—¬‚êچ‚فپAƒچƒfƒCƒ‹‚ھ–²Œ©‚½پu‰©‹à‚ج“yپv‚جƒSپ[ƒ‹ƒhƒ‰ƒbƒVƒ…‚ھŒ»ژہ‚ج‚à‚ج‚ئ‚ب‚ء‚½پB‚»‚جˆê•û‚إپA—L‹@‚ئ‚ح‰½‚©‚ً‚ك‚®‚é‹cک_‚حپA–{—ˆ‚جژv‘z‚ةچھچ·‚µ‚½پu–{•¨پiƒfƒBپ[ƒvپjپv‚جƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚ئ—ک‰v—Dگو‚جپuگَ”–پiƒVƒƒƒچƒEپjپv‚بƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚ئ‚ج‹و•ت‚ض‚ئ“WٹJ‚µ‚½پB‚±‚جڈح‚إ‚حپA–{•¨‚جƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚جژ–—ل‚ئ‚µ‚ؤپA“ْŒnژOگ¢‚ج“چ”_‰ئƒfƒCƒ”ƒBƒbƒhپEƒ}ƒXپEƒ}ƒXƒ‚ƒg‚ًٹـ‚ق4–¼‚ج—L–¼‚ب”_‰ئ‚ًڈذ‰î‚µ‚ؤ‚¢‚éپB
—L‹@گH•i‚جژsڈê‚ھٹg‘ه‚·‚é‚ئپAƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚حگ¶ژYگ«‚ًچإ‘هŒہ‚ةچ‚‚ك‚ؤŒّ—¦“I‚ةژ–‹ئ‚ً“WٹJ‚·‚邱‚ئ‚إ—ک‰v‚ًڈم‚°‚و‚¤‚ئ‚·‚éپA‹K–ح‚جک_—‚âژsڈê‚جک_—‚ةٹھ‚«چ‚ـ‚ê‚ؤ‚¢‚پBگ”گçƒLƒچ‚à—£‚ꂽژY’n‚©‚çپA‘ه—¤‚ً‰،’f‚µ‚ؤڈء”ïژز‚جŒ³‚ض‚ئ“ح‚¯‚ç‚ê‚é—L‹@گH•i‚ھپA‰ت‚½‚µ‚ؤ–{“–‚ة’n‹…ٹآ‹«‚ة—D‚µ‚¢”_–@‚جژY•¨‚ئŒ¾‚¦‚é‚ج‚©پAٹé‹ئ‚ج—‹ü‚ةˆù‚فچ‚ـ‚ꂽƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚ً‚ك‚®‚è‹cک_‚ھٹھ‚«‹N‚±‚éپB’nˆو‚ةچھچ·‚µ‚½گH‚ً‘هگط‚ة‚µ‚ؤپA’nژY’nڈء‚ًŒf‚°‚éپuƒچƒJƒ”ƒHƒGپv‚ھگV‚µ‚¢گH‚ج‰^“®‚ئ‚µ‚ؤچL‚ـ‚ء‚½‚ج‚à‚±‚جژ‘م‚إ‚ ‚ء‚½پB
‘و5ڈح‚إ‚حپAƒIپ[ƒKƒjƒbƒNگH•i‚جڈء”ïژز‚ة’چ–ع‚µپAڈ¤•iچw“ü‚ج“®‹@‚ة‚آ‚¢‚ؤ•ھگح‚ًچs‚ء‚ؤ‚¢‚éپBŒ’چN‚ض‚جٹضگS‚جچ‚‚ـ‚è‚ًژَ‚¯‚ؤپAƒpƒbƒPپ[ƒWگH•i‚ة‚ح‰h—{گ¬•ھ•\ژ¦‚ھ‹`–±‚أ‚¯‚ç‚êپA’لƒJƒچƒٹپ[‚⌸‰–‚ً“ء’¥‚ئ‚·‚é‹@”\گ«گH•i‚âپAٹî‘b“I‚ب‰h—{‚ً•â‚¤‰h—{•âڈ•گH•i‚ھ“oڈꂵ‚½پB‚±‚جگH•i‚ة“ء’è‚جگ«ژ؟‚ً•t—^‚·‚é‚ئ‚¢‚¤“_‚ة’چ–ع‚µ‚½ٹé‹ئ‚ھپAƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚ًƒ}پ[ƒPƒeƒBƒ“ƒO‚جƒcپ[ƒ‹‚ةژو‚è“ü‚ê‚و‚¤‚ئژژ‚ف‚éپBƒnƒCƒ“ƒcپAƒZƒŒƒbƒVƒƒƒ‹پEƒOƒ‹پ[ƒvپAƒXƒgپ[ƒjپ[ƒtƒBپ[ƒ‹ƒh‚ئ‚¢‚ء‚½ƒIپ[ƒKƒjƒbƒNڈ¤•i‚ًˆµ‚¤‘هٹé‹ئ‚ھپA’n‹…‚ة—D‚µ‚¢”_‹ئ‚ًŒf‚°‚ؤڈء”ïژز‚ج—د—ٹد‚ة‘i‚¦‚½‚èپA•a‹C‚ض‚ج•sˆہ‚ً‹ى‚è—§‚ؤ‚½‚è‚·‚éƒ}پ[ƒPƒeƒBƒ“ƒO‚ًچI‚ف‚ة—p‚¢‚ب‚ھ‚çپAژsڈê‚ةƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚ً”„‚èچ‚ٌ‚إ‚¢‚ء‚½پB
‘و6ڈح‚إ‚حپA‘هڈO‰»‚ھ‚·‚·‚قƒIپ[ƒKƒjƒbƒNژsڈê‚جŒ»ڈَ‚ً‘¨‚¦‚½‚¤‚¦‚إپA‚±‚جژsڈê‚جچ،Œم‚ج“W–]‚ة‚آ‚¢‚ؤŒں“¢‚·‚éپBƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚جڈء”ïژز‚حپAڈ‰ٹْ‚جŒ¤‹†‚إ‚حگ¢‘ر”Nژû7000ƒhƒ‹ˆبڈم‚جچ‚ڈٹ“¾”’گl‘w‚ئ•ھگح‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½‚ھپAچ،“ْ‚إ‚حچ•گl‚âƒqƒXƒpƒjƒbƒN‚ة‚àچw”ƒ‘w‚ھچL‚ھ‚èپA’لڈٹ“¾‘wŒü‚¯‚جگH—؟ژx‰‡•i‚ة‚àƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚ج‘I‘ًژˆ‚ًٹـ‚ق‚ئ‚±‚ë‚ھڈoژn‚ك‚ؤ‚¢‚éپBƒIپ[ƒKƒjƒbƒNگ»•i‚جڈء”ï‚حپAگlژي‚â”NژûپAژذ‰ïٹK‘w‚ئ‚ح–³ٹضŒW‚ةٹg‘ه‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚ ‚éپB
ƒzپ[ƒ‹ƒtپ[ƒYƒ}پ[ƒPƒbƒg‚حپAƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚ج‘هڈO‰»‚ًگ¬Œ÷‚ض‚ئ“±‚¢‚½‚à‚ء‚ئ‚à‰e‹؟—ح‚ج‚ ‚ء‚½ٹé‹ئ‚إ‚ ‚ء‚½پB‘هڈO‰»‚جگi“W‚ة‚و‚ء‚ؤپAƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚جƒ`ƒ‡ƒRƒŒپ[ƒgƒoپ[‚âƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚جƒrپ[ƒ‹‚ھ“oڈꂵپA‚¢‚¸‚ê‚حƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚جƒWƒƒƒ“ƒNپEƒtپ[ƒh‚ـ‚إڈoŒ»‚·‚é‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©‚ئ‚جŒœ”O‚à‚ ‚éپB–{ڈ‘‚إ‚حƒIپ[ƒKƒjƒbƒNژsڈê‚جٹg‘ه‚ًکëلص‚µ‚آ‚آپAƒIپ[ƒKƒjƒbƒNگH•i‚جژù—v‚ج’†ٹj‚ً’S‚¤پuگ^‚جژ©‘Rژه‹`ژزپv‘w‚âپAŒ’چN‚إژ‘±‰آ”\‚بگ¶ٹˆ‚ً–عژw‚·پuƒچƒnƒXپv‚ئŒؤ‚خ‚ê‚é’ھ—¬پA‚ـ‚½‚؟‚ه‚ء‚ئ‚µ‚½وز‘ٍ•i‚ًٹy‚µ‚قپuƒjƒ…پ[پEƒ‰ƒOƒWƒ…ƒAƒٹپv‚ئ‚¢‚ء‚½ڈء”ïچs“®‚©‚çپA‘هڈO‰»‚µ‚½ƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚جڈء”ïچs“®‚ً•ھگح‚µ‚ؤ‚¢‚éپB
ˆبڈمپAٹeڈح‚ج“à—e‚ًٹTگà‚µ‚½‚ھپAƒIƒTƒٹƒoƒ“ژپ‚ھپu‚ح‚¶‚ك‚ةپv‚إ‹L‚µ‚ؤ‚¢‚é’ت‚èپA–{ڈ‘‚إ‚حڈح‚ً‚ـ‚½‚¢‚إ•،گ”‚جک_“_‚ھ•ہ‘–‚µپAکb‘è‚à‘½ٹٍ‚ة‚ي‚½‚邽‚كپA‹cک_‚ج‘S‘ج‘œ‚ً”cˆ¬‚·‚邱‚ئ‚ح—eˆص‚إ‚ح‚ب‚¢پBƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚ج—ًژj‚ة‚حپA‚³‚ـ‚´‚ـ‚ب—حٹwٹضŒW‚ھ—چ‚فچ‡‚¤پB‚¢‚¸‚ê‚جکb‘è‚à‹»–،گ[‚پA‚©‚آڈd—v‚إ‚ ‚邽‚كپA‚»‚ê‚ç‚ً–ش—…‚µ‚ب‚ھ‚çŒn“—§‚ؤ‚ؤگà–¾‚·‚é‚ج‚حژٹ“ï‚ج‹ئ‚إ‚ ‚éپB‚¾‚ھƒIƒTƒٹƒoƒ“ژپ‚حپA‚»‚ê‚ً–{ڈ‘‚إŒ©ژ–‚ة‚â‚ء‚ؤ‚ج‚¯‚½پB
‚ب‚¨پAƒIƒTƒٹƒoƒ“ژپ‚حƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚ًگ„ڈ§‚µ‚½‚èپA‚ ‚é‚¢‚ح”ل”»‚µ‚½‚è‚·‚éپA“ء’è‚ج—§ڈê‚©‚ç–{ڈ‘‚ًژ·•M‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ي‚¯‚إ‚ح‚ب‚¢پBٹwژز‚ئ‚µ‚ؤ’†—§‚ج—§ڈê‚ًژç‚èپAٹw–â“I‚ب’T‹پگS‚ةٹî‚أ‚«پAƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚ة‚آ‚¢‚ؤŒ¤‹†‚µ‚ؤ‚¢‚éپB‚±‚ج“_‚ح‚ئ‚‚ة‹’²‚µ‚ؤ‚¨‚•K—v‚ھ‚ ‚éپB
‚³‚ؤپAƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚ج—ًژj‚ھ•،ژG‚إ‚ ‚é——R‚حپAŒë‰ً‚ً‹°‚ꂸ‚ةŒ¾‚¦‚خپAƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚ة‚ح‚»‚ê‚ًچ\گ¬‚·‚é–{ژ؟‚ھ‘¶چف‚µ‚ب‚¢پA‚ئ‚¢‚¤“_‚ة‹Nˆِ‚µ‚ؤ‚¢‚é‚©‚ç‚ئ‚¢‚¦‚é‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚¾‚낤‚©پBƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚ج‰^“®‚حپA“–ڈ‰‚حٹµچs”_‹ئپAچ‡—‰»‚âŒّ—¦‰»پA‰بٹwژه‹`پAژY‹ئژ‘–{ژه‹`‚ئ‚¢‚ء‚½•¶–¾ژذ‰ï‚ة‘خچR‚·‚镶‰»“I•¶–¬‚ةچھچ·‚µ‚ؤ‚¢‚½پB‘¼•û‚إ‚حپA’n‹…ٹآ‹«‚âژ©‘R‚ة—D‚µ‚¢”_–@پAگg‘ج‚ة‚à—D‚µ‚¢گH•i‚ئ‚¢‚ء‚½•¶–¬‚ة‚àژ²‘«‚ھ‚ ‚ء‚½پB
‚¾‚ھپA”Fڈطگ§“x‚ھƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚ة’è‹`‚ًژ‚؟چ‚ٌ‚¾‚±‚ئ‚إپA—L‹@”_–@‚ج—”O‚â—‘zپAٹ´ٹo“I‚بŒoŒ±‚ئٹ¨‚حپAچ‡—“I‚©‚آ—گ«“I‚ب–@“Iکg‘g‚ف‚ض‚ئ‘g‚ف‘ض‚¦‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ء‚½پBƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚حپA‚à‚ح‚âژ©‘R‚ةٹw‚ر‚ب‚ھ‚çŒoŒ±‚ًڈd‚ث‚½Œ؛گl‚ة‚ج‚ف‹–‚³‚ê‚é”_–@‚إ‚ح‚ب‚پA‰وˆê“I‚بٹîڈ€‚ًڈ‡ژ炵‚³‚¦‚·‚ê‚خپA—eˆص‚ةژو‚è‘g‚ق‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚é”_–@‚ئ‚ب‚ء‚½پB
ژ؟‚ض‚ج‚±‚¾‚ي‚è‚ھ–@“I‚بکg‘g‚ف‚ةژو‚ء‚ؤ‘ض‚ي‚èپAƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚جˆس–،‚·‚é‚à‚ج‚ھ–{ژ؟“I‚ة“ü‚ê‘ض‚ي‚ء‚½‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚حپAƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚ًچ\گ¬‚·‚é•پ•ص“I‚ب–{ژ؟‚ح‘¶چف‚µ‚ب‚¢پA‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ة‚ب‚éپB‚»‚ê‚إ‚àڈء”ïژز‚ھƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚ة–£—¹‚³‚ê‚é——R‚حپAژ©‘R‚جŒb‚ف‚إ‚ ‚é”_ژY•¨‚ةگlˆ×“I‚ب•t‰ء‰؟’l‚ً—^‚¦‚é—]’n‚ًپAƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚ھŒ©ڈo‚µ‚½‚©‚ç‚ئ‚¢‚¦‚é‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚¾‚낤‚©پB
”üگH‰ئ‚جƒuƒٹƒAپپƒTƒ”ƒ@ƒ‰ƒ“‚ةŒ¾‚ي‚¹‚ê‚خپAگH‚ح‘ج‚ً•\‚µپAگH‚حچ‘‚ج‰^–½‚ً‚àچ¶‰E‚·‚éپBگH‚ئ‚ح•sژv‹c‚ب‚à‚ج‚إپAچ‹‰ط‚بژM‚ة–ع‚ً’D‚ي‚ê‚ؤ‚àپA“éگُ‚ف‚ج–،‚ةڈں‚é‚à‚ج‚ح‚ب‚¢پB–،‚جچD‚ف‚حپA—گ«‚إ‚ح‚ب‚ٹ´گ«‚ةچھچ·‚µ‚ؤ‚¢‚éپB‚»‚جٹ´گ«‚ھڈh‚錴Œ^‚©‚ç‘ه‚«‚ˆي‚ê‚邱‚ئ‚ب‚پAڈ¤•i‚ج•iژ؟‚ج—Dˆتگ«‚ًژ¦‚·‚±‚ئ‚ح“‚¢پB‚±‚±‚ةپAƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚جڈ¤•iژsڈê‚ھٹJ‚¯‚½—vˆِ‚ھ‚ ‚é‚ئ‚¢‚¦‚éپB
ƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚ة‚حژٹشژ²‚ھڈd—v‚ب–ًٹ„‚ً‰ت‚½‚µ‚ؤ‚¢‚éپBƒIپ[ƒKƒjƒbƒN”Fڈط‚حپA—D‚ꂽ•iژ؟‚ً•غڈط‚·‚é‚à‚ج‚إ‚ح‚ب‚پA‚»‚ج•iژ؟‚ًپu•¨Œê‚éپv‚à‚ج‚إ‚ ‚éپBڈء”ïژز‚حپA‚»‚جگ¶ژY‰ك’ِ‚ً•]‰؟‚µپAŒû‚ة‚·‚éگl‚جŒ’چN‚â’n‹…ٹآ‹«‚ة‚ب‚ٌ‚ç‚©‚ج—ا‚¢‰e‹؟‚ھ‹y‚ش‚±‚ئ‚ًٹْ‘ز‚µ‚ؤچw“ü‚·‚éپB‚»‚ê‚ن‚¦پAƒIپ[ƒKƒjƒbƒNگ»•i‚ج•t‰ء‰؟’l‚ئ‚حپA‚»‚جگ»•i‚جژٹشژ²ڈم‚ةچL‚ھ‚镶–¬‚ة‚ ‚èپAڈء”ïژز‚ح‚»‚ج•¨Œê‚ً”ƒ‚ء‚ؤ‚¢‚é‚à‚ج‚ئ‚¢‚¦‚邾‚낤پB
–{ڈ‘‚ج–|–َ‚ج‚«‚ء‚©‚¯‚حپAژ„پi•l–{پj‚ھ’S“–‚·‚é‘هٹw‚ج‰‰ڈKژِ‹ئ‚إپAٹwگ¶‚ئژ‹’®‚µ‚½ƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[پEƒtƒBƒ‹ƒ€پwƒtپ[ƒhپEƒCƒ“ƒNپxپiƒچƒoپ[ƒgپEƒPƒiپ[ٹؤ“آپA2010”Nپj‚ةڈصŒ‚‚ًژَ‚¯‚½‚±‚ئ‚ة‚½‚ا‚ç‚ê‚éپBƒAƒپƒٹƒJ‚جگH‚ة”E‚رٹٌ‚éٹë‹@‚ة”—‚ء‚½‚±‚جƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[‚ًŒ©‚ب‚ھ‚çپA“ْ–{‚جگH‚ة‚آ‚¢‚ؤٹwگ¶‚ھچs‚ب‚ء‚½ƒٹƒTپ[ƒ`‚ج•ٌچگ‚ً•·‚‚ب‚©‚إپA‚±‚ê‚ـ‚إٹyٹدژ‹‚µ‚ؤ‚¢‚½“ْ–{‚جگH‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚àپA‚«‚؟‚ٌ‚ئŒü‚«چ‡‚ء‚ؤچl‚¦‚ؤ‚ف‚½‚¢‚ئژv‚¤‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½پB
ٹwگ¶ژ‘مپAژ„‚ح‘نڈٹ‚ج‚ب‚¢ٹشژط‚è‚إ‰؛ڈh‚µپAگHژ–‚ح‚à‚ء‚د‚ç‹چک¥‰®‚ب‚ا‚جٹOگH‚ة—ٹ‚èپAگH”ï‚ًچي‚邽‚ك‚ةƒhƒbƒOƒtپ[ƒh‚ةƒ}ƒˆƒlپ[ƒY‚ً‚©‚¯‚ؤگH‚ׂؤ‚¢‚½‚±‚ئ‚à‚ ‚é‚ظ‚اپAگH‚ة‚ح–³“ع’…‚إ‚ ‚ء‚½پB‚¾‚ھپA“ٌژ™‚ج•ƒ‚ة‚ب‚ء‚½‚¢‚ـپAژq‚ا‚à‚ة‚ح—ا‚¢‚à‚ج‚ًگH‚ׂ³‚¹‚½‚¢‚ئژv‚¤‚و‚¤‚ة‚ب‚èپA‹كڈٹ‚جژY’¼ژsڈê‚ةڈoŒü‚‚±‚ئ‚ھپA‰ئ‘°‚إ‰ك‚²‚·‹x“ْ‚ج’è”ش‚ئ‚ب‚ء‚½پB‚»‚ê‚إ‚àپA–ىچط‚ة‘N“x‚ح‹پ‚ك‚é‚ھپAƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚ب‚ا‚جچح”|•û–@‚ة‚ـ‚إ‚ح‚±‚¾‚ي‚ء‚ؤ‚±‚ب‚©‚ء‚½پB
ƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚ة‚آ‚¢‚ؤپAژ„Œآگl‚جŒ©‰ً‚ًڈq‚ׂé‚ئپAٹµچs‚ج”_ژY•i‚و‚è‚à‰½‚©‚µ‚ç—D‚ꂽ“_‚ھ‚ ‚èپAژc—¯”_–ٍ‚جگS”z‚ھ‚ب‚پAٹآ‹«‚ة‚à—D‚µ‚¢ˆç‚ؤ‚ç‚ê•û‚ً‚µ‚½پA—‘z‚ج”_ژY•i‚ئ‚¢‚¤ˆَڈغ‚ً‚à‚ء‚ؤ‚¢‚éپB‚»‚ê‚إ‚àپA‚±‚ê‚ـ‚إ‚ئ‚‚ةƒIپ[ƒKƒjƒbƒN‚ج”_ژY•¨‚ًگد‹ة“I‚ة‘I‚ٌ‚إ‚±‚ب‚©‚ء‚½——R‚ًچl‚¦‚é‚ئپAٹwگ¶ژ‘م‚©‚ç‚ج•n–Rگ«‚ھ”²‚¯‚«‚ء‚ؤ‚¨‚炸پA‰؟ٹiڈdژ‹‚إڈ¤•i‚ً‘I‚ٌ‚إ‚¢‚é“_پA—L‹@–ىچط‚ئ‚¢‚¤‘I‘ًژˆ‚ھگg‹ك‚بڈ¬”„“X‚جڈ¤•i’I‚ة‚حڈ‚ب‚¢پi‚©پA‚»‚ê‚ًˆسژ¯‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚¢پj“_پA‰؟ٹi‚ةŒ©چ‡‚ء‚½ژ؟‚âŒّ‰ت‚ھŒ©چ‚ك‚é‚ج‚©‚ي‚©‚ç‚ب‚¢“_پA‚ئ‚¢‚ء‚½‚à‚ج‚ھژv‚¢“–‚½‚é‚ھپA‚ب‚©‚إ‚à‚à‚ء‚ئ‚à‘ه‚«‚ب—vˆِ‚حپAٹµچs”_‹ئ‚ج”_ژY•i‚إ‚à–‘«‚µ‚ؤ‚¢‚é‚©‚ç‚ئ‚¢‚¤“_‚ة‚ ‚é‚ئ“àڈب‚µ‚ؤ‚¢‚éپB‚¨‚»‚炈ê”ت“I‚بڈء”ïژز‚جٹ´ٹo‚àپA‚±‚ê‚ة‹ك‚¢‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚¾‚낤‚©پB
‚µ‚©‚µ‚¢‚ـپAگ¢ٹE‚جگH‚ً‚ك‚®‚éٹآ‹«‚ح‘ه‚«‚بٹٍکH‚ةچ·‚µٹ|‚©‚©‚è‚آ‚آ‚ ‚éپB2020”N5ŒژپA‚d‚t‚حپuFarm to Forkپi”_ڈê‚©‚çگH‘ى‚ـ‚إپjگي—ھپv‚ً”•\‚µپA2030”N‚ـ‚إ‚ة—L‹@”_‹ئ‚ً25پ“‚ةٹg‘ه‚µپA‰»ٹw”_–ٍ‚جژg—p“™‚ً50پ“Œ¸‚ç‚·‚ئ‚¢‚¤–ع•W‚ً”•\‚µ‚½پB“¯”N2Œژ‚ة‚حپA•ؤچ‘‚à2050”N‚ـ‚إ‚ة”_‹ئگ¶ژY‚ة‹Nˆِ‚·‚éٹآ‹«•‰‰×‚ً”¼Œ¸‚³‚¹‚éپu”_‹ئƒCƒmƒxپ[ƒVƒ‡ƒ“ƒAƒWƒFƒ“ƒ_پv‚ً‘إ‚؟ڈo‚·‚ب‚اپAژ‘±‰آ”\‚بگH—؟گ¶ژYƒVƒXƒeƒ€‚ض‚جٹضگS‚حگ¢ٹE“I‚ب’ھ—¬‚ئ‚ب‚è‚آ‚آ‚ ‚éپB
‚±‚جگ¢ٹE‚ج’ھ—¬‚ًژَ‚¯‚ؤپA“ْ–{‚ج”_—رگ…ژYڈب‚à2021”N5ŒژپA2050”N‚ـ‚إ‚ة—L‹@”_‹ئ‚ج”_’n–تگد‚ً25پ“‚ةٹg‘ه‚·‚邱‚ئ‚ب‚ا‚ًٹـ‚قپAپu‚ف‚ا‚è‚جگH—؟ƒVƒXƒeƒ€گي—ھپv‚ً”•\‚µ‚½پBŒ»چفپA“ْ–{‚ج—L‹@”_‹ئ‚ج”_’n”ن—¦‚ح0.5پ“’ِ“x‚إپA‚»‚ê‚ًچ،Œم30”N‚إ25پ“‚ة‚ـ‚إٹg‘ه‚³‚¹‚é‚ئ‚¢‚¤–ع•Wگف’è‚حپA‚ب‚©‚ب‚©’§گي“I‚إ‚ ‚éپB
‚ظ‚©‚ة‚àپA”_—رگ…ژY‹ئ‚جCO2ƒ[ƒچƒGƒ~ƒbƒVƒ‡ƒ“‰»‚≻ٹw”_–ٍ‚جژg—p—ت‚ً50پ“’لŒ¸‚·‚é‚ئ‚¢‚ء‚½پA14چ€–ع‚ج–ىگS“I‚ب–ع•W‚ھ•ہ‚رپA‹ï‘ج“I‚بگ”’l‚ھگ·‚èچ‚ـ‚ꂽپA‚±‚ê‚ـ‚إ‚ة‚ب‚¢‘ه’_‚بŒv‰و‚ئ•]‰؟‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپB
‚±‚ج’§گي“I‚بگ”’l–ع•W‚حپA“ْ–{‚ج—L‹@”_‹ئ‚جŒ»ڈَ‚ة‘خ‚·‚é”_گ…ڈب‚ج”Fژ¯‚âپAچ‘“à”_‹ئ‚جچ،Œم‚ة‘خ‚·‚铯ڈب‚جٹë‹@ٹ´‚ج•\‚ê‚ئژَ‚¯ژو‚ê‚éپB—L‹@گH•i‚ھ‚و‚èگg‹ك‚ب‘I‘ًژˆ‚ة‚ب‚邱‚ئ‚حٹ½Œ}‚³‚ê‚éˆê•ûپA‚±‚جŒv‰و‚ة‚ح‹C‚ة‚ب‚é“_‚àژw“E‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپB‚½‚ئ‚¦‚خپAƒQƒmƒ€•زڈW‚âˆâ“`ژq‘g‚فٹ·‚¦‹Zڈp‚ةچm’è“I‚بژpگ¨‚âپAˆê•”‚جٹé‹ئ‚ھگ¶ژYژè’i‚ًڈ¶ˆ¬‚·‚邱‚ئ‚ض‚جŒœ”O‚ج‚ ‚éچ‚“x‚ب‚h‚s‹Zڈp‚ج”_‹ئ‚ض‚ج“±“üپA‚ ‚é‚¢‚حˆہ‘Sگ«‚âٹآ‹«‚ض‚ج‰e‹؟‚ھ–¢’m‚ج‚q‚m‚`”_–ٍپiٹQ’ژ‚جˆâ“`ژq‚ً‘€چى‚·‚éژںگ¢‘م”_–ٍپj‚جژg—p‚ب‚ا‚إ‚ ‚éپBŒ©•û‚ة‚و‚ء‚ؤ‚حپA”_‹ئ‚ة”²–{“I‚بƒCƒmƒxپ[ƒVƒ‡ƒ“‚ً“±“ü‚·‚邽‚ك‚جپA•zگخ‚ئ‚µ‚ؤ‚جˆس–،چ‡‚¢‚ھ‹‚¢‚ج‚إ‚ح‚ئ‚àژَ‚¯ژو‚ê‚é–ع•W‚إ‚ ‚éپB
”_گ…ڈب‚ئ”_‹¦‚ھپAژè‚ًژو‚èچ‡‚ء‚ؤ”_–ٍ‚âژE’ژچـ‚ًژè•ْ‚µپA‘ح”ى‚أ‚‚è‚ًڈ§—م‚µ‚ح‚¶‚ك‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ب‚ج‚¾‚낤‚©پB‚»‚¤‚إ‚ب‚¯‚ê‚خپA‚±‚جŒv‰و‚ھوگ‚¤—L‹@”_’n‚ً25پ“‚ةٹg‘ه‚µپA‰»ٹw”_–ٍ‚ً50پ“چيŒ¸‚·‚é‚ئ‚¢‚¤‚©‚آ‚ؤ‚ب‚¢–ع•W‚حپA‚ا‚ج‚و‚¤‚ة’Bگ¬‚³‚ê‚é‚ج‚إ‚ ‚낤‚©پB—âگأ‚ة‚ب‚ء‚ؤچl‚¦‚é‚ئپA‚ق‚µ‚ë•s‹C–،‚ة‚àژv‚¦‚ؤ‚‚éپB—L‹@”_’n‚جٹg‘ه‚ئ‚¢‚¤–ع•W’Bگ¬‚ج‚½‚ك‚ةپAگ”’l‚خ‚©‚è‚ً’ا‚¤‚±‚ئ‚ة‚ب‚ê‚خپA—L‹@”_‹ئ‚ة‘خ‚·‚éگM—ٹژ©‘ج‚ھ—h‚炬‚©‚ث‚ب‚¢پB“ْ–{‚ج—L‹@”Fڈط‚ً’S‚¤‚i‚`‚rگ§“x‚ھپAگV‚µ‚¢”_‹ئ‹Zڈp‚ئ‚ا‚¤Œü‚«چ‡‚¤‚ج‚©پA’چژ‹‚µ‚ؤ‚¢‚•K—v‚ھ‚ ‚éپB
2019”N‚و‚èگ¢ٹE‚ًگk‚³‚¹‚½گVŒ^ƒRƒچƒiƒEƒCƒ‹ƒXپiCOVID-19پj‚ئ‚حپA‚¢‚ي‚خ‰بٹw‚ئ•¶–¾‚جپu–h”g’çپv‚ً‰z‚¦‚ؤژ©‘RٹE‚©‚猻‘مژذ‰ï‚ة—¬‚êچ‚ٌ‚إ‚«‚½پAگlڈb‹¤’تٹ´گُڈا‚جƒEƒCƒ‹ƒX‚إ‚ ‚éپB‚±‚ê‚ـ‚إ‚àپA‚±‚ê‚©‚ç‚àگl—ق‚حپA‚±‚¤‚µ‚½ƒEƒCƒ‹ƒX‚ئ‚ح‹¤‘¶‚µ‚ؤ‚¢‚©‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢پB‚»‚µ‚ؤ‚±‚¤‚µ‚½ƒEƒCƒ‹ƒX‚حپA—L’{”_‹ئ‚ئگط‚è—£‚³‚ꂽچHڈêŒ^’{ژY‹ئ‚ئ–³‰ڈ‚إ‚ح‚ب‚¢‚±‚ئ‚à’m‚ء‚ؤ‚¨‚‚ׂ«‚¾‚낤پBگl—ق‚جˆس‚ج‚ـ‚ـ‚ة‚ح‚ب‚ç‚ب‚¢ژ©‘R‚ً‘ٹژè‚ة‚µ‚½”_‹ئ‚حپA‚آ‚ث‚ة‚±‚ج‚و‚¤‚ب•sٹm’è—v‘f‚ئŒü‚«چ‡‚¢‚ب‚ھ‚çپAگـ‚èچ‡‚¢‚ً‚آ‚¯پA‰ن‚ي‚ê‚ج–L‚©‚بگHگ¶ٹˆ‚ًژx‚¦‚ؤ‚‚ê‚ؤ‚¢‚éپB‚±‚ê‚ة‚حپA—L‹@‚âٹµچs‚ج•ت‚ب‚پA‚½‚¾ٹ´ژس‚ج”O‚µ‚©‚ب‚¢پB‚¢‚ـ‰ن‚ي‚ê‚ة•K—v‚ب‚ج‚حپA‚±‚جپu“–‚½‚è‘Oپv‚¾‚ئژv‚ء‚ؤ‚¢‚é–L‚©‚بگHگ¶ٹˆ‚ً‚¢‚©‚ةژç‚ء‚ؤ‚¢‚‚ج‚©پAچl‚¦‚é“_‚ة‚ ‚é‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚¾‚낤‚©پB
‚½‚ئ‚¦‚خ–{ڈ‘‚إ‚حپAڈ¤•i‚ج‘I‘ً‚حپu“ٹ•[پvچs“®‚ئ“¯‚¶‚¾‚ئڈذ‰î‚µ‚ؤ‚¢‚éپi‚»‚جŒہٹE‚àژw“E‚³‚ê‚ؤ‚ح‚¢‚éپjپBڈء”ïژز‚جڈء”ïچs“®‚ة‚حپA”_‹ئگچô‚â”_–@‚ة‚آ‚¢‚ؤˆسژu•\ژ¦‚ً‚·‚é—ح‚ھ‚ ‚éپB‰ن‚ي‚ê‚حگH‚جژہڈî‚ً’m‚èپAچl‚¦پAڈ¬‚³‚بگ؛‚ًڈم‚°‚ؤپA‰ن‚ي‚êژ©گg‚جپA‚»‚µ‚ؤ–¢—ˆ‚جگ¢‘م‚جپA–L‚©‚إˆہ‘S‚بگH‚ًژç‚ء‚ؤ‚¢‚©‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢پBگH‚ًژو‚èٹھ‚ڈَ‹µ‚حپAŒˆ‚µ‚ؤٹyٹد‚إ‚«‚é‚à‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢پB–{ڈ‘‚ھ“ْ–{‚جگH‚ج–¢—ˆ‚ًچl‚¦‚邽‚ك‚جپA‚³‚³‚â‚©‚بˆêڈ•‚ة‚ب‚ê‚خ–َژز–»—ک‚ةگs‚«‚éپBپiŒم—ھپj