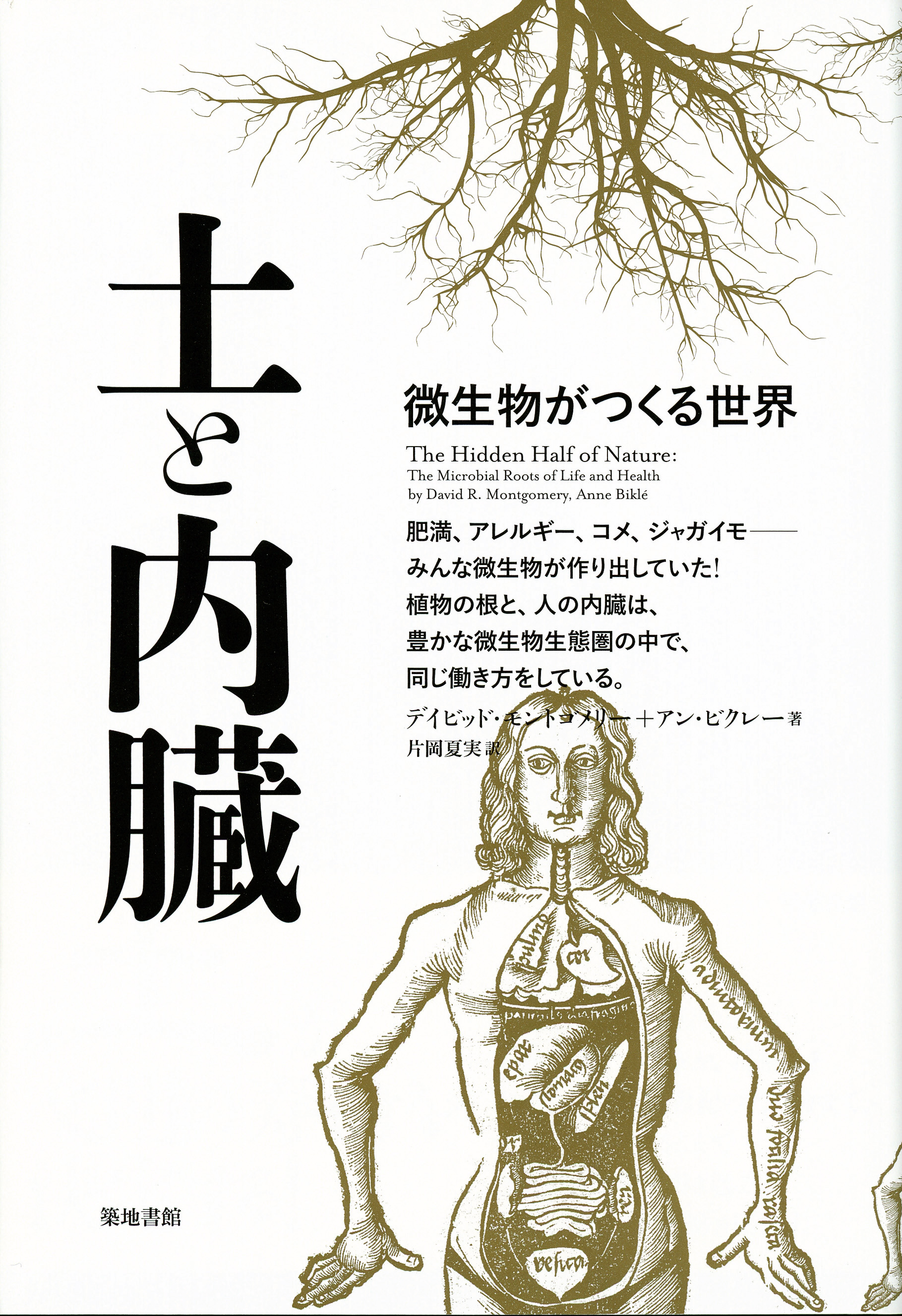土が変わるとお腹も変わる 土壌微生物と有機農業

| 吉田太郎[著] 2,000円+税 四六判 256頁 2022年3月刊行 ISBN978-4-8067-1631-0 日本の農地の25%を有機農業に、それ以外の全農地も化学肥料や農薬を削減する----日本でも生物多様性の激減と気候危機に適応した農政転換がおこっている。とはいえ、有機農業面積はわずか0.5%。病害虫や雑草が多い日本では、ゲノム編集技術やドローン、AIといったハイテク技術の実装がなければ不可能だというのが世間一般の見解だ。 実際には欧米はもちろん、日本以上に高温多湿なインドや台湾などでも有機農業は広まっている。そのカギは、4億年かけて植物と共進化してきた真菌、草本と6000万年共進化してきたウシなどの偶蹄類にある。 本書は、最先端の研究を紹介しながら、土壌と微生物、食べ物、そして気候変動との深い関係性を根底から問いかける。世界各地で取り組まれる菌根菌を活かした不耕起自然農法や自然放牧での畜産の実践事例は、「一度失われた表土再生には何百年もかかる。化学肥料や有機堆肥がなければ農業はできない」という通説を見事に覆していく。 腸活や健康を考えれば有機農産物はコスパがいい。川下の消費者意識がカギと、国をあげて有機学校給食を推進するデンマーク。森林、海、農地の循環と地域経済再生のコアに土づくりを据える大分県臼杵市。篤農家が在野で開発した農法を横展開して、流通や消費を総合的にガバナンスすればどうなるか。「有機」こそが、日本の食べ物を担う、あたりまえの農業であることがわかるだろう。 |
吉田 太郎(よしだ・たろう)
1961年生まれ。東京都杉並区で育つ。
筑波大学自然学類卒。同大学院地球科学研究科中退。
大学では地質学を専攻。
東京都及び長野県の農業関係行政職員として長期計画づくりや補助事業に携わる他、長野県農業大学校教授として土壌肥料学演習も担当。
有機農業推進担当職員として、本書の内容と重なる現地の農業者や消費者、国内外の研究者とも交流した。
なお、大学院時代に川喜田二郎教授とともに初めて訪れた海外はネパール。
2022年3月には定年退職し本書で描いた菌根菌を活かし川喜田二郎氏が提唱した「晴耕雨創」の生活を送る予定。
主な著作は、韓国でも翻訳出版されている『200万都市が有機野菜で自給できるわけ』『世界がキューバ医療を手本にするわけ』、『文明は農業で動く─歴史を変える古代農法の謎』などのほか、本書と三部作を成す『タネと内臓─有機野菜と腸内細菌が日本を変える』、『コロナ後の食と農─腸活・菜園・有機給食』(いずれも築地書館)がある。
はじめに オーガニック給食実現の鍵は関係者のマインド・リセット
序章
カーボン・ゼロでは防げない地球の危機
土壌にカーボンを戻し有機農業で地球を冷やす
重労働低収量の有機農法から科学的に洗練された再生農業へ
世界ですでに始まっている再生農業革命
本書の構成と登場人物
COLUMN1 再生農業とロデール研究所
第1章 有機農業で洪水と旱かん魃ばつを防ぐ
ヨーロッパの洪水とオーストラリアの緑野を結ぶ土壌とは
気候変動で多発する洪水と旱魃
夏は緑─入植者たちが見たオーストラリアの原風景
土壌団粒によって高まる透水性と保水力
植物の吸水力を飛躍的にアップさせる助っ人、菌根菌
ニューヨークの空を暗黒に染めたダストボウル
カバークロップ革命で土壌は簡単に作れる
団粒構造が構築されれば干上がった河川も蘇る
COLUMN2 団粒構造を構築する接着剤グロマリン
第2章 土が健康なら無肥料で農業ができる
根からの液体カーボンと菌根菌ネットワークの共生進化
農業とともに始まった地球温暖化
耕起は真菌の身体を切り裂き土壌を壊す
締固めと耕起 耕せば耕すほど雑草は増える
生物多様性の九五%を占める目に見えない土の中の世界
リン酸肥料は不要 着目される菌根菌ネットワーク
根からの糖分と交換されるミネラル
菌根菌にカーボンを提供し光合成能力を高める共利関係
菌根菌ネットワークを養う栄養パーティーの主催者は植物
化学肥料と農薬で台無しにされる地下の饗宴
インクルーシヴの摂理─誰一人取り残されずメンバー全員の参加でミネラルは循環する
農業は土壌生物たちを育むアート─ハイテク・アプリよりも顕微鏡
COLUMN3 メタンへの濡れ衣 工場型畜産が問題
第3章 草本と偶蹄類の共進化が生み出した肥沃な土壌
野生動物の行動パターンを模倣して肉牛を飼育しながら地球温暖化を防ぐ
牛は地球温暖化の犯人なのか─草原の価値を見直す
地上部よりも根が多い草の高い適応力と過放牧による植生破壊
牛をたくさん飼うほど砂漠化が防げる─常識を覆すホリスティックな放牧マネジメント
サバンナでのゲリラとの命がけの戦いの中から生まれた気づき
密集して絶えず移動する野生動物の群から、草を根こそぎにする家畜飼育へ
草は齧られると成長する─肥沃な土壌は偶蹄類が作り出した
COLUMN4 科学的に検証できないが世界から注目
第4章 表土は根から放出される液体カーボンで作られる
化学窒素肥料と菌根菌
窒素施肥で失われる土壌カーボン
大半が無駄となり環境汚染や病気の原因となる化学窒素肥料
植物と菌根菌と半共生窒素固定菌チームの無駄がない有機態窒素固定
団粒構造と生物的窒素固定と液体カーボンの深いつながり
表土は根から構築されるカーボンによって構築される
表土形成と森林での木材形成とのアナロジー
真菌が繁殖する切り返さない方法で良質な堆肥づくりに成功
バクテリアと真菌のバランスが養分や土壌カーボン以上に重要
COLUMN5 バクテリアと真菌のバランスの破壊者・化学肥料と農薬
COLUMN6 スマート農業とグリーン・ウォッシュ
第5章 土壌カーボン・スポンジで地球を冷やす
緑・土壌・微生物による水循環の再生が地球を蘇生させる
土壌から失われたカーボンが大気中の二酸化炭素を増やす
土壌にカーボンを戻せば二酸化炭素を減らせる
微生物の構成が変われば生産性が五倍向上
地球の熱収支を制御するのは二酸化炭素ではなく水蒸気
樹木は自然のエアコン─アマゾンを冷やす夜間放射と気化熱
雨は微生物が降らせていた─アマゾンにある立体河川
裸地になると土埃と赤外線の再放射熱でより乾燥化が進む
乾燥化で内陸部に居座った高気圧でさらに加速する温暖化
土壌団粒とセットとなった植生からの蒸発散で地球を冷却
土壌カーボン・スポンジを作り地球を再生する
第6章 生物はプチ飢餓が常態
土壌にカーボンを再び戻すことが大気中の二酸化炭素を減らす
気候変動問題を解決する鍵は菌根菌と不耕起と都市自給
炭素を元の鞘に戻せば温暖化は防げる
砂漠での発見─自然界は微生物による相互協力とミネラル循環で成り立っている
土壌、食べ物、ヒト、地球のつながり
日々の選択が地球を救う─小食こそが肝要
COLUMN7 二酸化炭素の増加はジャンクフードを増やす
終章 消費を変えれば腸も健全化し土壌と地球も再生する
EUのモデル 川下需要が牽引するデンマークの有機農業
調理員を教育することで経費をあげずにオーガニック給食を実現
テクノロジー重視の転換戦略は時代遅れ
鍵は公共、NGO、民間がコラボできる仕組みづくりとマインドのリセット
おわりに
引用文献
著者紹介
オーガニック給食での食品残渣の削減と脱ミートで
60%の二酸化炭素削減が可能
「給食を通じて人類を滅亡から救おう」。こんなことを口にしたら、少々頭がいかれた人物と胡散臭い目で見られること請け合いだ。けれども、千葉県いすみ市や木更津市、愛媛県の今治市、大分県の臼杵市、そして、長野県松川町と有機給食に取り組む自治体がジワジワと脚光を浴びている。国内の先進的な自治体は無論のこと、お隣の韓国であれ、台湾であれ、カリフォルニアであれ、フランスであれ、デンマークであれ、世界各地でいま給食、それもオーガニック給食に熱い眼差しが注がれている。
「できれば、子どもたちには美味しく安全なものを食べさせたい。ならば、オーガニックを」。そう願うのは保護者でなくとも人の常であろう。けれども、アカデミアはもちろん、世界各地の先見性のある社会起業家や政治家からも、地域再生の切り口として有機給食が注目されているのにはかなり本質的なわけがある。農薬をデトックスし、誰しもが不安に思う感染症に対する免疫力を高め、子どもを健康にすることはもちろん、地元経済を再生し、ひいては、地球温暖化や生物多様性の喪失という大きな環境問題を回避できる望みもそこに眠っているからだ。
2030年までに二酸化炭素の排出量を70%削減する。デンマークは世界でも最も野心的な気候変動対策目標を掲げている。2019年10月にコペンハーゲンで、東京、横浜を含む世界40の大都市からなる「C40市長気候サミット」が開催されたが、ここでオーガニック給食とフードロス削減に取り組むデンマーク・モデルが評価されたのも、すでに同市がCO261%削減を達成していたからだ。
2014年に同国でなされた研究から、有機に転換すれば、調理場では88%、輸送や食堂でも食品残渣が26?50%削減できることが判明している。2017年に「地球の友」が米国カリフォルニア州オークランド統合学区で行った研究でも、肉、乳製品を30%削減しただけで、同学区のすべての屋根にソーラーパネルを設置することに匹敵する二酸化炭素が削減できることが明らかとなっている。
つまり、食からのアプローチこそが温室効果ガス削減では最も威力を発揮する。おまけに、デンマークが取り組むように、それほど大変ではない。総合的な経済分析をせず、入札経費が安いというだけで、遠距離から大量生産された加工食材を調達するから食品残渣が発生し、その生ゴミを焼却処理するからまた温暖化ガスが発生する。悪循環だ。ならば、地元農家から必要な量だけ良質なオーガニック農産物を買って素材から調理すればいい。家畜の生理に反して不自然に飼料作物で太らせた抗生物質漬けの工業型畜産物をボイコットして、かわりに、草原でのびのびと育った牛肉や平飼いの自然卵を少量いただく。足りないタンパク質はマメや野菜で補えばいい。
規格が揃い虫に喰われず栄養価も高い有機農産物は作れる
「有機の方がいいことはわかっている。けれども、値段が高い。低所得世帯には手がでない」。消費者側がボヤけば、行政側も有機給食への転換が難しい理由をあげる。「収量は低下しロットが揃わないし、旬が重視されるから、レシピに見合った素材も確保できない。調理師が削減され、民間委託が進む中、泥付き野菜で調理に余計な負担はかけられない。効率化でセンター方式が進む中、機械で処理するには規格がバラバラの有機は使いたくても使えない」。断る理由はいくらでも出せるが、オーガニック米100%の有機給食を日本で最初に実現させた、千葉県いすみ市農林課の鮫田晋主査は「できない理由を考えるよりも、どうすればできるかを考えよう」と主張する。
実は、有機が虫食いだらけで規格も不揃いというのは神話だ。害虫が発生するのは化学肥料や畜糞堆肥の窒素が過多なためなのだ。農産物を作るには肥料が欠かせないと大学の農学部では教えられる。農業の専門指導員もそう言う。無肥料でできるなどと言うのは非常識と思われるかもしれない。では、山林の樹木は肥料をやらないのになぜ大きく育つのだろうか。
第2章で詳述するが、リンやカリウム等、作物が必要とする養分の95%は菌根菌を通じて微生物から植物へと運ばれ、マメ科に限らずほとんどの植物が窒素固定菌と共生関係を取り結び、アミノ酸等の形で直接根から吸収されていることがわかってきている。「有機農業=江戸時代を思わせる重労働を伴う趣味の農法」というイメージを持たれがちだし、確かに除草剤をまかないから草取りが大変になる面はある。けれども、伝統的な智慧と作物生理や微生物学、農業生態学の最先端の科学をドッキングさせた「アグロエコロジー」は、化学肥料や農薬漬けの農法よりもはるかに効率的で粋な農法であることがわかってきた。
例えば、前述のいすみ市にはモデルとなる有機農家が一人もいなかった。けれども、コウノトリと共生する兵庫県豊岡市の取組みに感銘を受けた太田洋市長の呼びかけで、有機稲作技術指導の第一人者、民間稲作研究所の稲葉光國氏(1944〜2020年)が現地で指導する。稲葉氏は雑草の生理を見極めることで、水を深く水田に溜めたり、早めに雑草を発芽させることで、除草剤を散布しなくても、慣行稲作に匹敵する収量が穫れる技を確立した。農家からすれば、除草の手間がいらず、除草剤のコストも削減できるのだから一石二鳥だ。そして、転換農家の期待に答えるかのようにいすみの水田にコウノトリが飛来した。
CSA農場で有機農産物の流通は可能だ
家庭菜園でちまちまと作られる農産物など、いちいち集荷できない。有機給食の実現には大規模な産地創出が必要だし、それがない以上は無理だという声がある。確かに、数万食を一時に調理するセンター方式での給食ではそうかもしれない。けれども、大量生産・大量消費を是とする既成概念が変わりつつある。
安全な食べ物を求める都会の消費者と新たに有機農業に挑戦したい生産者との模索の中から、1970年代に消費者と生産者とが顔が見える関係を通じて、互いがリスクをシェアしあうという考え方「提携」が生まれた。これは、地域支援型農業(Community Supported Agriculture=CSA)として世界中に広まった。この概念を最初に打ち出したのが日本の一楽照雄(1906〜1994年)であることは世界的にも認められているのだが、農水省は欧米発の先進事例としてCSAをPRしている。
そして、CSAが急発展しているのが中国だ。人民大学で農業経済を学んだシー・ヤン博士が、2008年にミネソタ州を旅し、CSAが素晴らしい機能を発揮しているのを目にしてからスタートしたから20年の歴史もない。
帰国後に博士は北京郊外で有機野菜の栽培を始める。2012年には社会的企業「Shared Harvest」をオープン。以来、45万人以上の顧客にサービスを提供する約1500のCSA農場が全国に出現した。その威力はコロナ禍下で一気に発揮される。パンデミックで既存の流通網が大打撃を受ける中、スマートアプリを活用した地域内の流通革命が起きている。信頼できる食料農産物の供給経路として注目されているだけでなく、都市近郊では、都市からの食品廃棄物を活用して、養分で循環も可能となれば、農業者と小売業者が互いに利益をあげるサーキュラー・エコノミーも実現できると期待されている。
京都でも、スマホ上でバーチャルに生産者と実需者ニーズの調整を行い、週に一便、二便、軽トラに有機野菜を満載して走らせる「京都オーガニックアクション」が始まっているのだが、アイデアを発案した鈴木健太郎氏も「提携」を知らなかった。「どこでアイデアを思いついたのか」と聞いたところ、米国で「CSA」に出会ったのがきっかけとの答えが帰ってきた。
栄養士を教育すれば有機給食でコストダウンも可能
生産者も消費者も忙しくなる中、野菜の季節感もすっかり記憶の片隅においやられ、いつが旬なのかを学ぶ余裕もないのだが、「京都オーガニックアクション」が斬新なのは、両者の仲を取り持つ「八百屋」が畑の情報を消費者に届けていることにある。
学校給食では、栄養士や調理師が献立を立てて、それから、農家に農産物を発注。「旬にこだわる有機農業では食材が揃わないから駄目だ」ということになるのだが、この課題も問題設定そのものがおかしい。冬に、化石燃料で加温して栽培する夏野菜であるキュウリやトマトを使う献立を立てることの方が不自然だからだ。兵庫県芦屋市でイタリアンレストラン、ボッテガブルーを経営するシェフ、大島隆司氏は、修業中に師匠から「残渣を出すな」との厳しい教えを受けた。そこで、氏が試みたのが、有機農家が一番作りやすい時期に旬の野菜を出してもらい、例えば、ケールがたくさん取れれば、前菜から、パスタ、ジェラート、そして、デザートもシュークリームの生地にまで練り込んで使い切ることだった。お客さんからは大好評だったが、農家ではまだ余っていたため、ケールを使う野外イベントを企画したという。
フランスでは公共調達される食材の50%を持続可能、うち20%は有機農産物とし、なおかつ、週に一度はベジタリアン給食を設けるエガリム法が2018年に制定された。この結果、ドルドーニュ県等、各地で有機100%給食の学校が誕生しているが、その実現に大きく寄与したCPPと呼ばれる栄養士と調理師からなるグループのフィリップ・エネ氏は「有機食材の量が増すほど給食費が下がる」という意外な経験を披露する。
まゆつばのようにも思えるが、これもタネを明かせばちゃんとわけがある。センター方式化が進んだ大規模給食では少ししか食べない子どもがいても、それとは無関係に機内食のようなセットが提供される。賞味期限も短い。そこで、提供される給食の実に40%が廃棄されているという。CPPは調理師を啓発することから始めた。一人一人の子どものニーズと向き合い配膳方式に変えれば無駄も省け食材量もカットできる。また、肉をヒヨコマメに変え、その煮込んだ煮汁も捨てずにスープに生かすといった工夫で残渣も出さず原料を使い切る。食品会社からの出来合い品を配膳するだけで疎外されていた調理師たちも「次は旬の食材を使って何をこさえてやろうか」と手ぐすねを引くようにやる気を出す。有機農家は納得がいく価格で買ってもらえ、調理人はプロとしての生きがいを実現し、子どもたちは栄養価が高い美味しいもの食べられ、残食も減り、経費は削減される。
終章で詳述するが、有機給食100%を成功させたコペンハーゲンにしてもまず調理師や栄養士の教育から始めている。そう。生産者、料理人、消費者と誰もが満足できるウィン・ウィン状況は可能なのだ。川下の食品ロスを減らし、栄養価が高い有機食材に切り替えることで生産サイドへの負荷そのものを減らす消費者サイドの意識転換、つまり、「フードシステム」全体の転換が、2020年にEUが打ち出した化学農薬50%減、有機25%へ拡大「農場から食卓まで戦略」の根底に流れている。
生産技術、流通のスキル、そして、コストを上げずにオーガニック給食を実装できる調理現場でのノウハウやスキルも蓄積されているとすれば、ネックとなっているのは、仕組みづくりに欠かせない学校や栄養士や行政職員のマインドの問題だ。実は、この改革が一番むずかしい。というか、日本では「イノベーション=ハイテク」と思われているのだが、世界的にはこうした仕組みを変えることも「イノベーション」とされている。
生産、流通、消費のいずれもが可能であって、マインド・リセットが最大のネックだとすれば、まずは有機農業そのものが異端のマイナーな高付加価値化のための農法ではなく、あたりまえの農業であることを大前提とする必要があるだろう。長野大学の相川陽一教授はこれを「ふだん着の有機農業」と呼ぶ。明治大学の小田切徳美教授は農林水産省の「みどりの食料システム戦略」に対して、「これは外からのイノベーションであって、これまでの工場誘致による開発がドローンやAIになっただけだ」と批判し、大江正章(1957〜2020年)氏が『有機農業のチカラ─コロナ時代を生きる知恵』(2020、コモンズ)で指摘した内発的発展、地域政策と農業政策の統合が必要だと述べる。
そこで、本書では、なぜ有機農業があたりまえなのか、「生産」の本質となる部分に特化して、土壌と微生物の面に重点をおいて紹介することから始めてみたい。
長野県庁で有機農業推進担当官だった著者が、
土壌微生物学の発達により明らかにされつつある、4億年に及ぶ植物と真菌の共進化を描きます。
この土壌微生物学の最前線を紹介しながら、日々接してきた勘と経験の篤農家の技術の普遍化が可能であることを示します。
コロナ禍と戦乱での農業資材のサプライチェーンの綻びのなか、農地・草地をカーボンの排出源から吸収源へ転換させるべく、
世界で同時進行する肥料、農薬、除草剤不要の農業での土の扱い方に起こっているパラダイムシフト、カーボン農業の世界へようこそ。