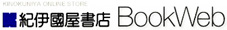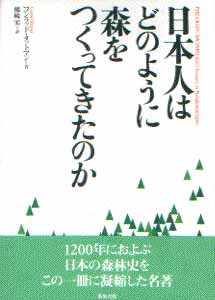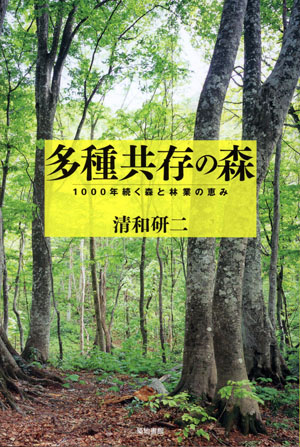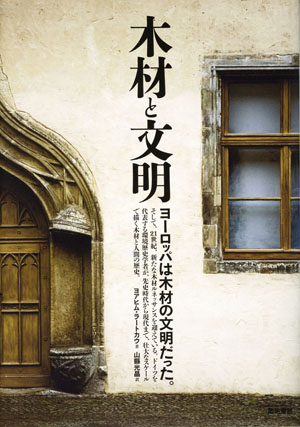林業がつくる日本の森林
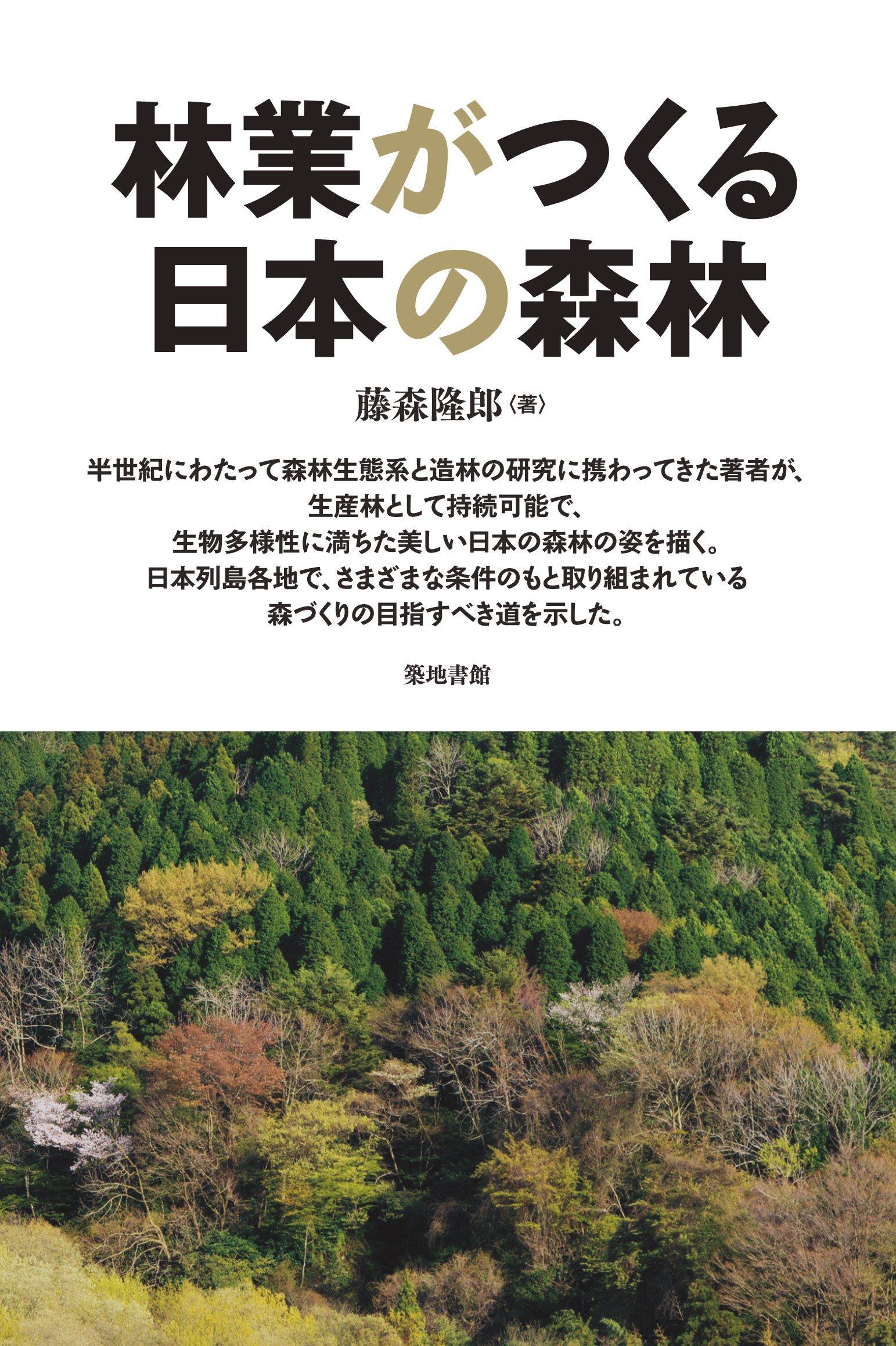
| 藤森隆郎[著] 1,800円+税 四六判上製 200頁 2016年10月刊行 ISBN978-4-8067-1526-9 半世紀にわたって森林生態系と造林の研究に携わってきた著者が 生産林として持続可能で、 生物多様性に満ちた美しい日本の森林の姿を描く。 日本列島各地で、さまざまな条件のもと取り組まれている 森づくりの目指すべき道を示した。 |
藤森隆郎(ふじもり・たかお)
1938 年京都市生まれ。
1963 年京都大学農学部林学科卒業後、農林省林業試験場(現在の森林総合研究所)入省。
森林の生態と造林に関する研究に従事。農学博士。
研究業績に対して農林水産大臣賞受賞。
1999 年、森林環境部長を最後に森林総合研究所を退官。
社団法人日本森林技術協会技術指導役、青山学院大学非常勤講師を務めた。
国連傘下の持続可能な森林管理の基準・指標作成委員会(モントリオールプロセス)の日本代表、
IPCC の執筆委員など国際活動を務め、IPCC のノーベル平和賞受賞に貢献したとして、IPCC 議長から表彰された。
主な著書として、『森との共生─持続可能な社会のために』(丸善、2000 年)、
Ecological and Silvicultural Strategies for Sustainable Forest Management(Elsevier, Inc.Amsterdam 2001 年)、
『森林と地球環境保全』(丸善、2004 年)、『森林生態学─持続可能な管理の基礎』(全国林業改良普及協会、2006 年)、
『森づくりの心得─森林のしくみから施業・管理・ビジョンまで』(全国林業改良普及協会、2012 年)などがある。
はじめに
第1部 日本の森林・林業の現状と問題点
1 何を問題として問うのか
2 木材生産量は減り続け、人工林は劣化している
●コラム1 天然林、天然生林、人工林(更新、天然更新)
3 山で働く人が減少し様々な問題が起きている
4 ビジョンの見えない森林管理が進んでいる
●コラム2 本来の間伐とは
5 林業力低下の理由
6 林業関係者に必要なこと
7 林業の背景となる日本社会の歩み
8 林業の歩み
●コラム3 複相林施業
9 国産材の供給、販売体制が遅れてきた
10 木を使うことの意味
11 地域における循環と文化の喪失
12 国民と森林との距離が遠すぎる
第2部 問題を解決するために必要なことは何か
1 目標とする社会の姿
2 目標とする森林の姿
3 森林についてよく知ること
4 目標林型の求め方
5 合意形成のプロセスと科学的根拠
6 日本の自然、森林との付き合い方
7 森林を扱う技術者と経営者
8 自伐林家と集約化
9 林業と木材産業の関係
10 木を扱う技術者の育成
第3部 新たな森林管理のために必要なこと
1 森林管理のリーダーであるフォレスターの必要性
2 今の制度では技術の専門家は育たない
3 研究機関と行政の間の関係の改善
4 「根拠」を問うこと
5 ボトムアップの法律・制度・政策が必要
6 ボトムアップのための地域から国へのシステム
7 森林所有者と市民との関係
8 国際的視野に立つこと
第4部 豊かな日本の農山村と社会を目指して
1 地球環境保全と森林との付き合い方
2 持続可能な社会のために農山村に必要なこと
3 技術者が誇りを持てる社会
4 日本の森林と社会への決意
おわりに
主な参考文献
私は国立の研究所で「森林生態系に基づく森づくりの研究」に長年従事してきた。若い間は自分の専門分野の研究に専念していたが、やがて自分とその周辺の研究成果が現場にどのように活かされ、社会的にどのような貢献をしているのかに疑問を抱くようになってきた。それはもちろん私自身の能力や努力不足によるところもあるが、森林と林業の現場と研究の世界との間に大きな隔たりがあり、現場と行政との間の隔たりがさらに大きいことが痛感されるようになってきた。そして森林所有者や林業経営者の意欲はどんどん低下し、現場の技術力は低下し、農業の不振とも相まって農山村は過疎化し、持続可能な社会の基盤が失われてきていることに大変な危機感を持つようになってきた。そのために一研究者としてだけでなく、一市民の立場として日本の森林と林業のあり方をいろいろな立場の人たちとともに考えていかなければならないと考えるようになった。それが本書を執筆した理由である。
日本は明治維新から近代国家の道を歩みはじめ、激動の時代を繰り返しながらも著しい経済成長を経て、今日では世界の中でも有数の豊かな国の一つとなっている。だがそれに伴い豊かさの大事な一面を失ってきている。それは日本の自然を活かした一次産業が、二次、三次産業に比べて著しく低い位置に追いやられていることであり、そのことは日本の持続可能な社会を根底から危うくするとともに、日本人の生き様を示す美しい景観や伝統的な文化の崩壊にも連なる。このことは新たな社会理念である持続可能な循環型社会の構築に反することであり、それは日本の問題だけではなく、地球環境問題の解決への全人類の道にも反することである。
本書は、私が専門としてきた森林と林業について、その問題点とあるべき姿を考えていく。だがそのためには一次産業の農業や二次、三次産業との関係、そしてそれにより醸し出される生活文化とも結びつけながら見ていかなければならない。すなわち森林・林業のあるべき姿は、日本の国のあるべき姿に照らして考えていかなければならないということである。そしてそれは国際的にもしっかりと主張できる内容のものでなければならない。
持続可能な循環型社会の構築のためには、それぞれの地域の、それぞれの国の自然資源を有効に持続的に活用するしっかりとした理論的根拠と、それを実践する人材の育成とシステムを構築していくことが必要である。それができるか否かは、それぞれの地域の、それぞれの国の底力と文化の程度を問われるものである。日本の国土の67%は森林である。先進国の中でこれだけの森林率を有する国は稀有である。だが現在の我が国の木材生産量(供給量)は、その蓄積のポテンシャルに比べて非常に低く、木材の自給率は2012年現在わずかに28%である。2002年には18%にまで低下した。森林の多い先進国の中でこのようにその資源を活かせていない国は異例である。この問題を捉えることは、林業関係者だけではなく国民全体にとって極めて重要である。
森林はいうまでもなくその生態系の多様な機能(その中で人間社会にとって有用なものを生態系のサービスという)を有し、そのサービスを市民ひとりひとりが享受できるものであり、それなくしては持続可能な社会を維持することはできない。したがって市民ひとりひとりは森林から物質とエネルギーとしての木材などを収穫するとともに、水資源の保全、そしてそれらの基盤となる土壌の保全と生物多様性の保全を調和的に求めていかなければならない。そのような森林の保全と木材などの利用を通して、多くの雇用が生まれ、人々の精神性が高められ、保健文化の向上が図られる。そしてそれらのサービスを市民ひとりひとりがバランス良く享受していけば、それは結果的に気象の緩和、地球温暖化防止にも強く連なる。それらの要求事項がトータルとして調和的に得られるか否かは、持続可能な社会の基盤に関わることであり、それぞれの地域の人々の、ひいては国民の賢さが問われる。その賢さとはどういうものかを本書では考えていきたい。
森林生態系は生産機能と環境保全機能を備えているが、様々な立場の人たちによって、「生産」と「環境保全」に対する要求の度合いに違いがあり、それをどう調和させ、両立させていくかに森林・林業政策の大事さと難しさがある。その政策を正しい方向に導くには、様々な立場の人たちが日常的に森林に親しみ、森林と林業について正しい知識を持ち、持続可能な社会の構築に向けて皆で議論していかなければならない。そのためにはまず森林生態系の機能を正しく知り、それらを調和的に発揮させていくにはどうしたらよいかを市民ひとりひとりが考えていかなければならない。そしてそれを議論していくと、必ずそれを誰がどのようにやっていくのかという、林業の担い手、現場の技術・技能者、行政担当者、研究者などのあり方と、それらを?ぐシステムへの言及が不可欠となる。そしてさらにそれは関連する地域の産業や地域の住民、国民との関係の重要性が問われることになる。日本の森林と林業の現状を改善し、持続可能な循環型社会を構築していくためには、このような視点から考察を進めていかなければならない。
先に持続可能な社会の構築のためには、それぞれの地域の自然を活かした循環型社会が基本になければならないことを述べたが、森林は日本の自然資源の中で、その気になれば恐らく自給率100%に近づけられる唯一の資源ではないかと考えられる。それは日本人の知恵と努力にかかわることであり、社会全体で考えていかなければならないことである。我々はどのような社会を構築していくのかのビジョンを描く時に、その循環型社会の中に森林生態系の力がいかに大事かを認識し、森林の適切な管理経営のあり方を考えていかなければならない。言い換えれば、豊かな日本列島の自然の恵みをていねいに引き出す賢さである。それは自然の力と相談しながら実践していく極めて創造的な活動であり、そのことは日本の技術力や文化の向上の基盤を築いていくことに強く連なるはずである。
私が森林・林業に関する仕事についてから50年以上になるが、その間に日本でどれだけの森林管理と林業経営に関する進歩の蓄積があったかは大きな疑問である。それは材価の低迷でやむを得ないことだという見方をする人たちもいる。しかしドイツをはじめとするヨーロッパ諸国や森林を有する多くの先進国では、国際的に同じような材価の中で林業を成り立たせ、生産と環境を調和させているところが多い。我々はそういう国々に大いに学ばなければならない。日本は工業力において世界有数の地位を築いてきたが、その空洞化が言われて久しい。都市中心の経済原理に傾き、一次産業を犠牲にしてきた結果、一次産業も二次産業も失いつつある。日本人の祖先である縄文人は1万年以上にわたり森林と草地の中での持続可能な社会を築いてきたが、そのように長く続いた文化は世界にないといわれている。我々日本人はそういう知恵を引き継いでいるのだということを忘れず、新たな時代に向けてそのような文化の素地を活かしていかなければならない。
本書は上述したような大きな社会問題の中で、持続可能な循環型社会の構築のために、雇用の再生のために、美しい農山村の再生のために、日本の木材自給率を100%に近づけていくためにどうしたらよいのか、そして森林の多様なサービスを市民、国民がどのように受けられるようにしていけばよいかを考えていくものである。