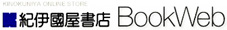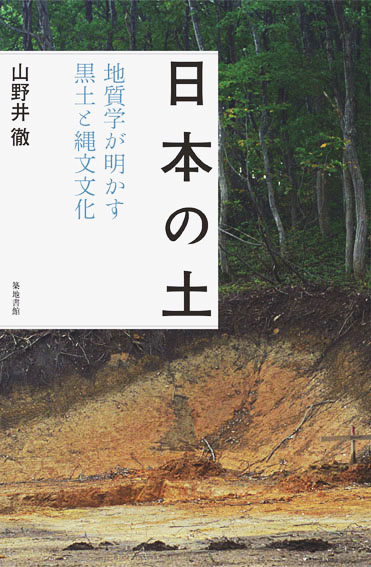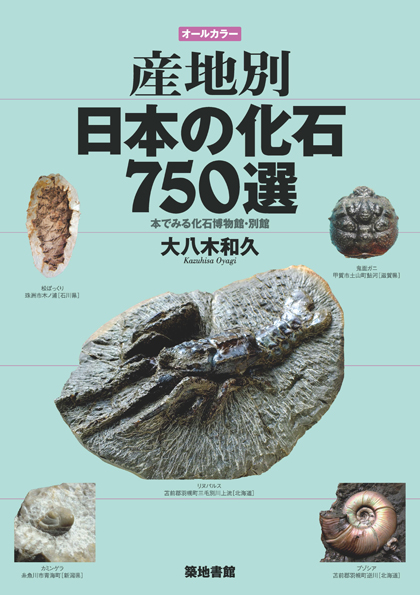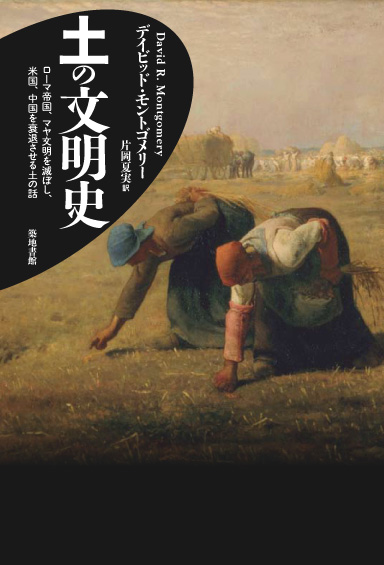�n���n���[���T���̗��j
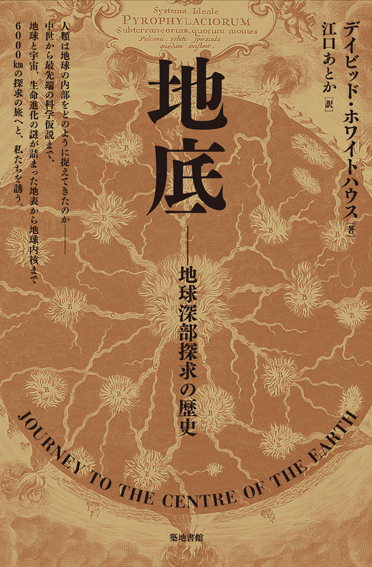
�f�C�r�b�h�E�z���C�g�n�E�X�m���n�]�����Ƃ��m��n
2,700�~+�Ł@�l�Z���㐻�@264�Ł@2015�N12�����s�@ISBN978-4-8067-1505-4
�l�ނ͒n���̓������ǂ̂悤�ɑ����Ă����̂��\�\�\
��������Ő�[�̉Ȋw�����܂ŁA�n���ƉF���A�����i���̓䂪�l�܂����n�\����n�����j�܂łU�O�O�O�q�̒T���̗��ւƁA��������U���B
�W���[���E���F���k�́w�n�ꗷ�s�x����150�N�B�n�������ւ̗��͓��X�i��ł���B
����������̒n�k�Ď����u�A�\�A����Ɍv�悳�ꂽ���V�A�̒��[�x�@��B�v���W�F�N�g�A�n���[���̈��͂��Č����鍂���������u�̔�������A
�n�k�E�Ôg�ϑ��̐��E�I�l�b�g���[�N�\�z��b�܂ŁA�V���w�҂ł����钘�҂��V���Ȓn��T���̗��ւƑ��������A
�őO���Ŋ��錤���҂����̍ŐV�m�����Љ�Ȃ���A�n�������̐^�̎p�ɔ���B
���ҏЉ�
�f�C�r�b�h�E�z���C�g�n�E�X�iDavid Whitehouse�j
�C�M���X�̉Ȋw���C�^�[�B���Ă̓W���h�����o���N�d�g�V���䂨��у����h����w�}���[�h�F���Ȋw�������̓V���w�҂ŁA
�m�`�r�`�̃~�b�V�����ɂ��Q���o��������B���̌�A�a�a�b�����̉Ȋw�S���L�҂ƂȂ�A�e���r�ԑg��W�I�ԑg�ɏo�����邩�����A
�C�M���X�̎G����V���ɒ���I�Ɋ�e�B�����V���w�����B2006 �N�ɂ͉Ȋw�ƃ��f�B�A�ւ̍v�����������āA
���f���i4036�j���u�z���C�g�n�E�X�v�Ɩ��t����ꂽ�B�����ɁA�gThe Moon: A Biography�h�i2002�j�A�gThe Sun: A Biography�h�i2005�j�A�gOne Small Step�h�i2009�j�A�gRenaissance Genius�h�i2009�j�Ȃǂ�����B
��ҏЉ�
�]�����Ƃ��i�������E���Ƃ��j
�|��ƁB�J���t�H���j�A��w���T���[���X�Z�n���F���Ȋw���n���w�ȑ��ƁB�ɁA
���`���[�h�E�m�[�g���w覐R���N�^�[�x�i�z�n���فA2007�j�A
�����E�U���V�[���B�b�`�w���A�n���̗��������x�i�݂������[�A2012�j������B
�ڎ�
�܂�����
��P�� �w�n�ꗷ�s�x�ւ̗U��
��Q�� �n���̒��S��
�n�ꗷ�s�̓����
�n�������ƉF���̂Ȃ���
�n�ꍂ�M������
�n���̒��S��ڎw���j����
��R�� ���l�Ȓn�����E
��S�� �n�������̉ߋ��Ɩ���
���n���z�n���_
���n�n���̎p
���肭��f��
��T�� �l�Z���N�O�̗��q
�T���v���v
������̒n��
�[����
��U�� �[������̃��b�Z���W���[
�n�k�͓V�̍ق���
�n�k�v�̊���
�ߑ�n�k�w�̒a��
��V�� �e���n����覐�
��W�� �L����n�k�ϑ���
�n�k�R���N�^�[�A�~����
�ގ������ƒn�k�v
�O��̔g
�[���n�k�͂��邩
��X�� �E�F�Q�i�[�̑嗤�ړ���
��P�O�� �R���������[�x�@��B�v���W�F�N�g
�v��̏I���ƍĊJ
�}���g���̊��
��P�P�� �n�\�Ɛ[�����Ȃ�����
�}���g���̓�
���ݍ��݂́u���v
�₦�Ă����n��
�J�ڑw�̔���
��P�Q�� ���͂ƃ}���g��
�����Ɗi������Ȋw��
�_�C�������h�A���r���Z��
�}���g�����\���������
��P�R�� ���̔j�ЁA�_�C�������h
��P�S�� �}���g���̒�ŋN���Ă��邱��
�|�X�g�y���u�X�J�C�g�̔���
�j�����ƒn�k�w
��P�T�� ������
��P�U�� ����n�k�̊�����
�n�k�g�g���O���t�B�[
��P�V�� ��̏z��
�z�b�g�X�|�b�g�̖���
�N��ɑ��ł�
��P�W�� �n���T���ƃj���[�g���m
��P�X�� �n���̊j�ɂ��Ă̘_��
�ő̂��t�̂�
���ƂȂ�t�̓S
��Q�O�� ���C�Ɉ���������
���ʎ��j�̗��j
�^�k���w���Ȃ����C�Ίp
��Q�P�� �����̒T��
�n���[�ƍL�接�C�}
�n�����ꔭ���̎d�g��
�������̃_�C�i�����_
��Q�Q�� �n���̉ߋ��Ǝ�����
�����K�Ǝ��C
�n�����C�̋t�]
�O�j�Ɠ��j�̂��߂�����
�_�C�i���̔����ɔ���
�_�̌�Ƃ�m�邽�߂�
��Q�R�� ���j�̔�����
�����Ȃ����
�n���̐V�����̈�̔���
�A���X�J�n�k�Ɠ��j
��Q�S�� ��߂��S�̋�
��ȓ��j
�œ��j�͂��邩
��]������j
��Q�T�� �����̐X
�����̋N���Ǝ��C
�����T���̉\��
��Q�U�� �f���̒n�ꐢ�E
�ٍʂ���ؐ�
�A�C�X�E�W���C�A���g�ƃX�[�p�[�E�A�[�X
��Q�V�� ���̏I���
���z�̎���
�n���̍Ŋ�
��Q�W�� ���F���k�Ǝ������́w�n�ꗷ�s�x
�V���������������炷����
����
��҂��Ƃ���
��҂��Ƃ���
�@�n�����w��ł��邱�Ƃ͒N�����m���Ă���B�����A�^�}�l�M�̔���ނ��悤�ɁA�ꖇ�ꖇ�߂���ƁA���ꂼ��̑w���ǂ̂悤�ȏ�Ԃɂ���̂��A
�͂�����v�������ׂ���l�͏��Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B���������ꖇ�ꖇ�A���ꂢ�ɂނ����ƂȂǂł��Ȃ��̂�������Ȃ��B
�n�\����n���̒��S�܂ł̗���N���Ɏv�������ׂ�͓̂���B
�@�{���̓f�C�r�b�h�E�z���C�g�n�E�X��
�gJourney to the Centre of the Earth: The Remarkable Voyage of Scientific Discovery into the Heart of Our World�h�iWeidenfeld & Nicolson, 2015�j
�̑S��ł���B�t�����X�̍�ƃW���[���E���F���k�ɂ�铯�������w�n�ꗷ�s�x�i1864�N�j��150���N���}���邱�Ƃ�m��A
�V���w�҂̃z���C�g�n�E�X���m����Ă�150�N��̒n�ꗷ�s���B
�@�������̂Ƃ��胔�F���k�́w�n�ꗷ�s�x�́A�n���̓�����T������s��ȗ�����ł���B
�z���w�̌��ЃI�b�g�[�E�����f���u���b�N�������A16���I�̘B���p�t�A���l�E�T�N�k�b�Z�������c�����Í�����ǂ��A
�A�C�X�����h�̉ΎR�̕��Ό�����A�n���̒��S��ڎw�����s�ɏo������B�����鉙�̃A�N�Z����A��A���n�Ōق����K�C�h�̃n���X�ƂƂ��ɒn���T�����A
�n���ɍL����C��n���āA������L�m�R�̐X��ʂ�A��ł����͂��̌Ð����Əo��B�O�l�����̒n�����E
�i�T�N�k�b�Z���������łɒ��S�Ɏ������Ƃ������ƂȂ̂Ŏ��ۂ͑O�l�����ł͂Ȃ��̂����j�ɂ͒n���̗��j���܂��Ă����B
���F���k�́w�n�ꗷ�s�x����150�N�A�n���ς͑傫���ω����A���ł��ω��������Ă���B
�Ȋw�҂ɂ���ĉ�����������Ă����n���̓����Ɋւ���m���܂������́A�ǂ�ȋ��قɖ����Ă���̂��낤���B
�@���݂͎�ɉȊw���C�^�[�Ƃ��Ċ�������{���̒��ҁA�f�C�r�b�h�E�z���C�g�n�E�X���m�́A
�ȑO�̓W���h�����o���N�d�g�V����ƃ����h����w�}���[�h�F���Ȋw�������̓V���w�҂ŁA�m�`�r�`�̂������̃~�b�V�����ɂ��Q�������B
���̌�A�a�a�b�����̉Ȋw�S���L�҂ƂȂ�A�e���r�ԑg��W�I�ԑg�ɏo�����邩�����A
�C�M���X�̉Ȋw�G���w�j���[�E�T�C�G���e�B�X�g�x��V���w�C���f�B�y���f���g�x���ɒ���I�Ɋ�e���Ă���B�܂��A�����V���w��̉���ł���A
�ߋ��ɂ̓\�T�G�e�B�[�E�t�H�[�E�|�s�����[�E�A�X�g���m�~�[�̉�����߂��B���̃C�M���X�̒c�̂͐��̈��D�Ƃ̂��߂̉�ŁA
�����҂ƃA�}�`���A�������Ɍ𗬂���ꂾ�������B�z���C�g�n�E�X���m�͉Ȋw�[�ւɔM�S�ŁA2006�N�ɂ́A�ނ̉Ȋw�ƃ��f�B�A�ւ̍v�����������āA
���f���i4036�j�Ɂu�z���C�g�n�E�X�v�Ƃ������O������ꂽ�B�����ɂ́A���Ƒ��z�Ɋւ���Í������̓`������j�A�Ȋw��ԗ�����
�gThe Moon: A Biography�h�i2002�N�j�ƁgThe Sun: A Biography�h�i2005�N�j�A�F����s�m�̃C���^�r���[�������Ȃ���F����s�̗��j���Ђ��Ƃ�
�gOne Small Step�h�i2009�N�j�A�K�����I�E�K�����C���͂��߂Ė]�����ʼnF�����ϑ����Ă���400�N�ɂȂ邱�Ƃ��L�O���ď����ꂽ�K�����I�̓`�L
�gRenaissance Genius�h�i2009�N�j�Ȃǂ�����B
�@�{���ł́A�z����̃J�v�Z���ɏ���āA�ő̂̒n�\����o�����A�n���̒��S�܂Ŗ�6370�L�����[�g���̗�������B
�^�������j��ڎw���̂����A�n�������̍\�������������I�Ɍ����킯�ł͂Ȃ��B�\���A���j�A�Ɍ��̈��͂��Č��ł��鑕�u�A
�閧�ɔ��鐔�X�̌v�������A�����Ɋւ�����l�X��_�@�ƂȂ����ł����ƂȂǂ����̓I�ɐD��Ȃ���A�s��ȃh���}���W�J����B
����͒n���̓����̃h���C�Ȑ����Ƃ��������A�N���ǂ̂悤�ɔ��������̂��Ƃ����l�X�̕��ꂾ�B���̂��߁A
�������Ɋւ���Ă���Ȋw�҂��C���^�r���[���A�ނ�̐��̌��t�����p����Ă���B�O�����猩��ƒn���͐Â��Ȑ��E���B
�����A�ΎR��n�k�A�I�[�����Ȃǂ��A�n���ŋN�����Ă����K�͂Ȍ��ۂ�\���Ă���B�n��ɂ͉��x�∳�́A������z���ɍ��ݍ��܂ꂽ�n���̗��j������A
�n�k�w�̔��W�ɂ���āA���̎p�����傶��ɕ����яオ���Ă����B�z�R�ɐ���A�n���ōł��[������K��A�����ɑ��݂���ΐ��T�C�Y�̐��E��T�K���A
�����̂Ƃ����т��Ă��Ȃ��ő̂̓��j�̌����ׂ�B���ɓ��j�Ɋւ���ŐV�̔����͋����[���B�����āA���̘f���́u�n�ꗷ�s�v�A
�n���O�����́A�n���̖����ւƑz���͉ʂĂ��Ȃ��L�����Ă����B�܂��A���������I�ŁA�b�肪�]�X�ƈڂ낢�A��݊|����悤�ɐ����������A
�b�����S�Ɉ��邩�Ǝv���ƌ��ɖ߂�Ƃ����悤�Ȑ▭���������I���B�����ǂ݂ɂ�����������Ȃ����A�����̎����͋C�𖡂���Ă������������Ǝv���A
���ݍӂ��Ė��Ƃ͋ɗ͔������B�����炱����Ɏv����y���Ȃ���A���m�̐��z���y����ł���������Ǝv���B
�@�����A�n���w�I�Ȓn�ꗷ�s���Ǝv���ēǂݐi�߂���A����������a���������邩������Ȃ��B�n���̓����ƕ����Ďv�������ׂ�悤�Șb��A
���z���̖��O�A���ʑ́A�n���N��Ȃǂɂ��܂�G����Ă��Ȃ����炾�B����ɂ͗��R������B
���F���k�̗����z���̖͂L���ȍ�Ƃɂ��n�ꗷ�s�ł������悤�ɁA����̂���͓V���w�҂ɂ��n�ꗷ�s�ł��邩�炾�B
�z���C�g�n�E�X���m�̎��_�͂����܂ł��O���A�܂�F���ɂ���A�e���݂����߂Ēn�����u�������̘f���v�ƌĂԁB
�n���Ƃ����f���Ɛl�ԂƂ̌��т��ɒ��ڂ��A�u�������̒n�ꗷ�s�ł́A�����������ɒn���Ɩ��ڂɊW���Ă��邩��m�����v�Ƃ����B
�u�����č��ł́A�������グ�邽�тɁA���̐S�̈ꕔ�͎��c����鄟�����̏Z�ނ��̘f���A�����Č����ĖK��邱�Ƃ��ł��Ȃ��ꏊ�Ɂv�Ƃ������A
���̒n�������ւ̗��̒��ł͂ނ���A�u�S�̈ꕔ�͉F���Ɏ��c�����v�Ƃ������ق���������������Ȃ��B���̎��_�������A�{���̖��͂ł͂Ȃ����Ǝv���B
�@�z���C�g�n�E�X���m�͖{�������M���钆�ŁA�����ɑ���Ȃ��������̂�m�����Ƃ����B����́A�F���ɂ���ڂ������Ă������A
�����̑����ɂ��������̐��E���������Ƃ������Ƃł���B�ȑO�ɖ|���w覐R���N�^�[�x�i�z�n���فA2007�N�j�̒��҂��V���w�҂ŁA
�n���ɖڂ�������̂��x�������ƂȂ����Ă���ꂽ�B�������p����ƁA�u�f���w�҂�V���w�҂͖�������Ȃ��l�킾�B
����f������������Ȋw�҂͉i���Ɏ�ɐG����Ȃ����̂�ǂ����߂�^���ɂ���m�������n�F���T���@�ɂ���Č���f���⏬�f���̉摜������ꂽ���A
�������������[�ɐ����āA�����ق��̐��E�֏o�����ăT���v�����̎悷��Ƃ����i�ɂȂ�A�V���w�҂͈�������ŁA
���w�҂�n���w�ҁA�z���w�҂ɏꏊ�𖾂��n���Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B�܂�A��ŐG�������͓̂V���w�҂̗̕��ł͂Ȃ��̂ł���v�B
�n���̒��S�ւ̗��́A���ꂱ��z�����邱�Ƃ͂ł��Ă��A���ۂɊ��s���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���Ȃ��Ƃ������_�ł́B�����ł���A
�������Z�ސ��ł���Ȃ���������ĖK��邱�Ƃ̂ł��Ȃ��A��ŐG��邱�Ƃ̂ł��Ȃ��n�����E�̈ē����Ƃ��āA
�V���w�҂قǂ̓K�C�҂͂��Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�������̒n�ꗷ�s�͏��������̕��ꂾ�B�i���ɏ�����������ʂĂ��Ȃ�����ł���B�{����ʂ��Ēn�������𗷂��A�Ǒ̌����邱�ƂŁA
����A�V���������̃j���[�X�����邽�тɁA�n�����E���܂��܂��g�߂ɁA�N�₩�Ɋ����邱�Ƃ��ł��邾�낤�B
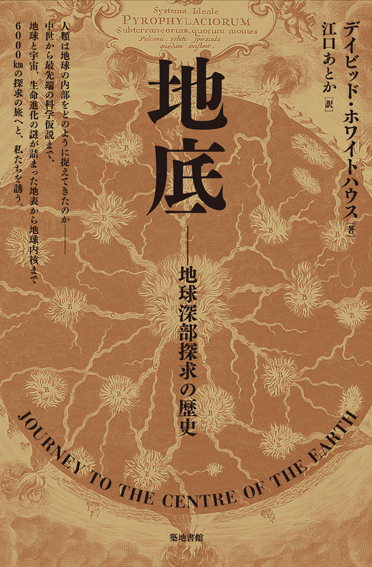
| �f�C�r�b�h�E�z���C�g�n�E�X�m���n�]�����Ƃ��m��n 2,700�~+�Ł@�l�Z���㐻�@264�Ł@2015�N12�����s�@ISBN978-4-8067-1505-4 �l�ނ͒n���̓������ǂ̂悤�ɑ����Ă����̂��\�\�\ ��������Ő�[�̉Ȋw�����܂ŁA�n���ƉF���A�����i���̓䂪�l�܂����n�\����n�����j�܂łU�O�O�O�q�̒T���̗��ւƁA��������U���B �W���[���E���F���k�́w�n�ꗷ�s�x����150�N�B�n�������ւ̗��͓��X�i��ł���B ����������̒n�k�Ď����u�A�\�A����Ɍv�悳�ꂽ���V�A�̒��[�x�@��B�v���W�F�N�g�A�n���[���̈��͂��Č����鍂���������u�̔�������A �n�k�E�Ôg�ϑ��̐��E�I�l�b�g���[�N�\�z��b�܂ŁA�V���w�҂ł����钘�҂��V���Ȓn��T���̗��ւƑ��������A �őO���Ŋ��錤���҂����̍ŐV�m�����Љ�Ȃ���A�n�������̐^�̎p�ɔ���B |
�f�C�r�b�h�E�z���C�g�n�E�X�iDavid Whitehouse�j
�C�M���X�̉Ȋw���C�^�[�B���Ă̓W���h�����o���N�d�g�V���䂨��у����h����w�}���[�h�F���Ȋw�������̓V���w�҂ŁA
�m�`�r�`�̃~�b�V�����ɂ��Q���o��������B���̌�A�a�a�b�����̉Ȋw�S���L�҂ƂȂ�A�e���r�ԑg��W�I�ԑg�ɏo�����邩�����A
�C�M���X�̎G����V���ɒ���I�Ɋ�e�B�����V���w�����B2006 �N�ɂ͉Ȋw�ƃ��f�B�A�ւ̍v�����������āA
���f���i4036�j���u�z���C�g�n�E�X�v�Ɩ��t����ꂽ�B�����ɁA�gThe Moon: A Biography�h�i2002�j�A�gThe Sun: A Biography�h�i2005�j�A�gOne Small Step�h�i2009�j�A�gRenaissance Genius�h�i2009�j�Ȃǂ�����B
�]�����Ƃ��i�������E���Ƃ��j
�|��ƁB�J���t�H���j�A��w���T���[���X�Z�n���F���Ȋw���n���w�ȑ��ƁB�ɁA
���`���[�h�E�m�[�g���w覐R���N�^�[�x�i�z�n���فA2007�j�A
�����E�U���V�[���B�b�`�w���A�n���̗��������x�i�݂������[�A2012�j������B
�܂�����
��P�� �w�n�ꗷ�s�x�ւ̗U��
��Q�� �n���̒��S��
�n�ꗷ�s�̓����
�n�������ƉF���̂Ȃ���
�n�ꍂ�M������
�n���̒��S��ڎw���j����
��R�� ���l�Ȓn�����E
��S�� �n�������̉ߋ��Ɩ���
���n���z�n���_
���n�n���̎p
���肭��f��
��T�� �l�Z���N�O�̗��q
�T���v���v
������̒n��
�[����
��U�� �[������̃��b�Z���W���[
�n�k�͓V�̍ق���
�n�k�v�̊���
�ߑ�n�k�w�̒a��
��V�� �e���n����覐�
��W�� �L����n�k�ϑ���
�n�k�R���N�^�[�A�~����
�ގ������ƒn�k�v
�O��̔g
�[���n�k�͂��邩
��X�� �E�F�Q�i�[�̑嗤�ړ���
��P�O�� �R���������[�x�@��B�v���W�F�N�g
�v��̏I���ƍĊJ
�}���g���̊��
��P�P�� �n�\�Ɛ[�����Ȃ�����
�}���g���̓�
���ݍ��݂́u���v
�₦�Ă����n��
�J�ڑw�̔���
��P�Q�� ���͂ƃ}���g��
�����Ɗi������Ȋw��
�_�C�������h�A���r���Z��
�}���g�����\���������
��P�R�� ���̔j�ЁA�_�C�������h
��P�S�� �}���g���̒�ŋN���Ă��邱��
�|�X�g�y���u�X�J�C�g�̔���
�j�����ƒn�k�w
��P�T�� ������
��P�U�� ����n�k�̊�����
�n�k�g�g���O���t�B�[
��P�V�� ��̏z��
�z�b�g�X�|�b�g�̖���
�N��ɑ��ł�
��P�W�� �n���T���ƃj���[�g���m
��P�X�� �n���̊j�ɂ��Ă̘_��
�ő̂��t�̂�
���ƂȂ�t�̓S
��Q�O�� ���C�Ɉ���������
���ʎ��j�̗��j
�^�k���w���Ȃ����C�Ίp
��Q�P�� �����̒T��
�n���[�ƍL�接�C�}
�n�����ꔭ���̎d�g��
�������̃_�C�i�����_
��Q�Q�� �n���̉ߋ��Ǝ�����
�����K�Ǝ��C
�n�����C�̋t�]
�O�j�Ɠ��j�̂��߂�����
�_�C�i���̔����ɔ���
�_�̌�Ƃ�m�邽�߂�
��Q�R�� ���j�̔�����
�����Ȃ����
�n���̐V�����̈�̔���
�A���X�J�n�k�Ɠ��j
��Q�S�� ��߂��S�̋�
��ȓ��j
�œ��j�͂��邩
��]������j
��Q�T�� �����̐X
�����̋N���Ǝ��C
�����T���̉\��
��Q�U�� �f���̒n�ꐢ�E
�ٍʂ���ؐ�
�A�C�X�E�W���C�A���g�ƃX�[�p�[�E�A�[�X
��Q�V�� ���̏I���
���z�̎���
�n���̍Ŋ�
�V���������������炷����
����
��҂��Ƃ���
�@�n�����w��ł��邱�Ƃ͒N�����m���Ă���B�����A�^�}�l�M�̔���ނ��悤�ɁA�ꖇ�ꖇ�߂���ƁA���ꂼ��̑w���ǂ̂悤�ȏ�Ԃɂ���̂��A
�͂�����v�������ׂ���l�͏��Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B���������ꖇ�ꖇ�A���ꂢ�ɂނ����ƂȂǂł��Ȃ��̂�������Ȃ��B
�n�\����n���̒��S�܂ł̗���N���Ɏv�������ׂ�͓̂���B
�@�{���̓f�C�r�b�h�E�z���C�g�n�E�X��
�gJourney to the Centre of the Earth: The Remarkable Voyage of Scientific Discovery into the Heart of Our World�h�iWeidenfeld & Nicolson, 2015�j
�̑S��ł���B�t�����X�̍�ƃW���[���E���F���k�ɂ�铯�������w�n�ꗷ�s�x�i1864�N�j��150���N���}���邱�Ƃ�m��A
�V���w�҂̃z���C�g�n�E�X���m����Ă�150�N��̒n�ꗷ�s���B
�@�������̂Ƃ��胔�F���k�́w�n�ꗷ�s�x�́A�n���̓�����T������s��ȗ�����ł���B
�z���w�̌��ЃI�b�g�[�E�����f���u���b�N�������A16���I�̘B���p�t�A���l�E�T�N�k�b�Z�������c�����Í�����ǂ��A
�A�C�X�����h�̉ΎR�̕��Ό�����A�n���̒��S��ڎw�����s�ɏo������B�����鉙�̃A�N�Z����A��A���n�Ōق����K�C�h�̃n���X�ƂƂ��ɒn���T�����A
�n���ɍL����C��n���āA������L�m�R�̐X��ʂ�A��ł����͂��̌Ð����Əo��B�O�l�����̒n�����E
�i�T�N�k�b�Z���������łɒ��S�Ɏ������Ƃ������ƂȂ̂Ŏ��ۂ͑O�l�����ł͂Ȃ��̂����j�ɂ͒n���̗��j���܂��Ă����B
���F���k�́w�n�ꗷ�s�x����150�N�A�n���ς͑傫���ω����A���ł��ω��������Ă���B
�Ȋw�҂ɂ���ĉ�����������Ă����n���̓����Ɋւ���m���܂������́A�ǂ�ȋ��قɖ����Ă���̂��낤���B
�@���݂͎�ɉȊw���C�^�[�Ƃ��Ċ�������{���̒��ҁA�f�C�r�b�h�E�z���C�g�n�E�X���m�́A
�ȑO�̓W���h�����o���N�d�g�V����ƃ����h����w�}���[�h�F���Ȋw�������̓V���w�҂ŁA�m�`�r�`�̂������̃~�b�V�����ɂ��Q�������B
���̌�A�a�a�b�����̉Ȋw�S���L�҂ƂȂ�A�e���r�ԑg��W�I�ԑg�ɏo�����邩�����A
�C�M���X�̉Ȋw�G���w�j���[�E�T�C�G���e�B�X�g�x��V���w�C���f�B�y���f���g�x���ɒ���I�Ɋ�e���Ă���B�܂��A�����V���w��̉���ł���A
�ߋ��ɂ̓\�T�G�e�B�[�E�t�H�[�E�|�s�����[�E�A�X�g���m�~�[�̉�����߂��B���̃C�M���X�̒c�̂͐��̈��D�Ƃ̂��߂̉�ŁA
�����҂ƃA�}�`���A�������Ɍ𗬂���ꂾ�������B�z���C�g�n�E�X���m�͉Ȋw�[�ւɔM�S�ŁA2006�N�ɂ́A�ނ̉Ȋw�ƃ��f�B�A�ւ̍v�����������āA
���f���i4036�j�Ɂu�z���C�g�n�E�X�v�Ƃ������O������ꂽ�B�����ɂ́A���Ƒ��z�Ɋւ���Í������̓`������j�A�Ȋw��ԗ�����
�gThe Moon: A Biography�h�i2002�N�j�ƁgThe Sun: A Biography�h�i2005�N�j�A�F����s�m�̃C���^�r���[�������Ȃ���F����s�̗��j���Ђ��Ƃ�
�gOne Small Step�h�i2009�N�j�A�K�����I�E�K�����C���͂��߂Ė]�����ʼnF�����ϑ����Ă���400�N�ɂȂ邱�Ƃ��L�O���ď����ꂽ�K�����I�̓`�L
�gRenaissance Genius�h�i2009�N�j�Ȃǂ�����B
�@�{���ł́A�z����̃J�v�Z���ɏ���āA�ő̂̒n�\����o�����A�n���̒��S�܂Ŗ�6370�L�����[�g���̗�������B
�^�������j��ڎw���̂����A�n�������̍\�������������I�Ɍ����킯�ł͂Ȃ��B�\���A���j�A�Ɍ��̈��͂��Č��ł��鑕�u�A
�閧�ɔ��鐔�X�̌v�������A�����Ɋւ�����l�X��_�@�ƂȂ����ł����ƂȂǂ����̓I�ɐD��Ȃ���A�s��ȃh���}���W�J����B
����͒n���̓����̃h���C�Ȑ����Ƃ��������A�N���ǂ̂悤�ɔ��������̂��Ƃ����l�X�̕��ꂾ�B���̂��߁A
�������Ɋւ���Ă���Ȋw�҂��C���^�r���[���A�ނ�̐��̌��t�����p����Ă���B�O�����猩��ƒn���͐Â��Ȑ��E���B
�����A�ΎR��n�k�A�I�[�����Ȃǂ��A�n���ŋN�����Ă����K�͂Ȍ��ۂ�\���Ă���B�n��ɂ͉��x�∳�́A������z���ɍ��ݍ��܂ꂽ�n���̗��j������A
�n�k�w�̔��W�ɂ���āA���̎p�����傶��ɕ����яオ���Ă����B�z�R�ɐ���A�n���ōł��[������K��A�����ɑ��݂���ΐ��T�C�Y�̐��E��T�K���A
�����̂Ƃ����т��Ă��Ȃ��ő̂̓��j�̌����ׂ�B���ɓ��j�Ɋւ���ŐV�̔����͋����[���B�����āA���̘f���́u�n�ꗷ�s�v�A
�n���O�����́A�n���̖����ւƑz���͉ʂĂ��Ȃ��L�����Ă����B�܂��A���������I�ŁA�b�肪�]�X�ƈڂ낢�A��݊|����悤�ɐ����������A
�b�����S�Ɉ��邩�Ǝv���ƌ��ɖ߂�Ƃ����悤�Ȑ▭���������I���B�����ǂ݂ɂ�����������Ȃ����A�����̎����͋C�𖡂���Ă������������Ǝv���A
���ݍӂ��Ė��Ƃ͋ɗ͔������B�����炱����Ɏv����y���Ȃ���A���m�̐��z���y����ł���������Ǝv���B
�@�����A�n���w�I�Ȓn�ꗷ�s���Ǝv���ēǂݐi�߂���A����������a���������邩������Ȃ��B�n���̓����ƕ����Ďv�������ׂ�悤�Șb��A
���z���̖��O�A���ʑ́A�n���N��Ȃǂɂ��܂�G����Ă��Ȃ����炾�B����ɂ͗��R������B
���F���k�̗����z���̖͂L���ȍ�Ƃɂ��n�ꗷ�s�ł������悤�ɁA����̂���͓V���w�҂ɂ��n�ꗷ�s�ł��邩�炾�B
�z���C�g�n�E�X���m�̎��_�͂����܂ł��O���A�܂�F���ɂ���A�e���݂����߂Ēn�����u�������̘f���v�ƌĂԁB
�n���Ƃ����f���Ɛl�ԂƂ̌��т��ɒ��ڂ��A�u�������̒n�ꗷ�s�ł́A�����������ɒn���Ɩ��ڂɊW���Ă��邩��m�����v�Ƃ����B
�u�����č��ł́A�������グ�邽�тɁA���̐S�̈ꕔ�͎��c����鄟�����̏Z�ނ��̘f���A�����Č����ĖK��邱�Ƃ��ł��Ȃ��ꏊ�Ɂv�Ƃ������A
���̒n�������ւ̗��̒��ł͂ނ���A�u�S�̈ꕔ�͉F���Ɏ��c�����v�Ƃ������ق���������������Ȃ��B���̎��_�������A�{���̖��͂ł͂Ȃ����Ǝv���B
�@�z���C�g�n�E�X���m�͖{�������M���钆�ŁA�����ɑ���Ȃ��������̂�m�����Ƃ����B����́A�F���ɂ���ڂ������Ă������A
�����̑����ɂ��������̐��E���������Ƃ������Ƃł���B�ȑO�ɖ|���w覐R���N�^�[�x�i�z�n���فA2007�N�j�̒��҂��V���w�҂ŁA
�n���ɖڂ�������̂��x�������ƂȂ����Ă���ꂽ�B�������p����ƁA�u�f���w�҂�V���w�҂͖�������Ȃ��l�킾�B
����f������������Ȋw�҂͉i���Ɏ�ɐG����Ȃ����̂�ǂ����߂�^���ɂ���m�������n�F���T���@�ɂ���Č���f���⏬�f���̉摜������ꂽ���A
�������������[�ɐ����āA�����ق��̐��E�֏o�����ăT���v�����̎悷��Ƃ����i�ɂȂ�A�V���w�҂͈�������ŁA
���w�҂�n���w�ҁA�z���w�҂ɏꏊ�𖾂��n���Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B�܂�A��ŐG�������͓̂V���w�҂̗̕��ł͂Ȃ��̂ł���v�B
�n���̒��S�ւ̗��́A���ꂱ��z�����邱�Ƃ͂ł��Ă��A���ۂɊ��s���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���Ȃ��Ƃ������_�ł́B�����ł���A
�������Z�ސ��ł���Ȃ���������ĖK��邱�Ƃ̂ł��Ȃ��A��ŐG��邱�Ƃ̂ł��Ȃ��n�����E�̈ē����Ƃ��āA
�V���w�҂قǂ̓K�C�҂͂��Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�������̒n�ꗷ�s�͏��������̕��ꂾ�B�i���ɏ�����������ʂĂ��Ȃ�����ł���B�{����ʂ��Ēn�������𗷂��A�Ǒ̌����邱�ƂŁA
����A�V���������̃j���[�X�����邽�тɁA�n�����E���܂��܂��g�߂ɁA�N�₩�Ɋ����邱�Ƃ��ł��邾�낤�B