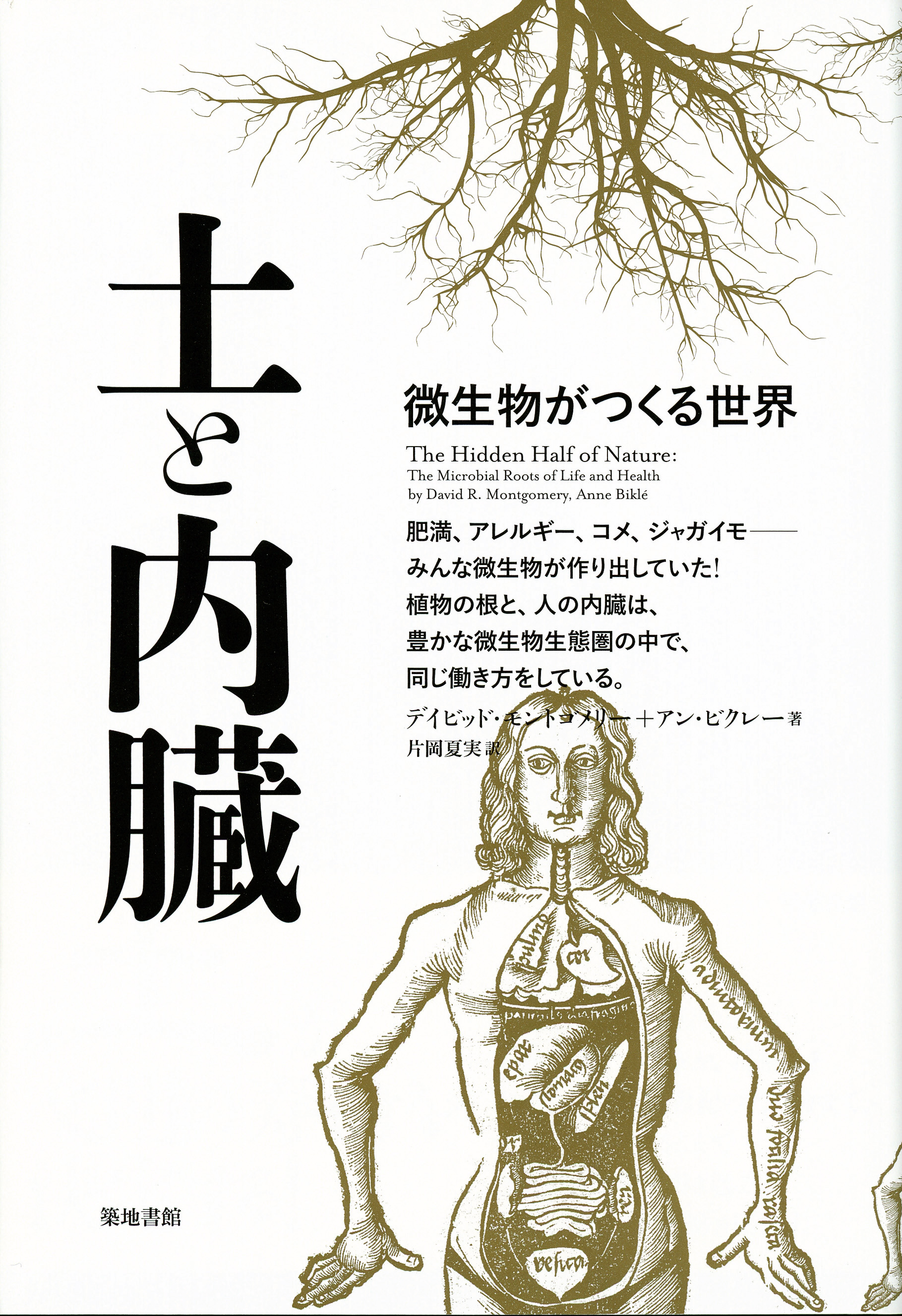生物界をつくった微生物

| ニコラス・マネー[著]小川真[訳] 2,400円+税 四六判上製 256頁 2015年11月刊行 ISBN978-4-8067-1503-0 DNAの大部分はウィルス由来。 植物の葉緑体はバクテリア。 生きものは、微生物でできている! 何世紀もの間、我々人類は自分が目にした動物や植物をもとにして、生物の世界を描いてきた。顕微鏡が微生物の隠れた世界を垣間見せてくれたが、微生物世界の真の大きさとその重要性に光が当てられたのは、ここ10年ばかりのことである。 人体、樹木、海水や海底の泥、土壌や湖沼や河川、大気などのすべてが、微生物に満ちあふれている。しかも、その活動は地球の歴史とともに、生物圏を形作り、維持するのに必要不可欠なものなのだ。微生物は、我々自身にとっても必須の存在であり、食べ物を消化するという点で膨大な数の微生物に頼っているのだ。 著者のニコラス・マネーは、地球上の生物に対する考え方を、ひっくり返さなければならないと説く。葉緑体からミトコンドリアまで、生物界は微生物の集合体であり、動物や植物は、微生物が支配する生物界のほんの一部にすぎないのだ。 著者は単細胞の原核生物や藻類、菌類、バクテリア、古細菌、ウイルスなど、その際立った働きを紹介しながら、我々を驚くべき生物の世界へ導いてくれる。また、繊細で美しい植物プランクトンから、空気中の菌の胞子や土の中にいる空中窒素固定細菌、海底の黒い噴出孔にくらす極限環境微生物の古細菌に至るまで、地球上のあらゆる場所に微生物が満ちあふれていることも教えてくれる。 肉眼では見えない小さな生物の大きな世界へ想像の翼をひろげよう。 |
ニコラス・P・マネー(Nicholas P. Money)
イギリス生まれ、エクセター大学で菌類学を学ぶ。アメリカ合衆国オハイオ州オックスフォードにあるマイアミ大学で、植物学の学部長を務める。
70報を超える菌類学に関する研究論文を書き、
『ふしぎな生きものカビ・キノコ』(築地書館、2007年)
『チョコレートを滅ぼしたカビ・キノコ』(築地書館、2008年)
などの菌学の教養書を執筆。彼の研究は『ネイチャー』誌上で「素晴らしい科学的・文化的な探求」と称賛された。
小川真(おがわ・まこと)
1937年京都府生まれ。京都大学農学部卒業。同博士課程修了。農学博士。
森林総合研究所土壌微生物研究室室長、環境総合テクノス生物環境研究所所長を経て、大阪工業大学工学部環境工学科客員教授。
日本林学賞、ユフロ(国際林業研究機関連合)学術賞、日経地球環境技術賞、愛・地球賞(愛知万博)、日本菌学会教育文化賞など、数々の賞を受賞。
著書に『[マツタケ]の生物学』『マツタケの話』『きのこの自然誌』『炭と菌根でよみがえる松』『森とカビ・キノコ』『菌と世界の森林再生』(以上、築地書館)、
『菌を通して森をみる』(創文)、『作物と土をつなぐ共生微生物』(農山漁村文化協会)、『キノコの教え』(岩波新書)、
訳書に『ふしぎな生きものカビ・キノコ』『チョコレートを滅ぼしたカビ・キノコの話』(以上、築地書館)、『キノコ・カビの研究史』(京都大学学術出版会)など多数。
序章
第1章 エデン
池の中の生き物
生物多様性を知る方法
系統樹から生命の輪へ
アメーボゾア
ハクロビア
ストラメノパイル
アルベオラータ
リザリア
アーケプラスチダ
エクスカバータ
オピストコンタ
第2章 レンズ
顕微鏡の始まり
異端者ガリレオ・ガリレイ
嫌われたロバート・フック
初めて微生物を見たレーウェンフク
菌学の創始者ミケーリ
ヒドラとトレンブレー
生命の本質
進歩する顕微鏡と微生物
見直される生物界
第3章 大いなるもの、リヴァイアサン
大きな目玉
サンゴ礁と渦鞭毛藻類
海のシアノバクテリアと地球環境
海の珪藻
ホワイトクリフと円石藻
海にいる無数の微生物
海の微生物の生態
やたら多いウイルス
系統樹を揺さぶるウイルス
第4章 土と水
チャールス・ダーウィンとミミズ
アーケプラスチダ、植物の祖先
画一的な陸上植物
見直される土壌微生物
土壌微生物と養分循環
共生体としての地衣類
植物を支える菌根菌
未知の生物を探す
ウイルスハンター
陸と水に住む微生物
第5章 大気
リンドバーグと空中浮遊微生物
砂嵐に運ばれて
軍医の誤診
天候を変える微生物
海を渡るサビ病菌
胞子を撃ち出す菌
家の中から成層圏まで
第6章 裸のサル
母から子へ乗り移る微生物
大便と腸管の微生物叢の働き
創薬と微生物
抗生物質、微生物、アトピー、喘息
肥満と微生物
腸管の真核生物
腸管に住むウイルス
ヒトとゴリラの違い
体を包む微生物群
第7章 ウルカヌス神の鍛冶場とダンテの神曲、地獄篇
焼かれても生きる菌、アグニ
低温好き
深海に暮らす微生物
アスファルト好きの微生物
強酸と強アルカリが好き
黒いカビと放射線
紫外線と乾燥に強い
家の中の極限環境
研究開発での利用
極限環境生物としての真核生物
巨大な単細胞生物
極限環境で育つ地衣類
第8章 新エルサレム
忘れられていた微生物
微生物抜きの生態学
種多様性の保全と自然保護のあり方
細菌を取り巻く環境
生物学教育のあり方
エデンの園とは
謝辞
註
訳者あとがき
索引
さて、今回は「動物や植物は生物全体の中で最も小さなグループだ」という、ちょっと風変わりな見方で話を進めてみよう。
この一見突飛な考え方をわかりやすくするには、たとえ話が役に立つかもしれない。それは亡くなった家主がつけていたカツラのことなのだ。
私は子どもが思いつくままクマのことをベアリー、クロコダイルのことをスナッピーというように、この家主をランディーと呼んでいた。
彼は借家から離れたところにある、ピカピカに磨き上げた家で、豹紋柄のカーテンと真っ白な敷物に囲まれて暮らしていた、背の高い年配の紳士だった。
頭はつるつるに禿げていたが、てっぺんにはふわふわとした金髪の束が飾りのように乗っていた。
この毛の束がどうやってくっついているのか、私にはまったくわからなかったが、それは彼が頭を振るたびにくるくる回るのだった。
ランディーのカツラはまさに地球上の大型生物で、それは彼にとってさほど大切ではないが、誰の目にも触れやすいものだった。
カツラだけからランディーのことをわかろうとするのは馬鹿げている。
その通気のよい鳥の巣のようなカツラをいくら調べても、誰も彼が先の大戦の英雄で、裸のパラグライダー乗りとして有名だったことなどわかりもしない。
同じような見当違いのとらえ方が、現代生物学の弱点にもなっているのだ。
人類を含むすべての動物とあらゆる植物はいずれも進化のうえでは後発の生物群で、何十億年も前に動き出したルールに則って進む、宇宙のゲームに遅れて加わったグループなのである。
見ればすぐわかることだが、我々は生命体の本質、つまり「部屋の中のアメーバ」のことを忘れているか、ほとんど無視しているのだ。
ロバート・ルイス・スティーヴンスンは1885年に出した『子どもの詩の園』の序文で、「世界は無数の生き物にあふれ、私たちは王様と同じように幸せだ」と言う。
彼はこの小さな散文詩に『幸せな思い』という題名をつけたが、それはそのまま現在の生物学者に当てはまりそうである。
最近の推計によれば種の数は多いが、核の中に染色体を持つ生物、いわゆる真核生物は900万種ほどだという。
動物と植物は真核生物だが、過去250年の間に記載された動物は100万種以下、植物はわずか20万種にすぎない。
この種数の推定値と実数との間のギャップを埋めているのが微生物なのだ。
生物分類学の通説によると、微小な生物は真核生物の菌類と原生生物および細胞の中に核を持たない2種類の原核生物、すなわち細菌(バクテリア)と古細菌(アーケア)の4グループまたは界にまとめられている。
これらの生物群の存在は17世紀になって顕微鏡を用いたロバート・フックとアントニ・ファン・レーウェンフクらの素晴らしい仕事が世に出るまで、知られないままだった。
アメーバにいたっては、次の世紀までその片鱗すら知られていなかった。
フックの時代に「アニマルキュール」と呼ばれた、微細な生物のすべてに種名をつけて数え上げようというのは、かなり無駄な努力である。
なぜそういえるのか。もし人がチンパンジーと交雑するとしたら、何が起こるか想像もつかない。
さらに同じ実験をシェトランド産のポニーで試みるとなると、増殖の見込みははるかに遠のくだろう。
よく知られているように、「種」という科学用語は我々が動物の交配不能なものについていう場合だけ、明瞭な意味を持つのである。
同じことは植物についてもいえるはずだ。
ところで、もう一度顕微鏡サイズの生物に目を向けると、「種」の定義は科学的というよりむしろ哲学的課題である。
とくに細菌と古細菌については種の概念を当てはめること自体、ほとんど無意味だといえる。にもかかわらず、生物学者たちはこの小さな生き物に1万以上の名前をつけ、
それらが動植物のグループ分けに使われたルールに合わないという事実を知りながら、薄っぺらな細菌の目録を作ってきた。
おそらく、それはまず大きなものを取り上げ、しかも一番わかりやすいものから扱いたいという生物学者の積年の妄執によってなされたことらしい。
鳥や昆虫はじつにわかりやすい。撃ち殺すか、網でとって毒殺し、内臓を取り出したり、ちょっと針を刺してとめたりして引き出しにしまいこんでおけばよい。
時間があれば、引き出しを開けて動物の形や大きさ、色などを記載し、多くのほかの特徴も書いておく。
また、おそらく撃ち殺される前の様子、例えば「高い枝に止まっていた」とか、「自然観察していた人の頭に糞をした」などと書き加え、
その生物にラテン名をつける。これが、鳥類学者が1万種の鳥を命名し、ハチ学者が2万種ものハチを同定してきた分類学の実態なのである。
顕微鏡サイズの生物の広がりを量的に示すには、別の手法が必要なのだ。その一つは遺伝子、時にはその変異を調べることだが、
これが多様性を知るための基盤になる。名前がつけられていたかどうかは別にして、採集した生物からDNAを取り出すことは容易である。
また、実物を顕微鏡で見なくとも、海水や土からサンプルをとって核酸を抽出し、サンプルの中に何があったか思い描くこともできる。
次に、細胞形態の変異も微生物の多様性を調べるのに役立つが、収斂進化にこだわると、ありもしない類縁関係を取り上げるという大きな過ちを犯すことがある。
顕微鏡で見ると、菌類の糸状細胞とミズカビと呼ばれている原生生物のあるグループは非常によく似ており、同じやり方で成長するが、
これらの仲間は進化の過程で何億年も前に分かれたものである。細胞分裂のときに染色体を分ける分子的な仕組みは、
祖先が共通であることをうまく表わす動的構造の一つのよい例である。というのも、近縁のものは同じ仕組みによるからである。
細胞構造の非収斂的な細部を解析することは進化の歴史に関する高度な推論を導くのに役立ち、それは遺伝学によって検証されている。
3番目の判断基準は生物の代謝機構に現われる変異である。植物は自分で食べ物を作り、動物はほかの生物が作ったものを食べる。
また、多くの微生物は動植物と似たことをしており、すべての菌と細菌の多くはほかの生物が育てた組織を消費する。
したがって、彼らは捕食者であり、分解者でもあるが、光合成細菌や藻類は一次生産者である。
例えば、海にいるシアノバクテリアは植物と同じように、空気中の二酸化炭素から糖類を作り出す。この生理的共通性は、歴史上現われた偶然の出来事ではない。
植物はシアノバクテリアと同じように光合成をするが、これは植物体の中の葉緑体がシアノバクテリアだからである
(ある細胞がほかの細胞を飲みこんだが消化しなかったという、太古の内部共生によって結合し、その結果変形しているとしても)。
樹木の遺伝子は超高層ビルディングを育てて、この青緑色の細菌が詰まったソーラーパネルを広げているのだ。
微生物たちは何十億年もの間、さまざまな方法で自分自身を養ってきたのである。
化学合成無機栄養細菌と呼ばれている細菌や古細菌の仲間は、硫黄や2価鉄のほか水素、硫化水素、アンモニア、亜硝酸、メタンなど、
還元しやすい物質からエネルギーを取りこんできた。
水素ガスを酸化してエネルギーをとる細菌は温泉にいるが、その仲間のヘリコバクター・ピロリは人間の胃の中にも住んでいて、
胃潰瘍や癌の発生にかかわりがあるという。ちなみに、ある研究によると同じ細菌が体重コントロールに役立ち、
これを除くと小児喘息の発生が増えるともいわれている。この細菌を養っている水素ガスは地熱の作用で温泉の熱水の中に噴き出し、
腸の中にいる細菌によって胃の中へ吐き出されている。水素酸化細菌は地球上に暮らす生物の中で最も古いものの一つで、
その生き方は生物学の教科書の大部分を埋めている、ほかのどんな生物の範疇にも入らないだろう。
ウイルスは生物全体の中で重要な位置を占めているが、生物学者が生物の差異を議論する際には無視されがちである。
誰も異論はないと思うが、それはウイルスが非生物的存在だという問題を抱えているからである。
生物学の入門コースで学生たちは生物の特性について、繁殖して成長し、刺激に反応し、時に美味しいワインに酔いしれることなどと教わる。
もちろんウイルスも繁殖するが、それは宿主細胞に入って生化学的機能を乗っとり、それを使って自分自身を複製して増えるというやり方である。
ウイルス粒子の形成過程は成長とはみなされていない。というのは、ウイルスはカロリーを燃焼してそれ自体を作り上げるだけで、
細胞のように大きくならないからである。ウイルスは細胞と違って、有害な化学物質に反応して泳いで逃げたり、
何らかの生理的防御装置に頼ったりすることもない。言い換えれば、生物を我々自身のように細胞から成り立っているもの、
すなわち細胞生物と厳密に定義するなら、ウイルスは生物の仲間には入らないことになる。
ところが、ウイルスは細胞を構成する複雑な生物的分子と同じものからできており、その遺伝子情報は同じタイプの核酸に刻みこまれている。
そのため、分子的生物という用語はウイルスを入れる便利な屑カゴとして、このところよく使われている。
しかし、たとえ地球上の生命体の中で優勢な存在ではないとしても、生物学者たちはウイルスが大きな役割を担っているとみなしている。
実際、ウイルスは細胞生物よりもずっと多く、地球上の多様な遺伝子のほとんどはウイルスの形になっているのである。
微小な細胞生物同様、ウイルスは生物学者に数多くの問題を提起している。生命の最も小さな形は生物学者以外の者にとっても大きな問題である。
というのは、生物多様性の本質をよく理解していないということ、言い換えれば我々が微生物にどっぷり浸って満たされ、
それからできあがっているのに少しも気づいていないということなのだが、それは自分のよって立つところを見失っていることになるのだ。
なぜなら、我々は多くの生命体の働きに無知なまま、つまりもともと我々人類がいなくとも非常にうまく働いてきたし、
働くだろうということに気づかないまま真実を理解することを怠り、ゾウの大切さを強調する頭脳集団に誤って引きずられているからなのである。
我々はほんの少し想像力を働かせてアメーバのことを知る必要がある。おそらく、この生物の見直しが生命の本質にかかわる問いかけに対する唯一賢明な答えになることだろう。
書き換えられた生物学は、必要とされる光を投げかけるはずである。では早速、生物界の再構築を始めてみよう。
さて、私はイエローストーン国立公園にもアフリカのサファリにも行かずに、この惑星地球の多様な生物界を見渡す偉業を成し遂げてみようと思う。
実際、オハイオ州郊外にある自宅の裏庭の命あふれる木立や小さな池以外、私はどこへも出かけていないのだ。
一度よく知れば、このプラスチックに囲われたオアシスがどんな国立公園の豊かな生物相にも匹敵することがわかるはずである。
この生命体のとらえ方は17世紀以前のものとは対照的で、生物圏に対する理解の革命的変化は顕微鏡の発明によって可能になったのである。
その歴史的考察は第2章で紹介するよりも、もっと面白いはずである。それに続く章では海洋、土壌、大気などの生態系における生物多様性について考察する。
次に出てくる話題は人間生態系を構成する10兆の動物細胞と100兆の微生物の共生関係である。彼ら(微生物)と我々(受精卵から発達した細胞体)
の間に残っている相違は、人間の細胞の複合性と人間の遺伝子の多くがウイルス起源であることを考えると、頭が混乱してくるほどである。
デカルトは、考えることが存在の証明であるという理論を打ち立てたが、もし我々が培養された微生物の複雑な混合物以上(か以下)のものだとしたら、
我々人類は生物学的現実を超えて存在することになるのだろうか。このことを知るために温泉を含む特殊環境を訪れ、
同時に消毒済みの家のような場所にも出かけてみよう。最後に生物学教育の再構築に必要な地球上の生物のとらえ方を示して、終わりの章を閉じることにしよう。
小冊子にしては目標が高すぎるかもしれないが、小さなものほどよいと私は信じているのだから。
(注)
各章の冒頭に、ジョン・ミルトンの『失楽園』の一節を挙げておいた。目が見えなくなって痛風に悩まされ、
2番目の妻にも先立たれたミルトンは秘書や友人にあてて、1658年から1663年の間にこの叙事詩を書いたといわれている。
この作品を通して、科学が超自然的なものの中に取りこまれている。ミルトンは1638年か1639年にガリレオに会ったと伝えられており、
多くの場面に天文学上の発見がちりばめられている。『失楽園』は1667年に出版されたが、それはフックの『ミクログラフィア』が出た2年後、
ニュートンの『プリンキピア』が出る20年前のことだった。チャールス・ダーウィンは1830年代のビーグル号による航海にこの詩の縮刷版を持っていき、かなりの部分を暗記していたという。
神の力を「偉大なる創造者の御業」と讃えたミルトンの考え方が、ダーウィンの進化に対する考えを揺さぶったのだろう。
詩人が生命の素晴らしさについて語る調子は、熱帯を旅して心が「喜びのきわみ」だったと書いたときのダーウィンの情熱に通じる。
若い科学者の採集品の中に種の創造にかかわる無限の時間を意識するにつれて、次第に彼の心の中に生命に対する畏敬の念が高まっていったように思える。
ミルトンとダーウィンは心を通わせていたのだ。かのヴィクトリア朝の自然科学者は正道を歩んでいたが、今日の我々は地球の豊かさを知るために、
どれほど遠くまで行かなければならないか、完全に忘れているのである。ミルトンは科学の案内人ではないが、その経験を通して我々を大いに楽しませてくれる。
この本を書き始めたときはまとめをどうするか考えていなかったが、
何か月か経つと自分でも驚くほど第1章に掲げたミルトンの一節がこの仕事の結びにふさわしいと思うようになったのである。