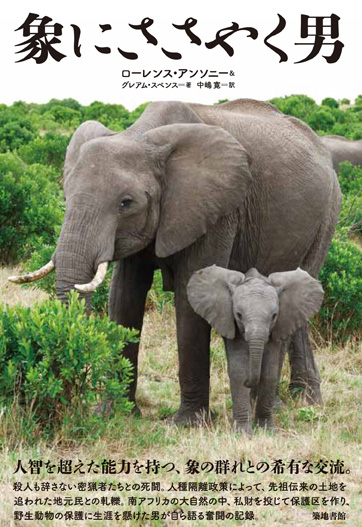都会の野生オウム観察記お見合い・リハビリ・個体識別

| マーク・ビトナー[著]小林正佳[訳] 2,400円+税 四六判並製 368頁 2015年1月刊行 ISBN978-4-8067-1487-3 大都市サンフランシスコに生息する、野生オウムの群れ。 個性豊かなオウムたちと一人の男の親密な交流を通して描かれる、 都市の自然と人間社会との関わり。 映画『The Wild Parrots of Telegraph Hill』原作、全米ベストセラーの話題作! 「野生とのつながりを求める一人の人間の、胸打ち、心温まる記述の中で、著者は語りかける。 野鳥たちと、どのように友だちになり、その過程で、どのように自分自身の人生の意味を見出したのかを」 パブリッシャーズ・ウィークリー評 |
マーク・ビトナー(Mark Bittner)
1951年、バンクーバーに生まれる。高校卒業後4ヶ月間ヒッチハイクと汽車でヨーロッパを旅行し、帰国後シアトルに移ってミュージシャンの活動を開始。
1973年バークレーに移り、挫折を経験し、西海岸を旅した後、サンフランシスコのノースビーチでホームレスの暮らしに入る。
その後15年間転々と住まいを変えながらその日暮らしの生活を送り、その間に東洋の宗教やゲーリー・スナイダーの詩などに関心を抱くようになった。
1988年雑用係の仕事を得てテレグラフヒルのコテージに住み込み、2年後、そこで4羽の野生のオウムに遭遇。
群れは次第に大きくなり、その後6年間にわたり餌やりなどを通してオウムたちと交わり、鳥たちについて学んだ。
1996年オウムについての本を書き始め、2004年に出版。その間にオウムとの交流がドキュメンタリー映画化され、監督のジュディー・アービンと結婚。
現在もテレグラフヒルに住み、路上生活者時代の経験を描いた次作『ストリート・ソング』の執筆に取り組んでいる。
小林正佳(こばやし・まさよし)
1946年、北海道札幌市生まれ。国際基督教大学教養学部、東京大学大学院博士課程(宗教学)を修了。
1970年以来日本民俗舞踊研究会に所属して須藤武子師に舞踊を師事。
1978年福井県織田町(現越前町)の五島哲氏に陶芸を師事し、1981年織田町上戸に開窯。1988年から現在まで天理大学に奉職。
その間、1996〜1998年トロント大学訪問教授、セント・メリーズ大学訪問研究員としてカナダに滞在。
2000〜2002年、2010〜2011年、中国文化大学交換教授として台湾に滞在。
現在は、天理大学総合教育研究センター特別嘱託教授。
民俗舞踊を鏡に、宗教体験と結ぶ舞踊体験、踊る身体のあり方を探ってきた。民俗と創造、自然を見つめる眼ざしといったテーマにも関心がある。
著書に『踊りと身体の回路』『舞踊論の視角』(共に青弓社)、訳書にヒューストン著『北極で暮らした日々』、ロックウェル著『クマとアメリカ・インディアンの暮らし』(共にどうぶつ社)、モウェット著『狼が語る』(築地書館)など。
序
ローリングストーン
テレグラフヒルでの日々
嬉しい出会い
信頼関係を築く
赤ん坊のマンデラ
オウムの科学
復活を遂げたドーゲン
すべてが変わる
ブルークラウンのバッキー
パコと仲間たち
過酷な野生
事態が動く
不思議なオウム、テュペロ
人間社会に戻る
鳥のように自由に
幸せな時間の終わり
スナイダーとスナイダー
流れにまかせて
説明できるものと、できないもの
遅い巣立ち
訳者あとがき
私は今、サンフランシスコの街の一角、テレグラフヒルにある古いコテージの玄関前のデッキに立っている。
ツタが絡みつき崩れ落ちそうなコテージは、丘の東側の急斜面を転がり落ちるように広がる、乱雑に草木が生い茂った大きな庭の緑の中に埋まっている。
私のすぐ右側の大きな鳥籠に、サクランボのように赤い頭をしたライムグリーンのオウムが三羽。籠の上を、別のオウムが自由にゴソゴソ動きまわる。
左手に持ったカップにはヒマワリの種がいっぱい入っていて、二羽のオウムがしがみつき、素早く巧みにそれをついばむ。
右手にも、両肩にも、頭にも、オウムたち。 目の前の灌木の枝に十羽以上のオウムがとまり、私が手一杯の種を差し出すのをじっと見つめている。
その中の一羽が注意を惹こうと意を決し、盛んに翼をばたつかせ、足元の細い枝が上下に大きく揺れる。
デッキの手すりの上で、五羽のオウムが小さな種の山をついばむ。ずっと右手、手すりを越えて鬱蒼と伸びたツタの上にも大きなお皿が置かれ、
皿の上の種のまわりに十五羽ほどの一団が群れている。さらに、十羽が頭上の電線にとまり、全部で五十羽以上のオウムが私を取り囲む。
電線にとまった鳥たちが執拗なキーキー声のスタッカートを刻みはじめ、その声がさらに大きく切実なものになるにつれ、
下にいる鳥たちが次第にそれに加わる。旅行者たちの一団が魅入られたように顔を輝かせ、立ち止まって眺めている。
キーキー声があまりに大きくなり、旅行者の中には耳を覆わなければならない人がいるほどだ。
「どこかへ行ってしまったりしないの?」
「僕の鳥じゃない」。私は、笑いながら大声で答える。
「野生の鳥ですよ」
「野生って?……本気なの。サンフランシスコに、野生のオウム?」
私が答える前に、オウムたちの叫び声はピークに達し、群れ全体が突然飛び立った。
飛び立つ際の混乱の中で二、三羽のオウムが旅行者に追突しそうになり、驚いた旅行者が身を屈める。
こわばったような羽を狂わんばかりにばたつかせ、オウムは叫び続け、木々の列の隙間を抜け、視界から消えていく。
そう、サンフランシスコに棲む、野生のオウムたち。
この書はマーク・ビトナー著『The Wild Parrotsof Telegraph Hill (原題 テレグラフヒルの野生のオウムたち)』(初版 Harmony Books, 2004)の全訳で、
底本にはThree Rivers Press 発行のペーパーバック版(2004)を用いた。ただし、読みやすさを考え、編集部が章をいくつかの節に区切り、
新たに小見出しを付けた。もうひとつ、原著では本文の後にABC順でオウムたちが短く紹介されている。
本文との重複も多いのでそれを削除し、命名の由来など興味深い部分を適宜本文に挿入した。
オウムの呼称についてひとこと。ここに登場してくる主要な2種のオウムの和名はオナガアカボウシインコとトガリオインコで、
しかもチェリーヘッドは英語名としても正式なものではない。しかし、文中にも断られているように、
著者自身敢えてチェリーヘッドという俗名を用いていることと、赤と青との視覚的対照を生かすため、チェリーヘッド(サクランボの頭)、
ブルークラウン(青い冠)という英語の表記をそのままカタカナに置き換えて用いた。
私がこの本を知ったのは、家内がアメリカ北東部メイン州の小都市ウォーターヴィルで毎夏催される国際映画祭で本と同名のドキュメンタリー映画を観、
監督のジュディー・アービンさんの話を聞いたのがきっかけだった。本文にも示されている通り、映画作りは本の執筆と並行して進められ、
床を歩き回るドーゲン、ドーの巣立ちなど、ああ、これがあの場面、とまるで懐かしくさえ感じるようなシーンが次々に出てくる。
美しい映像は著者とオウムたちとの交流を生き生きと伝えていて、まさしく本と一対の作品といっていい。
この本の面白さには、相互に絡み合う3つの話題があると思う。ひとつは、今までほとんど知らなかった、あるいは普段思い描いていたのとは随分違う、
意外なオウムたちの姿。何と個性溢れる、愉快で、奇妙な鳥たちなのだろう。騒がしさ喧嘩と苛めと妬みに呆れながら、
剽軽な活発さと感情表現の直截さ、互いの絆の深さに惹かれずにいられなかった。しかもその舞台がサンフランシスコという、
多くの日本人が毎年訪れる都会のまっただ中だというのだから驚いてしまう。
2つ目は、ビートニク・ヒッピー世代のその後の生活と彼を取り囲む人間模様の面白さ。
60年代最後に大学生活を送り、ある面で同じような空気を吸って生きていただろう私にとっても懐かしい名前が次々に登場し、
頷いたり、思わず微笑んでしまう場面もしばしばだった。確かに、こんなナイーヴさと真剣さの共存が、あの時代の人間にはあったと思う。
自ら路上にさまよい出るところまでいった者はごくごく少数でも、実際には海外旅行さえままならなかったあの時代、
心だけは太平洋の向こう側にも飛んでいたし、人間を越えた自然の世界にも向かっていた。
そして3つ目は、もちろん、この書の最も核心というべき、その両者の結びつき。おずおずと、
しかもなお旺盛な好奇心と憧れに後押しされながら野生の鳥と人間との距離が一歩一歩縮められていくようすは、
記述の響きから伺われる以上に希有な出来事だったに違いない。オウムと人間という一見どこにでもありそうな関係が、
しかしここでは、通常とは違う眼差しの中で、違った形で形づくられていく。著者自身十分批判を意識しながら、
しかしなお自らの心に映る風景や出来事を積極的に受け入れ肯定していく、まさしくこれは、心の交流と自己発見の物語でもある。
私が初めてサンフランシスコを訪れたのは、1973年の夏だった。著者がシアトルからバークレーに移り、
いよいよノースビーチで暮らし始めたのと同じ年だ。その後何度か街を訪問しているから、
ひょっとしてノースビーチやテレグラフヒル界隈のどこかですれ違ったことだってあるかもしれない、などと考えたり。
すでにカウンターカルチャーも峠を越え、フラワーチルドレンたちの姿も表舞台からは消えていた。それでも、
ふと街のどこかで何となく線香の香りが漂っているのを感じたり、書店にはホールアースカタログやカスタネダの本が並んでいたり、
そこここに時代の残り香は漂っていた。ギンズバーグの詩集やケルアックの本が並ぶシティ・ライツ書店も印象深かった。
今も書店は健在で、街の史跡に指定され、店内の壁にはビートニク詩人や作家たちの足跡を辿るウォーキングツアーの案内などが貼られていたりする。
訪問のたびにテレグラフヒルやコイトタワーにも行ったけれど、その東斜面を歩いたことはあまりなかったように思う。
オウムに気づいたこともなく、それだけに、『テレグラフヒルの野生のオウムたち』という原題を目にしたときは奇妙な感じがした。
著者のマーク・ビトナーは、本の最後に出てくるテレグラフヒルの家に今も暮らしている。http://www.markbittner.net/ のホームページを開くと、
Viewsfrom a Hill という通信で、本書に対する反応、著者とオウムとのその後の関わり、Street Song という新著の進捗状況、
最近の出来事に対する著者の思いなどを読むことができる。差し上げたメールへの返事では、オウムの群れは今では200羽以上にふくらみ、
活動範囲をサンフランシスコの南ブリスベーンにまで広げ、以前より頻繁に街中あちこち違う場所で見られるようになったという。
今も毎日通りかかるし、姿を見ることができる。といっても、すでにたまにしかしなくなっていた手からの餌やりも、
思うところあって2006年を最後にやめてしまったとのことだった。
おそらくこの本の読者の中にも、人間とオウムとの希有な繋がりはそれとして、
それが野生の鳥たちへの餌やりによって達成されたという点に引っかかりを感じた方がいらっしゃるに違いない。
私自身野生動物に対する餌やりに断固反対する原則主義に与するつもりはないけれど、野生動物への餌やりがさまざま複雑な問題を孕んでいることは事実だと思う。実際本の出版
と映画の評判がサンフランシスコのオウムたちに対する広範な関心を引き起こし、その結果公園や路上で餌をやろうとする人が一気に多くなった。
次第にそれは観光客や子どもたちを巻き込み、ある日フェリー・パークを訪れた著者は、人々の体のあちこちにオウムがとまり、
中には地上を歩き回るオウムさえいることに大きな衝撃を受ける。それほど気軽な、度を超えた接触を目にするようになって大きな危惧の念を抱いたのは、
著者だけではなかった。怪我や病気は人間と鳥双方にとって脅威だし、そうした事故を契機にオウム全体が排除されてしまう可能性だってあるだろう。
事実、アメリカのいくつかの州では、オウムは害鳥として駆除の対象になっている。また、中にはオウムを捕まえて持ち帰ろうとする人もいるだろうし、
何より、過度の接触によってオウムたちの行動パターンが変わり、人間が与える餌への依存が行き過ぎれば、
そもそも鳥たちの自由さえなし崩し的に失われていきかねない。そうした懸念がオウムへの餌やりそのものの禁止を求める動きを生み、
しかも著者自身、その条例の制定を強く働きかけた当事者のひとりだった。その結果2007年に条例が制定され、
今ではサンフランシスコの公園や街路で野生のオウム(実際に条文に記載されているのはオナガアカボウシインコ)に手から餌を与えること自体禁止されている。
そこに至る過程には、インターネットを通しての激しい議論もあった。
さんざん自分だけ楽しんでおきながら特権を独占しようとしているといった誹謗中傷もなかったわけではなく、
著者自身新しい事態に関わっていくには大きな躊躇もあったという。
それでもなお、ある意味ヒッピー世代の心情とは矛盾する法律による禁止という形をとってまで
オウムとの直接の接触をやめさせなければならないと思ったのはなぜなのか、
その間の事情に関しては、インターネットに掲載されている
「野生のオウムへの餌やり禁止条例」(The Ordinance to Ban the Feeding of the Wild Parrots)という著者自身の文章をお読みいただきたい。
わたしたちにとっては「籠の中の鳥」でしかないオウムを「野生の鳥」として認識することのむずかしさは、著者がしばしば指摘する通りだと思う。
繰り返し触れられているように、オウムの群れの第一世代の鳥たちはそもそも「野生」で捕らえられ、人の手を離れて以来異国の環境に適応して暮らし、
今ではたいていの鳥がそこで生まれ育ったものたちだ。決して人の手によって飼い馴らされた「ペット」の鳥ではない。
その彼らをいかに「野生」として認識することができるか、そうした眼差しの有無が、
鳥たちの「自由」をどれほど当然のあり方として受け入れられるかどうかの分かれ目になるのは確かだ。
ちなみに、文中に出てくる幼いオウムたちを襲う奇病について、今ではアライグマ回虫(Baylisascaris procyoni)が原因で、
糞便の中の卵がオウムの体内にとり込まれ、体内で孵化した幼虫が脊柱や脳に入り込んで引き起こされると考えられているという。
時には人間にも感染し、特に幼児の場合脳や目に障害を及ぼすこともある。どうやら、同じ回虫は、日本国内でも確認されているらしい。
ところで、文中にはわたしたちには奇妙とも思える「大乗仏教」談義が出てくるけれど、本の中に出てくる「仏教」の教えは、鈴木大拙や、
スナイダーやギンズバーグを通して六60年代以降のアメリカの若者たちに影響を与えた仏教、特に禅仏教の姿を反映し、
欧米における東洋宗教の受容として読むとそれなりに興味深い。一方、この中の進化論の理解は、
アメリカにおける「反ダーウィニズム」の潮流と軸を共にしていて、決して正しいとはいえない。
「自然選択」を「弱肉強食」や「生存競争」という言葉が示す闘争のイメージで理解する誤りは、ダーウィンの思想というより、
そうしたキャッチコピーを生みだしたスペンサーによって広められた通俗的な進化論理解に基づく誤解と言っていい。
特にアメリカでは、宗教的な保守層を中心に確かに「反ダーウィニズム」の潮流は根強い。それほど極端ではなくとも、
「闘争」の図式で理解されるダーウィニズムに対する反発は大きい。もちろんそこにはそれなりの事情もあって、
20世紀前半、急速な工業化に伴う経済格差の拡大や労働環境、生活環境の悪化、
さらには「人種偏見」をさえ「客観的に」正当化する裏付けとなったのが「適者生存」を旨とする「通俗進化論」であったという面は否定できないからだ。
もっとも日本における進化論理解とて大同小異で、「進化」は決して「進歩」のことではないし、
「進化」のプロセスは個々人の闘争や生き残りといったレベルで実現されるわけではない。
ここにも言葉が出てくる「利他主義」は、確かに長いあいだ進化論によってうまく説明できない難題であったけれど、
今やそれが「進化」の原則と矛盾しないことは明らかになっている。というより、
そもそも「利己主義」といった言葉で人間の倫理的な態度が問題にされる位相は、進化における適応といった議論とはまったくレベルを異にしている。
最初に言及した映画のDVDは、地域コードの違いがあって日本で容易に観ることができない。著者自身国外での販売を模索しているとのことで、
誰か日本版を作ってくれる人はいないだろうか。
映画を制作したジュディー・アービンさんはその後サンフランシスコのペリカンを描いた「Pelican Dreams」を完成させ、
この10月に劇場公開されたとのことだった。ここでも野生のペリカンとサンフランシスコの街との関わりが描かれていて、それを観るのが楽しみだ。
2014年11月 小林正佳
築地書館の電子書籍を初めてご購入される方へ・利用規約:
http://www.tsukiji-shokan.co.jp/ebookinfo

|
7-4-4-201 TSUKIJI CHUO-KU TOKYO, JAPAN
TEL:03-3542-3731 FAX:03-3541-5799
© 2011 tsukiji shokan publishing co., ltd. All rights reserved.