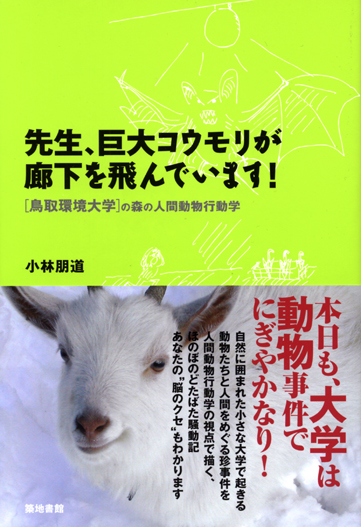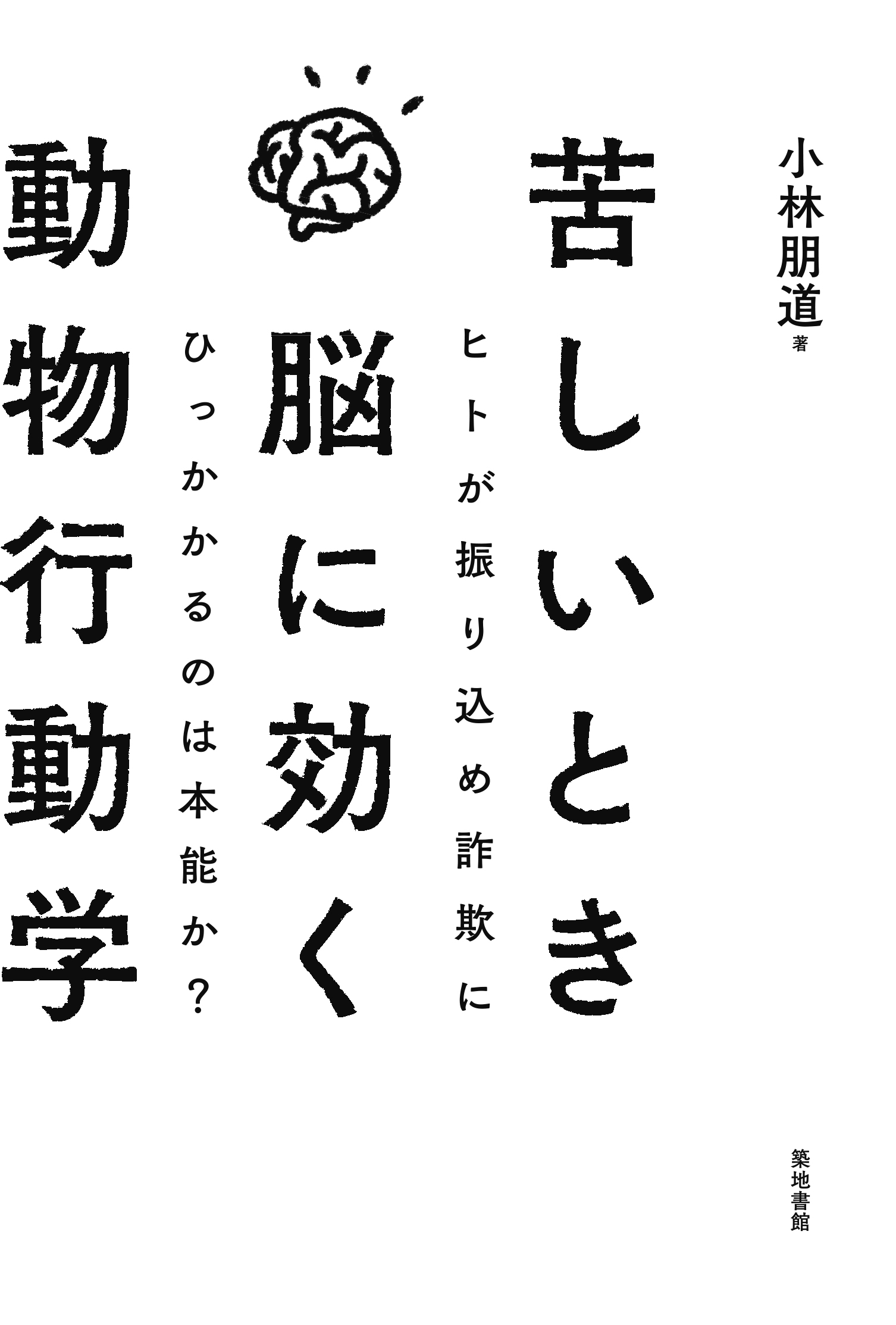|
ちょっとした“泣き言”から。
6月のなかばごろだった。
なにか、いつもと違う疲れを体全体に感じ、顔の目の下あたりに、違和感を覚えはじめた。会議の最中に不快な頭痛がして、数日前に治療を終えた歯も痛み出した。
ちなみに、私は、これまでの人生で、いわゆる肩こりやそれからくる頭痛というものを体験したことがなかった。妻からは、“野生児的な特異体質”と呼ばれていた。だから、鈍痛が続くはじめての頭痛の経験も、野生児の身にはこたえた。
そんな状態で、平日は勤勉に(!)仕事をし、休日は学生の研究のサポート、その間に、ちょうどそのころテレビやラジオの取材も重なって忙しくしていたら、目の下が腫れてきて、発疹のようなものもできはじめた。
これは何かある、と感じて医者に行ったら、私より少し若いくらいの上品な女医さん(それはどうでもよいのだが)から、上品に言われた。「帯状性発疹(帯状疱疹)でしょう」
もちろん“野生児”は、帯状疱疹といった単語は知らなかった。あとで、いろいろな(特に年配の)人に聞くと、さまざまな表現でこの「帯状疱疹」について説明してくれた。つまり、一般には比較的よく知られたものだったのだ。けっこうたくさんの人が、この帯状疱疹なるものをわずらった経験があったのだ。ただし、そのなかに、私のようにそれが顔に発症した人は一人もいなかった。やはり“野生児”は特異的なのだろうか。
原因は、子どものころ罹った水痘のウイルスが、体内の神経節(さまざまな種類の神経が集合したところ)の内部に残り、50歳くらいを超えて免疫機能が低下し、かつ、ちょうど疲れがたまったようなときに、ウイルスが増殖して起こるものらしいのだ。私にピッタシじゃないか。
そのウイルスは、神経の配線に沿って増殖・拡散していくので、腫れや発疹が帯状に広がり、だから「帯状疱疹」と言うのだそうだ(安易な命名だ)。
私の場合、三叉神経という頭部から顎にかけて分布する神経に沿ってウイルスが増殖したようで、そう考えると、腫れの状態や発疹(発疹という表現はなまぬるすぎる。“ただれ”みたいな感じだ)の分布がよく理解できる。
「なるほどねー」と、感心して鏡を見たのも事実である。
申し上げるのを忘れていたが、三叉神経は顔の左右で対になっていてつながっていないため、症状は顔の右側だけに現われた。やがて私は、少しでも会う方を驚かせないように、広めの眼帯をするようになるのだが(野生児は、けっこう小心なのだ)、つくづく右半分だけでよかったと思った。これがもし顔の両側だったら、両目の眼帯で、前が見えなくなるところだった。
さて、私より少し若いくらいの上品な女医さんから、上品に、「帯状性発疹でしょう」と言われたあと、病院から帰るとき、帯状疱疹に関する説明が書かれた冊子をもらった(そんな冊子が用意されているということは、帯状疱疹はけっこう一般の方にはポピュラーなものなのだ)。そして、それに目を通した私は、軽いショックを受けた。
というのも、そこには「ケースによっても異なるが、症状のピークは、発症から3、4週間後にきて、それからゆっくりと治癒していくでしょう」といった内容が書いてあったからである(ということは、これから数週間、今の症状がもっと進行していくということかよー。勘弁してよー)。
さらに、次のようなことも書いてあった。
「無理をすると、神経への傷が残り、治ってからも神経痛などの症状がずっと続く場合もありますから、発疹が見られる間はできるだけ安静にしましょう」(安静にしましょうって、これからやらなければならない仕事がいっぱいあるんだよー。どうすりゃいいのよー。)
その後、帯状疱疹の状態は、冊子に書いてあったように、二つの面で着実に進行していった。一つは顔の外観であり、もう一つは“疲れ”である。
右顔面はどんどん腫れていき、発疹とただれもひどさと広さを増していった。一方で、何か考えごとをしようという気分にはなれず、無理をして仕事を頑張ると、数十分で、「もう限界。横になりたい」という状態になった。でも講義はあるし、会議もある。マスコミ関係で約束している仕事もある。
私は、広めの眼帯をして、苦しみを感じつつ、それらの仕事に臨んでいったのである(ジャーン)。
ちなみに、眼帯をして講義室に現われた私を見て、いつも最前列あたりで講義を聞いている学生たちは、「先生、どうしたんですか」と、面白そうに聞いてきた。もちろんまったく悪気はない、気のいい学生たちだ。
私は、渾身の力をこめて、何か気の利いたセリフを返そうと思うのであるが、言葉が出てこない。でも、不思議なもので、講義を始めると、苦しさがやわらぎ、口から文章が次々に出てくる。なんとか九〇分の講義がやりきれるのである。自分でも意識しない、教員としての強靭なハートが潜んでいるのだろうか。
ただし、その反動もあった。研究室にもどって一人になると、どっと疲労感と痛みが押し寄せてきて、椅子を並べて横になった。夜は夜で、痛みや、わけのわからない不安で何度も目が覚めた。
こうして、苦しさに耐えながらの日々はけっこう長く続いていった(野生児は自然治癒力が高いと言うが、私は虚弱な野生児なのである)。でも、私は、その最中でも、体を休めながらも止まることはしなかった。本書の文章のなかには、そんななかで書いたものもある。
そして、私にはとてもとても長く感じられた1、2カ月が過ぎ、雨は上がった。
さて、なぜ私が本書の冒頭で、こんな話を書いたのか。それには深い深い理由があるのだ(二つほど)。
その一つは、現代の、なにかと痛みや不安を感じることが多い日本にあって、苦しみのなかにいる人たちに、なんというか、エールを送りたかったのである。帯状疱疹は一つのシンボルであって、野生児だって(というか野生児ゆえに)日々、いろいろな苦しみや哀しみを感じて生きているのである。だからこそ、エールを送りたいという気持ちにもなり、同時に、自分自身にも元気を出せ、と言い聞かせているのである。
もう一つの理由は、帯状疱疹で苦しんでいる最中に、心に固く誓ったのだ。
「これだけ苦しいのだから、絶対、どこかでネタにしてやる」と。
そういうわけで、ちょっとした泣き言を言ってしまったが、これを読んでくださった方には深くお礼を申し上げるとともに、懸命に生きる野生動物の話を知っていただき、少しでも元気を感じていただければとてもうれしい。
本書を手にとってくださってありがとう。
最後に、築地書館の橋本ひとみさんには、いつにもましてお礼を申し上げたい。いつもは締め切りよりかなり早めに原稿をお送りするのに、今回はぎりぎりになって(ちょっと遅れて?)の脱稿になってしまった。すべて帯状疱疹が悪いのだ。出版までの大変な作業に、苦しみを増やしてしまったにちがいない。
小林朋道
|