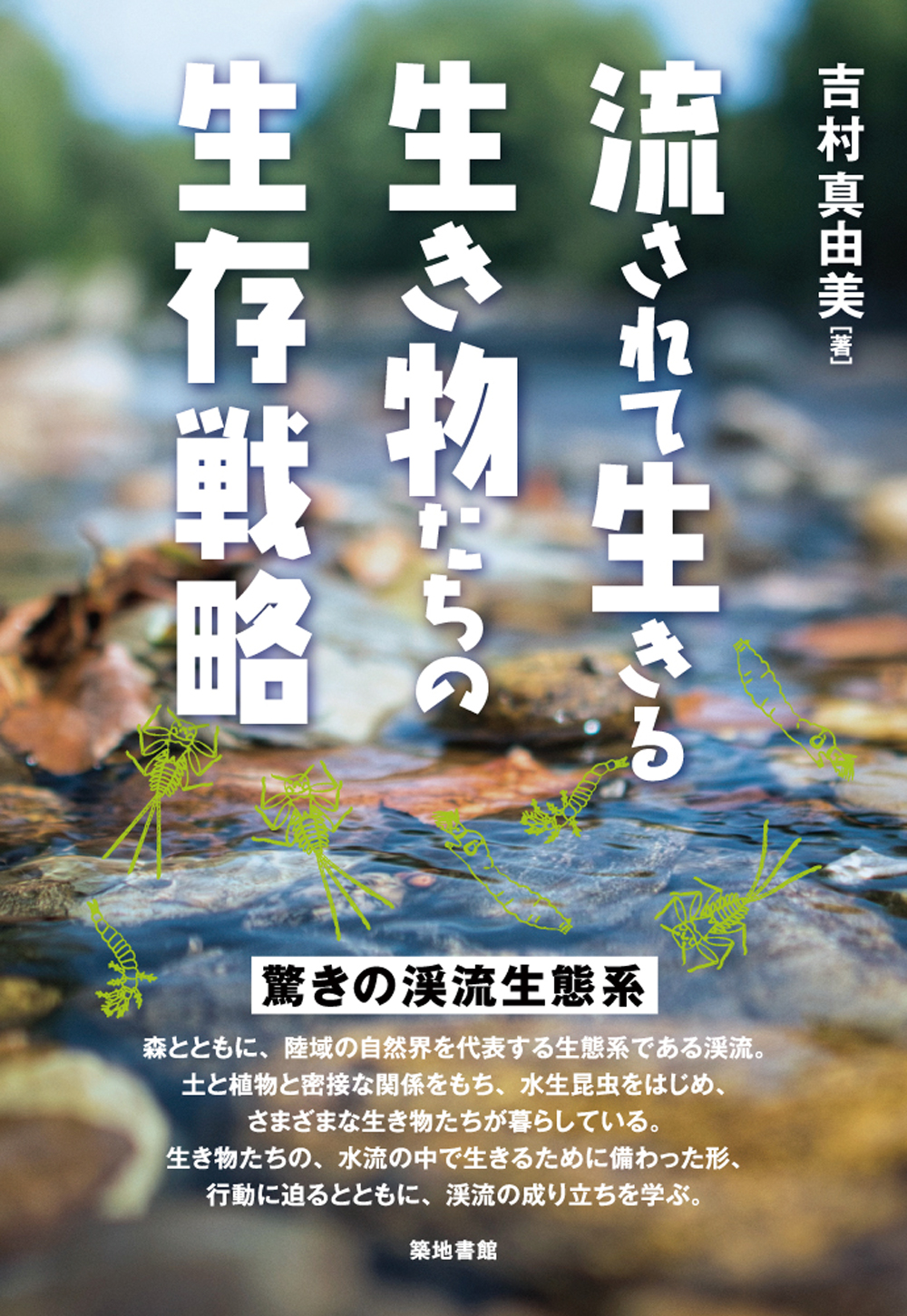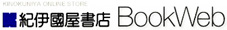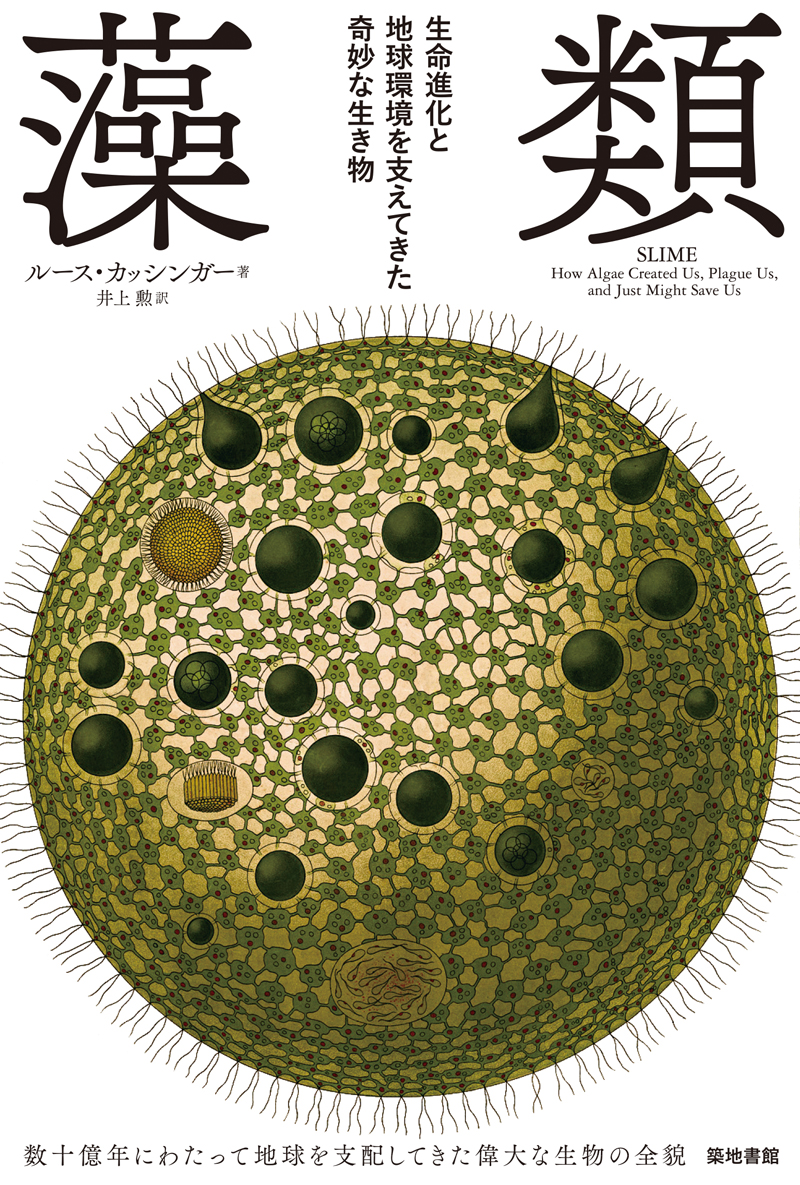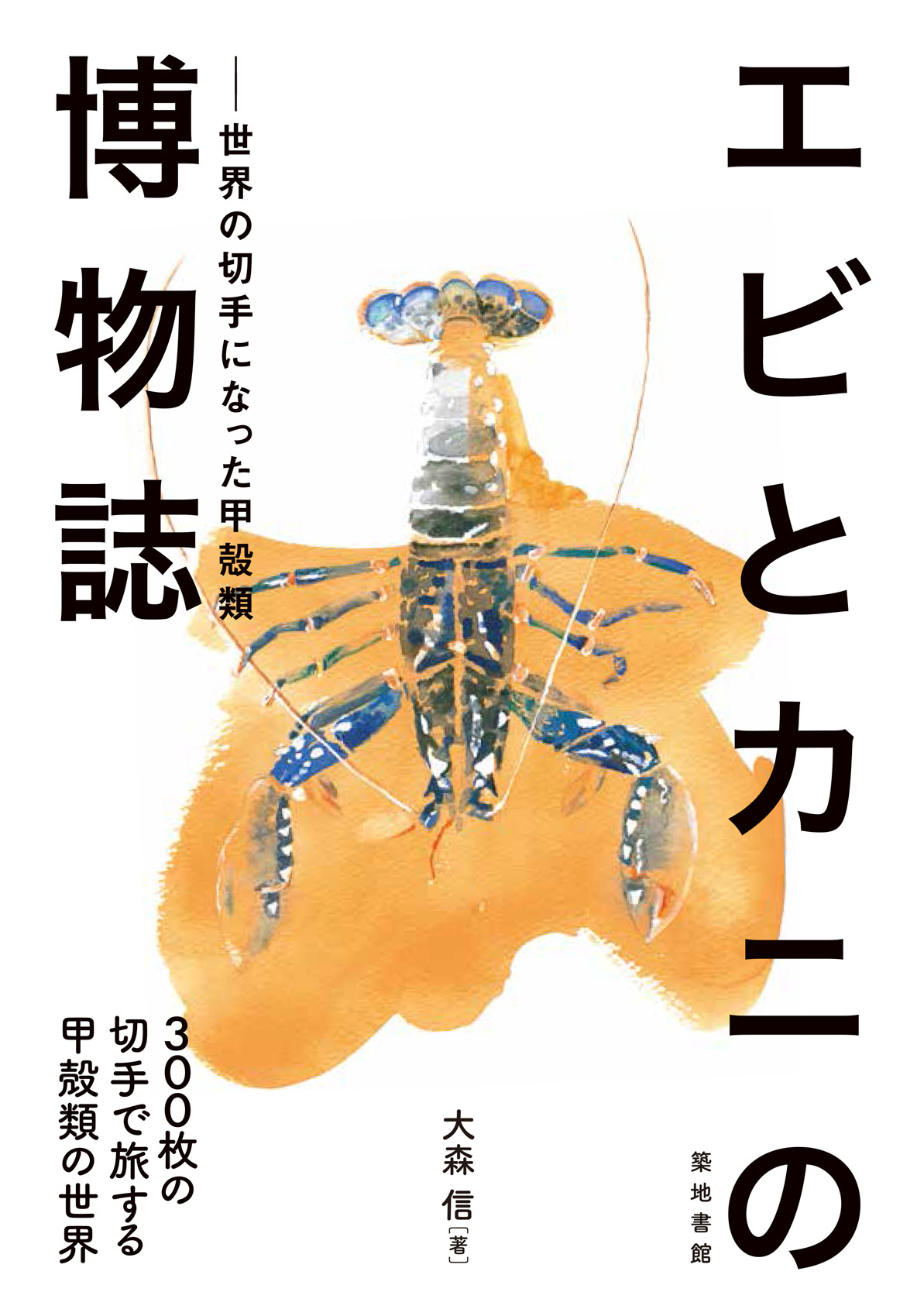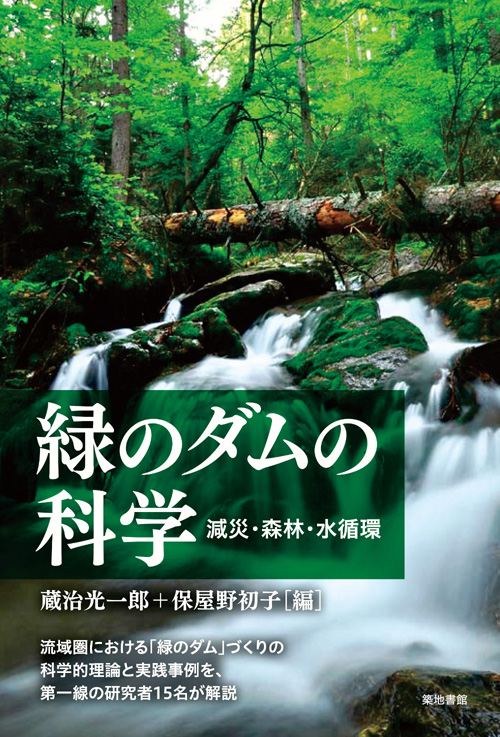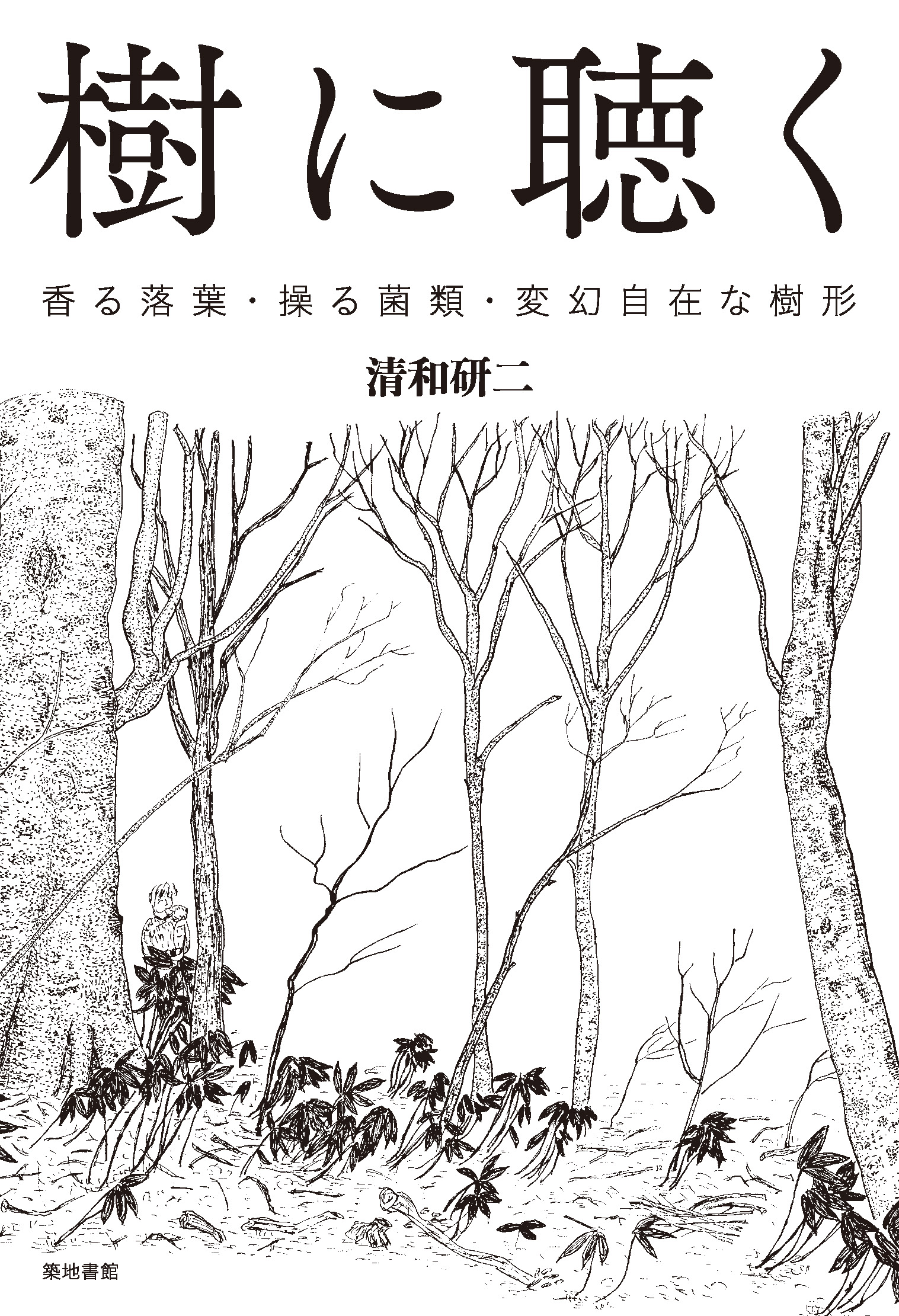|
はじめに
第1章 水の循環と河川
川の流れを追う
川の誕生―渓流から河川へ
川を数える
瀬と淵
隠れた水域、河床間隙水域
渓流域の樹木と水
川の構造をとらえる
渓流の環境
酸素濃度
水温
日射量
渓畔林
河床と石
流域の構造
川の水の流れ方
河床で決まる層流と乱流
水の粘性と慣性
川の中の流速
流量変化の要因
渓流の水質を決めるもの
大気汚染物質と雨水
酸性化をもたらす流域植生
軟水と硬水
土壌と有機物の中和作用
農業用水と農薬
絡みあうさまざまな要素
水質変化のパターン
水生昆虫による水質判定
川の生き物たちのさまざまな生息地
渓流の生き物のおもな生息地
高標高、高緯度
渓流の流れがとぎれている場所
湖やダムから流出する河川
氾濫原のある大河川
乾燥地域の河川
そのほかの生息地
南極の川
氷河が溶けた川
環境と生活史
コラム 渓流で注意すること(渓流遊び、釣りなど)
コラム 河川の分類
コラム 生活史と生活環
第2章 流水をいなして生きる生き物たち
攪乱を耐え忍ぶ
流れからの待避
流れを利用して移動する
小さな移動と大きな移動
流れにのって移動する─ドリフト
受動的ドリフトと能動的ドリフト
ドリフトで上流の個体数は減少するか
生き物が定着するまでの時間
コラム 渓流で水生昆虫を見てみよう
コラム 森と渓流を行き来する生き物たち
第3章 流水に適応する
外部環境への適応
成虫の呼吸のしくみ
幼虫のさまざまな呼吸法
浸透圧の調節
乾燥に耐える
生息環境と生き物の形状
体の形を適応させる
体の大きさと捕食リスク
絹糸で網や巣をつくる
生活環と生活史
生活史を決める二つの要因
生活史の期間
生活史の違い
個体間のばらつきと柔軟性
羽化、交尾、産卵
流水の中
酸素と呼吸量
積算水温と生活史
光と底生動物
不均一な河床がつくる多様性
空間の広がりをつくる石
pHと水生生物
流れを活かすもの、回避するもの
コラム 渓流における人工構造物がつくる新しい生態系
第4章 生き物どうしの関係
さまざまな察知能力
情報伝達の方法
テリトリーを守る
餌をめぐるやりとり
餌と消化
餌の分布と採餌効率で決まる行動
餌の獲得方法、5つのタイプ
多様な餌
成長とともに変化する餌
餌場をめぐる熾烈な争い
プレデターはどうやって餌を取るか
食われる側はどう行動するか
寄生という関係
コラム ウナギのシラスはなぜ不漁なのか─川と海の物質循環
第5章 渓流域における落葉の重要性
渓流域のエネルギーの流れ
有機物の循環
1ミリメートルより大きい粗粒状有機物、CPOM
CPOMより小さい有機物、FPOM
藻類の光合成と一次生産量
バイオフィルムと微生物ループ
溶存有機物、DOM
渓流域のエネルギー収支
落葉と底生動物
落葉が餌に変わるまで
好みの落葉と分解速度
底生生物たちと森
コラム 水生昆虫と放射能
コラム 富士山に川がない理由
【付録】 渓流に生息している主な生き物
水生昆虫
カゲロウ目
カワゲラ目
トビケラ目
ハエ目
ユスリカ科
ガガンボ科
ブユ科
甲虫目
カメムシ目
ヘビトンボ目
トンボ目
水生昆虫以外の底生動物
貧毛類
ヒル類
ダニ目
三岐腸目
巻き貝類
甲殻類
エビ類
カニ類
ヨコエビ類
原生動物
微生物類
細菌
真菌類
植物
藻類
コケ類
水生植物
脊椎動物
魚類
両生類
鳥類
おわりに
参考文献
索引
|