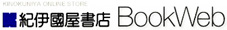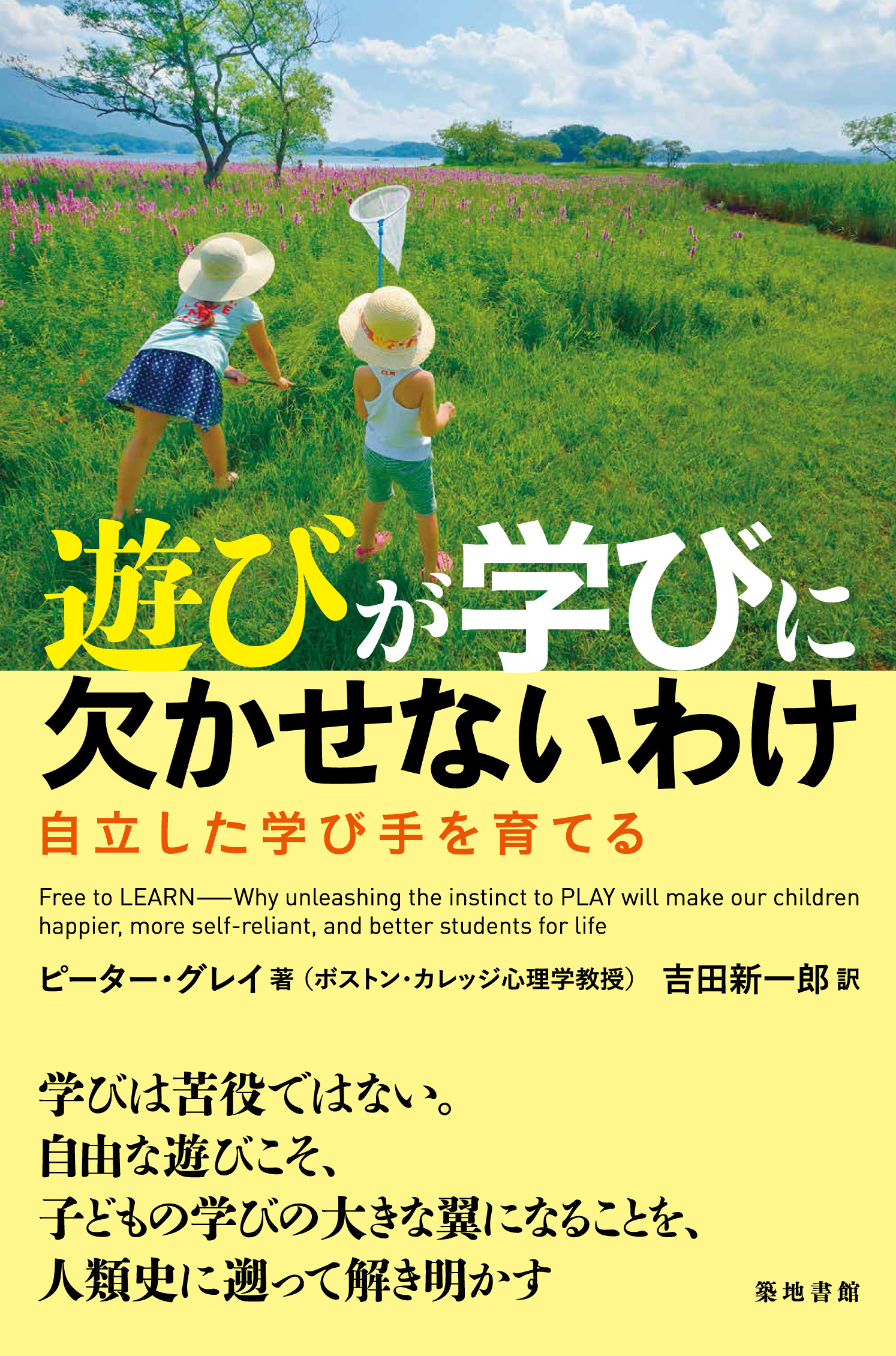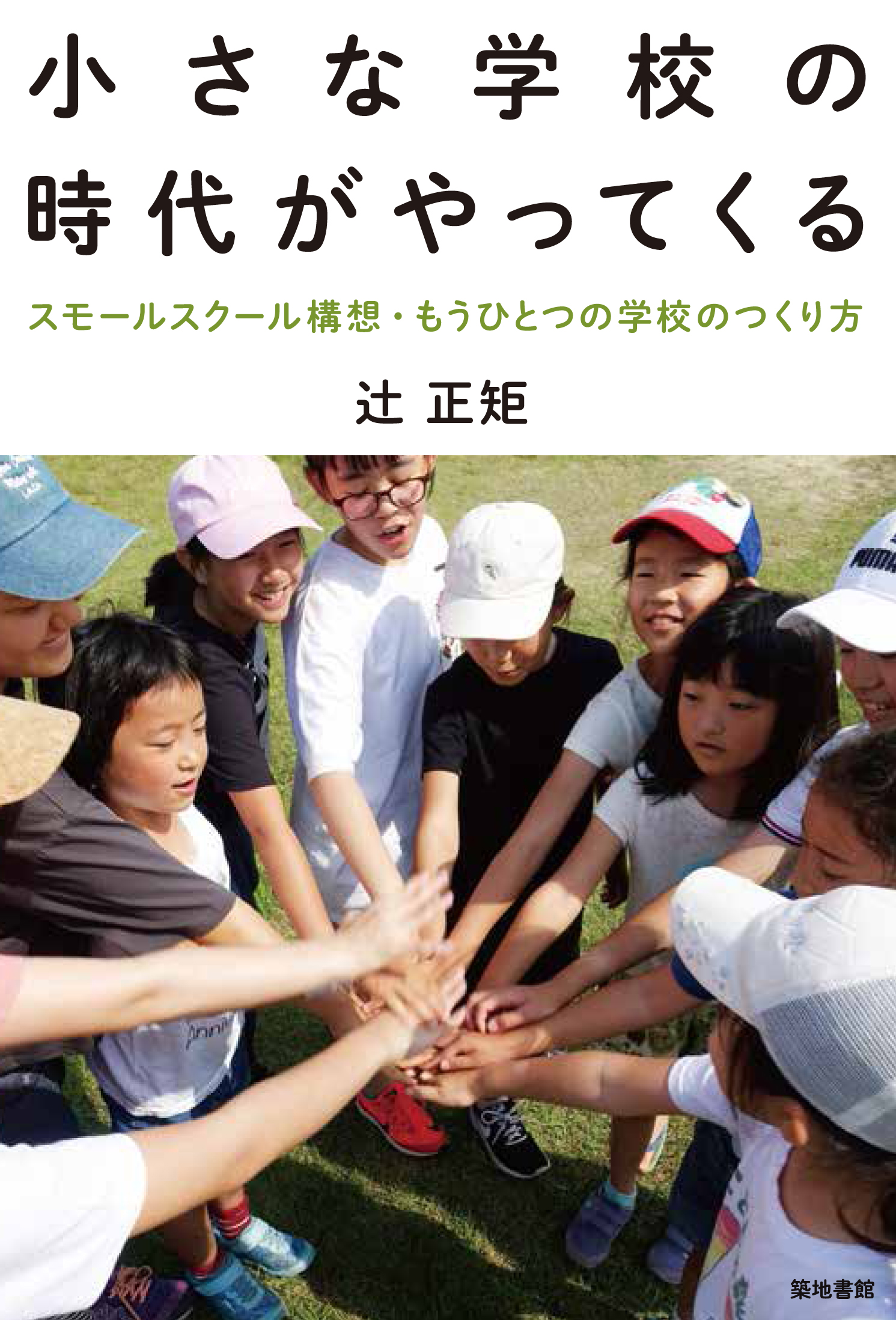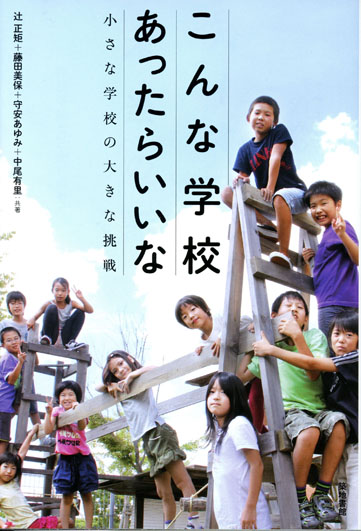一人ひとりを大切にする学校 生徒・教師・保護者・地域がつくる学びの場
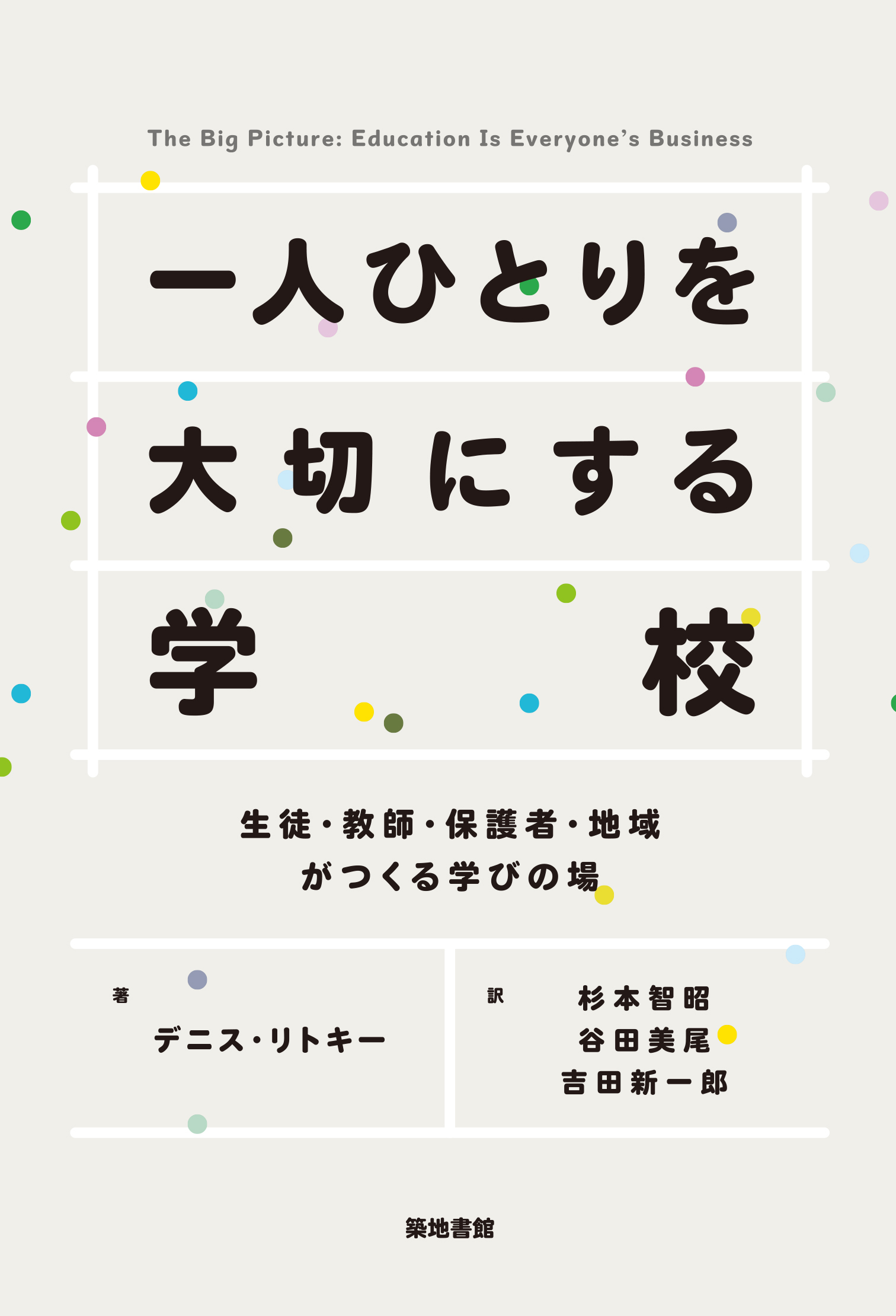
| デニス・リトキー[著] 杉本智昭+谷田美尾+吉田新一郎[訳] 2,400円+税 四六判 296頁 2022年8月刊行 ISBN978-4-8067-1639-6 これまでの学校で「勉強が苦手」だと思われていたり、 「落ちこぼれ」というレッテルを貼られてきた生徒が、 自ら学び、卒業後も成長し続けられるようになる学校の理念とはどのようなものなのか? アメリカの小規模公立学校でありながら、 全米および世界の100校ものモデルとなったMETの共同創設者がその理念と実践を語る。 [METの特徴] ・生徒の一人ひとりの興味関心をもとに個別化されたカリキュラムづくり ・保護者や地域も巻き込んだ教育環境 ・生徒は「リアル」な社会に出て、学びを深めていく ・生徒が、学校で家族の一員と思える「アドバイザリー」の導入 大阪教育大学 水野治久教授評 「一人ひとりを大切にする学校−生徒・教師・保護者・地域がつくる学びの場(デニス・リトキー著)」を読んで |