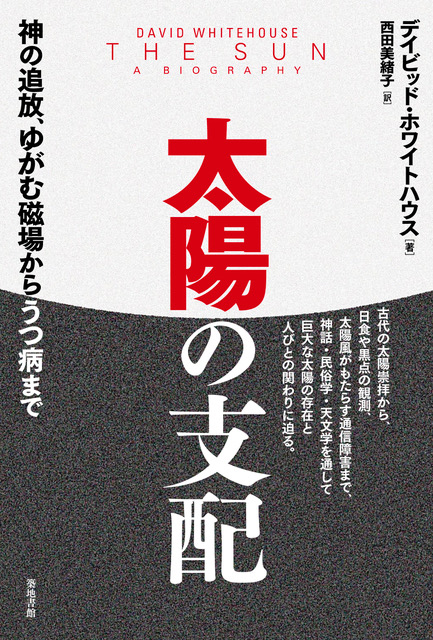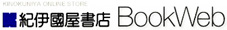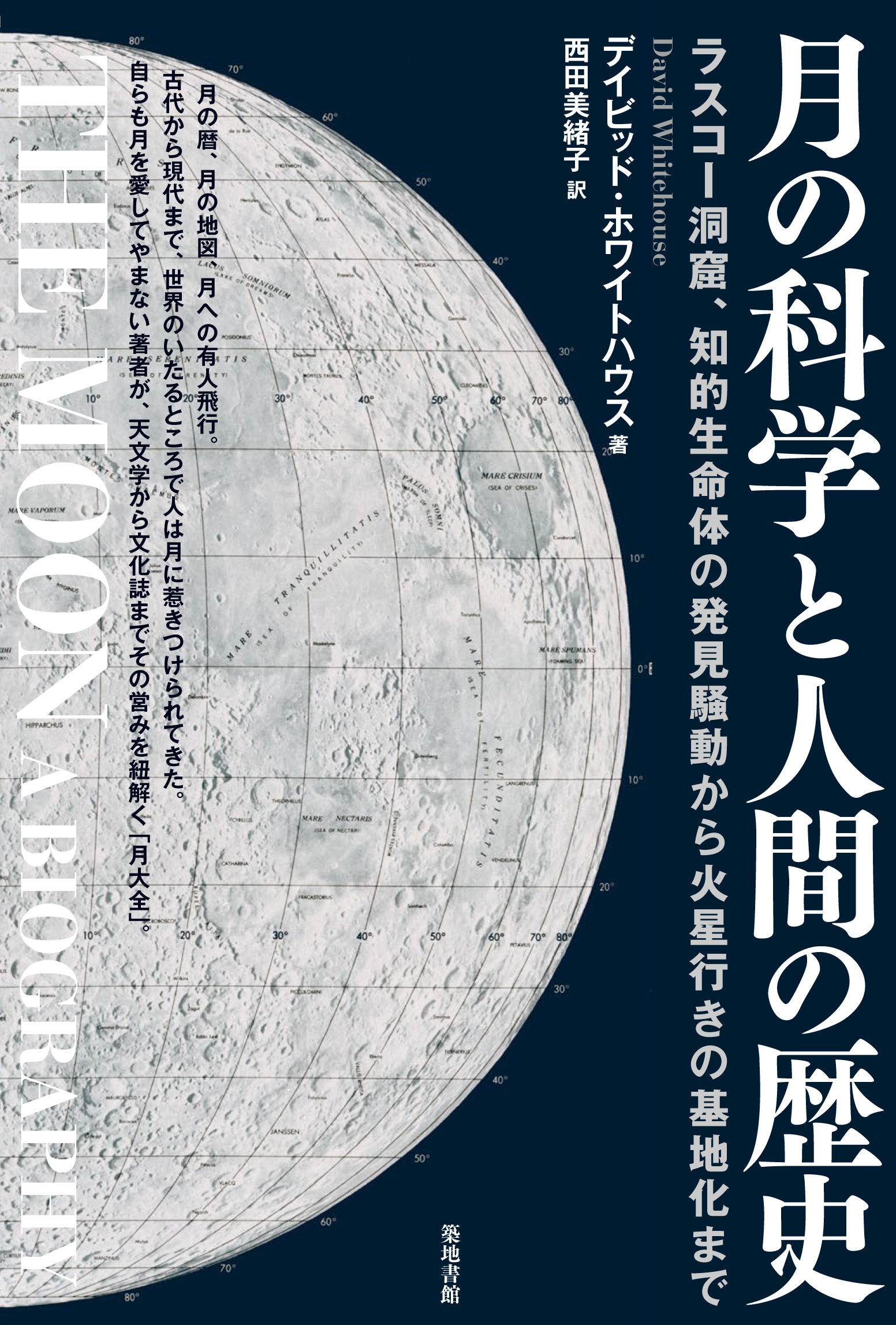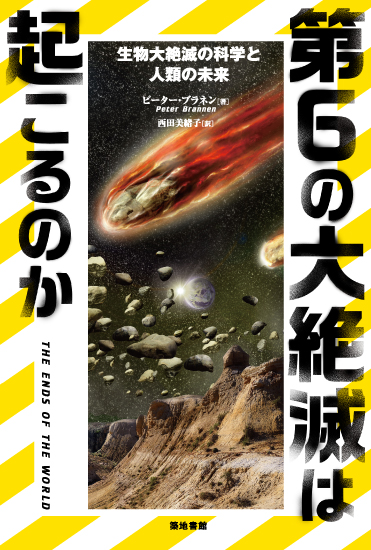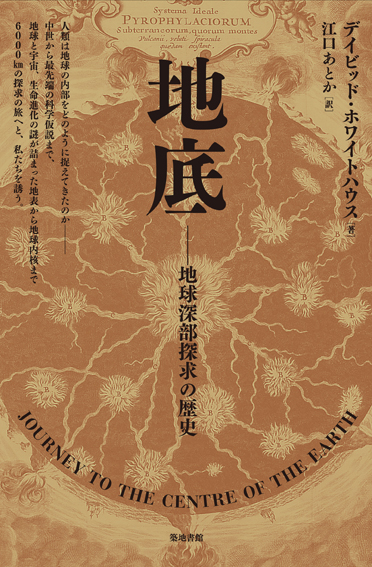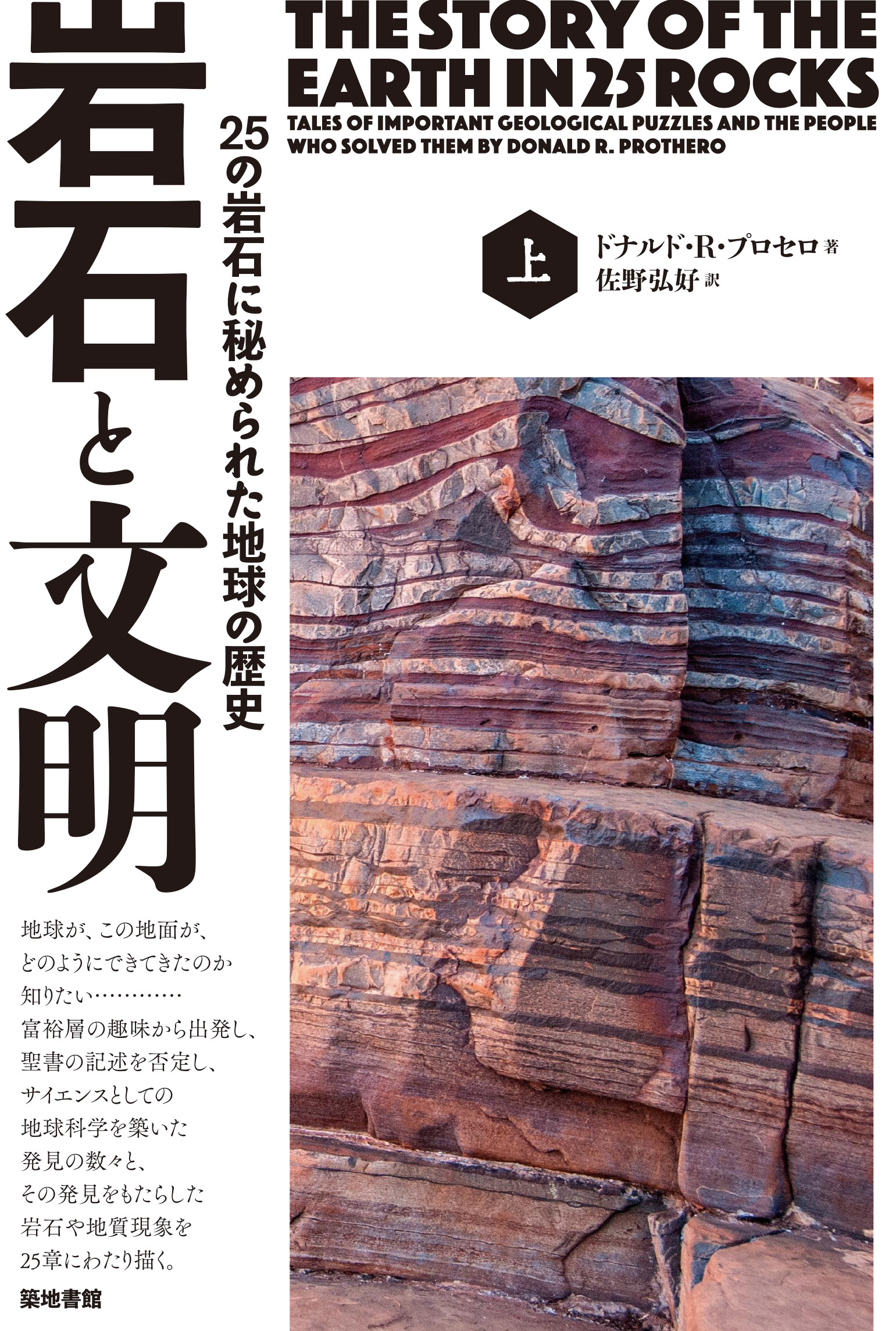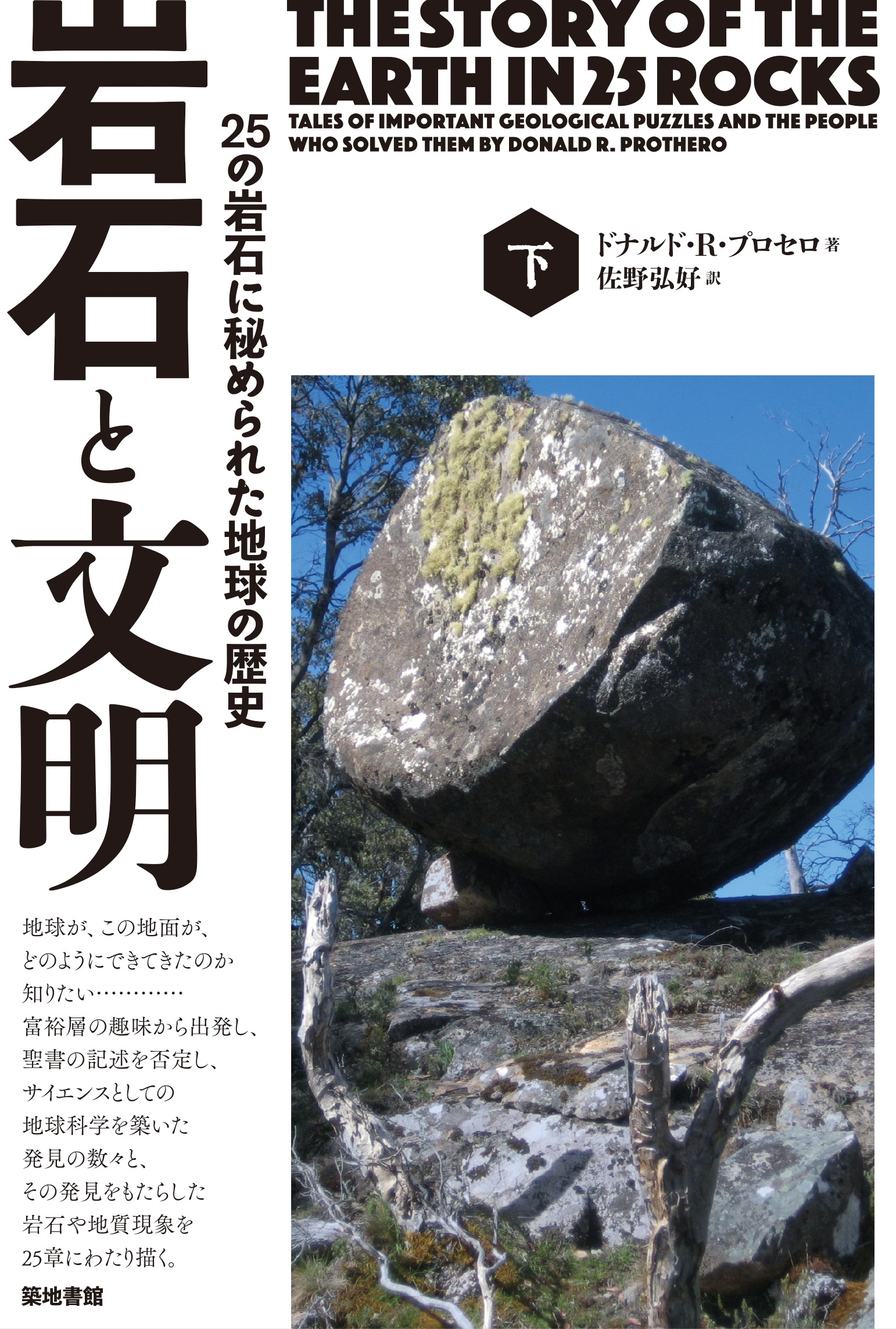|
はじめに 星のかけら
1 おあつらえ向きの星
あらゆる場所で太陽観測
太陽に似た星たち
2 通常物質と暗黒物質が混じり合った世界
恒星が生まれる前
初期の恒星の強烈なエネルギー
3 さまざまな太陽崇拝
太陽と古代の人々
世界各地の太陽神
4 ずれていく暦
太陽とうるう年
5 アナクサゴラスと日食
墓所の太陽
権力者と太陽
天動説の誕生
6 太陽による神の追放
天動説を打ち崩したコペルニクス
禁書『天球の回転について』
7 星の誕生
ラプラスの仮説
太陽の年齢
8 17世紀の太陽観測
ニュートンとプリズム
観測技術の進歩
太陽に生物は存在するか
9 マンハイムの火事とレンズ
太陽をとらえるレンズ
太陽の組成の解明
10 太陽光と人体
太陽と季節性感情障害
日光と睡眠サイクル、くる病
ビタミンDと肌の色
太陽光の恵みと危険性
11 重要書『ローザ・ウルシナ』
黒点の記録
4人の天文学者と黒点
ガリレオvsシャイナー
へヴェリウスの『天文機械』
進む黒点観測
12 2人の黒点観測者
太陽天文学者、キャリントン
太陽の写真を撮る
13 消えた黒点
太陽王、ルイ14世
黒点周期の発見
黒点と磁気嵐と年輪年代学
14 太陽研究の大変革
黒点の磁場
15 太陽の中心で起きていること
相対性理論を立証したエディントン
太陽の総エネルギー出力
太陽の年齢は46億歳
恒星の大気の解明
恒星のエネルギー生成
16 太陽風とオーロラ
オーロラにまつわる伝承
荷電粒子が降り注ぐ
17 太陽活動極大期と太陽嵐
磁気嵐が破壊したパイプラインと電力設備
太陽周期がもたらす脅威
18 究極のエネルギー
光合成の仕組み
太陽の子
人工の葉、太陽電池
石油時代の終焉
核融合の利用へ
国際熱核融合実験炉の実現
19 太陽エネルギーの衰え
冷たい地球
太陽研究と気象予報
太陽は完璧ではなかった
これから太陽に起こること
20 太陽が放出しているもの
とらえられたニュートリノ
太陽の放射線と宇宙探査
21 太陽を目指す人工衛星
米ソ、人工衛星打ち上げ競争
宇宙ステーションから太陽観測
探査機はどこまで太陽に接近できるか
太陽観測探査機のミッションは続く
22 宇宙の大海へ漕ぎ出す
太陽風をとらえる
太陽帆で進む宇宙船
23 太陽の中心を探る
太陽の内部へ
太陽の表面と波動
太陽の細部に迫る
謎に満ちたコロナ
捨てられる磁場
24 太陽ダイナモ
歪む磁場
さそり座18番星
25 太陽の隣人
赤色矮星、バーナード星
星の寿命とスペクトル分類
超巨星から超新星へ
26 地球以外の星で生存する方法
地球の行く末
地球脱出
27 さまよい続ける探査機
人類の痕跡
おわりに 神の目
訳者あとがき
索引
|