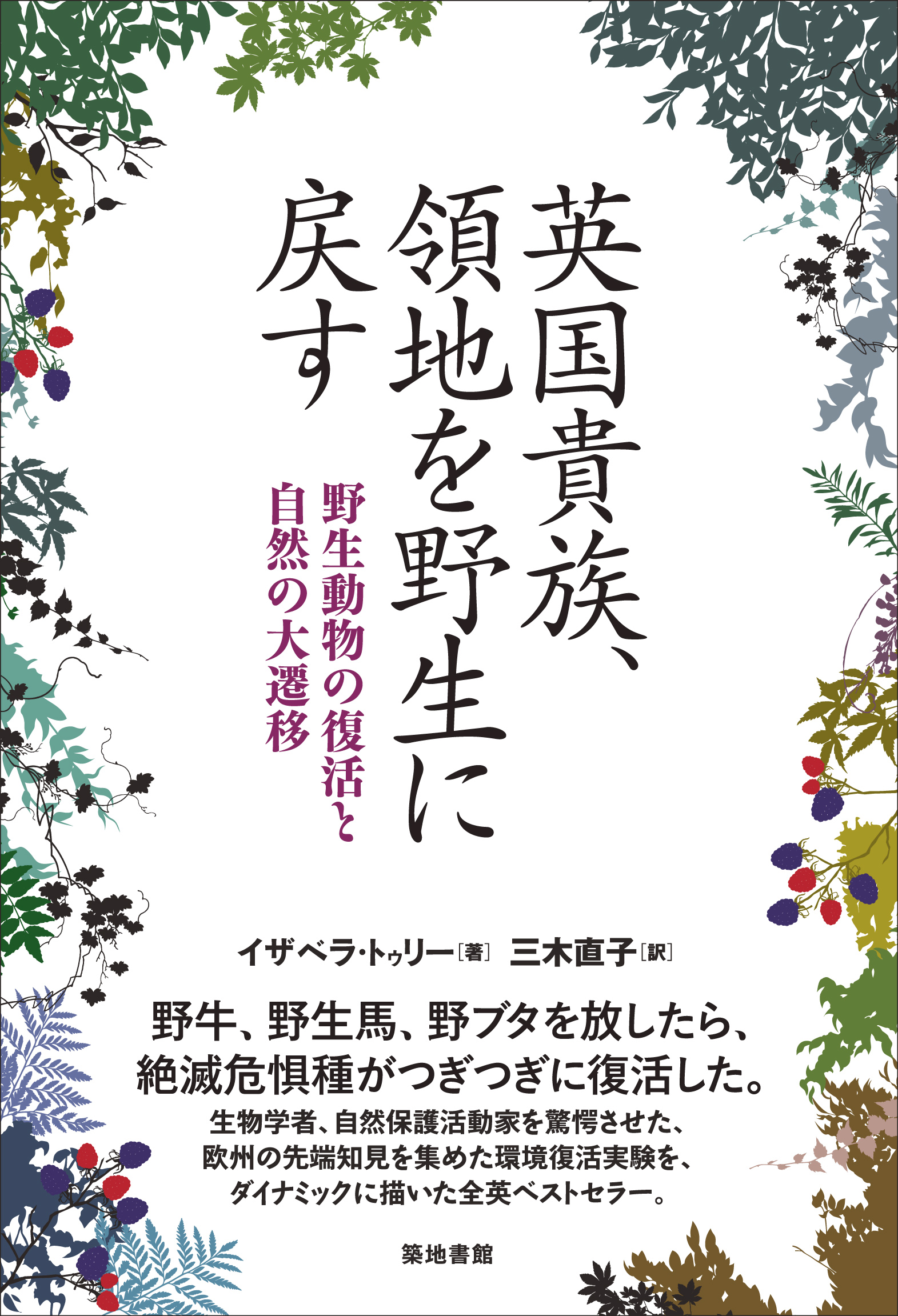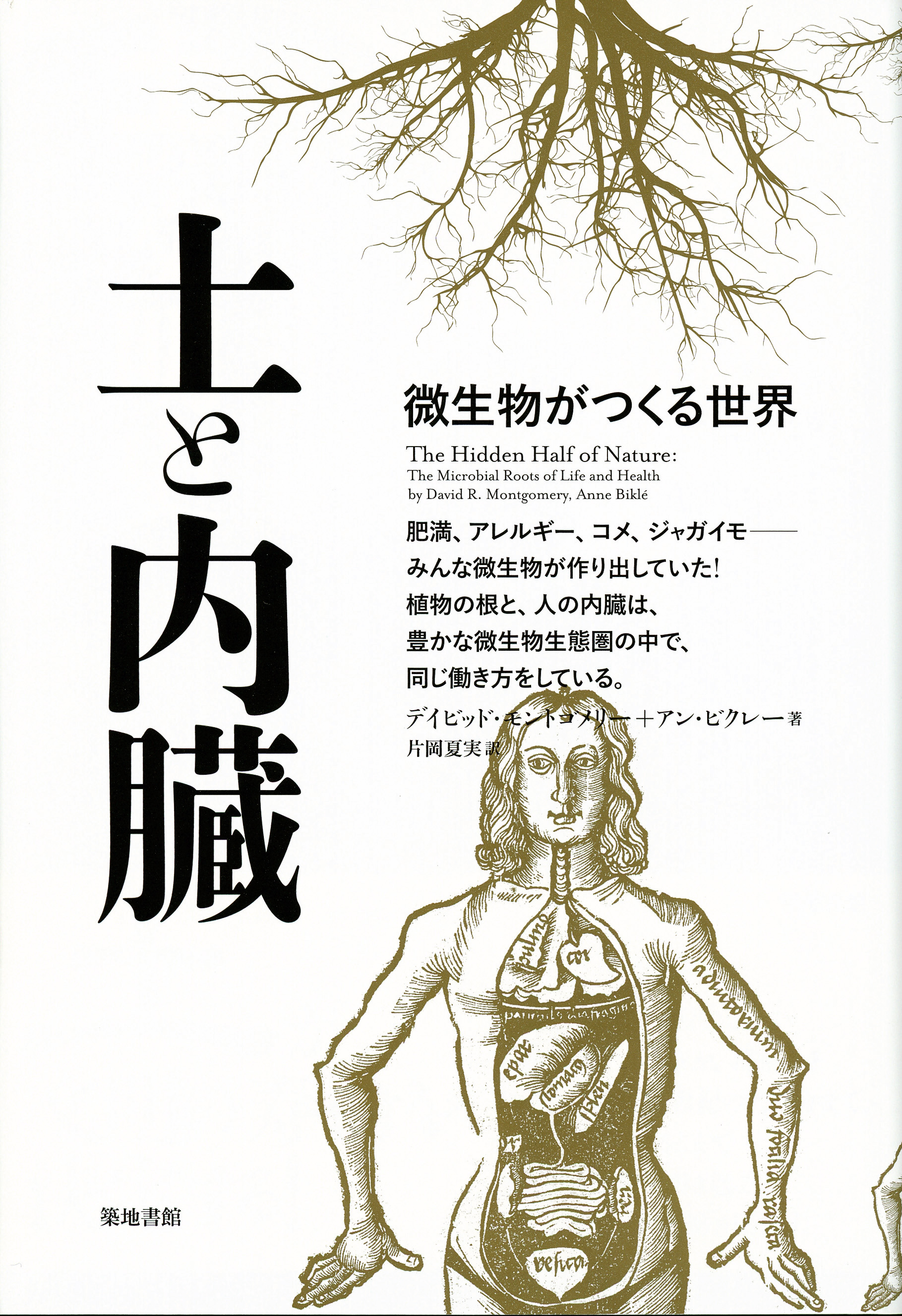食卓を変えた植物学者 世界くだものハンティングの旅

| ダニエル・ストーン[著]三木直子[訳] 2,900円+税 四六判 384頁+カラー口絵8頁 2021年4月刊行 ISBN978-4-8067-1620-4 大豆、アボカド、マンゴー、レモンから日本の桜まで。 世界の農産物・食卓を変えたフルーツハンター伝。 第一次世界大戦前のアメリカで、自国の農業と食文化発展のために、 新たな農作物を求めて世界中を旅してまわった男、植物学者デヴィッド・フェアチャイルド。 アメリカに初めてアボカドを持ち込んだのは彼だし、マンゴーや種なしブドウ、ダイズなど、 後にアメリカで大規模に栽培されるようになった植物が根付いたのも彼のおかげである。 スパイと間違われたり、カニバリズムの残る地を訪れたり、苦労と驚きに満ちた旅を繰り広げ、 エキゾチックな果物を世界に紹介した男の一代記。 ――――― [原著書評より抜粋] 著者は、植物学、食の歴史、そして紀行文をバランス良く織り込んだ気持ち良い語り口で、 登場人物を生き生きと描き、テンポの良い冒険物語を繰り広げる。 ――ウォール・ストリート・ジャーナル 鮮やかな筆致と豊かな表現力を持った著者の文章が、添えられた写真とともに、 アメリカの植物に多様性をもたらすことに重要な貢献をした人物の生涯を蘇らせる。 これは、食の世界のパイオニアの、学問的かつ娯楽性に富んだ一代記である。 ――カーカス・レビュー 情報に富み、同時に娯楽性に富んだ本書には、美食家も科学者もともに満足することだろう。 ――パブリッシャーズ・ウィークリー この魅惑的な一冊は、アメリカ史と食文化、旅行記、 そして農業に関心のある人々のすべてを惹き付けるだろう。 ――ライブラリー・ジャーナル(星付きレビュー) |
ダニエル・ストーン(Daniel Stone)
ニューズウィーク誌の元ホワイトハウス特派員。
科学雑誌サイエンティフィック・アメリカンやワシントン・ポスト紙などで執筆、CBS テレビのドキュメンタリー番組にも出演している。
ボタニカルライター。
三木直子(みき・なおこ)
東京生まれ。国際基督教大学教養学部語学科卒業。
外資系広告代理店のテレビコマーシャル・プロデューサーを経て、1997 年に独立。
訳書に『CBD のすべて:健康とウェルビーイングのための医療大麻ガイド』(晶文社)、
『アクティブ・ホープ』(春秋社)、『コケの自然誌』『錆と人間』『植物と叡智の守り人』
『英国貴族、領地を野生に戻す』(ともに築地書館)、他多数。
プロローグ
第1部 旅の始まり
1章 偶然の出会い
スパイ容疑で捕まる
アメリカの食文化を豊かに
食への意識の高まり
ウォレスとの出会い
農務省研究員になる
運命の人、バーバー・ラスロップ
2章 1000ドルの投資
植物の乏しい北米大陸
種を配る政治家たち
スミソニアン博物館からナポリへ
ラスロップとの再会
3章 スエズ運河の東で
シトロンへの貢献
遠のくジャワ行き
スエズ運河を渡る
シロアリ研究に没頭
ラスロップという男
2人旅の始まり
4章 客と愛弟子
忍耐の日々
旅の目的
新しい作物を探せ
耕作地とビジネスの拡大
植物採取から輸送まで
5章 太平洋の憂鬱
ハワイへ進出
オーストラリアからフィジーへ
サトウキビとハワイ王国の崩壊
遠征失敗
第2部 世界を股にかける
6章 大義はひとつ、国も一つ
旧友ウォルター・スウィングルとの再会
新興国アメリカの台頭
米西戦争と熱帯のフルーツ
農業拡大時代の新規プログラム
「種子と植物導入事業部」設立
フロリダの将来性
ラスロップ、再び
7章 越境
アメリカ横断、そして南米へ
カリブ海の小さな島々
農家の不満
南米大陸初上陸と黄熱病
8章 アボカドの普及に貢献
早すぎたキヌア
コカインの発見
アメリカに最適なアボカド
命がけの旅
9章 ベニスの僧侶のブドウ
農務省VSラスロップ
種無しブドウを入手
綿生産大国エジプト
綿市場を席巻するアメリカ
10章 アジアへ進出
マレー諸島と白人
フィリピン支配とマンゴー
中国人のエネルギーに圧倒される
腸チフスにかかる
第3部 新たな出会い
11章 レモン、ホップ、新しい夜明け
最高のホップを入手せよ
覚醒するアメリカ
ケールと種無しレモン
育てられるものと好まれるもの
12章 チグリス川の岸辺で
植物調査員と不動産デベロッパー
再びハワイへ
インドへ向かう
日本の桜に惹かれて
13章 ベルの一大計画
社交界デビュー
アフリカでの収穫
グラハム・ベルとの親交
14章 千々に乱れる心
運命の女性、マリアン
板挟み
結婚へ
15章 サクランボのならない桜の木
宿敵あらわる
ワシントンDCに桜を
桜と外交
燃やされた桜の木
東京市長のリベンジ
第4部 行き詰まる採集事業
16章 羽をもがれて
後継者、フランク・マイヤー
マイヤーの中国探査
新技術の誕生に立ち会う
最初のダイズ
マイヤー・レモンの誕生
17章 マイヤーの躍進
フェアチャイルドVSマーラット
外来植物をめぐる争い
植物検疫法の制定
18章 大きな足枷
止まらないマイヤー
後継者不足
激務が続く
19章 戦渦に巻き込まれる
第一次世界大戦勃発
マイヤーの孤独
すれ違うフェアチャイルドとマイヤー
戦時下の2人
最悪の事態
20章 植物園と戦争
プログラムから手を引く
ラスロップの死
最後の探検旅行
エピローグ
訳者あとがき
参考文献
索引
アメリカ人として恥ずかしいと思うことの一つは、アメリカがどれほど肥大した自尊心と権力を持っていようとも、「アメリカの」という形容詞が使われるようになってから大して時間が経っていないということを、しょっちゅう思い知らされることである。数年前、僕は気づいたのだ――移民がアメリカにやってきたのと同じように、僕たちの食べ物もまた海外からやってきたのだということに。
ある朝、机に向かって『ナショナル・ジオグラフィック』誌に寄稿する記事のためのリサーチをしていたとき、一般的な農作物が最初に人間の手で耕作されたのがどこだったかを示す地図をたまたま見つけた。有名なフロリダ州のオレンジが最初に栽培されたのは中国。アメリカのどこのスーパーマーケットにもあるバナナはもともとはパプアニューギニアのものだ。ワシントン州が昔から受け継いできたものだと主張するリンゴはカザフスタンから来たものだし、ナパバレーのブドウが初めて育ったのはコーカサス地方である。これらがいったいいつ「アメリカの」作物になったのかを問うのは、イギリスから来た人たちがいつアメリカ人になったのかと問うこととちょっと似ている。一言で言えば、それは複雑なのだ。
だが、どんどん深く掘り下げていくにつれて、突如それが鮮明になる瞬間があるらしいことがわかった。蒸気船が突如として港に姿を現すように、新しい食べ物がアメリカの海岸に到着した歴史上の一点である。19世紀後半――「金ピカ時代」と呼ばれる、アメリカ資本主義が成長した旅行の黄金期――は、アメリカが一気に成長した時代だった。世界各国への航海という道が開かれ、そのおかげで、デヴィッド・フェアチャイルドという若き研究者が、新しい食物や植物を求めて世界を歩き回り、それらを自国に持ち帰って市場を活気づかせたのである。フェアチャイルドは世界を一変させる革新技術の誕生を目撃し、科学者や上流階級の人間がもてはやされたこの時代、血筋ではなくその飽くなき好奇心によって支配階級の仲間入りを果たした。
今思えば、僕がこの物語に取り憑かれたのは当然のことだった。生まれてこのかた僕は果物に夢中で、それが熱帯のものであればあるほど良かった。子どもの頃両親が、僕と妹をハワイに連れていったことがある――「いろんな経験をしないと」というわけだ。僕は丸々2つパイナップルを平らげ、おかげでマウナロア山よりもカッカと燃えるような腹痛を起こした。家ではときどき母が、マンゴーを縦にスライスしてくれた。僕がスライスを食べている間に母は種の周りを少しずつ削っていく。デンタルフロスの有り難みを教えてくれたのは歯医者ではなくてマンゴーだった。
大学在学中は農園で働き、暑さの中、果樹園の木々の間を歩いてモモの等級付けをした。目的は、次のシーズンに優先的に栽培する優れた品種を見つけることだった。果物に優生学を適用したわけだ。だが作業に集中するのは難しかった。仕事の時間が終わる頃には、何十個も食べたモモの果汁でシャツはぐしょぐしょ、大抵はその後に腹が痛くなった。政治記者としてワシントンDCに移る前に、友人が彼の農場に就職しないかと言ってくれた。果実を収穫し、北カリフォルニアの、一種のファーマーズ・マーケット─―「変種」とか「テロワール」みたいな言葉を使う人たちが集まるところ─―で売る仕事だった。僕は夢を追うためにその申し出を辞退したが、その後何年も、連邦議会聴聞会に出席しながら、ピックアップトラックの窓を開け放って人気のない農道を走るもう一人の自分を想像した。
数年後、フェアチャイルドのことを聞いて僕がまず最初に思ったのは、こいつは果物を仕事にしたんだな、ということだった。それもおなじみの作物だけではなく、それまで誰も食べたことがなかったようなものを。友人たちに、アメリカに初めて公式にアボカドを持ち込んだのはフェアチャイルドだという話をすると、みんな彼を聖人候補に挙げたがった。僕は、フェアチャイルドが持ち込んだ人気の作物─―デーツ、マンゴー、ピスタチオ、エジプト綿、ワサビ、桜の花─―の話をしてみんなが驚くのを見るのが楽しくなっていった。必ずと言っていいほど誰かが、「へえ、誰かがそれをアメリカに持ってきたなんて、考えたこともなかったな」というようなことを言った。僕たちは、地面から生えてくる食べ物を、人間が生まれる前からもともとその環境にあったものであり、生の地球そのものとのつながりだと思いがちだ。だが、僕たちが食べているものは、人の手で選ばれ、管理されたものであるという意味で美術館の展示と変わらないのだ。フェアチャイルドは、真っ白なキャンバスに新しい色や質感を加えるチャンスを見出したのである。
フェアチャイルドの生涯は、20世紀初めに世界との関係を花開かせたアメリカの物語だ。彼は50か国以上、そのほとんどを船で訪れた。飛行機や自動車が地球を狭くする前の話だ。彼が植物採集に情熱と関心を注いだのは、僕たちが今のように食べ物に執着したり、食べ物の栽培、輸送、消費が経済、生物、環境に影響を与えるようになる以前の出来事である。フェアチャイルドはまさに、旅をすることへの尽きせぬ欲求を絵に描いたような人物だった。「そこには何があるのか?」という問いに答えを見つけることが、彼のライフワークだったのだ。
と同時に彼の物語は、世界に対するアメリカの興奮が、海の向こうの未知のものに対する嫌悪へと変化するなか、失望と波乱に満ちたものだった。フェアチャイルドの運命はアメリカのそれと一つであり、第一次世界大戦勃発でアメリカの注意が散漫になると、フェアチャイルドの才気は、恐怖に縮こまっている国家による厳しい批判の的となった。
彼は多弁な男であり、そしてそのすべてを書き記した。僕は彼が書いたラブレターを、下書きの原稿を、封筒やナプキンの裏に書き留めた思索の断片を読んだ。彼がアレクサンダー・グラハム・ベルやセオドア・ルーズベルトやジョージ・ワシントン・カーヴァー[訳注:アメリカの植物学者]に会ったときの回想も読んだ。そして、自分のことが本になり、功績を称えられるのを、彼はものすごく嫌がるだろうと感じた─―もっとも、彼の逸話の多くがそうであるように、彼の生涯は、彼以外の人たちがした仕事と、他人のお金と承認がなければ実現しなかったわけだが。
フェアチャイルドの物語には、今では存在し得ない男とその時代を目にする哀しさが漂う。文化と科学と通信が互いにつながり合い、一日に何千キロも移動が可能な世界で、人がこう問うのは当然だ─―いったいこの世には、未開の地は残されているのだろうか? フェアチャイルドならなんと答えるだろうか、と僕はさんざん考えた。彼は自分の死を、それ以前の時代の大いなる探索の終点と考えただろうか?
その後、数年前の夏のある日、僕はフロリダの、フェアチャイルドの孫にあたる81歳のヘレン・パンコーストの家にいた。ヘレンはかつて、祖父とともにマイアミからノバスコシアまでの長いドライブに出かけたものだった。そしてその間フェアチャイルドは彼女に数々の質問を浴びせ、彼女が好奇心を持つことを奨励したのだ。今ヘレンは、生まれ育った家からほんの数ブロックのところに住み、彼女の家の庭には、フェアチャイルドがインドネシアで夢中になったヤシの木が植わっている。僕はヘレンに、ずっと気になっていたことを尋ねてみた─―答えに溢れたこの世界にフェアチャイルドが生きていたら、それでもまだ彼は新しい質問を見つけるだろうか? ヘレンは僕の腕を掴むと僕の目を正面から見つめた。
「祖父は言ったものよ、『知っていることで満足してはいけないよ、まだこれから知ることのできることがどれほどあるかに満足しなさい』と」
自分が今、当たり前のようにスーパーマーケットで目にし、購入し、食卓に並べている食べ物が、実はあるときにはっきりした意図をもった誰かの手で我が国に持ち込まれ、栽培されるようになった、あるいは輸入されるようになったものであるという可能性を、多くの人は考えたこともないかもしれない。本書はアメリカの物語だが、今や手に入れられない食材はないと言ってもいいアメリカは、今からほんの百数十年前には、ヨーロッパからの移民が植民地に持ち込んだわずかな食材しかない、食の貧しい国だった。そこに、いわば「国策」として海外から多種多様な「食べられる植物」が導入されることになる。そしてその中心的な役割を果たしたのが、本書の主役、デヴィッド・フェアチャイルドである。
19世紀の終わりから20世紀前半にかけてアメリカに初めて持ち込まれた食物について、その植物学的・園芸学的特徴やアメリカでの本格的な栽培に至る歴史的な経緯を正確かつ詳細に記した学術書をお探しの方には、本書は少々物足りないかもしれない。
むしろ本書は、アメリカがその歴史上最も華々しい発展を遂げた魔法のような時代に生きた、異様なまでに幸運な一人の男の生涯を綴った伝記であり、冒険談であり、紀行文であると言う方が正しい。建国100年、シカゴ万博、蒸気船による遠洋航路の発達、電話、飛行機の発明……。「金ぴか時代」と呼ばれる、まさに絢爛とした時代背景に、個性の強い登場人物たちが歴史に残る冒険を繰り広げる本書は、映画化したらさぞや面白いものになるに違いないと思う。
主役のデヴィッド・フェアチャイルドは、題名の通り植物学者であり、1890年代から1920年代にかけて、それまでアメリカになかった数百種類の植物を海外から持ち込むという功績を残した「プラントハンター」の草分け的存在である。持ち帰った珍しい植物で植物園をつくりました、という話ではない。組織的に海外から植物を導入し、農家に提供して農業という産業を支援する、というアイデアを実現させ、米農務省内に「種子と植物導入事業部」を創設し、彼が海外から送った種子が、挿し穂が、アメリカの土で芽を出し、根を下ろし、大々的に栽培されて他国と競合できる産業を生み出し、アメリカの農業を根幹から創造し、まさにアメリカ人の食卓に大きな変革をもたらしたのはフェアチャイルドだと言っても過言ではないのである。
もう一人の主役バーバー・ラスロップは、莫大な父親の遺産を受け継ぎ、贅沢三昧の海外旅行に日々を費やす有閑階級で、デヴィッド・フェアチャイルドより22歳年上の伊達男である。怖いものを知らない傍若無人の典型のような、大きく膨らんだ自我ではちきれんばかりの、だが時折意外な優しさと無防備さを見せる洗練されたラスロップと、カンザスの田舎出身で、知的好奇心に溢れてはいるが世間知らずで自信もなければ金もない不器用なフェアチャイルド。何の接点も共通点もないように見える2人は、船上で偶然に出会い、やがて世界を股にかける旅をともにするようになる。新しい植物・食物をアメリカに紹介するというフェアチャイルドの野望にはラスロップの金が必要だったし、贅沢ではあるが目的のない旅に満足できなくなっていたラスロップには、フェアチャイルドの計画を助けることで自らの旅を意味のあるものにすることが必要だった。
初めのうちは感情的にすれ違い、衝突もする2人だが、旅を続け、苦楽を共にする中で、互いが互いの持つものを必要としていたというだけではない、生涯続く真の友愛が育まれていく。世界五大陸のすべてを豪華客船で巡りながら二人が採集してアメリカに送った農作物は、アボカド、マンゴー、デーツ、タバコ、綿花、米、レモンをはじめ数百種に及び、現在のアメリカの農業と人々の食生活に多大な影響を与えている。またフェアチャイルドは、有名なワシントンDCの桜を日本から輸入するのにも大きな役割を果たしている。
この2人の旅と植物探しの背景に彩りを添える脇役もまことに豪華である。フェアチャイルドが少年の頃に、生涯消えることのない熱帯の島への憧憬を彼の心に植え付けた、進化論の実証をダーウィンと競い合ったアルフレッド・ラッセル・ウォレス。電話を発明したアレクサンダー・グラハム・ベルとその娘マリアン。動力飛行機を発明したライト兄弟、その他、フェアチャイルドの脇を、金ぴか時代のアメリカの富裕層・知的エリートたちが見事に固めている。
さらに、後半になって登場する重要人物が、フェアチャイルドの幼なじみであったチャールズ・マーラットという昆虫学者だ。彼は新しい植物とともにアメリカに植物の病原菌や害虫が入ってくる危険性を訴え、フェアチャイルドと激しい闘いを繰り広げる。昆虫学者としての懸念に、フェアチャイルドの幸運さに対する私怨が重なって、フェアチャイルドへの彼の攻撃は熾烈を極める。アメリカの生活をより豊かなものにするために新しいものを貪欲に迎え入れようとするフェアチャイルドの楽観性と、未知のもの、知らないものを恐れ、嫌悪し、遠ざけようとするマーラットの悲観的な考え方の対立。結局、2人の争いは、マーラットが検疫法を制定させることに成功して決着するのだが、ハリウッド映画ならば当然、観客が応援し、軍配を上げるのはフェアチャイルドのはずだ。
だが、私が本書を翻訳した2020年は、ご存知の通りCOVID-19が世界的に大流行し、人も物流も否応なく足止めを食らった1年だった。中国のどこかで新しいコロナウイルスが見つかったらしい、という情報が流れてきた、と思ったらあれよあれよという間にウイルスは世界中に広がり、蔓延し、気がついたら世界を膠着状態に陥れていた。ウイルスの侵入を防ぐために国境は閉鎖され、海外旅行どころか国内の移動すらままならなくなった。
フェアチャイルドとラスロップが乗っていた船の上でペストを発症した乗客が「事故で」死亡し、ぞんざいに水葬されて、船は検疫のための隔離を免れた、というエピソードが登場する。それが遠い昔の、自分とはまるで関係のない他人事とは思えないシュールな状況がリアルタイムに進行する中で、このフェアチャイルドとマーラットの検疫法の制定をめぐる熾烈な闘いを訳していた私が、ともすればマーラットの肩を持ちたくなったということは否めない。本書の著者がフェアチャイルドの味方であり、ほぼ手放しで彼の功績を称えているのは明らかだが、本書が書かれたのが2020年であっても著者の心情は同じだっただろうか。
外来種の侵攻によって在来の動物や植物が絶滅に追いやられる、というのは事実としてこれまで繰り返されてきたことだし、フェアチャイルドの事業がいかに計画的かつプロフェッショナルに行われたことであろうとも、望まれざる客を招いてしまう危険があったことは事実だろう。また今回のコロナ騒動で、「病原菌の侵入を水際で食い止める」ことの重要性と困難さは、世界中の人々が否応なく思い知らされたことでもある。だから、マーラットをゼノフォビアの権化であるかのように言う気には、私にはなれなかったのだ。
私がついマーラットを応援したくなった理由はそれだけではない。
子どもの頃からの夢であったマレー諸島を初め、世界中の国々に人の金で贅沢三昧しながら訪れ、大好きな仕事をして社会的にも認められ、愛する人(それもかのアレクサンダー・グラハム・ベルの娘である)に出会い、結ばれ、生涯裕福な暮らしを満喫して、自分が愛した熱帯の木の下で息を引き取る、という、およそこれ以上に恵まれた人生はなかろうと思われるフェアチャイルドの、一種呆れるほどの純粋さとまっすぐさには、どこかまた一抹の物足りなさを感じるのだ。
たとえば、フェアチャイルドが結婚して植物探しの旅に出ることができなくなった後、フェアチャイルドの後を継いでその任務を背負ったフランク・マイヤーは、フェアチャイルドのように大金持ちのパトロンが付いているわけでもなく、過酷かつ危険な条件下での孤独な旅を続け、やがて精神を蝕まれていく。彼がフェアチャイルドに救いを求め、振り絞るようにして書き送った言葉に対してフェアチャイルドは為すすべを知らず、マイヤーに精神的に一番近いところにいたはずの彼は、結局マイヤーを救うことができなかった。マイヤーの死が自死であったことを最後まで理解しなかった、あるいは信じようとしなかった、ということを知れば、彼にはマイヤーの苦しみを理解するのに必要な共感力も想像力もなかったのではないのかと思わざるを得ないのである。
フェアチャイルドが優れた植物学者であり、猛烈な働き者であったことは確かだ。飛行機も冷蔵輸送技術もなかった時代に、西欧人がほとんど訪れたこともない、しばしば豊かな暮らしがあった地から、アメリカで育つであろう植物を見分けて送り届ける、というのがどれほど大変なことかは想像がつく。そして、高齢になってからも好奇心を失うことなく常に新しい知識を求め、純真な探究心を生涯失わなかったというのは素晴らしいことだ。けれども同時に彼が、英国から独立し、意気揚々と国力を増していく得意満面のアメリカの、とりわけ東海岸のエリート層の手本のような存在であるのもまた事実である。もちろん、自分のしていることが、後年アメリカを中心に進むグローバル化(とその弊害)の一助となっていくことを、当時の彼に自覚できようはずはない。とは言え、アメリカの植民地政策を「悲しいこと」と言う彼の言葉は真摯なものであったかもしれないが、海外の植物を導入してアメリカで産業として育て、競争力をつけて世界市場を制覇する、というのは、植民地政策と同様の帝国主義ではないか。
ちなみに、彼が20代になったばかりの1890年、アメリカの西部開拓は、米第七騎兵隊によるウンデッド・ニーでのネイティブアメリカンの人々の虐殺をもって終焉したと言われている。彼は、そのことをどう受け止めたのだろう、とふと考える。
仮にフェアチャイルドがこうやって植物導入をしなかったとしても、交通手段の発達とともに地球が小さくなり、食物のグローバル化が進むことは歴史の必定だったことだろう。人間は旅先で美味しいものを食べればそれを持ち帰りたくなるのが自然というものだ。そして、私を含め、そうやって豊かになった食生活の恩恵を受けていない人など、少なくとも先進諸国にはいないだろう。今、青果売り場には、もともとは外国産だけれども日本で栽培されるようになったもの、あるいは海外から空輸されるものを含め、世界中から届いた食物が並んでいる。フェアチャイルドやマイヤーが世界各地からアメリカに運んだものの遺伝子を引き継ぐ青果や観葉植物は、おそらく私たちの身の回りにいくらでもある。
地球が気候温暖化の脅威に晒される今、フェアチャイルドの時代には誰一人考えたこともなかったであろう「カーボン・フットプリント」という言葉が生まれ、食の地産地消の見直しを訴える声がある。一方、見直すべきは食物の輸送によるカーボン・フットプリントとあわせて、食物をどのように育てるかであるとする主張もあり、この議論には未だ結論が出ていないようだ。食のグローバル化はもはや止めようがないだろうが、本書が「ウィズ・コロナ」の時代の始まりとなる2021年に刊行されるという一つの偶然も、この問題について考えるきっかけを与えてくれたような気がしている。
そんな問題提起はさておき、蒸気船で巡る世界の国々の描写は、旅心をくすぐるノスタルジックかつロマンチックな魅力が満載で楽しめる。途中からは、ラスロップ役には今よりもう少し若い頃のダニエル・デイ=ルイスあたりが適役だなどと考えながら、頭の中に映像を思い描きつつ訳した。一方、優れた植物学者として大きな功績を残しながら純粋さを失わず、永遠の少年を心に宿すフェアチャイルド役の俳優は、残念ながらまだ候補が見つかっていない。