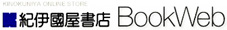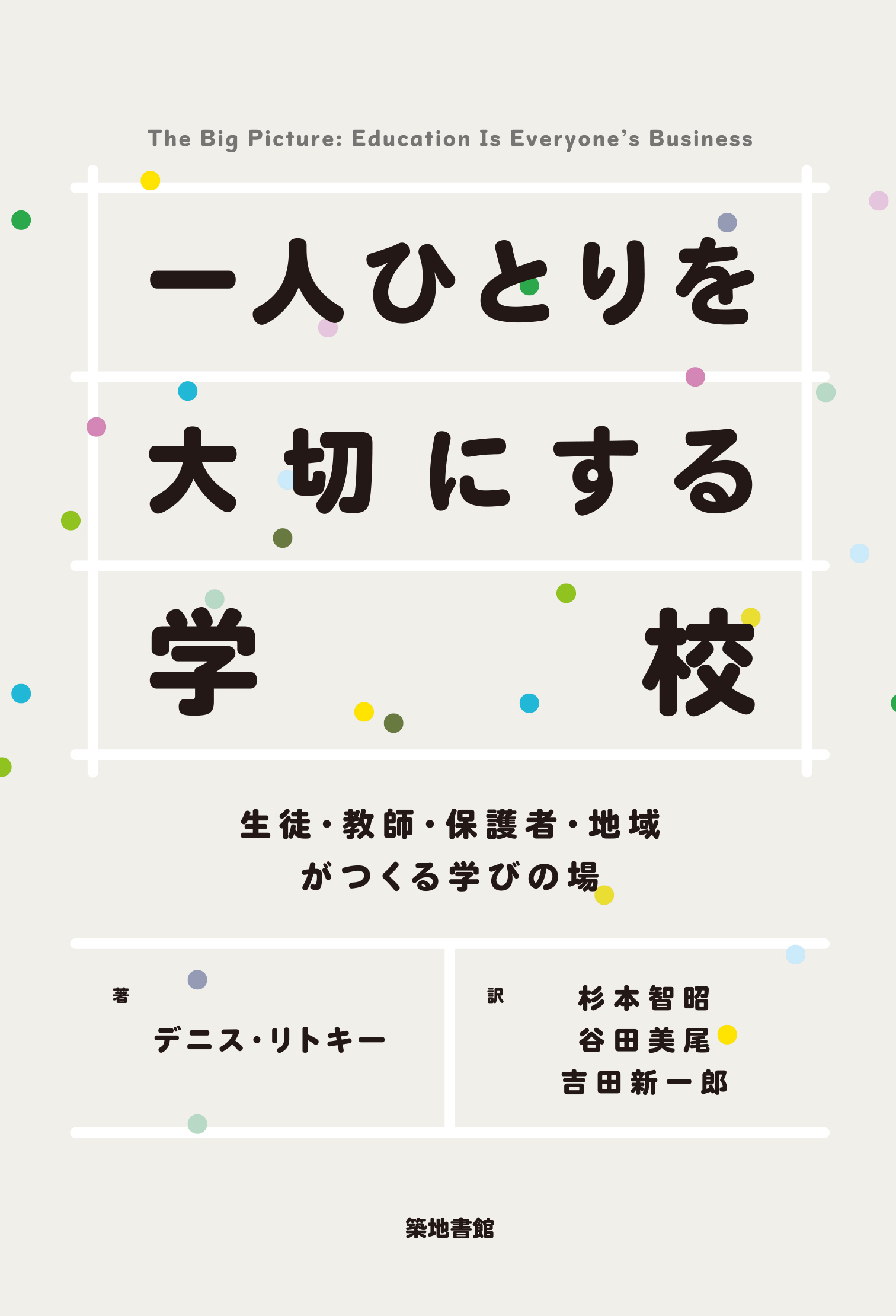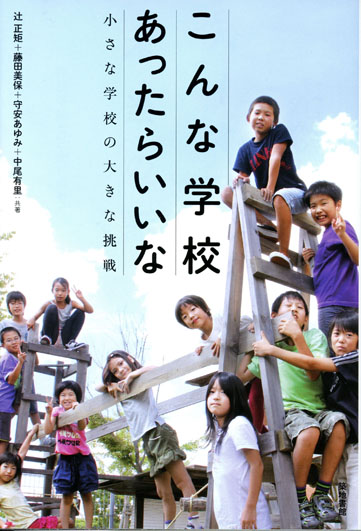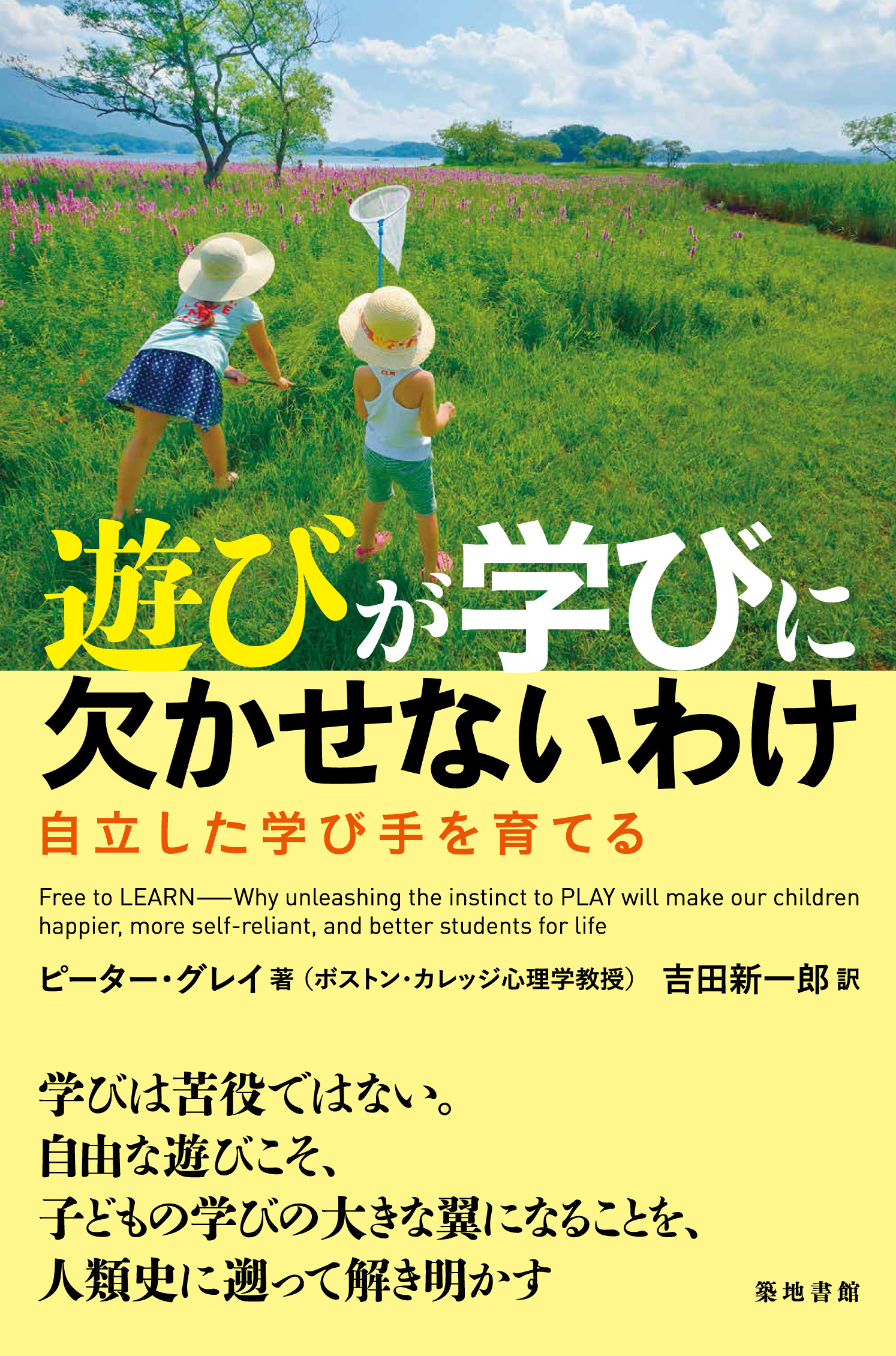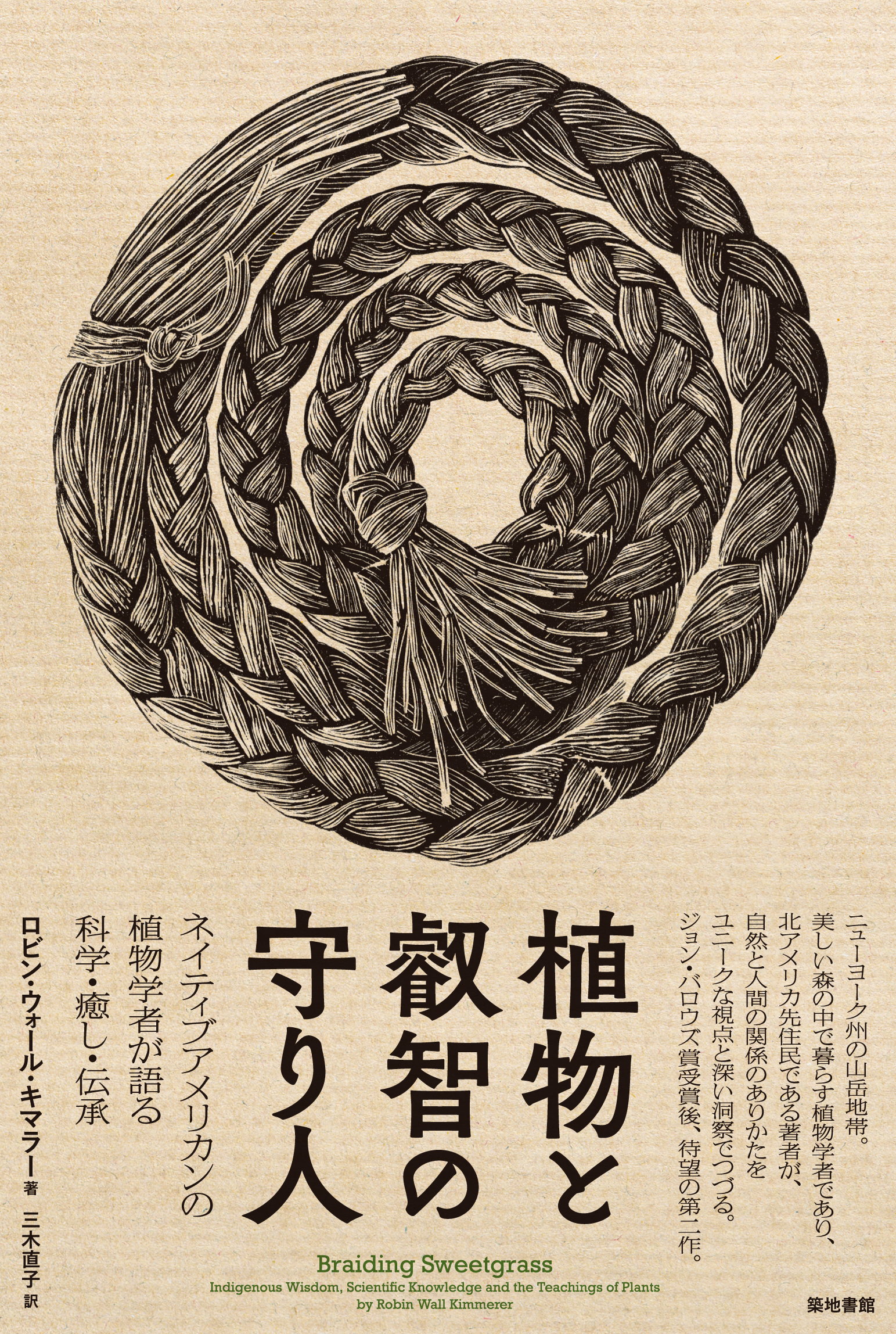�����Ȋw�Z�̎��オ����Ă��� �X���[���X�N�[���\�z�E�����ЂƂ̊w�Z�̂����
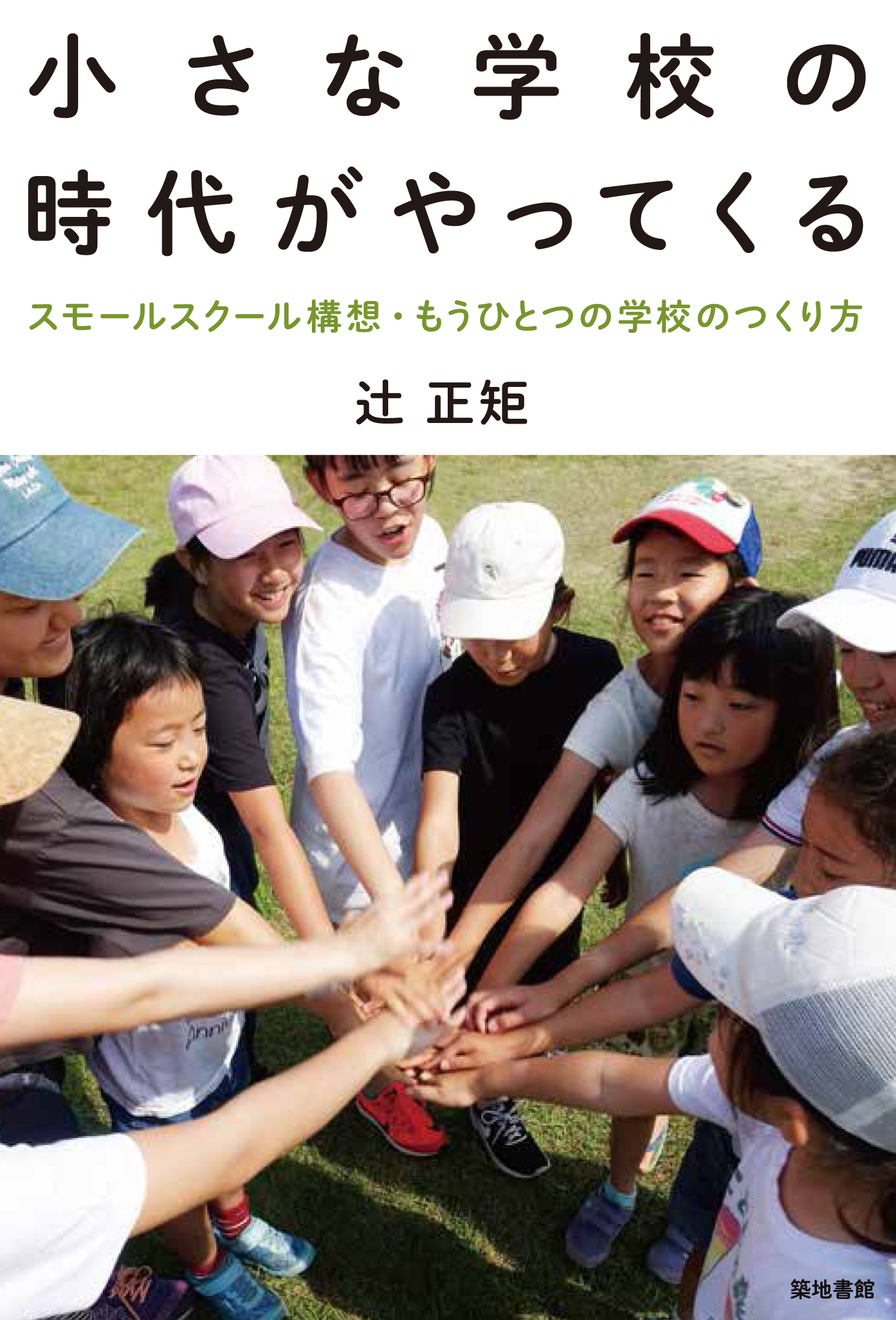
| �Ґ���m���n 1,600�~+�Ł@�l�Z�������@192�Ł@2021�N2�����s�@ISBN978-4-8067-1613-6 �u�w�т̈Ӗ��v�����ς��錻�݁A �w�K�w���v�̂ɑ��������I�ȋ��炩�痣��A �w�т̐[�����ς��ٔN��W�c�w�K�������ꂽ�A ���k�̎�̓I�E�Θb�I�Ȋw�т��ł���A ����I�ȏ����Ȋw�Z���A���X�Əo���Ă���B ���E�̐�i�I�Ȏ��R�w�Z����ނ��A ��������ŃI���^�i�e�B�u�X�N�[���̉^�c�Ɍg��钘�҂��A ���k��200�l�ȉ��̏����Ȋw�Z���������邽�߂� ���@�A���x��肩�狳��\�z�܂łՂɉ������ �u�X���[���X�N�[���v�B [���E�̂��Ƃ�] �|�X�g�E�R���i����̋���͂ǂ�ȋ���ɂȂ�̂��낤�H �u���ɖ߂��Ȃ��v�Ƒ����̐l�͌�������ǁA �u�ǂ̂悤�ɁH�v�Ɩ����ƁA�r���ɕ��Ă��܂��B �������{���ɂ́A�V���Ȏ���ɋ��߂��鋳��݂̍���ƕ��������`����Ă���B ���l�X�R�������[�h���ASDGs���������邽�߂̋���ł����� ESD�̓����ł���u�ϗe�v�u�����v�u���V�v�̂��ׂĂ������ɂ���B �\�\�\�i�c���V�i���S���q��w�����j 8�̓ǎґw 1 �q��Ē��̐e 2 ���w�Z�E���w�Z�E���Z�̐搶 3 ���t�ɂȂ낤�Ǝv���Ă���w�� 4 ���������Ŋw�Z��n�낤�Ǝv���Ă���l 5 �ߑa���⏭�q���Ŋw�Z���ɒ��ʂ��Ă���w�Z�̕ی�҂�Ǘ��� 6 ��w���̋���Ɍg��鋳���A����w������ 7 ���ȏȁA�����̂̋���s���Ɍg���l 8 ����Ɋւ��闧�@�Ɍg��鐭���� |