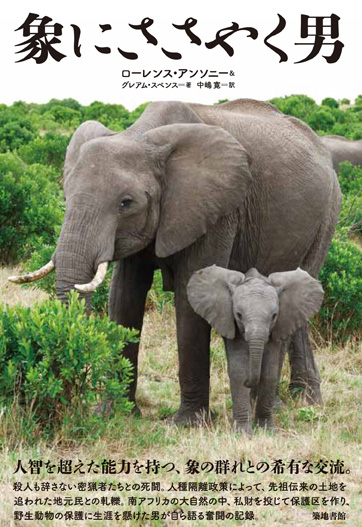狼が語る ネバー・クライ・ウルフ

| ファーリー・モウェット[著]小林正佳[訳] 2,000円+税 四六判上製 240頁 2014年1月刊行 ISBN978-4-8067-1471-2 カナダの国民的作家が、北極圏で狼の家族と過ごした体験を綴ったベストセラー 政府の仕事で、カリブーを殺す害獣・狼の調査に出かけた生物学者が、現地で眼にしたものは……。 狼たちが見せる社会性、狩り、家族愛、カリブーやほかの動物たちとの関係。 極北の大自然の中で繰り広げられる狼の家族の暮らしを、情感豊かに描く。 |
ファーリー・モウェット(Farley Mowat)
1921年、カナダ、オンタリオ州生まれ。
幼い頃からナチュラリストとして育ち、動物や自然とのふれあい、北極圏への旅などの体験から50冊以上にのぼるノンフィクション、小説、児童文学を生み出してきた。
カナダ北極圏に暮らす人々の過酷な生活を描いたもの、マリタイムと呼ばれるカナダ東海岸と北大西洋、なかでも8年間を過ごしたニューファンドランド島を舞台にしたもの、イタリア戦線での体験を描いたもの、ヴァイキングをはじめ航海者たちがコロンブス以前の北アメリカにしるした足跡をたどったもの、さらに伝記や自伝など、作品は多岐にわたる。
その作品には一貫して、人間と動物を問わず、過酷な状況の下で生き残りを懸けて苦闘する者たちへの深い共感と、彼らに手を差し伸べようとする熱い思いやりがあふれている。しかも、痛烈なまでの皮肉やユーモアとともに。
活発な環境保護運動家としても知られ、現在なお、オンタリオ州ポート・ホープとノバスコシア州ケープ・ブレトンで旺盛な執筆活動を続けている。
小林正佳(こばやし・まさよし)
1946年、北海道札幌市生まれ。
国際基督教大学教養学部、東京大学大学院博士課程(宗教学)を修了。
1970年以来日本民俗舞踊研究会に所属して須藤武子師に舞踊を師事。
1978年福井県織田町(現越前町)の五島哲氏に陶芸を師事し、1981年織田町上戸に開窯。
1988年から現在まで天理大学に奉職。その間、1996〜1998年トロント大学訪問教授、セント・メリーズ大学訪問研究員としてカナダに滞在。
現在は、天理大学総合教育研究センター特別嘱託教授。
民俗舞踊を鏡に、宗教体験と結ぶ舞踊体験、踊る身体のあり方を探ってきた。民俗と創造、自然を見つめる眼ざしといったテーマにも関心がある。
著書に『踊りと身体の回路』『舞踊論の視角』(共に青弓社)、訳書にヒューストン著『北極で暮らした日々』、ロックウェル著『クマとアメリカ・インディアンの暮らし』(共にどうぶつ社)など。
1 オオカミ調査計画
2 オオカミジュース
3 着陸、おめでとう
4 オオカミはどこ?
5 接触
6 巣穴
7 観察される観察者
8 土地の囲いこみ
9 やさしいアルバートおじさん
10 野ネズミとオオカミ
11 野ネズミのクリーム煮
12 オオカミの霊
13 オオカミたちの会話
14 子どもたちの季節
15 恋に落ちたアルバートおじさん
16 朝の肉の配達
17 隠れ谷からの訪問者
18 家族生活
19 裸での追跡
20 カリブーのからだの中の虫
21 狩りの学校
22 糞便学
23 オオカミを殺す
24 失われた世界
何が変わっただろう
訳者あとがき
この本は、Farley Mowat 著『Never Cry Wolf』(1963)の全訳で、底本には2001年発行 Back Bay Books 版を用いた。古い版の各章に付された標題と最後の短いエピローグが、新しい版にはない。本書では、ほぼ旧版に倣い各章の内容に即した見出しを付すことにした。
最初に、書名と著者名について記しておきたい。原題「Never Cry Wolf」の「クライ・ウルフ」は、「ありもしない危険を言い立てること」を意味する慣用句で、いうまでもなく、イソップ童話に登場する「オオカミだあ!」と叫んではみんなをびっくりさせていた羊飼いの少年の話に由来する。ただし、イソップ童話の中のオオカミは、依然危険な動物であることに変わりはない。それに対しここでは、オオカミの危険を叫び立てること自体に「ネバー」、そんなことはやめよという言葉が付されている。「オオカミの危険を言い立てることはやめよ」という原題をそのまま活かした簡潔な表現は難しく、といって今や著者のトレードマークとさえなっているフレーズを消し去るのも忍びなく、「ネバー・クライ・ウルフ」を副題に残し、書名を『狼が語る』とした。
一方著者のモウェットは、これまでは通常ファーレイ・モワット、あるいはモウワットなどと表記されてきた。1985年発行の一冊に『My Discovery of America』(わたしのアメリカ発見)という書がある。冷戦の時代、何やら定かではない理由で彼の名が危険人物リストに載せられ、アメリカ入国を拒否された際の顛末を綴った書だ。その中に、「お前の名前は何と発音するんだ、マオ・イットか」「名字は、フェアレイか」と意地悪そうに尋ねる出入国管理官に、「詩人と同じ音」「大麦と同じ」、と答える場面がある。将来その場面を翻訳する際の不便を考えたわけではないけれど、名前は、ポウェット(詩人)という音に倣いモウェット、姓はバーリー(大麦)に倣いファーリーと表記する。
じつは、地元カナダにおいてさえ、しばしば彼は少しずつ違った名前で呼ばれることがあるらしい。ハリファックスで開かれた朗読会の折にも、私はポウェットと同じモウェットですと、笑いながら改めて自己紹介していた。
ファーリー・モウェットは、1921年カナダのオンタリオ湖に面したベルヴィルで生まれ、92歳になる現在も、生地に近いポート・ホープと、夏場を過ごすノバスコシア州ケープ・ブレトンで精力的に執筆活動を続けている。50冊を超える著書は、1700万部以上を売りあげ、50数か国で翻訳出版されてきた。「総督文学賞」(1959年)をはじめ、カナダにおける数々の図書賞を総嘗めにしてきたといっても過言ではない。
カナダに滞在していた2年間、わたしは足しげく古本屋に通っては、いかにも本のことならまかせなさいといった風情の店主たちに、誰よりもカナダらしい作家は誰かといつも尋ねていた。そのたびに返ってくる名前のひとりが、モウェットだった。間違いなく、カナダを描き続けた、カナダで最も人気のある著者のひとりといってよい。しかも、子ども向けの物語からおとな向けの小説やノンフィクション、ユーモアあふれる楽しい話題から鋭い政治批判に至るまで、年代を超えた幅広い読者層を誇っている。
モウェットは図書館員だった父親の影響で早くから文章を書きはじめ、十代前半にはすでに新聞のコラムを担当していたという。引っ越し先のカナダ中部サスカチュワン州サスカトゥーンでいっそう自然との交わりを深め、本格的な少年ナチュラリストとして成長していく。イヌやネコや昆虫だけではなく、ヘビやフクロウやワニに至るさまざまな動物と暮らし、そのようすは、日本語訳もある『犬になりたくなかった犬』(1957)や『ぼくとくらしたフクロウたち』(1962)に生き生きと描かれているし、1933年に書かれた自伝『Born Naked』(生まれたときは裸)にも詳しい。
1943年に入隊し1945年に除隊するまで、イタリア戦線での激しい戦闘に参加した。その時の体験は、『And No Birds Sang』(そして、鳥は歌わなかった)(1979)、『My Fathers' Son』(わたしの父の息子)(1993)などに記されている。
除隊後トロント大学に入学し、改めて生物学を勉強した。その研究の一環で北極圏、亜北極圏カナダに足を運び、その土地や、そこで暮らす人々との結びつきを深めていく。その時出会ったカリブー・イヌイット(イハルミュート)たちの惨状に衝撃を受けて書いたのが、第一作、『People of the Deer』(カリブーと暮らす人々)(1952)だった。この本で一躍作家として注目され、これ以降カナダ北部のツンドラや氷の大地は、次々に発表される小説やノンフィクションの主要な舞台となる。特に、それまで多くのカナダ人すら知らなかった(本が発行された当初は、本に描かれている人々の存在すら否定されたという)北方のイヌイットに対する関心を呼び起こし、政府の政策、あるいは無策に対する世論の抗議を生み出す原動力となった。少数民族政策に対する厳しい批判、環境破壊に対する怒りは、終始彼の作品の基音をなしている。彼の文章のスピード感あふれる激しい口調、諧謔的で時として辛辣な調子の語り口は、現在なお環境問題をめぐる戦闘的なスポークスマンとして、さらには活発な運動家として、常に実践力を備えた言葉を紡ごうとしてきた彼の姿勢と切り離しがたい。
こうした流れの中で、本書、『ネバー・クライ・ウルフ』も書かれた。
オオカミが危険な動物だという観念は、ひょっとすると「赤ずきんちゃん」の物語とともに広がったのだろうか。今では、貴重な生物種の減少も決してオオカミが原因ではないこと、オオカミによる家畜被害もきわめて特殊な状況でしか起きないことなどが、多くの論者によって明らかにされている。ましてや、人間を襲う冷酷無血なオオカミなど、勝手に作り出されたフィクションにすぎない。モウェット自身述べているように、それこそ、オオカミに投影された人間自身の「反転像」というほうが当たっている。『ネバー・クライ・ウルフ』は、何世紀にもわたって広く受け入れられてきたオオカミについての観念は明々白々なだということを最初に主張し、オオカミのイメージを大きく転換させる契機となった。
1963年に初版が出て以来、いくつかの出版社から何度も発行されて版を重ね、カナダでは最もたくさん読まれている本と目されている。ご覧の通り、生物学者として訪れたハドソン湾西岸のキーワティンで、彼を雇った官僚たちの目論見とは裏腹に、カリブーの激減にオオカミはどんな関わりももたないこと、むしろ、生態系の維持に重要な役割を果たしていることを発見し、オオカミの本当の姿に触れていく過程が新鮮な驚きや感動とともに語られている。邪悪なオオカミというイメージとはまったく異なり、彼が目にしたのは、好奇心に満ち、仲間との強い絆の中で穏やかに暮らす、親しみあふれる生き物の姿だった。
彼が描いたオオカミ像は、当然、怖いオオカミ神話になじんだ多くの読者に意外な驚きをもたらした。それだけではなく、大勢の読者の共感を呼び覚まし、ここでも、ひたすら殺戮を繰り返す政府のオオカミ駆除政策に対する大きな批判を喚起した。もちろん、それで、政府の政策がオオカミ保護に転じたわけではない。21世紀に入った今なおカナダ西部のアルバータ州やユーコン・テリトリー、さらにブリティッシュ・コロンビア州では、森林地帯に棲むカリブー保護を口実にオオカミ狩りが続けられている。しかも、そうした動きの背後には、スポーツ・ハンターたちだけではなく、巨大な石油利権者たちの姿さえちらついているともいう。加えて、アメリカ側のアラスカや北部ロッキーでは、依然大がかりなオオカミ殺戮作戦がやみそうにない。しかしなお、以前のように世論に隠れてそれを続けていくことは難しくなったし、批判者の大きな声に対処しなければならなくなったのは事実である。それだけに、オオカミを嫌う人々からの、この本に対する反感や攻撃も激しかった。
「何が変わっただろう」というタイトルを付して巻末に収めた文章は、1993年に出された三十周年版の「まえがき」として書かれたものである。そこにもあるように、この本に対する否定的反応はじつに激しく、時として執拗だった。今なお賛否両論がさかんに戦わされ、いろいろな文献やインターネットで双方の激しいやり取りを目にすることができる。しかも、聖人かペテン師か、真正なナチュラリストか大ぼら吹きかといった言葉が飛び交うその激しさは、一種異様な熱気さえ帯びていて、それを解説したり整理したりすることは決して容易ではない。
もちろん、反論にもさまざまなレベルがある。最も学術的なレベルでは、彼が観察したオオカミの行動についての理解に対する異論は多い。たとえば、彼が観たオオカミは確かにネズミを主食としていたかもしれないが、大型動物がいる場所では当然大型獣を捕食するほうが効率的であろうし、実際そうしているという指摘。この面では、著名なオオカミ学者デイヴィッド・メックも、モウェットの主張の実証性に異を唱えている。多くの科学理論の展開と同じく、本が出版されて50年、オオカミに関する大量の知見が積み重ねられてきた。その意味では、科学理論としての彼の主張はさまざまな形で乗り越えられていくだろう。一方、彼自身喜びをもって語っているように、彼の観察の正しさが追認されていく場合もあるに違いない。
こうした批判だけではなく、モウェットは経歴を詐称しているという疑問、北極圏での滞在期間に関する疑問、イヌイット語によるコミュニケーション能力についての疑問、などなど、本に書かれた「事実」をめぐる反論も多い。
「何が変わっただろう」にも見る通り、「真実の発露が事実によって妨げられるのを許さない」と半ば冗談めかした調子で自ら宣言するように、彼自身、厳密な意味での客観性や個別の観察事実の正確さを文字通り主張しているわけではないようにも見受けられる。どこまでが事実でどこからが脚色か、あくまで「真実」を伝えようとする熱い情念に動かされ、人々の心に響く言葉や表現を紡ごうとする中で、両者を分ける明確な線引き自体消え去っていることだってあっただろう。この本をフィクションとして読むべきなのか、ノンフィクションとして読むべきなのか。彼の書のファンであり訳者でもあるわたし自身は、狭い意味での実証主義を避けながら、しかしなお安易にフィクションの中に逃げこむことは決してしないという彼の言葉を支持したい。
こうした議論とは別に、この書が一般に流布した誤ったオオカミ観を正す発火点になったという点に関しては、大方の論者が一致している。オオカミに関する著名な著者バリー・ロペスも、特にその点でモウェットを高く評価する。カナダの小説家マーガレット・アトウッドは、政府をも巻きこむ侃々諤々たる議論の引き金となった『カリブーと暮らす人々』を論ずる中で、レイチェル・カーソンの『沈黙の春』を引き合いに出していた。そのことは、そのままこの書に関しても当てはまる。わたしがハリファックスで接した女性のオオカミ研究者も、研究成果としてはその後さまざまな論文や本が発表されてはいるけれど、 オオカミに対する偏見や誤った神話に批判の目を向けさせ、オオカミに対する正しい見方に人々の目を開くという意味では、いまだにこれに勝る書は書かれていないと力説していた。
ちなみにこの本は、1983年ディズニーによって映画化された。物語そのままではないし、撮影の都合か景観が幾分南の印象がないではない。しかし、ディズニーにしては、原作の雰囲気を伝え、比較的よく作られていると思う。
1998年春の一日、家族と暮らしていたカナダ・ノバスコシア州ハリファックスのダウンタウンで、路上を会場にブックフェアが開催されていた。その折、一角にある図書館の小さな講堂で、モウェットの自作朗読会が開かれた。私は詩人と同じモウェットですと彼が自己紹介した、あの会だ。会場には聴衆があふれ、彼はじつに楽しげに、少年時代の自然探索と冒険の物語を朗読してくれた。朗読会の後、ひとこと言葉を交わそうとたくさんの人々が彼をとり囲む。わたしと子どもたちも彼の前に進み、『ネバー・クライ・ウルフ』に感動したことのお礼を述べ、サインを求めた。といっても、あらかじめ彼の本を用意していたわけではなく、手元にはその日路上のテントで買い求めた別の著者の手になる小さなオオカミの本しかなかった。おずおずとそれを差し出すと、彼はそれを眺め、中身をパラパラとめくってニッコリ笑い、それからサインしてくれた。自分の名前の横に、「オールド・ウルフ」と書き添えられていた。そのとき、ふと、この本を日本語にしたいという思いが浮かび、早速翻訳を始めた。その時の翻訳原稿を抱えたまま15年の時が経ち、今こうして、やっと出版の運びに至ったことを嬉しく思う。
帰国して後、この本にはすでに日本語訳があることを知った。今は絶版でなかなか手に入らない。新しい翻訳で、その本の読者をはじめ多くの方々に読んでいただけるとありがたい。
東吉野の山中で最後のニホンオオカミが殺されたとされてから100年、北海道のオオカミがあっという間に駆逐されてから100年の時が経ち、今また生態系の回復を目指してオオカミを再導入しようといった動きさえ生まれつつある。実際アメリカでは、イエローストーン国立公園を皮切りに各地でオオカミの再導入が図られ、生態系回復の成果も確認されている。同時に、オオカミは、クジラやパンダと並ぶ自然保護運動のシンボルにもなりつつある。オオカミとの共存を実現していくためには、何より、ひたすら否定的イメージを背負わされてきたオオカミに対する新しい眼ざしの獲得(あるいは、オオカミを大神ともしてきたわたしたち自身の古い感性の復活というべきだろうか)から始めなければならない。原書のインパクトにははるか遠く及ばないにしても、この翻訳がそうした共存に向けてのささやかな一石となるなら、密かにオオカミを我がトーテムとも戴いてきたわたしにとって大きな喜びである。
最終段階で、築地書館の橋本ひとみさんがじつに丁寧に原稿を読み、言葉遣いなど、いろいろ貴重な助言をしてくださった。自分自身久しぶりに原稿に目を通し、微妙なニュアンスの違いを正し、いっそう正確で読みやすくなるよう努めた。モウェットの文章にはひとつのスタイルがあって、断り書きなしに投げ出される比喩やたくさんのイディオム、さらにはその変形など、丸ごと英語に馴染んでいるわけではない者にはなかなか手強い。今回の翻訳でも、腑に落ちない点は英語を母語とする妻に読み解いてもらった。改めて感謝したい。最終的な翻訳が、橋本さんと、そもそもこの原稿を受け入れ出版への道を開いてくださった築地書館の土井二郎さんの期待に沿うものになっていることを願いつつ、ご両人にお礼申しあげる。
この翻訳のタイトル『狼が語る』は、オオカミが自分たちの本当の姿を著者を通して語っているという意味をこめて橋本さんたち出版社の方々が考えてくださった。「狼が語る」という言葉のイメージをたどりながら、「オールド・ウルフ」と名乗ったモウェット自身、自らオオカミとして語っていたのかもしれない、狼が語るとはそんな意味でもあるのだろうかと、改めてその時の出会いを懐かしく思い起こしている。このことについても、侃々諤々書名に関して議論してくださった方々に感謝したい。
誠にわたくし事ながら、この本を、モウェットと同じ1921年生まれのわたしの母と、あの日以来ずっと一緒にいつか日本語で出版されることを願っていてくれたわたしの家族に贈りたい。
『ネバー・クライ・ウルフ』が世に出て
半世紀が経った2013年 秋
小林正佳