ソ満国境15歳の夏
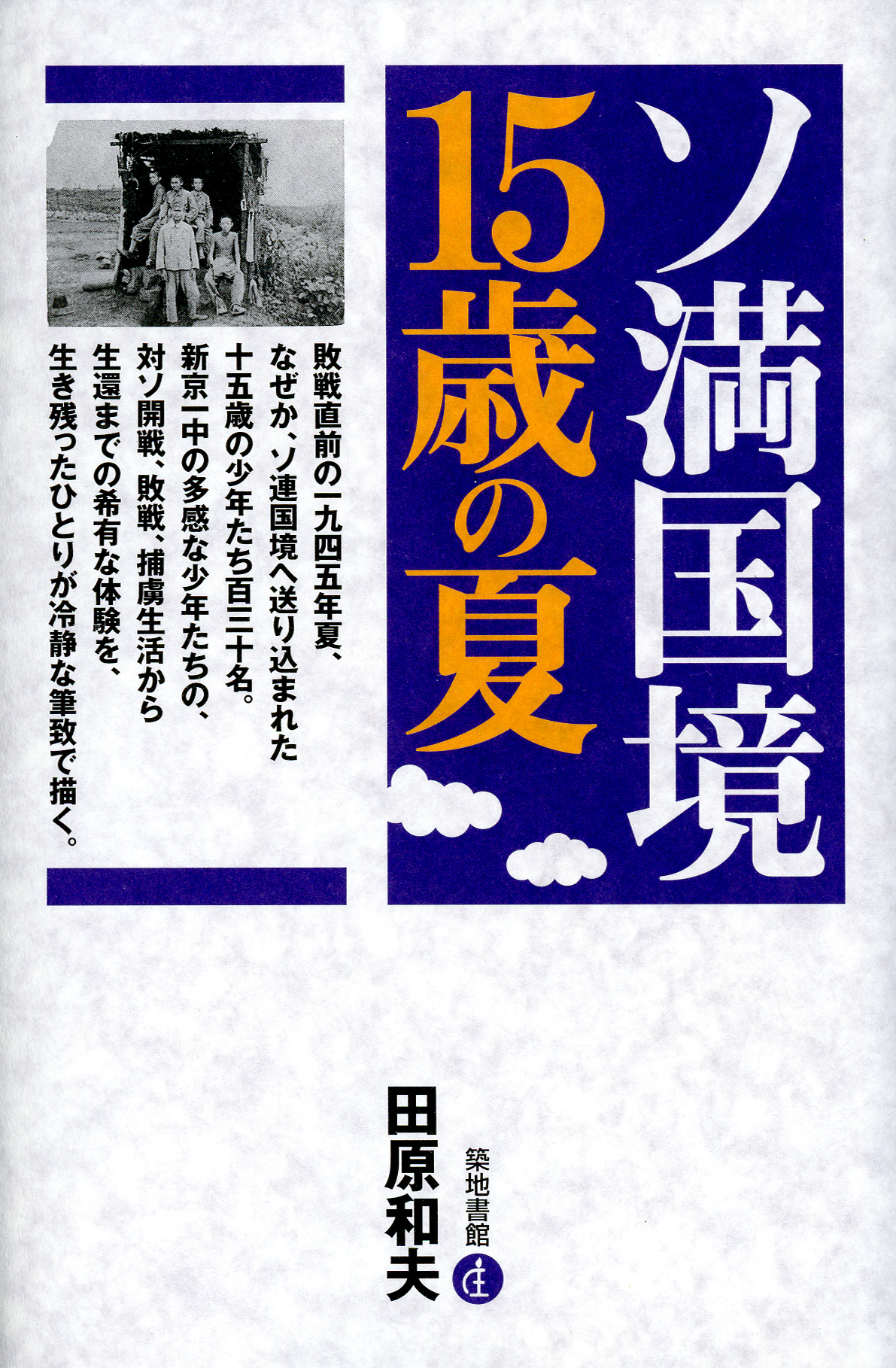
田原和夫[著]
2,400円+税 四六判並製 184頁 1998年2月刊行 ISBN978-4-8067-5564-7
敗戦直前の1945年夏、15歳の少年たち130名が最前線であるソ満国境へと送られたのはなぜか。
敗戦に際し、彼らはどんな悲惨な状況に陥り、ソ連軍の捕虜となってどんな目に遭ったのか。
生き残りの一人である著者が冷静な筆致でつづる、埋もれた昭和史をよみがえらせる貴重な記録。
2015年8月より本書原作の映画が公開。
映画『ソ満国境15歳の夏』公式サイト:http://xn--15-1b4au22psht.com/
著者紹介
田原和夫(たはら・かずお)
1930年、中国北京に生まれる。父は北京留学、母は北京育ちで、両親とも中国語に堪能だった。
幼児は四合院の中で中国人の社会にとけこんで生活した。中国語とともに、大陸の風土に慣れ親しんで成長した。
満州国政府高官・呂栄環氏の秘書官であった父にしたがい、ハルビン、新京(現・長春、旧満州国の首都)で、幼・少年期を過ごした。
一時、広島市内に寄宿し進学したが、敗戦直前、再び渡満した。
1945年、新京一中在学中に15歳で敗戦を迎える。
1946年、葫蘆島港経由で中国大陸を去り、家族とともに博多に上陸した。
1953年、旧制八高を経て東大経済学部を卒業、在学中は古谷ゼミに属し、近代経済学を専攻した。
卒業後、日東化学工業株式会社に入社し、主として労務人事部門のほか、横浜工場、大竹工場、化成品営業部などを経て、
関係会社である株式会社コステムヨシダ、三洋東北特機システム株式会社などの経営に携わった。
幼、少年期を通じ、中国大陸の人と風土の中で育ったせいか、日本社会の中で、異邦人としての自分自身を発見することがしばしばある。
横浜日中友好協会会員。
目次
第一章 前線
動員命令
出発
最前線
東寧報国農場
「天地根元造り」隊舎
なぜ東寧に
小川教官の記憶
戦車濠の設営
大八車で教練
三岔口の廃墟見学
綏芬河
雨の日の授業
延期された帰還期日
動員延期の背景
東寧地区における軍の配備・義勇隊、開拓団の配置
第二章 開戦
前兆
砲撃
脱出の指示
すでに発車していた避難列車
関東軍の東部国境防衛計画
日ソ開戦
独混第一三二旅団の転進
徹夜の行軍
“列車はあった”
脱水症状の窮地
先発隊、道河橋に
本隊、道河駅に
大堿厰橋の戦闘
第三章 無差別攻撃下の五日間
敵戦車隊と鉢合わせ
森林地帯
斎藤教官神隠し
誘導は謀略だった?
万才峠を越える
睡魔
大堿厰
第四章 敗戦
先発隊、大堿厰を出発
福井支隊、輜重隊幕営地をへて後馬厰へ
青柳支隊、輜重隊幕営地着
本隊、大堿厰を出発
自動車道路
青柳支隊、石頭へ
大鳥居伍長の乾パン
青柳支隊、東京城へ
関東軍の降伏
本隊、後馬厰をへて石頭着
“何のための戦争だったのか”
本隊、非常呼集で東京城へ
青柳支隊、鏡泊湖から敦化へ
南湖頭を去る
藤田、田口、新京に帰還
第五章 捕虜
ソ連軍機械化部隊、東京城入城
旧守備隊兵営
武装解除
ソ連の北海道占領計画
捕虜シベリア移送
青柳支隊、官地をへて敦化着
夜行列車の通過
「カネハカネネェ」
青柳支隊、新京に帰還
第六章 開拓団跡地
シベリア送りの捕虜収容所
安達の入院
点呼
久田見開拓団の入植と消滅
残苦の逃避行
棄民
陸軍の独善的感覚
第七章 収容所生活
畑の中の臨時収容所
寧安義勇隊
松尾の入院
斎藤教官、連行される
ジャガイモ掘り
東京城収容所(開拓会館跡)に移る
勃利義勇隊
収容所の給食
兵隊の死
蒸気機関車が通過した
主導権は義勇隊に
ドラム缶の露天風呂
使役
地元公安官による監視体制に
“カンホージ”
脱柵
Yの失踪
田原(節)、松田が収容所を脱出
衰弱
越冬準備
北進か南下か
解放証明書
解放!
停戦後の大堿厰の動向
第八章 帰途
石頭村民のお世話に
農家の家庭料理
還暦に報恩の旅
足止め
恐怖の徹夜行軍
牡丹江市
日本軍将校捕虜収容所
駅舎で待機、一路ハルビンへ
満鉄の終焉
中ソ友好同盟条約
無蓋貨車
ガリ版刷りの「日本字新聞」
ハルビン
第九章 生還
新京駅
道草
妹の記憶
流れ解散
第十章 救出隊
護照
救出隊編成
野辺父君の参加
収容所に残された衰弱者たち
4人の生還ならず
斎藤教官が帰還
終章 故郷喪失
私と広島1中とピカドンと
引揚げ
参考文献
あとがき
「はじめに」より
『ソ満国境最前線の「東寧報国農場」に中学生を派遣する、派遣校として新京1中3年生130名をあてる』という決定は、
どこでどういうふうに行われたのであろうか。
これは、私が新京に帰りついて自分の生還を自覚したとき以来ずっと抱きつづけてきた疑問である。そしてそれは、いまだに解明されていない。
この問題に漠然とたちふさがるのは「官僚の無責任性」という巨大な壁である。
東洋平和、国体護持、忠君愛国、滅私奉公などというもっともらしい大義名分のもとに、陸軍軍人の官僚システムが、統帥権をふりかざして国家を統治した。
その実、一皮むけば自分に都合の悪い事実は発表をのばし、どんな失敗に対してもそれをもたらした決定の責任を回避して、
自己の属するセクションの防衛と自分の保身、立身出世をはかるという習性がビルト・インされていた。
つまり問えば問うほど、「だれもまちがった決定はしていない、責任を問われるような決定はしていない」という答えが返ってくるシステムである。
事態はますます悪くなっているのではないかという素朴な庶民の実感に対し
「負けてはいない。弱気になることは事態を悪くするもとだ、必勝の信念をもて」といいつづけていた。
敗戦はだれもが想像できなかったような惨憺たる国富、国益の喪失をもたらした。
陸軍という官僚システムは消滅したけれども、しかし、わが国ではいまだになお「官僚の無責任性」が横行しているように思われてならない。
官僚システムに国政をまかせっきりにすることがいかなる結果をもたらすのか、庶民にとっていかに危険なことであるのか、
私はこのささやかな記録を書きつづけながらそのことをしきりに考えていた。
いまとなっては解明はむずかしいのかもしれないが、私は生還以来のこの疑問をあくまで追及していくつもりである。
この記録を通して、統治者や指導者の情報公開、透明性、説明能力などがいかに大切なことであるかということを、述べてみたい。
本書の読者とともにこれを再確認することで、生まれ故郷を喪失してしまったひとりの少年の15歳の夏のささやかな体験記が、
この国の歴史の中の一齣として、なにほどか読者に訴えることになれば幸いである。
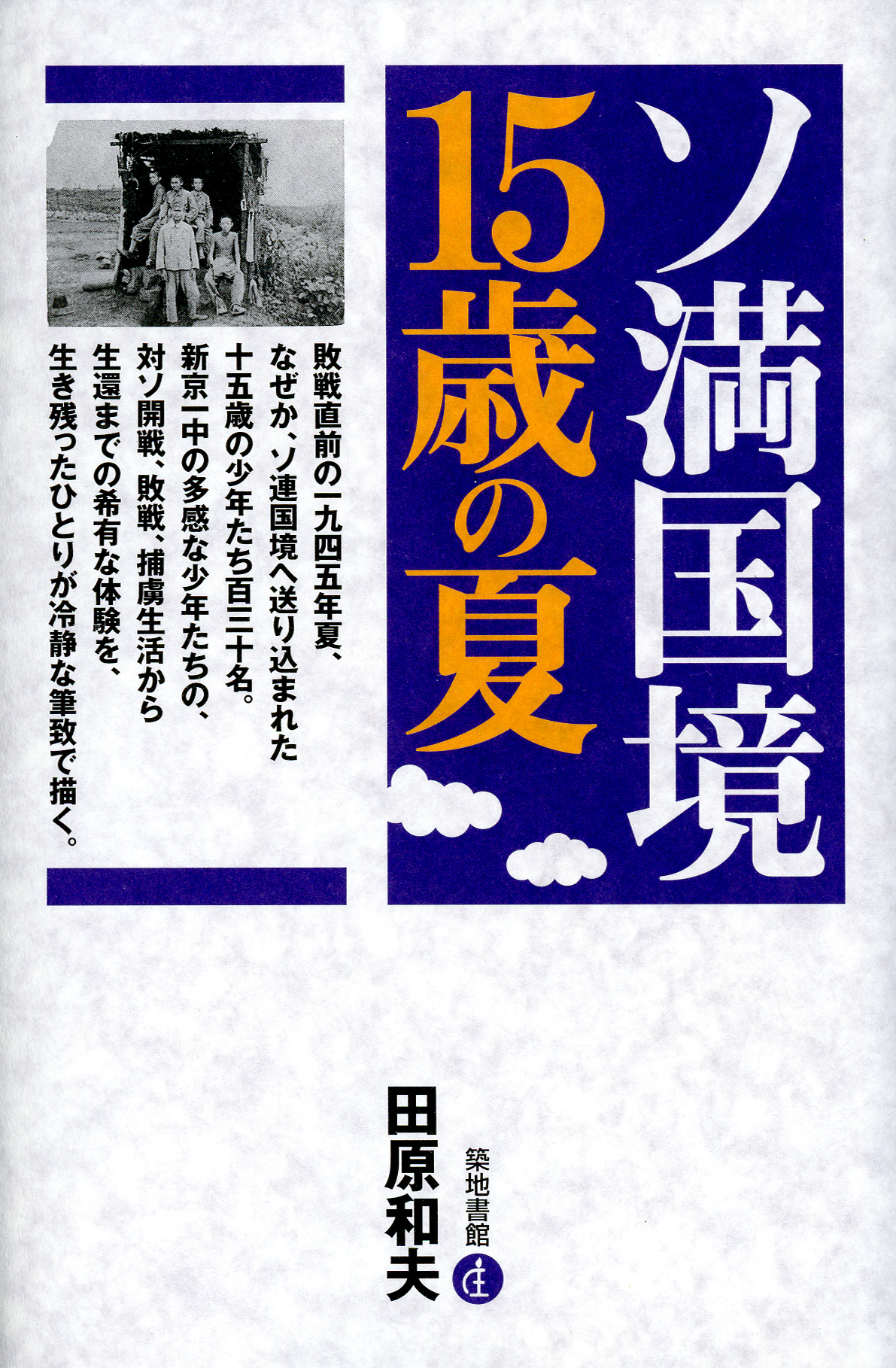
| 田原和夫[著] 2,400円+税 四六判並製 184頁 1998年2月刊行 ISBN978-4-8067-5564-7 敗戦直前の1945年夏、15歳の少年たち130名が最前線であるソ満国境へと送られたのはなぜか。 敗戦に際し、彼らはどんな悲惨な状況に陥り、ソ連軍の捕虜となってどんな目に遭ったのか。 生き残りの一人である著者が冷静な筆致でつづる、埋もれた昭和史をよみがえらせる貴重な記録。 2015年8月より本書原作の映画が公開。 映画『ソ満国境15歳の夏』公式サイト:http://xn--15-1b4au22psht.com/ |
田原和夫(たはら・かずお)
1930年、中国北京に生まれる。父は北京留学、母は北京育ちで、両親とも中国語に堪能だった。
幼児は四合院の中で中国人の社会にとけこんで生活した。中国語とともに、大陸の風土に慣れ親しんで成長した。
満州国政府高官・呂栄環氏の秘書官であった父にしたがい、ハルビン、新京(現・長春、旧満州国の首都)で、幼・少年期を過ごした。
一時、広島市内に寄宿し進学したが、敗戦直前、再び渡満した。
1945年、新京一中在学中に15歳で敗戦を迎える。
1946年、葫蘆島港経由で中国大陸を去り、家族とともに博多に上陸した。
1953年、旧制八高を経て東大経済学部を卒業、在学中は古谷ゼミに属し、近代経済学を専攻した。
卒業後、日東化学工業株式会社に入社し、主として労務人事部門のほか、横浜工場、大竹工場、化成品営業部などを経て、
関係会社である株式会社コステムヨシダ、三洋東北特機システム株式会社などの経営に携わった。
幼、少年期を通じ、中国大陸の人と風土の中で育ったせいか、日本社会の中で、異邦人としての自分自身を発見することがしばしばある。
横浜日中友好協会会員。
第一章 前線
動員命令
出発
最前線
東寧報国農場
「天地根元造り」隊舎
なぜ東寧に
小川教官の記憶
戦車濠の設営
大八車で教練
三岔口の廃墟見学
綏芬河
雨の日の授業
延期された帰還期日
動員延期の背景
東寧地区における軍の配備・義勇隊、開拓団の配置
第二章 開戦
前兆
砲撃
脱出の指示
すでに発車していた避難列車
関東軍の東部国境防衛計画
日ソ開戦
独混第一三二旅団の転進
徹夜の行軍
“列車はあった”
脱水症状の窮地
先発隊、道河橋に
本隊、道河駅に
大堿厰橋の戦闘
第三章 無差別攻撃下の五日間
敵戦車隊と鉢合わせ
森林地帯
斎藤教官神隠し
誘導は謀略だった?
万才峠を越える
睡魔
大堿厰
第四章 敗戦
先発隊、大堿厰を出発
福井支隊、輜重隊幕営地をへて後馬厰へ
青柳支隊、輜重隊幕営地着
本隊、大堿厰を出発
自動車道路
青柳支隊、石頭へ
大鳥居伍長の乾パン
青柳支隊、東京城へ
関東軍の降伏
本隊、後馬厰をへて石頭着
“何のための戦争だったのか”
本隊、非常呼集で東京城へ
青柳支隊、鏡泊湖から敦化へ
南湖頭を去る
藤田、田口、新京に帰還
第五章 捕虜
ソ連軍機械化部隊、東京城入城
旧守備隊兵営
武装解除
ソ連の北海道占領計画
捕虜シベリア移送
青柳支隊、官地をへて敦化着
夜行列車の通過
「カネハカネネェ」
青柳支隊、新京に帰還
第六章 開拓団跡地
シベリア送りの捕虜収容所
安達の入院
点呼
久田見開拓団の入植と消滅
残苦の逃避行
棄民
陸軍の独善的感覚
第七章 収容所生活
畑の中の臨時収容所
寧安義勇隊
松尾の入院
斎藤教官、連行される
ジャガイモ掘り
東京城収容所(開拓会館跡)に移る
勃利義勇隊
収容所の給食
兵隊の死
蒸気機関車が通過した
主導権は義勇隊に
ドラム缶の露天風呂
使役
地元公安官による監視体制に
“カンホージ”
脱柵
Yの失踪
田原(節)、松田が収容所を脱出
衰弱
越冬準備
北進か南下か
解放証明書
解放!
停戦後の大堿厰の動向
第八章 帰途
石頭村民のお世話に
農家の家庭料理
還暦に報恩の旅
足止め
恐怖の徹夜行軍
牡丹江市
日本軍将校捕虜収容所
駅舎で待機、一路ハルビンへ
満鉄の終焉
中ソ友好同盟条約
無蓋貨車
ガリ版刷りの「日本字新聞」
ハルビン
第九章 生還
新京駅
道草
妹の記憶
流れ解散
第十章 救出隊
護照
救出隊編成
野辺父君の参加
収容所に残された衰弱者たち
4人の生還ならず
斎藤教官が帰還
終章 故郷喪失
私と広島1中とピカドンと
引揚げ
参考文献
あとがき
『ソ満国境最前線の「東寧報国農場」に中学生を派遣する、派遣校として新京1中3年生130名をあてる』という決定は、
どこでどういうふうに行われたのであろうか。
これは、私が新京に帰りついて自分の生還を自覚したとき以来ずっと抱きつづけてきた疑問である。そしてそれは、いまだに解明されていない。
この問題に漠然とたちふさがるのは「官僚の無責任性」という巨大な壁である。
東洋平和、国体護持、忠君愛国、滅私奉公などというもっともらしい大義名分のもとに、陸軍軍人の官僚システムが、統帥権をふりかざして国家を統治した。
その実、一皮むけば自分に都合の悪い事実は発表をのばし、どんな失敗に対してもそれをもたらした決定の責任を回避して、
自己の属するセクションの防衛と自分の保身、立身出世をはかるという習性がビルト・インされていた。
つまり問えば問うほど、「だれもまちがった決定はしていない、責任を問われるような決定はしていない」という答えが返ってくるシステムである。
事態はますます悪くなっているのではないかという素朴な庶民の実感に対し
「負けてはいない。弱気になることは事態を悪くするもとだ、必勝の信念をもて」といいつづけていた。
敗戦はだれもが想像できなかったような惨憺たる国富、国益の喪失をもたらした。
陸軍という官僚システムは消滅したけれども、しかし、わが国ではいまだになお「官僚の無責任性」が横行しているように思われてならない。
官僚システムに国政をまかせっきりにすることがいかなる結果をもたらすのか、庶民にとっていかに危険なことであるのか、
私はこのささやかな記録を書きつづけながらそのことをしきりに考えていた。
いまとなっては解明はむずかしいのかもしれないが、私は生還以来のこの疑問をあくまで追及していくつもりである。
この記録を通して、統治者や指導者の情報公開、透明性、説明能力などがいかに大切なことであるかということを、述べてみたい。
本書の読者とともにこれを再確認することで、生まれ故郷を喪失してしまったひとりの少年の15歳の夏のささやかな体験記が、
この国の歴史の中の一齣として、なにほどか読者に訴えることになれば幸いである。















